☆09総選挙の行方~3
27日付の朝日新聞は「民主、320議席獲得も、自民100前後、公明20台」と総選挙中盤の情勢調査の結果を伝えた。有権者である我々でもちょっと怖い数字である。なぜなら「熱」がないのである。何人か集まって、世間話をしていても選挙が話題に上らない。政権交代が必要と熱く語る人(有権者)が周囲にいない。なのに05年のあの「小泉劇場」と呼ばれ、有権者が熱かった総選挙より、数字的にダイナミックに政権交代が起きるというのである。これは一体、どんな現象なのか。
不気味なほど静かなる選挙
 26日付の朝日新聞では、テレビの選挙報道が前回より「半減している」と報じていた。解散した日から1週間の間で、NHKや民放が取り上げた選挙に関する映像を時間で計測したデータの05年と今回の比較である。それを見ると、テレビ朝日の場合、前回がトータルで25時間、今回は16時間ほどなっている。フジテレビなどは3分の1だ。全体でデータを眺めると確かに今回はトーンダウンしている。テレビはある意味で正直だ。視聴率という数字が取れない、あるいは「絵にならない」(映像的に面白くない)と判断すると取り上げないものだ。確かに、前回は「刺客」「小泉敵情」の取り上げが過熱して、「テレポリティクス」と揶揄(やゆ)されたように、テレビが選挙を誘導しているとの批判の声もあった。テレビはその反省に立って、今回自重しているのか。「否」である。テレビはそんな殊勝な業界ではない。数字が取れると思えば、どこまでも食いついて行く。要は、選挙では数字が取れない、「酒井法子で行こう」と視聴者の心を読み取っているのである。
26日付の朝日新聞では、テレビの選挙報道が前回より「半減している」と報じていた。解散した日から1週間の間で、NHKや民放が取り上げた選挙に関する映像を時間で計測したデータの05年と今回の比較である。それを見ると、テレビ朝日の場合、前回がトータルで25時間、今回は16時間ほどなっている。フジテレビなどは3分の1だ。全体でデータを眺めると確かに今回はトーンダウンしている。テレビはある意味で正直だ。視聴率という数字が取れない、あるいは「絵にならない」(映像的に面白くない)と判断すると取り上げないものだ。確かに、前回は「刺客」「小泉敵情」の取り上げが過熱して、「テレポリティクス」と揶揄(やゆ)されたように、テレビが選挙を誘導しているとの批判の声もあった。テレビはその反省に立って、今回自重しているのか。「否」である。テレビはそんな殊勝な業界ではない。数字が取れると思えば、どこまでも食いついて行く。要は、選挙では数字が取れない、「酒井法子で行こう」と視聴者の心を読み取っているのである。
おそらく選挙期間中(8月18日~30日)なので、多くの選挙分析の専門家はこの「覚めた現象」の分析を避けているのかもしれない。個人的には投票率が気になる。どんな層が動くのか。
気になるのは、「ネガティブキャンペーン」がインターネットのユーチューブで盛んに流されている点だ。自民党が流している「プロポーズ編」「ブレる男たち編」「ラーメン編」では民主の幹部たちとおぼしき人物がアニメで表現されている。「プロポーズ編」は64万回も再生されている(28日現在)。民主党の鳩山党首とおぼしき人物が、「無料にする」などと女性に約束を乱発するアニメである。最後のナレーションで、「その根拠のない自信に人生を預けられますか?」と強調する。「ブレる男たち編」は「4人ばらばら、ブレ4です」と登場する「黒い影」は意味深だ、ちょっと見ようとクリックしてしまう。相手陣営を皮肉るという手法のテレビCMは、アメリカでは普通だ。先のアメリカの大統領選挙の民主党候補選びではオバマとヒラリー・クリントンの間でもこのネガティブ・キャンペーンが繰り広げられた。日本では表のCMはテレビ・新聞、裏のCMはインターネットと分けられている。
冒頭で紹介した民主320議席は電話調査、64万回も再生されたCMはインターネットだ。数字だけが積み上がる、不気味な選挙ではある。
⇒28日(木)朝・金沢の天気 はれ
 さて、公示日に候補者が出そろった。中で、興味深い顔ぶれも。比例代表北信越ブロックで、民主党は元自民党参院議員で国家公安委員長や内閣府特命担当大臣(防災担当)を歴任した沓掛(くつかけ)哲男氏(79歳)を、単独で名簿登載した。沓掛氏は金沢市在住で、もともと建設省技監を務めた官僚だ。3年前、議員会館を訪ねたことがある。大学のプロジェクトの立ち上げに際して、協力を求めに訪れたのだが、非常に丁寧な応対で、「お昼でもどうかね」と誘っていただいた。「政治家らしからぬ」柔軟さが好印象だった。
さて、公示日に候補者が出そろった。中で、興味深い顔ぶれも。比例代表北信越ブロックで、民主党は元自民党参院議員で国家公安委員長や内閣府特命担当大臣(防災担当)を歴任した沓掛(くつかけ)哲男氏(79歳)を、単独で名簿登載した。沓掛氏は金沢市在住で、もともと建設省技監を務めた官僚だ。3年前、議員会館を訪ねたことがある。大学のプロジェクトの立ち上げに際して、協力を求めに訪れたのだが、非常に丁寧な応対で、「お昼でもどうかね」と誘っていただいた。「政治家らしからぬ」柔軟さが好印象だった。 問われているのはメディアなのか。新聞各社の世論調査が圧倒的な「民主勝利」を早々と伝えている。ところが、最近出始めているインターネットによるアンケート調査は結果がまったく違う。
問われているのはメディアなのか。新聞各社の世論調査が圧倒的な「民主勝利」を早々と伝えている。ところが、最近出始めているインターネットによるアンケート調査は結果がまったく違う。 この映画の盗撮は、もともとハリウッドの権利を守るためにアメリカが主張したものだ。「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」(2006年12月5日)に盛り込まれた事項。日本とアメリカの経済パートナーシップを確立するとの名目で2001年に始まった「規制改革および競争政策イニシアティブ」(規制改革イニシアティブ)である。分野横断的改革を通して、市場経済をより加速させるとの狙い。06年当時は、安倍首相の時代だった。小泉内閣の遺産を引き継ぎ、日米関係はすこぶる順調だった。新しいビジネスチャンスを生み、競争を促し、より健全なビジネス環境をつくり出す改革として、アメリカ側の要望書には多くの案件が盛り込まれた。規制緩和が主流であったが、こと「知的財産権」に関してはアメリカのペースで規制強化が行われた。
この映画の盗撮は、もともとハリウッドの権利を守るためにアメリカが主張したものだ。「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」(2006年12月5日)に盛り込まれた事項。日本とアメリカの経済パートナーシップを確立するとの名目で2001年に始まった「規制改革および競争政策イニシアティブ」(規制改革イニシアティブ)である。分野横断的改革を通して、市場経済をより加速させるとの狙い。06年当時は、安倍首相の時代だった。小泉内閣の遺産を引き継ぎ、日米関係はすこぶる順調だった。新しいビジネスチャンスを生み、競争を促し、より健全なビジネス環境をつくり出す改革として、アメリカ側の要望書には多くの案件が盛り込まれた。規制緩和が主流であったが、こと「知的財産権」に関してはアメリカのペースで規制強化が行われた。 この日、珠洲(すず)市では全国に先駆けてアナログ停波のリハーサルが行われた。同市は能登半島の先端にある人口1万7000人の過疎化が進む地域である。戦後間もなく4万もいた人口が高度成長期を境に人口流出が起きた。揚げ浜塩田や珠洲焼、能登杜氏が有名であるほか、農業や漁業、そして街を取り巻く山々には30基の風力発電が建設され、新しいエネルギー発電に取り組んでいる。市内の電力需要を賄うには10基で足り、あと20基分は電力会社に売っている。三方を海に囲まれ、アナログ放送の停波リハーサルが行うのに、他の自治体に迷惑かからないというのが地デジ移行の国のモデル実験地に選ばれた理由だ。
この日、珠洲(すず)市では全国に先駆けてアナログ停波のリハーサルが行われた。同市は能登半島の先端にある人口1万7000人の過疎化が進む地域である。戦後間もなく4万もいた人口が高度成長期を境に人口流出が起きた。揚げ浜塩田や珠洲焼、能登杜氏が有名であるほか、農業や漁業、そして街を取り巻く山々には30基の風力発電が建設され、新しいエネルギー発電に取り組んでいる。市内の電力需要を賄うには10基で足り、あと20基分は電力会社に売っている。三方を海に囲まれ、アナログ放送の停波リハーサルが行うのに、他の自治体に迷惑かからないというのが地デジ移行の国のモデル実験地に選ばれた理由だ。 著書では、アメリカの事例が豊富だ。メディアの世界では、アメリカで起きている事象が3年後には日本で起きる傾向がある。その事例のいくつかを。アメリカの新聞社は経営危機にあえいでいる。その主な原因はインターネットで記事を読むようになり、新聞を購読しなくなったからだ。さらに、ネットは新聞から広告収入も奪っている。中でも、クラシファイド広告が顕著だ。日本で言えば、「売ります」「買います」「従業員募集」といった三行広告のこと。アメリカでは300億ドル(およそ3兆円)のマーケットになっていて、その半分以上を新聞が占めていた。この三行広告をインターネットで無料化したのが「クレイグズリスト」。サンフランシスコを本拠地にいまでは全米に広がり、職探し、部屋探し、ルームメイトの募集などさまざま日常で必要な情報を網羅している。月80億ページビューもある。
著書では、アメリカの事例が豊富だ。メディアの世界では、アメリカで起きている事象が3年後には日本で起きる傾向がある。その事例のいくつかを。アメリカの新聞社は経営危機にあえいでいる。その主な原因はインターネットで記事を読むようになり、新聞を購読しなくなったからだ。さらに、ネットは新聞から広告収入も奪っている。中でも、クラシファイド広告が顕著だ。日本で言えば、「売ります」「買います」「従業員募集」といった三行広告のこと。アメリカでは300億ドル(およそ3兆円)のマーケットになっていて、その半分以上を新聞が占めていた。この三行広告をインターネットで無料化したのが「クレイグズリスト」。サンフランシスコを本拠地にいまでは全米に広がり、職探し、部屋探し、ルームメイトの募集などさまざま日常で必要な情報を網羅している。月80億ページビューもある。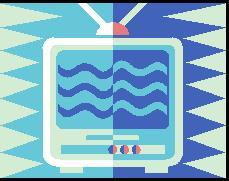 組織には何がしかの光と影がある。テレビ局の場合、どれだけ視聴率を取って、スポットライトを浴びた番組であっても、影の部分を残したまま増幅させてしまうと、その矛盾がいつかは番組に曝露してしまうものだ。520回余り続き、平均視聴率15%も取った「発掘!あるある大辞典」が問題発覚からわずか6日で番組打ち切りが宣言された。その影とは下請け問題だった。調査報告書によると、関西テレビから元請け会社(テレワーク)に渡った制作費は1本当たり3162万円だったが、孫請け会社(アジトなど9社)へは887万円だった。テレワークの粗利益率は18.6%あったという。しかし、孫請け会社は過酷な条件下に置かれた。
組織には何がしかの光と影がある。テレビ局の場合、どれだけ視聴率を取って、スポットライトを浴びた番組であっても、影の部分を残したまま増幅させてしまうと、その矛盾がいつかは番組に曝露してしまうものだ。520回余り続き、平均視聴率15%も取った「発掘!あるある大辞典」が問題発覚からわずか6日で番組打ち切りが宣言された。その影とは下請け問題だった。調査報告書によると、関西テレビから元請け会社(テレワーク)に渡った制作費は1本当たり3162万円だったが、孫請け会社(アジトなど9社)へは887万円だった。テレワークの粗利益率は18.6%あったという。しかし、孫請け会社は過酷な条件下に置かれた。 初日は、金沢からバスで出発し、石川県七尾市の能登演劇堂で開催された「環境国際シンポジウムin能登」に参加した。ノーベル平和賞を受賞した国連組織「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)のラジェンドラ・パチャウリ議長の基調講演を楽しみにしていたが、博士は体調不良を理由に欠席。その代わり、ビデオレターが上映され、その中で「今、何かの手を打たなければ、多くの生態系が危機にさらされる」と訴えていた。翌朝は船に乗り、ぐるりと能登島を回る七尾湾洋上コースと能登島をバスで巡るコースに分かれてのエクスカ-ション。能登島のカタネという入り江にミナミバンドウイルカのファミリーの親子(5頭)がコロニーをつくっていて、船からは、時折背ビレを海面に突き出して回遊する様子を見ることができた。午後からは、奥能登・珠洲で実施されている「生き物田んぼ」を見学し、直播(じかまき)の水田で水生昆虫の調査の説明を聞いた=写真=。両日とも雨にたたられずに済んだ。
初日は、金沢からバスで出発し、石川県七尾市の能登演劇堂で開催された「環境国際シンポジウムin能登」に参加した。ノーベル平和賞を受賞した国連組織「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)のラジェンドラ・パチャウリ議長の基調講演を楽しみにしていたが、博士は体調不良を理由に欠席。その代わり、ビデオレターが上映され、その中で「今、何かの手を打たなければ、多くの生態系が危機にさらされる」と訴えていた。翌朝は船に乗り、ぐるりと能登島を回る七尾湾洋上コースと能登島をバスで巡るコースに分かれてのエクスカ-ション。能登島のカタネという入り江にミナミバンドウイルカのファミリーの親子(5頭)がコロニーをつくっていて、船からは、時折背ビレを海面に突き出して回遊する様子を見ることができた。午後からは、奥能登・珠洲で実施されている「生き物田んぼ」を見学し、直播(じかまき)の水田で水生昆虫の調査の説明を聞いた=写真=。両日とも雨にたたられずに済んだ。 その日の日経新聞の別刷り面では、「夏休みに行きたい農園レストラン」のランキングが掲載されていた。1位の山形県鶴岡市の農家レストランは「農村の隠れ家」と紹介され、農業のサービス産業化を強調するような内容だった。農業参入にしても、農家レストランにしても何も珍しいことではないが、日経がこのように農業関連の記事を正面から取り上げること自体に何か新鮮さを感じる。
その日の日経新聞の別刷り面では、「夏休みに行きたい農園レストラン」のランキングが掲載されていた。1位の山形県鶴岡市の農家レストランは「農村の隠れ家」と紹介され、農業のサービス産業化を強調するような内容だった。農業参入にしても、農家レストランにしても何も珍しいことではないが、日経がこのように農業関連の記事を正面から取り上げること自体に何か新鮮さを感じる。 今からちょうど120年前の明治22年(1889)5月、東京に滞在していたアメリカの天文学者パーシバル・ローエル(1855-1916)は能登半島の地形とNOTOという地名の語感に惹(ひ)かれ、鉄道や人力車を乗り継いで当地にやってきた。七尾湾では魚の見張り台である「ボラ待ち櫓(やぐら)」によじ登り、「ここは、フランスの小説でも読んでおればいい場所」と、後に著した「NOTO: An Unexplored Corner of Japan」(1891)で記した。ローエルが述べた「フランスの小説」とは、当時流行したエミ-ル・ガボリオの「ルコック探偵」など探偵小説のことを指すのだろうか。ローエルの好奇心のたくましさはその後、宇宙へと向かって行く。
今からちょうど120年前の明治22年(1889)5月、東京に滞在していたアメリカの天文学者パーシバル・ローエル(1855-1916)は能登半島の地形とNOTOという地名の語感に惹(ひ)かれ、鉄道や人力車を乗り継いで当地にやってきた。七尾湾では魚の見張り台である「ボラ待ち櫓(やぐら)」によじ登り、「ここは、フランスの小説でも読んでおればいい場所」と、後に著した「NOTO: An Unexplored Corner of Japan」(1891)で記した。ローエルが述べた「フランスの小説」とは、当時流行したエミ-ル・ガボリオの「ルコック探偵」など探偵小説のことを指すのだろうか。ローエルの好奇心のたくましさはその後、宇宙へと向かって行く。