☆文明論としての里山5
「文明の繁栄には崩壊の芽が内包されている」。こんなキャッチフレーズが目に留まって、『文明崩壊』(ジャレド・ダイアモンド著、草思社)=写真=を手にした。上下巻で800㌻余りに及ぶ。イースター島、マヤ文明、現代中国など文明の繁栄は環境に負荷を与え、それが跳ね返って崩壊が始まる。一方で、環境危機を巧みに乗り越えて続く文明もある。文明の盛衰のサイクルの謎に、臨地的な調査(フィールドワーク)で迫った労作である。
危機は見えているのか
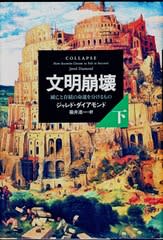 本文を引用しながら、いまから1千年以上前にメキシコ・ユカタン半島とその周辺で崩壊したマヤ文明の謎解きをしてみる。その崩壊のプロセスはこうだ。マヤ民族は少なくとも500万人はいた。「入手可能な資源の量が人口増加の速度に追いつけなくなった」ことで人口と資源の不均衡が始まる。「森林破壊と丘陵地の侵食」が農地の総面積を減らす。減少する食料資源をめぐって、人間が争いあうようになり「戦闘行為が増加」した。小国同士がつばぜり合いを演じた。統一帝国ができなかったのは、マヤにはウマやロバといった運送に利用できる家畜がいなく、陸路の運搬は人の背に載せて行われたからだ。つまり、長距離の戦闘はできなかった。しかも、主食であるトウモロコシを兵士も荷役も食べるので、長期間の戦闘でできなかった。マヤの軍事行動は「期間も距離も大きく制限されていた」のである。そして、マヤを気候変動が襲う。旱魃(かんばつ)だ。
本文を引用しながら、いまから1千年以上前にメキシコ・ユカタン半島とその周辺で崩壊したマヤ文明の謎解きをしてみる。その崩壊のプロセスはこうだ。マヤ民族は少なくとも500万人はいた。「入手可能な資源の量が人口増加の速度に追いつけなくなった」ことで人口と資源の不均衡が始まる。「森林破壊と丘陵地の侵食」が農地の総面積を減らす。減少する食料資源をめぐって、人間が争いあうようになり「戦闘行為が増加」した。小国同士がつばぜり合いを演じた。統一帝国ができなかったのは、マヤにはウマやロバといった運送に利用できる家畜がいなく、陸路の運搬は人の背に載せて行われたからだ。つまり、長距離の戦闘はできなかった。しかも、主食であるトウモロコシを兵士も荷役も食べるので、長期間の戦闘でできなかった。マヤの軍事行動は「期間も距離も大きく制限されていた」のである。そして、マヤを気候変動が襲う。旱魃(かんばつ)だ。
こうした目に見える危機に対しても、小国の王たちは、「よりみごとな神殿をより分厚い漆喰で塗り固め、互いに負けまいと懸命になった」。結局、現実の重大な脅威を前にしながら、支配者たちはなんら能動的な打開策を講じなかった。
著者は文明の崩壊だけを論じているのではない。危機に対応した例として徳川幕府を挙げている。首都・江戸の明暦の大火(1657年)、火災としては東京大空襲、関東大震災などの戦禍・震災を除けば、日本史上最大だったとされる。江戸再建のために膨大な木材を必要とした。森林を切り出した後、幕府は直轄山林に管理者(勘定奉行)を置き、さらに各藩の大名もそれにならって森林の管理者(山回り役)を設けた。また、村々の森林についても、村人全員が利用できる共有財産、いわゆる入会(いりあい)地として管理させた。このように、トップダウンで山の管理を徹底させることで、日本の森林の乱伐は防がれた、と述べている。
現在、自然環境を守る主役は国家権力や支配者ではない。国民や市民である。著者は、「神は大地を創ったが、オランダ人はオランダを創った」とのことわざを引き合いに出して、海抜がマイナスの干拓地(ポルダー)に肩を寄せ合って住むオランダ人の環境問題(地球温暖化など)に対する機敏な対応や、人々の連帯感を高く評価している。対照的に、アメリカの風潮を「裕福な階層はどんどん、ほかの階層から隔絶を図り、自分たちだけの仮想ポルダーを築き上げて、個人の安全と快適さを金で買い…」と痛烈に批判している。アメリカの仮想ポルダーとは塀で囲まれ、富裕層が住むゲート・コミュニティのことを指す。「そういう別格化の底には、エリートは一般社会の問題とは関わらずにいられるという誤った信念がある」とさえ。マヤの小国の王たちは危機に瀕してもひたすら神殿をつくり続けた。いまのアメリカのエリートたちはそれと同根だと著者は下巻の最終章で述べている。
以下、感じたことを述べる。このマヤの小国の王やアメリカの富裕な階層は、そのまま今の日本人に当てはまるのではないか、と。「豊かなニッポン」という仮想ポルダーをつくり、安全保障を他国に任せ、自国の農地や森林を放棄して食料や森林資源を海外から買いあさる。どこに日本人の危機感があるのだろうか。
「文明の繁栄には崩壊の芽が内包されている」と冒頭に紹介した。いまその崩壊の芽が膨らんでいる。
⇒2日(土)夜・金沢の天気 あめ
 前回述べたように、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。環境省がG8環境大臣会合(08年5月)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」を受け、「実行のための日本の約束」として「SATOYAMA=里山イニシアティブ」(以下「里山イニシアティブ」)を打ち出した。生物多様性条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏は、人と自然が共生するモデルとして描く里山イニシアティブに対し、「日本は成長を続けて現代的な社会を形成した一方で、文化や伝統、そして自然との関係を保ってきた。そのコンセプトは世界で有効であり、日本の経験に大きな期待が集まっている」(COP9での発言)と、条約事務局として支援を表明している。2010年10月にCOP10が名古屋市で開催されることもあり、日本発の<SATOYAMA=里山>は国際会議のキーワードになりつつある。
前回述べたように、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。環境省がG8環境大臣会合(08年5月)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」を受け、「実行のための日本の約束」として「SATOYAMA=里山イニシアティブ」(以下「里山イニシアティブ」)を打ち出した。生物多様性条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏は、人と自然が共生するモデルとして描く里山イニシアティブに対し、「日本は成長を続けて現代的な社会を形成した一方で、文化や伝統、そして自然との関係を保ってきた。そのコンセプトは世界で有効であり、日本の経験に大きな期待が集まっている」(COP9での発言)と、条約事務局として支援を表明している。2010年10月にCOP10が名古屋市で開催されることもあり、日本発の<SATOYAMA=里山>は国際会議のキーワードになりつつある。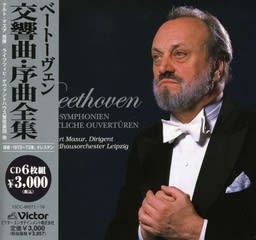 NHK教育で、N響による第九の演奏が放送された。指揮者はクルト・マズアだ。82歳・マズアといえば、「あれから20年」である。ベルリンの壁崩壊につながったとされる1989年10月9日、旧東ドイツのライプチヒで「月曜デモ」が起きた。民主化を要求するデモ参加者に、秘密警察と軍隊が銃口を向け、にらみ合いとなった。このとき、マズアは東ドイツ当局と市民に「私たちに必要なのは自由な対話だ」と平和的解決を要望するメッセージを発表した。この流血なき非暴力の反政府デモが広がり、「月曜デモ」の9日後にホーネッカー議長が退任し、11月9日のベルリンの壁崩、東西ドイツは統一へと向かう。そして、ベートーベンの第九は東西ドイツ統一の賛歌になった。そんなマズアの歴史的な功績に思いを重ね合わせながら、NHK教育の第九に耳を澄ませていた。
NHK教育で、N響による第九の演奏が放送された。指揮者はクルト・マズアだ。82歳・マズアといえば、「あれから20年」である。ベルリンの壁崩壊につながったとされる1989年10月9日、旧東ドイツのライプチヒで「月曜デモ」が起きた。民主化を要求するデモ参加者に、秘密警察と軍隊が銃口を向け、にらみ合いとなった。このとき、マズアは東ドイツ当局と市民に「私たちに必要なのは自由な対話だ」と平和的解決を要望するメッセージを発表した。この流血なき非暴力の反政府デモが広がり、「月曜デモ」の9日後にホーネッカー議長が退任し、11月9日のベルリンの壁崩、東西ドイツは統一へと向かう。そして、ベートーベンの第九は東西ドイツ統一の賛歌になった。そんなマズアの歴史的な功績に思いを重ね合わせながら、NHK教育の第九に耳を澄ませていた。 さらに、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。その認知度を一気に高めたのが、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD/COP9、ドイツ・ボン)で日本の環境省と国連大学高等研究所が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」(2008年5月28日)だった。スピーチの中で、環境省の黒田大三郎審議官(当時)らが「人と自然の共生、そして持続可能社会づくりのヒントが日本の里山にある」と述べ、科学者による知識と伝統的な自然との共存を組み合わせることを目的とした「里山イニシアティブ」を生物多様性の戦略目標として提唱した。さらに、石川県の谷本正憲知事は「石川の里山里海は世界に誇りうる財産である」と強調し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など具体的な取り組みを紹介した。
さらに、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。その認知度を一気に高めたのが、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD/COP9、ドイツ・ボン)で日本の環境省と国連大学高等研究所が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」(2008年5月28日)だった。スピーチの中で、環境省の黒田大三郎審議官(当時)らが「人と自然の共生、そして持続可能社会づくりのヒントが日本の里山にある」と述べ、科学者による知識と伝統的な自然との共存を組み合わせることを目的とした「里山イニシアティブ」を生物多様性の戦略目標として提唱した。さらに、石川県の谷本正憲知事は「石川の里山里海は世界に誇りうる財産である」と強調し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など具体的な取り組みを紹介した。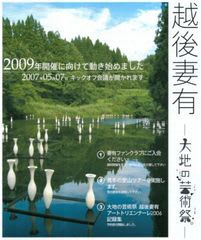 日本でも食の問題が起きた。どこの国で生産されたのかも不明な食材や加工食品を、安全性を二の次にして安価というだけで市場に流す。そのため価格では太刀打ちできない国内の小生産者は生産を止め、地域そのものが疲弊していく。地域の労働の担い手は都会に出て行く。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になる。彼らを待ち受けているのは結局、失業と貧困である。 これまで、「国民の経済」に歪みや偏りが起こると政府は、税金や補助金や社会保障給付というカタチで所得の再配分を行ってきた。ところが、一部を除いて世界的な不況となると自動車産業などグローバル企業でさえ赤字決算に陥る。日本を始め欧米は軒並み巨額な国債発行で財政をしのいでいが遅かれ早かれ国家自体が破綻する。民主党政権が、郵貯の民営化にストップをかけたのも、再び郵貯を「国債消化機関」として復活させようとしているからだとの見方もある。資本主義だけではなく、政治も国家も疲弊している。
日本でも食の問題が起きた。どこの国で生産されたのかも不明な食材や加工食品を、安全性を二の次にして安価というだけで市場に流す。そのため価格では太刀打ちできない国内の小生産者は生産を止め、地域そのものが疲弊していく。地域の労働の担い手は都会に出て行く。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になる。彼らを待ち受けているのは結局、失業と貧困である。 これまで、「国民の経済」に歪みや偏りが起こると政府は、税金や補助金や社会保障給付というカタチで所得の再配分を行ってきた。ところが、一部を除いて世界的な不況となると自動車産業などグローバル企業でさえ赤字決算に陥る。日本を始め欧米は軒並み巨額な国債発行で財政をしのいでいが遅かれ早かれ国家自体が破綻する。民主党政権が、郵貯の民営化にストップをかけたのも、再び郵貯を「国債消化機関」として復活させようとしているからだとの見方もある。資本主義だけではなく、政治も国家も疲弊している。 プロテスタントの教義は、身分は低くとも自分の仕事に誇りを持って専念しなさいと人々を諭した。これがカルヴァンが説いた予定調和説の「あらかじめ神が決めたこと」だ。プロテスタントの教会には階級序列がなく、人々にも上昇志向や贅沢志向というものがなかった。こうした生真面目な精神性が、高い生産性と「働いて貯める」倫理を生みだし、それが資本主義の蓄積へと間接的に連なって行く。一方、カトリック社会では階級序列があり、より高い階級へ上昇できる可能性がある。すると、今の仕事はより高い地位に就くための通過地点にすぎないと考える人々は実入りのよい仕事に目を向け、現状の仕事に専念しなくなる。その結果として生産性は低くなる、とウェーバーは分析したと覚えている。
プロテスタントの教義は、身分は低くとも自分の仕事に誇りを持って専念しなさいと人々を諭した。これがカルヴァンが説いた予定調和説の「あらかじめ神が決めたこと」だ。プロテスタントの教会には階級序列がなく、人々にも上昇志向や贅沢志向というものがなかった。こうした生真面目な精神性が、高い生産性と「働いて貯める」倫理を生みだし、それが資本主義の蓄積へと間接的に連なって行く。一方、カトリック社会では階級序列があり、より高い階級へ上昇できる可能性がある。すると、今の仕事はより高い地位に就くための通過地点にすぎないと考える人々は実入りのよい仕事に目を向け、現状の仕事に専念しなくなる。その結果として生産性は低くなる、とウェーバーは分析したと覚えている。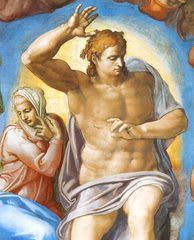 アメリカで一番有名な社説というのがある。取り上げるタイミングとしては少々遅きに失したが、「サンタはいるの」という8歳の女の子の質問に答えた社説だ。1897年9月、アメリカの新聞ニューヨーク・サンに掲載され、その後、目に見えないけれども心に確かに存在し、それを信じる心を持つことの尊さを説いた社説と評価され、掲載されてから110年余り経った今でも、クリスマスの時期になると世界中で語り継がれている。その社説を掲載する。
アメリカで一番有名な社説というのがある。取り上げるタイミングとしては少々遅きに失したが、「サンタはいるの」という8歳の女の子の質問に答えた社説だ。1897年9月、アメリカの新聞ニューヨーク・サンに掲載され、その後、目に見えないけれども心に確かに存在し、それを信じる心を持つことの尊さを説いた社説と評価され、掲載されてから110年余り経った今でも、クリスマスの時期になると世界中で語り継がれている。その社説を掲載する。 池の水面に映える。兼六園の心象風景は季節ごとに異なるのだ。
池の水面に映える。兼六園の心象風景は季節ごとに異なるのだ。 桜が晩春を締めくくる。桜にも役どころというものがある。
桜が晩春を締めくくる。桜にも役どころというものがある。 新聞各紙やテレビのニュースをまとめる。11月27日、フロリダ・オーランドの自宅前でウッズが乗用車で自損事故を起こし重傷との一報を、地元テレビ局が報じた(11月27日)。スーパースターのけが。マイケル・ジャクソンの急逝も記憶に新しいアメリカでは、国民の関心が一気にウッズに集中したのも無理はない。ウッズは顔面に軽い傷を負った程度で、病院で手当して帰宅したが、ウッズの退院後の姿を取材しようと、「ゲートコミュニティ」と呼ばれる塀で囲まれた高級住宅街のメインゲートにはテレビ中継用のSNG(Satellite News Gathering)車がずらりと並んた。このSNG車はカメラで撮影した素材(映像と音声)を電波として通信衛星を経由させ、本局に伝送する装置を搭載していて、パラボラアンテナが付いている。つまり、「おわん」の付いた車が横一列に並ぶ、日本のニュース現場ではおなじみの光景がオーランドでも再現されたのである。
新聞各紙やテレビのニュースをまとめる。11月27日、フロリダ・オーランドの自宅前でウッズが乗用車で自損事故を起こし重傷との一報を、地元テレビ局が報じた(11月27日)。スーパースターのけが。マイケル・ジャクソンの急逝も記憶に新しいアメリカでは、国民の関心が一気にウッズに集中したのも無理はない。ウッズは顔面に軽い傷を負った程度で、病院で手当して帰宅したが、ウッズの退院後の姿を取材しようと、「ゲートコミュニティ」と呼ばれる塀で囲まれた高級住宅街のメインゲートにはテレビ中継用のSNG(Satellite News Gathering)車がずらりと並んた。このSNG車はカメラで撮影した素材(映像と音声)を電波として通信衛星を経由させ、本局に伝送する装置を搭載していて、パラボラアンテナが付いている。つまり、「おわん」の付いた車が横一列に並ぶ、日本のニュース現場ではおなじみの光景がオーランドでも再現されたのである。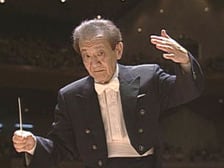 ある。これは世界の奇観であろう。
ある。これは世界の奇観であろう。 Go、Go! マツイ…」というサビの部分は松井選手が出番になるとヤンキー・スタジアムに響いたのだった。
Go、Go! マツイ…」というサビの部分は松井選手が出番になるとヤンキー・スタジアムに響いたのだった。