☆佐渡とグアムの島旅2
佐渡市から新潟市に戻り、16日にJR特急「北越」で夕方、いったん金沢に帰った。今度はグアムに行くための支度をして、その日の深夜(17日)、金沢駅3時10分発の急行「きたぐに」に家人と共に乗り込んだ。新大阪駅で特急「はるか」に乗り換え、8時前に関西空港に着いた。列車に乗っている時間がたっぷり8時間余りあったので、2冊の本を読むことができた。
~森と海の壮大なサイエンスの物語と絶望を見守る大いなる愛~
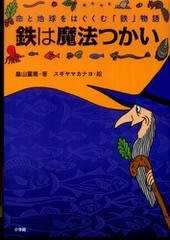 一冊目は畠山重篤氏の『鉄は魔法使い』(小学館)。この本は畠山さんのサイン入りだ。ちょっとした経緯があった。先のコラム(9月3日付)で書いた「地域再生人材大学サミットin能登」(9月1日~3日・輪島市)で畠山さんから依頼を受けた。公開シンポジウム(2日)が始まる30分前の9時半ごろだった。「宇野さん、20冊ほど持ってきたのですが、販売していただけませんか」(畠山)、「急な話でどれだけ売れるか分かりませんが、畠山さんの基調講演が終わった後の昼休みにロビーで販売しましょう。せっかくですからサイン会ということにして、畠山さんもその場に来ていただけませんか」(宇野)、「わかりました。急なお願いですみません」(畠山)。ということで急きょ、畠山氏のサイン会をしつらえた。聴衆はホール満員の入りだったので売り切る自信はあった。私が購入第1号となり、サイン本を掲げ、運営スタッフの女性が「ただいま、畠山さんの本のサイン会を行っています」と呼び込み、畠山氏がサインと握手を。列ができ、7分間で残り19冊は完売となった。「もう本はないのか」と苦情も出た。
一冊目は畠山重篤氏の『鉄は魔法使い』(小学館)。この本は畠山さんのサイン入りだ。ちょっとした経緯があった。先のコラム(9月3日付)で書いた「地域再生人材大学サミットin能登」(9月1日~3日・輪島市)で畠山さんから依頼を受けた。公開シンポジウム(2日)が始まる30分前の9時半ごろだった。「宇野さん、20冊ほど持ってきたのですが、販売していただけませんか」(畠山)、「急な話でどれだけ売れるか分かりませんが、畠山さんの基調講演が終わった後の昼休みにロビーで販売しましょう。せっかくですからサイン会ということにして、畠山さんもその場に来ていただけませんか」(宇野)、「わかりました。急なお願いですみません」(畠山)。ということで急きょ、畠山氏のサイン会をしつらえた。聴衆はホール満員の入りだったので売り切る自信はあった。私が購入第1号となり、サイン本を掲げ、運営スタッフの女性が「ただいま、畠山さんの本のサイン会を行っています」と呼び込み、畠山氏がサインと握手を。列ができ、7分間で残り19冊は完売となった。「もう本はないのか」と苦情も出た。
その本はイラストで解説し、自伝風に書かれとても読みやすい。漢字にはルビが打たれ、子供たちにも読んでほしいという意図が込められている。畠山氏は先の講演でも「森は海の恋人運動は、子供たちの心に木を植えたい」と語っていた。そして、読んでいるうちに、森と海のサイエンスの壮大なドラマが描かれていることに気が付いた。
畠山氏らカキの養殖業者が気仙沼湾に注ぐ大川の上流で大漁旗を掲げて植林する「森は海の恋人運動」はスタート当時、科学的な裏付けはなかった。畠山氏に協力して、北海道大学の松永勝彦教授(当時)が魚介類と上流の山のかかわりを物質循環から調査し、同湾における栄養塩(窒素、リン、ケイ素などの塩)の約90%は大川が供給していることや、植物プランクトンや海藻の生育に欠かせないフルボ酸鉄(腐葉土にある鉄イオンがフルボ酸と結合した物質)が大川を通じて湾内に注ぎ込まれていることが明らかとなった。この調査結果はダムの建設計画を止めるほどに威力があった。畠山氏は多くの科学者と交わりながら、魚介類と鉄の科学的な関わりにのめり込んでいく。地球と鉄の起源を知るために、オーストラリア・シャーク湾近くのハマースレー鉱山を見に行く。ジュゴンが1万頭も生息する海藻の森は、はやり鉄との関わりからからだと確信する。そして、最終章で、オホーツク海に注ぐアムール川が運ぶ鉄が三陸沖まで運ばれ豊かな漁場を形成しているとの総合地球環境学研究所のプロジェクト調査を紹介している。20数年前、気仙沼で問いかけた魔法の謎解きが、地球サイズの話へと小気味よく展開するのである。
本人は3月11日に被災した。津波でカキの養殖施設は流され、母親も亡くした。が、1ヵ月ほどして、海が少しずつ澄んできた。ハゼのような小魚など日を追うごとに魚の種類も海藻も増えてきた。つまり大津波によって海が壊れたわけではない。生き物を育む海はそのままで、カキの養殖も再開できる、「漁師は海で生きる」と自らを奮い立たせている。
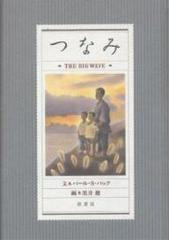 もう一冊の本が、あのノーベル作家のパール・バックの『つなみ ◆THE BIG WAVE◆』(径書房)。日本で滞在した折に取材し、アメリカで1947年に出版された。漁師の息子ジヤと友達の農家の息子キノの2人の少年。ある日突然に村を襲った大津波で、家も家族も失ったジヤをキノの両親が息子同様に育てる。ジアは周囲の愛情に包まれて成長し、やがて生まれ育った漁村に戻り、漁師と生きる決意をする。日本人の自然観や生活観、生死観を巧み取り込み、パール・バックはまるで自らの子のように少年たちを厳しくも優しく眼差しで描く。
もう一冊の本が、あのノーベル作家のパール・バックの『つなみ ◆THE BIG WAVE◆』(径書房)。日本で滞在した折に取材し、アメリカで1947年に出版された。漁師の息子ジヤと友達の農家の息子キノの2人の少年。ある日突然に村を襲った大津波で、家も家族も失ったジヤをキノの両親が息子同様に育てる。ジアは周囲の愛情に包まれて成長し、やがて生まれ育った漁村に戻り、漁師と生きる決意をする。日本人の自然観や生活観、生死観を巧み取り込み、パール・バックはまるで自らの子のように少年たちを厳しくも優しく眼差しで描く。
パール・バックには、重度の知的障害を持つ娘がいた。母親としての苦悩の日々ながら、娘の存在を創作の原点として文章を描いたという。ノーベル賞の賞金や著書の印税など収入のほとんどを養護施設に投じ、娘のほかに7人の戦争孤児を養育した。優しい眼差しの原点と、その生涯がだぶる。
⇒17日(土)夜・グアムの天気 あめ
 佐渡行きは、新潟大学「朱鷺の島環境再生リーダー養成ユニット」の特任助教、O氏から講義を依頼され引き受けた。同大学は佐渡に拠点を構え、社会人を対象とした人材養成にチカラを入れている。同大学にはトキの野生復帰で培った自然再生の研究と技術の蓄積があり、これを社会人教育向けにカリキュラム化し、地域で生物多様性関連の業務に従事する人材を育てることで、地元に役立ちたいと願っている。金沢大学が能登半島の先端・珠洲市を拠点に実施している「能登里山マイスター」養成プログラムと同じ文部科学省の予算(科学技術戦略推進費)なので、「兄弟プロジェクト」のようなもの。お願いされたら断れない…。
佐渡行きは、新潟大学「朱鷺の島環境再生リーダー養成ユニット」の特任助教、O氏から講義を依頼され引き受けた。同大学は佐渡に拠点を構え、社会人を対象とした人材養成にチカラを入れている。同大学にはトキの野生復帰で培った自然再生の研究と技術の蓄積があり、これを社会人教育向けにカリキュラム化し、地域で生物多様性関連の業務に従事する人材を育てることで、地元に役立ちたいと願っている。金沢大学が能登半島の先端・珠洲市を拠点に実施している「能登里山マイスター」養成プログラムと同じ文部科学省の予算(科学技術戦略推進費)なので、「兄弟プロジェクト」のようなもの。お願いされたら断れない…。 4本なのかよくわからないほどに束なっている姿には、日本海の風雪に耐えて威勢を張る、ある種の凄みがある。幹周り12.6㍍、樹高は21㍍。7階建てのビルくらいの高さだ。推定樹齢は300年~500年。ほかにもマンモスの象牙のような枝をはわせる「象牙杉」=写真・下=、樹木の上の樹相が丸形の「大黒杉」があって、天然杉のミュージアムといった雰囲気だ。
4本なのかよくわからないほどに束なっている姿には、日本海の風雪に耐えて威勢を張る、ある種の凄みがある。幹周り12.6㍍、樹高は21㍍。7階建てのビルくらいの高さだ。推定樹齢は300年~500年。ほかにもマンモスの象牙のような枝をはわせる「象牙杉」=写真・下=、樹木の上の樹相が丸形の「大黒杉」があって、天然杉のミュージアムといった雰囲気だ。 「地域再生人材大学サミットin能登j。畠山氏をお招きしたステージだ。地域再生のための人材養成に関わる全国の大学関係者らが集った全国会議のシンポジウム。シンポジウムは一般公開としたので、市民も聴講に訪れ、定員1200人のホール(輪島市文化会館)はいっぱいとなった。講演は40分、気仙沼の漁師としての思い、森は海の恋人の提唱者としてのこれからを語ってもらった。
「地域再生人材大学サミットin能登j。畠山氏をお招きしたステージだ。地域再生のための人材養成に関わる全国の大学関係者らが集った全国会議のシンポジウム。シンポジウムは一般公開としたので、市民も聴講に訪れ、定員1200人のホール(輪島市文化会館)はいっぱいとなった。講演は40分、気仙沼の漁師としての思い、森は海の恋人の提唱者としてのこれからを語ってもらった。 勝彦教授(当時)によって、植物プランクトンや海藻の生育に欠かせないフルボ酸鉄(腐葉土にある鉄イオンがフルボ酸と結合した物質)が大川を通じて湾内に注ぎ込まれていることを解明された。漁師の運動に科学的な論拠を与えてもらった。このおかげで、大川上流のダム建設計画も中止となった。植樹活動には子供たちを参加させている。かつて植樹に参加した子供たちの中には、いま生態学者を志す者もいる。森と川と海をつなげる森は海の恋人運動は、漁師の利害ではなく、未来の地球の環境を守るための「人々の心に木を植える」教育活動だと考えている。
勝彦教授(当時)によって、植物プランクトンや海藻の生育に欠かせないフルボ酸鉄(腐葉土にある鉄イオンがフルボ酸と結合した物質)が大川を通じて湾内に注ぎ込まれていることを解明された。漁師の運動に科学的な論拠を与えてもらった。このおかげで、大川上流のダム建設計画も中止となった。植樹活動には子供たちを参加させている。かつて植樹に参加した子供たちの中には、いま生態学者を志す者もいる。森と川と海をつなげる森は海の恋人運動は、漁師の利害ではなく、未来の地球の環境を守るための「人々の心に木を植える」教育活動だと考えている。 昨日のTBS系のニュース番組で紹介されていた。アメリカ・メリーランド州のコンビニエンスストアの防犯カメラがとらえた映像。店に突然、男女数十が入ってきて、次々に商品をつかむと、そのまま金も払わず店の外へと消えていく。集団が襲ったのは午前2時前、店員は1人で対抗措置を取ることができなかった。治安が悪い地区で起きているわけではない。静かなふつうの都市で起きている犯罪なのだ。
昨日のTBS系のニュース番組で紹介されていた。アメリカ・メリーランド州のコンビニエンスストアの防犯カメラがとらえた映像。店に突然、男女数十が入ってきて、次々に商品をつかむと、そのまま金も払わず店の外へと消えていく。集団が襲ったのは午前2時前、店員は1人で対抗措置を取ることができなかった。治安が悪い地区で起きているわけではない。静かなふつうの都市で起きている犯罪なのだ。 若者が暴走するのは世の常だ。ただし、警官による黒人男性射殺に端を発したイギリスの若者の暴動は理解を超えている。報道によれば、暴動に加わった若者の行動パターンは3つに分類されるという。それは「略奪」「放火などの破壊行為」「警察への攻撃」だ。貧民街での暴動で、停職をもたない若者の不満が爆発したのかと短絡的に考えていたがそうではないらいい。逮捕され裁判所に出廷した容疑者は、裕福な女子大生やグラフィックデザイナー、小学校の補助教員、しかも人種も多様なようだ。中には、11歳の少年もいるという。
若者が暴走するのは世の常だ。ただし、警官による黒人男性射殺に端を発したイギリスの若者の暴動は理解を超えている。報道によれば、暴動に加わった若者の行動パターンは3つに分類されるという。それは「略奪」「放火などの破壊行為」「警察への攻撃」だ。貧民街での暴動で、停職をもたない若者の不満が爆発したのかと短絡的に考えていたがそうではないらいい。逮捕され裁判所に出廷した容疑者は、裕福な女子大生やグラフィックデザイナー、小学校の補助教員、しかも人種も多様なようだ。中には、11歳の少年もいるという。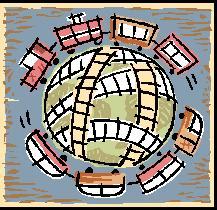 先月7月23日、中国・浙江省温州市付近で、高速鉄道「D3115」が脱線事故を起こし、車両4両が高架橋から転落し、多数の死傷者を出した。また、事故後に転落した車両を検証することもなく、地中に埋めるという当局の行為がニュースとして世界を駆け巡った。事故の一連のニュースで感じたことは、日本や諸外国の新幹線を形だけ真似しても、その安全性に対する考え方やスケジュール管理の具体的な方法などを学んでいなかったのはないかということだ。冒頭で述べた、真似ればよいというレベルでとどまっていたとうことになる。
先月7月23日、中国・浙江省温州市付近で、高速鉄道「D3115」が脱線事故を起こし、車両4両が高架橋から転落し、多数の死傷者を出した。また、事故後に転落した車両を検証することもなく、地中に埋めるという当局の行為がニュースとして世界を駆け巡った。事故の一連のニュースで感じたことは、日本や諸外国の新幹線を形だけ真似しても、その安全性に対する考え方やスケジュール管理の具体的な方法などを学んでいなかったのはないかということだ。冒頭で述べた、真似ればよいというレベルでとどまっていたとうことになる。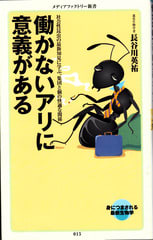 幼いころ読んだイソップ寓話に「アリとキリギリス」がある。夏の間、アリたちは冬の間の食料をためるために働き続け、キリギリスは歌を歌って遊び、働かない。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、アリたちに頼んで、食べ物を分けてもらおうとする。しかし、アリたちは「夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだ」と皮肉を込めて断る下りをいまでも覚えている。ことほどさように、アリは働き者というイメージが世界で共有されている。
幼いころ読んだイソップ寓話に「アリとキリギリス」がある。夏の間、アリたちは冬の間の食料をためるために働き続け、キリギリスは歌を歌って遊び、働かない。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、アリたちに頼んで、食べ物を分けてもらおうとする。しかし、アリたちは「夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだ」と皮肉を込めて断る下りをいまでも覚えている。ことほどさように、アリは働き者というイメージが世界で共有されている。 その熊楠がクジラの塩干しを炭火であぶって、よく酒を飲んだと著書にあり、この塩干しが食べたくなった。和歌山県太地町から「鯨塩干」を取り寄せた。黒くてフワフワ感がある。これをオーブンで5分間焼く=写真=。「これが熊楠の好物だったクジラの塩干しか」とわくわくしながら口にした。どこか覚えのある味だった。スルメイカの一夜干しのあぶったものと歯触りや味がそっくりなのだ。
その熊楠がクジラの塩干しを炭火であぶって、よく酒を飲んだと著書にあり、この塩干しが食べたくなった。和歌山県太地町から「鯨塩干」を取り寄せた。黒くてフワフワ感がある。これをオーブンで5分間焼く=写真=。「これが熊楠の好物だったクジラの塩干しか」とわくわくしながら口にした。どこか覚えのある味だった。スルメイカの一夜干しのあぶったものと歯触りや味がそっくりなのだ。 先のブログで紹介したミラー・ジェームス弁護士によると、アメリカの「2009年6月12日」では当日31万7000件の問い合わせがコールセンターに寄せられたという。地上波をアンテナで直接受信する世帯はアメリカで15%、およそ4500万人。日本では76%(2009年統計)が直接受信なので、およそ9600万人となり、アメリカの2倍以上となる。相談件数で見る限り、少なくとも日本はアメリカより混乱は少なかったといえる。
先のブログで紹介したミラー・ジェームス弁護士によると、アメリカの「2009年6月12日」では当日31万7000件の問い合わせがコールセンターに寄せられたという。地上波をアンテナで直接受信する世帯はアメリカで15%、およそ4500万人。日本では76%(2009年統計)が直接受信なので、およそ9600万人となり、アメリカの2倍以上となる。相談件数で見る限り、少なくとも日本はアメリカより混乱は少なかったといえる。 オバマの「チェンジ!」の掛け声はFCCにも及び、スタッフ部門1900人のうち300人ほどが地域に派遣され、視聴者へのサポートに入った。ミラー氏は2008年11月から地デジ移行後の7月中旬まで、カリフォニア州北部、シアトル、ポートランドに派遣された。その目的は「コミュニティー・アウトリーチ」と呼ばれた。アウトリーチは、援助を求めている人のところに援助者の方から出向くこと。つまり、地域社会に入り、連携して支援することだ。
オバマの「チェンジ!」の掛け声はFCCにも及び、スタッフ部門1900人のうち300人ほどが地域に派遣され、視聴者へのサポートに入った。ミラー氏は2008年11月から地デジ移行後の7月中旬まで、カリフォニア州北部、シアトル、ポートランドに派遣された。その目的は「コミュニティー・アウトリーチ」と呼ばれた。アウトリーチは、援助を求めている人のところに援助者の方から出向くこと。つまり、地域社会に入り、連携して支援することだ。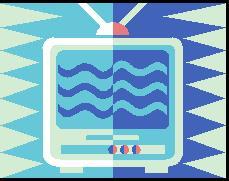 25日付の新聞報道によると、24日未明から同日午後6時までに総務省のコールセンターには9万8千件の電話相談や苦情があった。NHKには午後8時までに3万1千件、民放各社には午後7時までに1万6千件、まとめると14万5千件に上る。
25日付の新聞報道によると、24日未明から同日午後6時までに総務省のコールセンターには9万8千件の電話相談や苦情があった。NHKには午後8時までに3万1千件、民放各社には午後7時までに1万6千件、まとめると14万5千件に上る。