☆続々・トクソウの落とし穴
「戦後思想界の巨人」や「戦後最大の思想家」、「知のカリスマ」などと称された吉本隆明(よしもと・たかあき)氏が87歳で死去した(3月16日)。私のイメージで言えば、ヨシモトリュウメイは詩人であり評論家であり、大学などに足場を置くことはなく、在野から国家や言語について考察する思想家だった。ただ、個人的な蔵書には『共同幻想論』(1968年・河出書房新社)と『最後の親鸞』(1976年・春秋社)の2冊しかない。学生時代を過ごした1970年代中ごろ、ヨシモトリュウメイにはそれほど強いシンパシーを抱いていなかったのかもしれない。
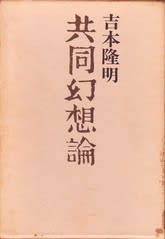 本棚の『共同幻想論』=写真・表紙=を再び手に取ってページをめくってみると、ラインを入れたり、書き込みもあって当時はそれなりに読み込んだ形跡がある。思い出しながら、共同幻想を一言で表現すれば、社会は言葉で創った幻想の世界を共同で信じ、それを実体のものと思い込んで暮らしている、ということか。言葉で編み込まれた世界を「現実そのもの」といったん勘違いすると、そこから抜け出すのは困難だ。相対化、客観化が難しいのである。今の言葉でたとえれば、マインドコントロールの状態か。遠野物語や古事記の2つの文献の分析を通して、共同幻想、対幻想、自己幻想という3つの幻想領域を想定し、吉本隆明の考える幻想領域の意味を次第に明確化し、古代国家成立の考察に至る過程は当時新鮮だった。
本棚の『共同幻想論』=写真・表紙=を再び手に取ってページをめくってみると、ラインを入れたり、書き込みもあって当時はそれなりに読み込んだ形跡がある。思い出しながら、共同幻想を一言で表現すれば、社会は言葉で創った幻想の世界を共同で信じ、それを実体のものと思い込んで暮らしている、ということか。言葉で編み込まれた世界を「現実そのもの」といったん勘違いすると、そこから抜け出すのは困難だ。相対化、客観化が難しいのである。今の言葉でたとえれば、マインドコントロールの状態か。遠野物語や古事記の2つの文献の分析を通して、共同幻想、対幻想、自己幻想という3つの幻想領域を想定し、吉本隆明の考える幻想領域の意味を次第に明確化し、古代国家成立の考察に至る過程は当時新鮮だった。
その時代、既存政党では前衛(知識人)が大衆を先導するマルクス主義が盛り上がっていた。このとき、ヨシモトリュウメイは「大衆の原像」というキーワードを掲げ、大衆を取り込め、大衆に寄り添えとダイナミズムを煽り、一時代の思想を築いた…。ここまで、書いて、ふと思った。共同幻想論はまだ生きているのでないか、と。地検特捜部の事件のことである。
「正義の地検」「泣く子も黙る鬼の特捜」、そんな言葉の呪縛。判決文にあるように、「特捜部の威信や組織防衛を過度に重要視する風潮が検察庁内にあったことを否定できず、特捜部が逮捕した以上は有罪を得なければならいないとの偏った考え方が当時の特捜部内に根付いていたことも見てとれる。犯行は、組織の病弊ともいうべき当時の特捜部の体質が生み出したともいうことができ、被告両名ばかりを責めるのも酷ということができる」(3月31日付朝日新聞より)。これはトクソウ村の共同幻想、とたとえたら言い過ぎか。素朴に自らの使命をまっとうするプロ集団であれば、とくに不正も生まれないだろう。判決文が指摘するような「特捜部の威信」や「組織防衛」といった政治的文脈を隠し持つ組織に変容していたのであれば、組織はバランスを欠き一方向に傾く。検察の自浄作用があるのか、ないのか。
⇒4日(水)朝・金沢の天気 くもり
 という手の込んだ仕掛けだった。なぜ2度も藩家老は悪のシナリオを描いたのか。「藩の財政窮乏の折、藩を守るため」と称し、新田開発の資金に充てようとしたのだ。藩を守るため、御用金を略奪して、領民を皆殺しにする。藩の武士たちは「藩のため、忠義」と孫兵衛に斬りかかる。浪人である脇坂は「罪なき人を殺(あや)めるな」と剣を抜く。脇坂が斬ったのは、病巣と化した組織防衛論だった。
という手の込んだ仕掛けだった。なぜ2度も藩家老は悪のシナリオを描いたのか。「藩の財政窮乏の折、藩を守るため」と称し、新田開発の資金に充てようとしたのだ。藩を守るため、御用金を略奪して、領民を皆殺しにする。藩の武士たちは「藩のため、忠義」と孫兵衛に斬りかかる。浪人である脇坂は「罪なき人を殺(あや)めるな」と剣を抜く。脇坂が斬ったのは、病巣と化した組織防衛論だった。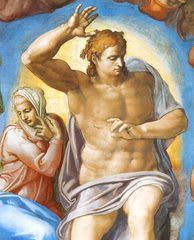 政治家汚職、大型脱税、経済事件を独自に捜査するのが地検特捜部だ。東京地検特捜部が発足したのが1947年。10年後の1957年に大阪地検特捜部ができた。さらに39年後の1996年に名古屋地検にも特捜部が置かれ、「3特捜」の態勢となった。
政治家汚職、大型脱税、経済事件を独自に捜査するのが地検特捜部だ。東京地検特捜部が発足したのが1947年。10年後の1957年に大阪地検特捜部ができた。さらに39年後の1996年に名古屋地検にも特捜部が置かれ、「3特捜」の態勢となった。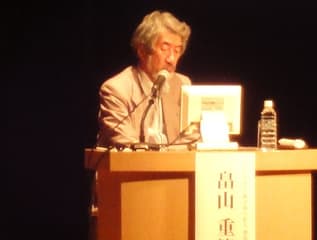 震災後、畠山さんとは3回お話をさせていただくチャンスを得た。1回目は震災2ヵ月後の5月12日にJR東京駅でコーヒーを飲みながら近況を聞かせていただき、9月に開催するシンポジウムでの基調講演をお願いした。その時に、間伐もされないまま放置されている山林の木をどう復興に活用すればよいか、どう住宅材として活かすか、まずはカキ筏(いかだ)に木材を使いたいと、長く伸びたあごひげをなでながら語っておられた。2回目は9月2日、輪島市で開催したシンポジウム「地域再生人材大学サミットin能登」(主催:能登キャンパス構想推進協議会)で。シンポジウムが終わり、居酒屋で地域の人たちと畠山さんを囲んで話し込んだ。3回目はことし2月2日、仙台市でのシンポジウム「市民による東日本大震災からの復興~創造と連携~」(主催:三井物産)の交流会で。9月のシンポジウムのお礼の挨拶をした。すると畠山さんの方から、「内緒なんだけれど、今度ニューヨークに表彰式があるんだ」とうれしそうに話された。UNFFのフォレストヒーローのことが新聞記事になったのはその数日後だった。
震災後、畠山さんとは3回お話をさせていただくチャンスを得た。1回目は震災2ヵ月後の5月12日にJR東京駅でコーヒーを飲みながら近況を聞かせていただき、9月に開催するシンポジウムでの基調講演をお願いした。その時に、間伐もされないまま放置されている山林の木をどう復興に活用すればよいか、どう住宅材として活かすか、まずはカキ筏(いかだ)に木材を使いたいと、長く伸びたあごひげをなでながら語っておられた。2回目は9月2日、輪島市で開催したシンポジウム「地域再生人材大学サミットin能登」(主催:能登キャンパス構想推進協議会)で。シンポジウムが終わり、居酒屋で地域の人たちと畠山さんを囲んで話し込んだ。3回目はことし2月2日、仙台市でのシンポジウム「市民による東日本大震災からの復興~創造と連携~」(主催:三井物産)の交流会で。9月のシンポジウムのお礼の挨拶をした。すると畠山さんの方から、「内緒なんだけれど、今度ニューヨークに表彰式があるんだ」とうれしそうに話された。UNFFのフォレストヒーローのことが新聞記事になったのはその数日後だった。 今回の大震災から学んだことが多々ある。その一つが日本は「災害列島」であるということだ。地震だけではない。津波、水害、雪害、火災、落雷などさまざまな災害がある。「天災は忘れたころにやってくる」(寺田寅彦の言葉とされる)は現代人への災害に備えよとの戒めの言葉だろう。改めてかみしめる言葉だ。
今回の大震災から学んだことが多々ある。その一つが日本は「災害列島」であるということだ。地震だけではない。津波、水害、雪害、火災、落雷などさまざまな災害がある。「天災は忘れたころにやってくる」(寺田寅彦の言葉とされる)は現代人への災害に備えよとの戒めの言葉だろう。改めてかみしめる言葉だ。 もう一つ。ことし金沢の自宅周辺は雪が多かった。スコップでの除雪は、2月前半は来る日も来る日もだった。そのうち、右肩が上がらなくなってきた。軽い腱鞘炎だと自己判断している。カバンがいつもより重い。テーブルに座って、ワインのボトルを持って、グラスに注ぐのでさえ痛みがある。57歳の身にとって、数日安静にして、休養すればよいのに、不徳のいたすところで、毎日酒は欠かさず、夜中に起きてはPCに向かってもいる。
もう一つ。ことし金沢の自宅周辺は雪が多かった。スコップでの除雪は、2月前半は来る日も来る日もだった。そのうち、右肩が上がらなくなってきた。軽い腱鞘炎だと自己判断している。カバンがいつもより重い。テーブルに座って、ワインのボトルを持って、グラスに注ぐのでさえ痛みがある。57歳の身にとって、数日安静にして、休養すればよいのに、不徳のいたすところで、毎日酒は欠かさず、夜中に起きてはPCに向かってもいる。 上勝町に宿泊して一番美味と感じたのは「かみカツ」だった。豚カツではない。地場産品の肉厚のシイタケをカツで揚げたものだ。上勝の地名とひっかけたネーミングなのだが、この「かみカツ丼」=写真=がお吸い物付きで800円。シイタケがかつ丼に化けるのである。こんなアイデアがこの地では次々と生まれている。全国的に上勝町といってもまだ知名度は低いが、「葉っぱビジネス」なら知名度は抜群だ。このビジネスはいろいろ考えさせてくれる。女性や高齢年齢層の住民を組織し、生きがいを与えるということ。「つま物」を農産物と同等扱いで農協を通じて全国に流通するとうこと。ビジネスの仕組みを創り上げたこと。たとえば、注文から出荷までの時間が非常に短い。畑に木を植えて収穫する。山に入って見つけていたのでは時間のロスが多いからだ。ただし、市場原理でいえば、つま物の需要が高くなって価格が跳ね上がることはありえないだろう。
上勝町に宿泊して一番美味と感じたのは「かみカツ」だった。豚カツではない。地場産品の肉厚のシイタケをカツで揚げたものだ。上勝の地名とひっかけたネーミングなのだが、この「かみカツ丼」=写真=がお吸い物付きで800円。シイタケがかつ丼に化けるのである。こんなアイデアがこの地では次々と生まれている。全国的に上勝町といってもまだ知名度は低いが、「葉っぱビジネス」なら知名度は抜群だ。このビジネスはいろいろ考えさせてくれる。女性や高齢年齢層の住民を組織し、生きがいを与えるということ。「つま物」を農産物と同等扱いで農協を通じて全国に流通するとうこと。ビジネスの仕組みを創り上げたこと。たとえば、注文から出荷までの時間が非常に短い。畑に木を植えて収穫する。山に入って見つけていたのでは時間のロスが多いからだ。ただし、市場原理でいえば、つま物の需要が高くなって価格が跳ね上がることはありえないだろう。 イツ製の木質チップボイラーを導入し、温泉や暖房設備に利用している=写真=。重油ボイラーは補助的に使っている。木質チップは1日約1.2トン使われ、すべて同町産でまかなわれている。チップ製造者の販売価格はチップ1t当たり16,000円。重油を使っていたころに比べ、3分の2程度のコストで済む。町内では薪(まき)燃料の供給システムのほか、都市在住の薪ストーブユーザーへ薪を供給することも試みている。地域内で燃料を供給する仕組みを構築することで、化石燃料の使用削減によるCO2排出抑制を図り、地域経済も好循環するまちづくりを目指している。さらに、森林の管理と整備が進むことになり、イノシシなどの獣害対策にもなる。
イツ製の木質チップボイラーを導入し、温泉や暖房設備に利用している=写真=。重油ボイラーは補助的に使っている。木質チップは1日約1.2トン使われ、すべて同町産でまかなわれている。チップ製造者の販売価格はチップ1t当たり16,000円。重油を使っていたころに比べ、3分の2程度のコストで済む。町内では薪(まき)燃料の供給システムのほか、都市在住の薪ストーブユーザーへ薪を供給することも試みている。地域内で燃料を供給する仕組みを構築することで、化石燃料の使用削減によるCO2排出抑制を図り、地域経済も好循環するまちづくりを目指している。さらに、森林の管理と整備が進むことになり、イノシシなどの獣害対策にもなる。 事を創るという発想に乏しい。日本全体がチャレンジ性が薄まっている中、受け身型になっていると常々考えている。事業をすることで地域が活性化し、社会貢献の意識があっても事業性がなければ継続しない。しかし、社会貢献をしようという若者を受け入れることは大いにプラスである。それはなぜか、現代は「役割ビジネス」だと思うからだ。
事を創るという発想に乏しい。日本全体がチャレンジ性が薄まっている中、受け身型になっていると常々考えている。事業をすることで地域が活性化し、社会貢献の意識があっても事業性がなければ継続しない。しかし、社会貢献をしようという若者を受け入れることは大いにプラスである。それはなぜか、現代は「役割ビジネス」だと思うからだ。 29日朝、徳島県の山間部にある上勝町(かみかつちょう)は雪だった=写真=。28日夜からの寒波のせいで積雪は5㌢ほどだが、まるで水墨画のような光景である。ただ、土地の人達にとって、この寒波は31年前の出来事を思い起こさせたことだろう。1981年2月2月、マイナス13度という異常寒波が谷あいの上勝地区を襲い、ほとんどのミカンの木が枯死した。当時、主な産物であった木材や温州みかんは輸入自由化や産地間競争が激しく、伸び悩んでいた。売上は約半分にまで減少し、上勝の農業は打撃を受けていた。そこへ追い打ちをかけるように強力な寒波が襲ったのだ。主力農産品を失って過疎化に拍車がかかった。若年人口が流出し、1950年に6356人あった上勝町の人口は一気に減り、2011年には1890人にまで低下した。高齢化率は49%となった。人口の半分が65歳以上の超高齢化社会がやってきた。
29日朝、徳島県の山間部にある上勝町(かみかつちょう)は雪だった=写真=。28日夜からの寒波のせいで積雪は5㌢ほどだが、まるで水墨画のような光景である。ただ、土地の人達にとって、この寒波は31年前の出来事を思い起こさせたことだろう。1981年2月2月、マイナス13度という異常寒波が谷あいの上勝地区を襲い、ほとんどのミカンの木が枯死した。当時、主な産物であった木材や温州みかんは輸入自由化や産地間競争が激しく、伸び悩んでいた。売上は約半分にまで減少し、上勝の農業は打撃を受けていた。そこへ追い打ちをかけるように強力な寒波が襲ったのだ。主力農産品を失って過疎化に拍車がかかった。若年人口が流出し、1950年に6356人あった上勝町の人口は一気に減り、2011年には1890人にまで低下した。高齢化率は49%となった。人口の半分が65歳以上の超高齢化社会がやってきた。 のつま物として商品化したもの。山あいの村では自生しているが、市場出荷が本格的になるにつれ、栽培も盛んに行われるようになった。採取は掘り起こしたり、機械を用いない。しかも、野菜などと比べて軽くて小さいので高齢者には打ってつけの仕事なのである。懐石料理など日本食には欠かせない、このつま物はこれまで店が近くの農家と契約したり、料理人が山に取りに行ったりすることが多かった。これを市場参入させたのが当時、農協の営農指導担当だった横石知二氏(1958年生)=写真=だった。
のつま物として商品化したもの。山あいの村では自生しているが、市場出荷が本格的になるにつれ、栽培も盛んに行われるようになった。採取は掘り起こしたり、機械を用いない。しかも、野菜などと比べて軽くて小さいので高齢者には打ってつけの仕事なのである。懐石料理など日本食には欠かせない、このつま物はこれまで店が近くの農家と契約したり、料理人が山に取りに行ったりすることが多かった。これを市場参入させたのが当時、農協の営農指導担当だった横石知二氏(1958年生)=写真=だった。 著書の中で興味深い下りがある。「地震情報が、いわゆる『予言』に近い情報から、純粋科学情報に移行しつつあった時代だったのだが、行政も企業も『予言時代』そのままの対応をしたのであった」「市民は、家具の固定といった、きわめて狭い範囲の防衛策であったとはいえ、生活レベルでの対応を始める兆しがみえるが、行政、企業は、そうした具体的防御策への想像力を全く欠いていた」。これは阪神・大震災(1995年1月17日)が起きる10日前に神戸新聞の一面で報じていた、当時兵庫県猪名川町で続発していた群発地震に触れ「いつM7級の大地震が起きても不思議ではない」との専門家の見方を警告として発していたものだ。しかし、パブル経済の崩壊で行政も企業も内需拡大策、開発に神経を集中していた。むしろ、この記事に反応していたのは市民だったという。
著書の中で興味深い下りがある。「地震情報が、いわゆる『予言』に近い情報から、純粋科学情報に移行しつつあった時代だったのだが、行政も企業も『予言時代』そのままの対応をしたのであった」「市民は、家具の固定といった、きわめて狭い範囲の防衛策であったとはいえ、生活レベルでの対応を始める兆しがみえるが、行政、企業は、そうした具体的防御策への想像力を全く欠いていた」。これは阪神・大震災(1995年1月17日)が起きる10日前に神戸新聞の一面で報じていた、当時兵庫県猪名川町で続発していた群発地震に触れ「いつM7級の大地震が起きても不思議ではない」との専門家の見方を警告として発していたものだ。しかし、パブル経済の崩壊で行政も企業も内需拡大策、開発に神経を集中していた。むしろ、この記事に反応していたのは市民だったという。