☆新幹線「かがやき」考
「かがやき」と聞いてどのようなイメージを持つだろうか。「未来にかがやく」、「かがやく明日」など夢と創造性をかきたてる言葉の響きと感じる。ただ、人名だと「名前負け」しそうだ。2015年春に開業予定の北陸新幹線について、その列車名が10日、JR西日本と東日本から発表された。
 北陸新幹線の金沢と東京間を最速で走る速達タイプの列車名が「かがやき」、停車駅を多くする停車タイプは「はくたか」、金沢駅と富山駅を結ぶシャトルタイプは「つるぎ」、東京駅と長野駅を往復する長野新幹線タイプは「あさま」と列車名がついた。名称については、事前に公募(5月31日‐6月30日)があり、約14万5千件の応募があった。この結果で一番多かったのは「はくたか」(9083件)で、2位「はくさん」(7323件)、3位「らいちょう」(5408件)だった。
北陸新幹線の金沢と東京間を最速で走る速達タイプの列車名が「かがやき」、停車駅を多くする停車タイプは「はくたか」、金沢駅と富山駅を結ぶシャトルタイプは「つるぎ」、東京駅と長野駅を往復する長野新幹線タイプは「あさま」と列車名がついた。名称については、事前に公募(5月31日‐6月30日)があり、約14万5千件の応募があった。この結果で一番多かったのは「はくたか」(9083件)で、2位「はくさん」(7323件)、3位「らいちょう」(5408件)だった。
1位「はくたか」は、立山の開山伝説に登場する白いタカの「白鷹」のこと。「はくさん」は石川、岐阜、福井にまたぐ白山、「らいちょう」は国指定の特別天然記念物のライチョウで、長野、岐阜、富山の県鳥でもある。今回、ベスト3の中で採用されたのは「はくたか」のみ。現在ほくほく線(北越急行)の特急の列車名だが、新幹線の列車名として残ることになった。「はくさん」と「らいちょう」は外れた。公募上位の「はくさん」が漏れたのは、今回採用された「はくたか」と紛らわしい名前を避けたためとする見方もあるが、理由はおそらくこうだ。かつて金沢駅と上野駅を結んだ特急「白山」はあった。が、2015年の新幹線開業時では、白山は沿線から見えないからだろう。そして、「らいちょう」だが、かつての特急「雷鳥」は現在「サンダーバード」として名称変更して北陸本線で運行している。新幹線開業後は金沢駅から東の北陸本線は並行在来線となるので、JR西日本から経営分離される。このため、「サンダーバード」は金沢駅止まりとして運行が継続される。
それにしても大出世は「かがやき」である。上越新幹線と連絡するため、新潟県の長岡駅と金沢駅を結ぶ特急「かがやき」が1988年に登場。その9年後、1997年にほくほく線が開業し、越後湯沢と北陸方面を結ぶ「はくたか」がデビューしたので引退していた。そこにまさかの北陸新幹線での復活。しかも速達タイプ、まさに優等列車の愛称に「かがやき」が採用されたのである。「かがやき」は公募順位では5位(4123件)だった。4位の「つるぎ」(4906件)を差し置いて躍り出たという感じだ。個人的には東海道新幹線の「ひかり」と並び、「かがやき」はそん色ない。ローカルな山の名称や動植物を感じさせない分、スピード感や透明感、未来性を感じさせる、ある意味でよい名だと思う。
金沢駅と富山駅を結ぶシャトルタイプの列車名として「つるぎ」も復活した。剣岳をイメージさせる「つるぎ」は1961年に大阪駅と富山駅を結び、その後に新潟駅まで運行区間が延長されたが、1996年廃止となっていた。東京駅と長野駅を往復するシャトルタイプの列車名が「あさま」なので、同じく山の名称をつけたのだろう。
※画像は石川県の新幹線開業に向けたアクションプラン「STEP21」ホームページから
⇒10日(木)夜・金沢の天気 くもり
 そうした希望ある試算が奏功してか、新聞やテレビなどでは連日のように、「おもてなし」のキャンペーンをどう繰り広げるかといったたぐいのニュースが掲載されている。面白いのは、石川県が先月27日、金沢開業のPRのために新たに作ったマスコットキャラクター。その名も「ひゃくまんさん」。加賀百万石にちなんだ名前だそうだ。郷土玩具の「加賀八幡起き上がり」をモチーフに、だるまに手足が生えたようなデザインだ。都内で開くイベントに向け、着ぐるみを現在制作中だとか。伝統工芸の加賀友禅を思わせる図柄に金箔や輪島塗もあしらうそうだが、マスコットキャラクターにしては面白味がない。そもそも、加賀百万石はキャラクターになりにくいイメージだ。そもそも「百万石」の意味すら理解できない人が多いだろう。たとえば、徳川幕府は何万石だと問われて、回答できる人や、1石を説明できる人すら少ないだろう。現代では死語なのだ。そんなものをテーマにマスコットキャラクターにしてどうキャンペーンを展開するのだろうか。むしろ、「けんろくくん」が分かりやすい。
そうした希望ある試算が奏功してか、新聞やテレビなどでは連日のように、「おもてなし」のキャンペーンをどう繰り広げるかといったたぐいのニュースが掲載されている。面白いのは、石川県が先月27日、金沢開業のPRのために新たに作ったマスコットキャラクター。その名も「ひゃくまんさん」。加賀百万石にちなんだ名前だそうだ。郷土玩具の「加賀八幡起き上がり」をモチーフに、だるまに手足が生えたようなデザインだ。都内で開くイベントに向け、着ぐるみを現在制作中だとか。伝統工芸の加賀友禅を思わせる図柄に金箔や輪島塗もあしらうそうだが、マスコットキャラクターにしては面白味がない。そもそも、加賀百万石はキャラクターになりにくいイメージだ。そもそも「百万石」の意味すら理解できない人が多いだろう。たとえば、徳川幕府は何万石だと問われて、回答できる人や、1石を説明できる人すら少ないだろう。現代では死語なのだ。そんなものをテーマにマスコットキャラクターにしてどうキャンペーンを展開するのだろうか。むしろ、「けんろくくん」が分かりやすい。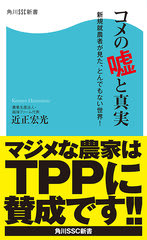 東京の不動産会社の社員(著者)が社長命令で、生まれ故郷の新潟でコメ生産を中心とした食糧事業部門を立ち上げる予定だったが、困難が待ち受ける。農地法に阻まれ個人負担で農業生産法人「越後ファーム」をつくり新規就農を始める。さらにそこから見えた農の世界。消費者のことなど一考もしない、「保護漬け」になり向上心を失った、コメの生産の場だった。農地法、農業委員会、村社会(兼業農家)など、コメを「ダメにした」存在と出会い面食らう。そこから著者が立ち上がる。機械化・大型化が条件の「集約型の米作農業」が不可能な中山間地=里山であえて耕作し、機械化・大型化とは真逆の「手作業農業」を選択するのである。
東京の不動産会社の社員(著者)が社長命令で、生まれ故郷の新潟でコメ生産を中心とした食糧事業部門を立ち上げる予定だったが、困難が待ち受ける。農地法に阻まれ個人負担で農業生産法人「越後ファーム」をつくり新規就農を始める。さらにそこから見えた農の世界。消費者のことなど一考もしない、「保護漬け」になり向上心を失った、コメの生産の場だった。農地法、農業委員会、村社会(兼業農家)など、コメを「ダメにした」存在と出会い面食らう。そこから著者が立ち上がる。機械化・大型化が条件の「集約型の米作農業」が不可能な中山間地=里山であえて耕作し、機械化・大型化とは真逆の「手作業農業」を選択するのである。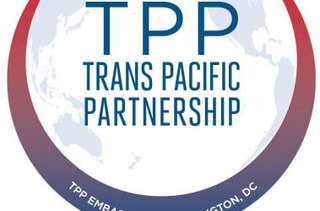 自民党の西川公也TPP対策委員長は、TPP交渉が開かれているバリ島で記者団に対し、「聖域」として関税維持を求めてきたコメなど農産物の重要5品目について、関税撤廃できるかどうかを党内で検討することを明らかにしたのだ。自民は前回の衆院選で、「聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加に反対」との公約を掲げていた。こうした公約を放棄したともいえる。
自民党の西川公也TPP対策委員長は、TPP交渉が開かれているバリ島で記者団に対し、「聖域」として関税維持を求めてきたコメなど農産物の重要5品目について、関税撤廃できるかどうかを党内で検討することを明らかにしたのだ。自民は前回の衆院選で、「聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加に反対」との公約を掲げていた。こうした公約を放棄したともいえる。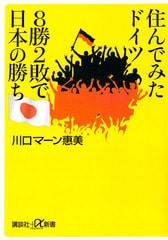 本著での「我々は原爆を持っているが、ドイツはマルクを持っている」と、ドイツを見つめるフランス人の考え方が圧巻だ。これは1989年、「ドイツ統一とユーロ導入の裏事情」という下りで出てくる。ドイツの経済は強く、ミッテラン大統領はドイツが統一を望むならとユーロ導入を強力に勧めた。他国が望まなかったドイツ統一の代償として、ドイツはマルクを手放したという裏情報である。これは腑に落ちる。壮絶な政治的駆け引きがあったのだろう。でもドイツはその後、ユーロ導入で域内の関税はなくなり、為替変動のリスクもなく、輸出大国ドイツの地位を確立する。が、ギリシア財政危機が表面化し、ユーロ圏が一蓮托生となるとのドイツにも焦りが生じる。ドイツもユーロ圏を抜けたがっているのだろうと想像に難くない。それでも、ドイツは近隣から憎まれる。ドイツがギリシアに対して財政規律と緊縮財政を求めれば、求めるほど、ドイツのメルケル首相に「ナチの制服を着せたカリカルチュアがギリシアの雑誌に出回る」ことになる。ドイツも辛い。
本著での「我々は原爆を持っているが、ドイツはマルクを持っている」と、ドイツを見つめるフランス人の考え方が圧巻だ。これは1989年、「ドイツ統一とユーロ導入の裏事情」という下りで出てくる。ドイツの経済は強く、ミッテラン大統領はドイツが統一を望むならとユーロ導入を強力に勧めた。他国が望まなかったドイツ統一の代償として、ドイツはマルクを手放したという裏情報である。これは腑に落ちる。壮絶な政治的駆け引きがあったのだろう。でもドイツはその後、ユーロ導入で域内の関税はなくなり、為替変動のリスクもなく、輸出大国ドイツの地位を確立する。が、ギリシア財政危機が表面化し、ユーロ圏が一蓮托生となるとのドイツにも焦りが生じる。ドイツもユーロ圏を抜けたがっているのだろうと想像に難くない。それでも、ドイツは近隣から憎まれる。ドイツがギリシアに対して財政規律と緊縮財政を求めれば、求めるほど、ドイツのメルケル首相に「ナチの制服を着せたカリカルチュアがギリシアの雑誌に出回る」ことになる。ドイツも辛い。 がついた。狭い入り江で両サイドでうっそうと木々で囲まれている。辺りは昼でも暗い。
がついた。狭い入り江で両サイドでうっそうと木々で囲まれている。辺りは昼でも暗い。
 小学生のときに視聴した「東京オリンピック」は鮮明だった。というのも、1953年に始まったテレビ放送で、それまで白黒だった画面がオリンピックを契機に一気にカラー化が進んだのだ。それだけでなく、スロービデオなどの導入でスポーツを見せる画面上の工夫もされた。また、静止衛星による衛星中継も初めて行われた。長野の冬季オリンピックでは、ハイビジョン放送としてハンディ型カメラが登場した。オリンピックとテレビの技術革新は無縁ではない。それでは、これからのオリンピックのテレビの存在価値はなんだろうか。ひょっとして、「4K」「8K」かもしれない。
小学生のときに視聴した「東京オリンピック」は鮮明だった。というのも、1953年に始まったテレビ放送で、それまで白黒だった画面がオリンピックを契機に一気にカラー化が進んだのだ。それだけでなく、スロービデオなどの導入でスポーツを見せる画面上の工夫もされた。また、静止衛星による衛星中継も初めて行われた。長野の冬季オリンピックでは、ハイビジョン放送としてハンディ型カメラが登場した。オリンピックとテレビの技術革新は無縁ではない。それでは、これからのオリンピックのテレビの存在価値はなんだろうか。ひょっとして、「4K」「8K」かもしれない。 中でも食品添加物は直接体に入ってくる。食品添加物には合成添加物と天然添加物があるが、合成添加物はいわゆる化学物質、431品目もある。スーパーやコンビニ、自販機、また一部の居酒屋や回転ずしなどで購入したり食する食品に含まれる。長年気にはなっていたが、その数が多すぎて「どれがどう悪いのかよう分からん」とあきらめムードになっていた。たまたま薦められて、『体を壊す10大食品添加物』(渡辺雄二著・幻冬舎新書)を読んだ。10だったら、覚えて判別しやすい、「買わない」の実行に移せる。
中でも食品添加物は直接体に入ってくる。食品添加物には合成添加物と天然添加物があるが、合成添加物はいわゆる化学物質、431品目もある。スーパーやコンビニ、自販機、また一部の居酒屋や回転ずしなどで購入したり食する食品に含まれる。長年気にはなっていたが、その数が多すぎて「どれがどう悪いのかよう分からん」とあきらめムードになっていた。たまたま薦められて、『体を壊す10大食品添加物』(渡辺雄二著・幻冬舎新書)を読んだ。10だったら、覚えて判別しやすい、「買わない」の実行に移せる。 論点の一つはGIAHSをめぐる「官」と「民」の関係性だ。韓国農漁村研究院の朴潤鎬博士は「農業遺産を保全発展させるためには地域住民の主体性が必要」と述べた。会場の質問者(韓国)からも、「今回のワークショップでは国際機関や政府、大学のパネリストばかり、なぜ非政府組織(NGO)の論者がいないのか」といった質問も出された。これに対し、パネリストからは「農業遺産の民間の話し合いや交流事業も今後進めたい」(韓国)や、「日本のGIAHSサイトではNPOや農業団体が農産物のブランド化やツーリズムなど進めている」(日本)の意見交換がされた。確かに認定までのプロセスでは情報収集や国連食糧農業機関(FAO)との連絡調整といった意味合いでは政府や自治体とった「官」が主導権を取らざるを得ない。認定後はむしろ農協やNPOといった民間団体などとの連携がうまくいかどうかがキーポイントとなる。討論会では「地域住民主体のサミット」(朴潤鎬氏)のアイデアも出されるなど、「民」を包含したGIAHSのガバナンス(主体的な運営)では韓国側の声が大きかった。
論点の一つはGIAHSをめぐる「官」と「民」の関係性だ。韓国農漁村研究院の朴潤鎬博士は「農業遺産を保全発展させるためには地域住民の主体性が必要」と述べた。会場の質問者(韓国)からも、「今回のワークショップでは国際機関や政府、大学のパネリストばかり、なぜ非政府組織(NGO)の論者がいないのか」といった質問も出された。これに対し、パネリストからは「農業遺産の民間の話し合いや交流事業も今後進めたい」(韓国)や、「日本のGIAHSサイトではNPOや農業団体が農産物のブランド化やツーリズムなど進めている」(日本)の意見交換がされた。確かに認定までのプロセスでは情報収集や国連食糧農業機関(FAO)との連絡調整といった意味合いでは政府や自治体とった「官」が主導権を取らざるを得ない。認定後はむしろ農協やNPOといった民間団体などとの連携がうまくいかどうかがキーポイントとなる。討論会では「地域住民主体のサミット」(朴潤鎬氏)のアイデアも出されるなど、「民」を包含したGIAHSのガバナンス(主体的な運営)では韓国側の声が大きかった。 同島は、アジア初のスローシティー指定(2007年1月、カタツムリをシンボルに取り組んでいる)。また、オンドル石水田システムは韓国の「国家重要農業遺産」の第1号に選定(2013年1月)された。昼食は廃校となった中学を改装した「ヌリソム旅行学校」で。ここではツアー参加者が、サザエ、コメ粉、ニンジン、ネギを刻んでゴマ油でいためる郷土料理「チョンサンドタン」をつくり試食。スローフードのツーリズムが人気となっている。
同島は、アジア初のスローシティー指定(2007年1月、カタツムリをシンボルに取り組んでいる)。また、オンドル石水田システムは韓国の「国家重要農業遺産」の第1号に選定(2013年1月)された。昼食は廃校となった中学を改装した「ヌリソム旅行学校」で。ここではツアー参加者が、サザエ、コメ粉、ニンジン、ネギを刻んでゴマ油でいためる郷土料理「チョンサンドタン」をつくり試食。スローフードのツーリズムが人気となっている。 珍しいもの見た。「草墳(そうふん)」である。段々畑の一角にこんもりしたワラづくりの墓なのだ。遺体をその土葬せずに3年から5年間、木棺にワラと草と遺体を入れて、骨だけにする。その後に再び木棺を開けて洗骨し、骨を全部土葬する。骨を洗うのは長男ら家族だ。棺桶に草を入れるので草墳と称するらしい。
珍しいもの見た。「草墳(そうふん)」である。段々畑の一角にこんもりしたワラづくりの墓なのだ。遺体をその土葬せずに3年から5年間、木棺にワラと草と遺体を入れて、骨だけにする。その後に再び木棺を開けて洗骨し、骨を全部土葬する。骨を洗うのは長男ら家族だ。棺桶に草を入れるので草墳と称するらしい。