★歴史家の「闘争」
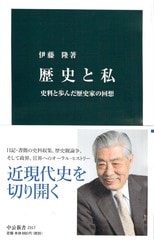 現在80歳超えた著者は東京大学や政策研究大学院大学で、日本近現代史を切り開いた研究者である。本の帯にも書かれている通り、若き日の共産党体験や、歴史観をめぐる論争、伊藤博文から佐藤栄作にいたる史料収集と編纂の経緯を回想している。著書の後半では、岸信介や後藤田正晴、竹下登らへのオーラル・ヒストリーの秘話やエピソードが綴られていて興味深い。
現在80歳超えた著者は東京大学や政策研究大学院大学で、日本近現代史を切り開いた研究者である。本の帯にも書かれている通り、若き日の共産党体験や、歴史観をめぐる論争、伊藤博文から佐藤栄作にいたる史料収集と編纂の経緯を回想している。著書の後半では、岸信介や後藤田正晴、竹下登らへのオーラル・ヒストリーの秘話やエピソードが綴られていて興味深い。
歴史学では主として文献から歴史を調べてゆくが、文献資料から知られる内容には限りがある。例えば、政策決定の過程を検討しようとしても、文献としては公表された結果のみで、どのようにそうした決定が行われたのかは、文書が残っていないことが多い(「ウィキペディア」引用)。オーラル・ヒストリー(oral history)は、当時の関係者にインタビューを行うことで、文書が残っていないことや、史料や文献からはわからないことを質問して、その史実や政策の過程などを埋めていく研究手法である。
このコラムの冒頭で「闘争」と表現したのも、インタビューする側とされる側は常に向き合い、対峙する場面もあるからだ。著書でも、元警察庁長官で中曽根内閣の官房長官をつとめた後藤田正晴氏へのインタビューでは、「なんで君たちは俺の話を聞くのか」と何度も逆に尋ねられたり、「突っかかってくるような感じだった」と。そして、後に著者の身元調査もされたことが後藤田氏本人から告げられ、著者は「後藤田さんはハト派だけれども、やっぱり警察なんだなと、思ったものです」とエピソードを述べている。インタビュー相手から逆に調べられるといった緊張感は、文献を漁る研究では得ることができない、フィールド研究の醍醐味なのだ。このほかにも、「昭和の妖怪」と呼ばれた政治家・岸信介やのオーラル・ヒストリーのエピソードも紹介している。内幕話では、読売新聞の渡邊恒雄氏へのインタビュー(1998年)がきっかけで、その連載を企画した中央公論社が読売新聞社に合併されるという「事件」も起きたこと。海千山千、手練手管の人物と貴重な証言を求めて対峙した回想録でもある。
著書は、こうしたエピソードや秘話、個人史を織り交ぜながら、日本の近現代史の面白さを伝えているだけでなく、最後の部分にあるように、膨大な史料を次世代へ引き継ぐ歴史家の責任も語っている。史料を発掘し、歴史を描き、そして史料を保存して公開する。著者の歴史家としての闘争はまだ続いていると察した。
⇒5日(日)朝・金沢の天気 くもり
 御所に進軍、また、久坂玄瑞は戦を避けたいと、意見が真っ向対立するが、結局、京にいる1500人の長州藩兵だけで、御所へ進軍することに決した。一方、西郷吉之助(隆盛)が薩摩藩兵を京に送り、幕府側は諸藩の兵あわせて2万人の大軍で御所の守り固める。
御所に進軍、また、久坂玄瑞は戦を避けたいと、意見が真っ向対立するが、結局、京にいる1500人の長州藩兵だけで、御所へ進軍することに決した。一方、西郷吉之助(隆盛)が薩摩藩兵を京に送り、幕府側は諸藩の兵あわせて2万人の大軍で御所の守り固める。 か」と一瞬思った。文字一句でも厳しい、あの教科書検定のチェックをスルリとかいくぐって、である。※掲載画像と本文はリンクしていません。
か」と一瞬思った。文字一句でも厳しい、あの教科書検定のチェックをスルリとかいくぐって、である。※掲載画像と本文はリンクしていません。
 イプが落ちてきて、ガクンと実際の床が下がり、キャーと観客(ゲスト)の悲鳴がする。自分自身もちょっと肝をつぶした。
イプが落ちてきて、ガクンと実際の床が下がり、キャーと観客(ゲスト)の悲鳴がする。自分自身もちょっと肝をつぶした。 く苦行の旅だったろう。そのときに浜辺のハマユウの白い花がなんともいとおしく思えた、そんな歌だったのだろうか。
く苦行の旅だったろう。そのときに浜辺のハマユウの白い花がなんともいとおしく思えた、そんな歌だったのだろうか。 以下、引用する。
以下、引用する。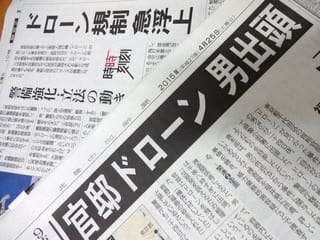 福井県警小浜署、40代の男が出頭して関与を認めたと、新聞・テレビのマスメディア報じている。
福井県警小浜署、40代の男が出頭して関与を認めたと、新聞・テレビのマスメディア報じている。 にと農家の若い人が意外と気を使って操縦している。コンバインや耕運機とは違い、農業と空飛ぶ工学機械のコラボレーションという感じがする。
にと農家の若い人が意外と気を使って操縦している。コンバインや耕運機とは違い、農業と空飛ぶ工学機械のコラボレーションという感じがする。
 ライ・ラマ14世は11日に金沢を離れた。市内の支援者からかつてこんな話を聞いたことがある。「ダライ・ラマ氏は金沢に前世からかかわりがあったという人がいて、いつもその人の家に宿泊するそうです」。「前世からかかわり」というのは、スピリチュアルな話でなので、定かではない。
ライ・ラマ14世は11日に金沢を離れた。市内の支援者からかつてこんな話を聞いたことがある。「ダライ・ラマ氏は金沢に前世からかかわりがあったという人がいて、いつもその人の家に宿泊するそうです」。「前世からかかわり」というのは、スピリチュアルな話でなので、定かではない。
 ク(富山‐羽田‐成田)で国内外へのフライトを考えれば当然、空の便も確保しておきたいと行政が必至になるのは当然だろう、と。
ク(富山‐羽田‐成田)で国内外へのフライトを考えれば当然、空の便も確保しておきたいと行政が必至になるのは当然だろう、と。