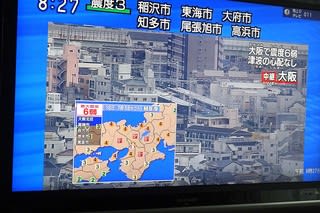★グランド・カバーの攻防 相手の巧みな戦術
それにしてもこの雑草は恐ろしいほどに手ごわい。向き合って戦いを挑んでも、必ず復活してくる。しかも、復活するとさらに茎を張りめぐらし、勢力を拡大しているのだ。これまでグランド・カバーの戦い(庭の雑草取り)で、いくつかの雑草と勝 負してきたが、レベルが格段に高い相手だ。その雑草の名はチドメグサ。漢字では「血止め草」と書き、学名は「Hydrocotyle sibthorpioides」。
負してきたが、レベルが格段に高い相手だ。その雑草の名はチドメグサ。漢字では「血止め草」と書き、学名は「Hydrocotyle sibthorpioides」。
チドメグサは実に巧妙に戦いを仕掛けてくる。その特徴は「隠れ蓑」戦術だろう。細い茎はよく枝分かれし、節から根を出して地面をはうのだが、芝生の生息地に入り込み、目立たないように勢力を拡大している。先日、「堂々と勝負しろ」と戦いを挑んだ。まず芝刈り機で芝生を刈り込み、隠れていた相手をリングに引きずり出した。
ところが、葉や茎は取れたが、芝生の根にチドメグサの根が絡まって離れようとしない。一本一本外すとなると膨大な労力と時間がかかる。「オレに勝ちたいのならば、芝生の根を絶やしてみろ」と不敵な笑みを浮かべているのだ。この日の戦いは午後7時を回り、時間切れでドローとなった。悔し涙がポロリと落ちた。
チドメグサとの戦いの第二幕は、スギゴケの庭での勝負となった。芝生ゾーンとは違って、スギゴケを刈り込むわけにはいかない。それだけに、相手の姿が見えにくい。葉と茎を1本取ったかと思ったら、隠れるように別の葉と茎がある。まるで分身があちこちにあり、根っ子がある本体が見つからない。これは忍法「空蝉(うつせみ)の術」だ。自分の分身を周囲につくり、敵の注意を分身に向けているのだ。根っ子がある本体はどこか。スギゴケをかき分けかき分け、チドメグサの根を探し出し、手繰り寄せるようにして抜く。こちらも誤って、大切にしているスギゴケを抜くこともある。
実に根気のいる勝負になると予測し、日曜日の午後に試合に挑んだ。ただ、気温がぐんぐんと上がり、水分補給も限界、熱中症が心配になり途中で退場した。すると、相手のせせら笑いが背後から聞こえた。「しょせん人間は弱い、オレたちに勝てるはずがない」と。闘争心がめらめらと燃えてきた。
⇒16日(月・海の日)夜・金沢の天気 はれ




 御像はどこですか」と小声でフランス人神父に尋ねた。実に七世代、250年もの隠れキリシタンの存在を知って驚いた神父はフランス、ローマに報告した。宗教史上、類まれなこの出来事が世界に広がった。
御像はどこですか」と小声でフランス人神父に尋ねた。実に七世代、250年もの隠れキリシタンの存在を知って驚いた神父はフランス、ローマに報告した。宗教史上、類まれなこの出来事が世界に広がった。