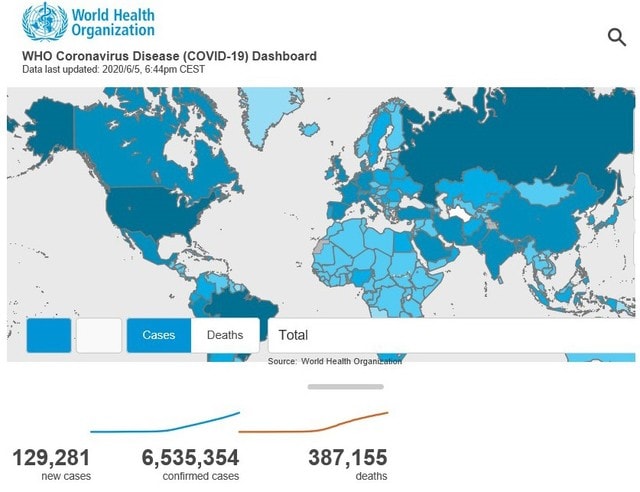☆持続可能な千枚田の風景~上
ことしの梅雨は過激だ。降るとなる激しい。きょう16日も金沢地方気象台は金沢など加賀地方で昼過ぎから夕方まで急な強い雨や落雷があると注意警戒情報を出している。今月11日に北陸は梅雨入りしたが、すでに石川県内の各地で土砂崩れなどが起きている。
深層崩壊から棚田をよみがえらせた2百年のレジリエンス
雨による土砂崩れをとくに警戒しているのは能登半島の尖端部分の日本海に面した、いわゆる外浦(そとうら)に住む人たちだろう。防災科学技術研究所「地滑り地形分布図データベース」によると、過去に起きた土砂崩れ現場は能登半島ではこの外浦と石川県と富山県の県境に集中している。滑りやすいリアス式 海岸の地形であることから大雨による土石流や地震による土砂災害、火山岩でできた凝灰岩の風化など要因がある。能登半島の里山里海をテーマに調査にでかけるとこの地に生きる人々の知恵に驚かされることもある。
海岸の地形であることから大雨による土石流や地震による土砂災害、火山岩でできた凝灰岩の風化など要因がある。能登半島の里山里海をテーマに調査にでかけるとこの地に生きる人々の知恵に驚かされることもある。
 輪島市白米町の千枚田は1004枚の棚田が海に向かって広がる=写真・上=。2001年に国の名勝に指定され、全国有数の観光地としても知られる。この地も地滑り地帯で、地元で語り継がれる「大(おお)ぬけ」と呼ばれる大規模災害が1684年(貞享元年)にあった。今の言葉でいう深層崩壊だ。その崩れた痕跡は今でも地肌がむき出しになった山側の斜面から見える。そして、田んぼのところどころに石に転がっていることからも、当時の様子が想像できる=写真・中=。その土砂崩れ現場を200年余りかけて、棚田としてよみがえらせた。
輪島市白米町の千枚田は1004枚の棚田が海に向かって広がる=写真・上=。2001年に国の名勝に指定され、全国有数の観光地としても知られる。この地も地滑り地帯で、地元で語り継がれる「大(おお)ぬけ」と呼ばれる大規模災害が1684年(貞享元年)にあった。今の言葉でいう深層崩壊だ。その崩れた痕跡は今でも地肌がむき出しになった山側の斜面から見える。そして、田んぼのところどころに石に転がっていることからも、当時の様子が想像できる=写真・中=。その土砂崩れ現場を200年余りかけて、棚田としてよみがえらせた。
 深層崩壊が起きた理由の一つが山からの地下水が地盤を軟弱化させた。棚田を再生するあたっては、逆にその地下水を田んぼに流し込み、その水がすべての田ぼに回るように水路設計が施された。つまり、用水からの分岐ではなく、田から田への水の流れである=写真・下。このため、地域の人たちは田起こしや田植えといった作業をほぼ同時に行うことで水の回しもよくすることができた。
深層崩壊が起きた理由の一つが山からの地下水が地盤を軟弱化させた。棚田を再生するあたっては、逆にその地下水を田んぼに流し込み、その水がすべての田ぼに回るように水路設計が施された。つまり、用水からの分岐ではなく、田から田への水の流れである=写真・下。このため、地域の人たちは田起こしや田植えといった作業をほぼ同時に行うことで水の回しもよくすることができた。
こうした知恵と工夫で災害地を生産地に回復させた、いわゆるレジリエンス(resilience)の事例として、国連食糧農業機関(FAO)が認定する世界農業遺産(GIAHS)で評価されている。
⇒16日(火)午前・金沢の天気 はれ

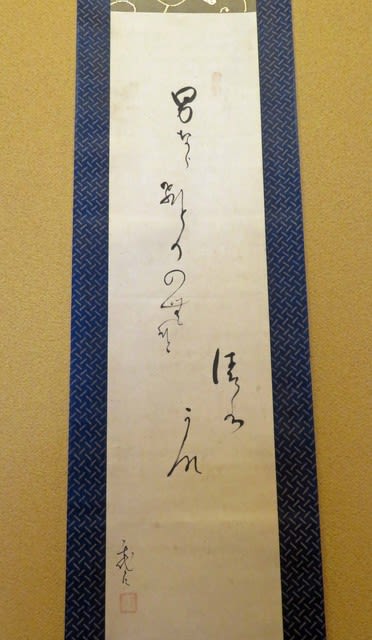


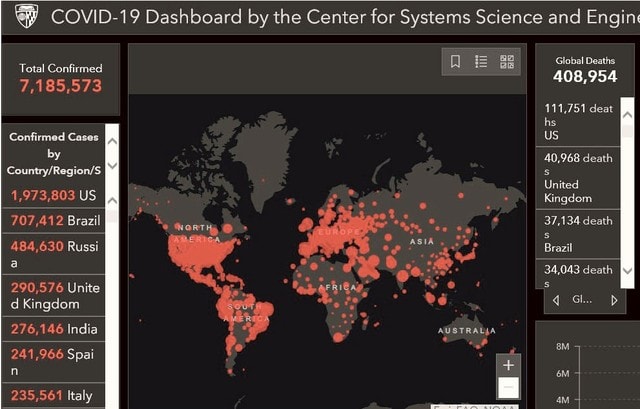


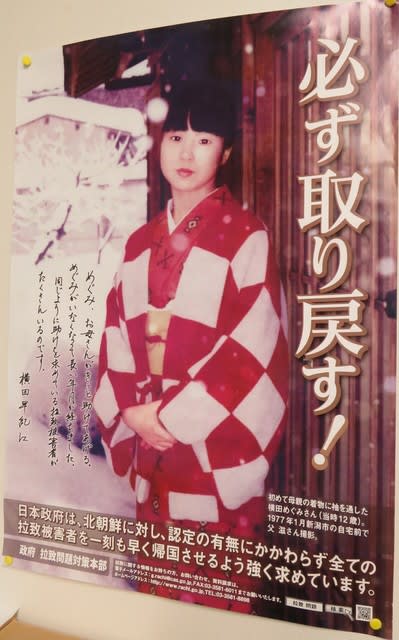
 警棒などが見つかった。
警棒などが見つかった。