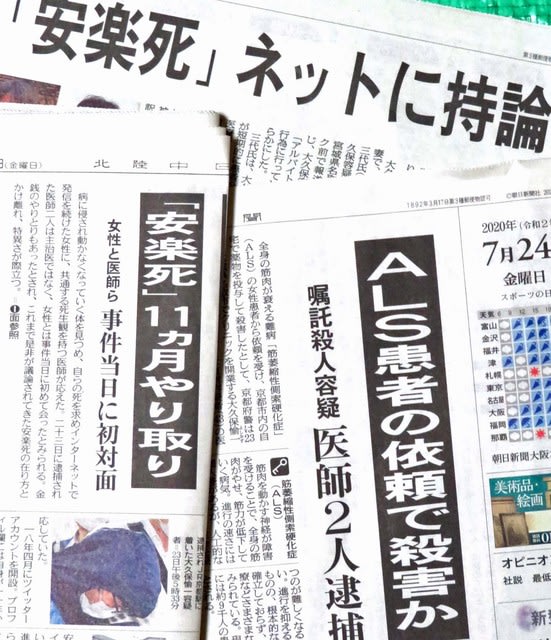☆北の非核化、泡と消ゆ
北朝鮮は核を手放さないとついに公言した。金正恩党委員長は27日に開かれた朝鮮戦争休戦67年の記念行事での演説で、核保有を正当化し一方的な核放棄に応じない立場を強調した(7月28日付・共同通信Web版)。朝鮮戦争に従軍した退役軍人らを平壌に招いた「老兵大会」での異例の演説。核抑止力によって国の安全が「永遠に保証される」と強調した(同)。
 2018年4月27日、板門店で開催された南北首脳会談では韓国の文在寅大統領と金氏との間では「完全な非核化」が明記された=写真・上=。さらに同6月12日の第1回の米朝首脳会談では、共同声明で「Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.(2018年4月27日の板門店宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む)」の文言を入れていた。
2018年4月27日、板門店で開催された南北首脳会談では韓国の文在寅大統領と金氏との間では「完全な非核化」が明記された=写真・上=。さらに同6月12日の第1回の米朝首脳会談では、共同声明で「Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.(2018年4月27日の板門店宣言を再確認し、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む)」の文言を入れていた。
ところが、2019年2月28日、ハノイでの第2回米朝首脳会談では、北の非核化に妥協しなかったトランプ大統領が先に席を立って会談は決裂した。おそらく金氏にとってこの会談は屈辱的だったのだろう。そしてついに今回、非核化を完全に反古する声明を出した。おそらく、南北首脳会談も、米朝首脳会談も今後開かれることはないだろう。そして、日本への脅威はさらに高まった。
では、日本国内では北からの核ミサイル攻撃に向けての防衛体制は進んでいるのだろうか。6月15日に河野防衛大臣が地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備計画を撤回すると表明してから40日余り経った。配備断念を受けて、自民党のミサイル防衛の在り方を検討するチームがきのう28日に続いてきょうも会合を開いた。政府に対する提言案が示された。相手の領域内でも弾道ミサイルの発射などを阻止する能力の保有も含め、政府として早急に検討して結論を出すよう求めつつ、攻撃的な兵器を保有しないという、これまでの政府方針を維持すべきだとしている。会合は非公開で、結局、提言案はまとまらなかった(7月29日付・NHKニュースWeb版)。
 日本海側に住めば北の脅威が実感できる。2017年3月6日、北朝鮮が「スカッドER」と推定される弾道ミサイルを4発発射し、そのうちの1発は能登半島から北に200㌔㍍の海上に着弾した=写真・下=。北が弾道ミサイルを撃ち込む標的の一つが能登半島だ。半島の先端・輪島市の高洲山(567㍍)には航空自衛隊輪島分屯基地のレーダーサイトがある。その監視レーダーサイトの目と鼻の先にスカッドERが撃ち込まれたのだ。
日本海側に住めば北の脅威が実感できる。2017年3月6日、北朝鮮が「スカッドER」と推定される弾道ミサイルを4発発射し、そのうちの1発は能登半島から北に200㌔㍍の海上に着弾した=写真・下=。北が弾道ミサイルを撃ち込む標的の一つが能登半島だ。半島の先端・輪島市の高洲山(567㍍)には航空自衛隊輪島分屯基地のレーダーサイトがある。その監視レーダーサイトの目と鼻の先にスカッドERが撃ち込まれたのだ。
これまで、南北首脳会談と米朝首脳会談に期待したが、北の非核化は泡と消えた。北からの核弾道ミサイルはいつでも飛んでくる。もちろん、監視レーダーサイトを能登半島から撤去せよという話ではない。
⇒29日(水)夜・金沢の天気 くもり