☆土砂降りの「内閣支持率」
この梅雨の時季、「線状降水帯」の言葉をテレビでいやほど聞いた。強烈な大雨は鹿児島や島根、鳥取の両県を襲い、熱海市では土砂崩れを誘発した。痛ましいばかりの光景だった。そして、土砂降りと言えば思い出すのが、北陸新幹線だ。忘れもしない2019年10月13日、台風10号の猛烈な雨の影響で、長野県の千 曲川が氾濫し、長野市の新幹線車両センターで10編成の北陸新幹線車両が水につかった。雪に強い北陸新幹線は案外にも雨にはもろかった。その想いが残った。
曲川が氾濫し、長野市の新幹線車両センターで10編成の北陸新幹線車両が水につかった。雪に強い北陸新幹線は案外にも雨にはもろかった。その想いが残った。
話は変わるが、土砂降りと言えば、菅内閣の内閣支持率にも豪雨が襲っている。NHKの最新の世論調査(7月9-11日)によると、菅内閣を「支持する」と答えた人は、先回より4ポイント下がって33%と、昨年9月の内閣発足以降で最も低くなった。一方、「支持しない」と答えた人は、1ポイント上がって46%で内閣発足以降で最も高くなった(7月12日付・NHKニュースWeb版)。
読売新聞の世論調査(7月9-11日)も、菅内閣の支持率は37%となり、昨年9月の内閣発足以降で最低だった前回の37%から横ばいだった。不支持率は53%(前回50%)に上がり、内閣発足後で最高となった。不支持率が支持率を上回るのは今年5月から3回連続。支持率低迷の背景には、政府の新型コロナウイルス対策や五輪対応への不満があるとみられる(7月12日付・読売新聞Web版)。
このままだと、政局は一気に揺らぐ可能性がある。メディア業界でよくささやかれるのは、内閣支持率の20%台は政権の「危険水域」、20%以下は「デッドゾーン」と。第一次安倍改造内閣の退陣(2007年9月)の直前の読売新聞の内閣支持率は29%(2007年9月調査)だった。その後の福田内閣は28%(2008年9月退陣)、麻生内閣は18%(2009年9月退陣)と、自民党内閣は支持率が20%台以下に落ち込んだときが身の引きどきだった。民主党政権が安倍内閣にバトンタッチした2012年12月の野田内閣の支持率は19%だった(数字はいずれも読売新聞の世論調査)。
菅内閣が「危険水域」に入るのは、あと8ポイント、さらに「デッドゾーン」へは、あと18ポイント下げたときだ。
(※写真は、今月12日、土砂災害に見舞われた熱海市の現場を視察する菅総理=総理官邸公式ホームページより)
⇒13日(火)夜・金沢の天気 くもり
 Byondコロナのセミナーでは、リモートワークが事例として論じられてきた。「働き方改革」は当時の安倍政権のテーマの一つだったが、進んでいるように見えなかった。ところが、コロナ禍でリモートワークやワーケーションという働き方が一気に加速した。日常の変化もある。コロナ禍で衛生観念が共有され、紙幣や硬貨にも触らないとい観念が広がり、キャッシュレス化も随分と進んだ。そして、日銀も現時点でデジタル法定通貨(CBDC)を発行する計画はないとしているが、決済システム全体の安定性と効率性を確保するよう準備するとしている。
Byondコロナのセミナーでは、リモートワークが事例として論じられてきた。「働き方改革」は当時の安倍政権のテーマの一つだったが、進んでいるように見えなかった。ところが、コロナ禍でリモートワークやワーケーションという働き方が一気に加速した。日常の変化もある。コロナ禍で衛生観念が共有され、紙幣や硬貨にも触らないとい観念が広がり、キャッシュレス化も随分と進んだ。そして、日銀も現時点でデジタル法定通貨(CBDC)を発行する計画はないとしているが、決済システム全体の安定性と効率性を確保するよう準備するとしている。 同湾にある小木漁港は全国で屈指のイカ類の水揚げを誇る。このことから町では特産イカの知名度向上にと昨年6月に観光交流センター「イカの駅つくモール」をオープンさせ、イカ料理などが味わえるレストランやイカの加工品を中心とした物産販売コーナーを設けた。さらセンターの芝生庭にことし4月に創ったのがイカキングだ。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、議論を呼んだ。
同湾にある小木漁港は全国で屈指のイカ類の水揚げを誇る。このことから町では特産イカの知名度向上にと昨年6月に観光交流センター「イカの駅つくモール」をオープンさせ、イカ料理などが味わえるレストランやイカの加工品を中心とした物産販売コーナーを設けた。さらセンターの芝生庭にことし4月に創ったのがイカキングだ。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、議論を呼んだ。 この都議に必要なのは記者会見を通して説明責任を果たすことではないだろうか。「心よりお詫び申し上げます」は自らの言葉で述べるべきであって、ホームページで発する言葉ではない。これでは誠意が有権者には伝わらない。問題の本質は、無免許運転での人身事故(今月2日)を故意に隠して4日の投開票日後に都民ファーストの会に報告したことだ。
この都議に必要なのは記者会見を通して説明責任を果たすことではないだろうか。「心よりお詫び申し上げます」は自らの言葉で述べるべきであって、ホームページで発する言葉ではない。これでは誠意が有権者には伝わらない。問題の本質は、無免許運転での人身事故(今月2日)を故意に隠して4日の投開票日後に都民ファーストの会に報告したことだ。 払うようにロシア側に申し入れを行うとともに、わが国周辺におけるロシア軍の活動を関心を持って注視していることを伝達をいたしました。わが国周辺において、演習や訓練を含めたロシア軍の活動が活発化する傾向にあります」
払うようにロシア側に申し入れを行うとともに、わが国周辺におけるロシア軍の活動を関心を持って注視していることを伝達をいたしました。わが国周辺において、演習や訓練を含めたロシア軍の活動が活発化する傾向にあります」 近から発射し、いずれも約450㌔飛行。日本の領海域には到達せず、EEZの外に落下した。北朝鮮の弾道ミサイル発射は昨年3月29日以来だった。事前通告なしに発射が繰り返されている。
近から発射し、いずれも約450㌔飛行。日本の領海域には到達せず、EEZの外に落下した。北朝鮮の弾道ミサイル発射は昨年3月29日以来だった。事前通告なしに発射が繰り返されている。 た。四女らは特別抗告していたが、最高裁は今月2日付で退ける決定をした。これにより、松本元死刑囚の遺骨は次女に引き渡すとした決定が確定した(7月5日付・テレビ朝日ニュースWeb版)。
た。四女らは特別抗告していたが、最高裁は今月2日付で退ける決定をした。これにより、松本元死刑囚の遺骨は次女に引き渡すとした決定が確定した(7月5日付・テレビ朝日ニュースWeb版)。 がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。
がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。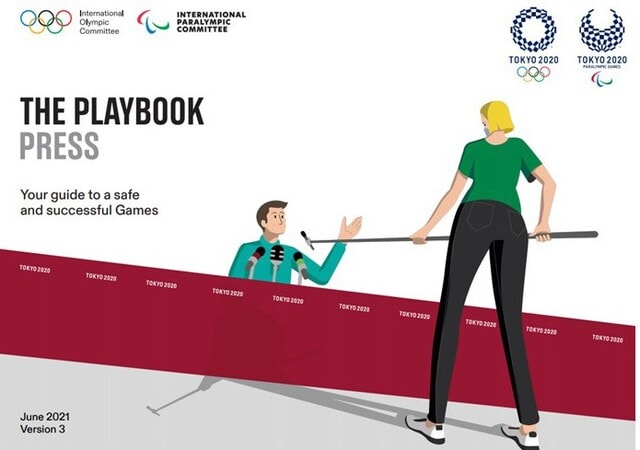 抗議の論点は主に2つ。日本と海外のメディアの取材陣にはソーシャルディスタンス(2㍍以上)を守り、ワクチン接種をしてマスクを着用することが前提となっている。しかし、日本人記者には自由な取材が認められているのに、海外メディアの記者には観客へのインタビューや都内での取材が制約される。こうした取材制限は不公平で、外国人記者を標的にした行き過ぎた規制だ。また、スマートフォンの位置情報(GPS)をオンにして知らせることになっているが、このGPS情報がどのように使われるのか不安があり、報道の自由が阻害されないよう、メディア側にもアプリの使われ方を検証する機会を与えよと求めている。
抗議の論点は主に2つ。日本と海外のメディアの取材陣にはソーシャルディスタンス(2㍍以上)を守り、ワクチン接種をしてマスクを着用することが前提となっている。しかし、日本人記者には自由な取材が認められているのに、海外メディアの記者には観客へのインタビューや都内での取材が制約される。こうした取材制限は不公平で、外国人記者を標的にした行き過ぎた規制だ。また、スマートフォンの位置情報(GPS)をオンにして知らせることになっているが、このGPS情報がどのように使われるのか不安があり、報道の自由が阻害されないよう、メディア側にもアプリの使われ方を検証する機会を与えよと求めている。 つか建っていた=写真=。夕食を終え、帰り道、それらのマンションからは明かりがほとんど見えない。おそらく、買って値上がりするのを待つ投資向けマンションなのだろう。前年の2011年6月に訪れた首都・北京でも夜に明かりのないマンションがあちこちにあった。
つか建っていた=写真=。夕食を終え、帰り道、それらのマンションからは明かりがほとんど見えない。おそらく、買って値上がりするのを待つ投資向けマンションなのだろう。前年の2011年6月に訪れた首都・北京でも夜に明かりのないマンションがあちこちにあった。