☆田の神にもてなしを演じる「奥能登のあえのこと」
能登半島の北部、奥能登で伝承される農耕儀礼「田の神さま」がきょう各農家で営まれた。この行事は2009年のユネスコ無形文化遺産で、「奥能登のあえのこと」として登録されている。「あえ」は「饗」、「こと」は「祭事」の意で饗応する祭事を指す。
一つの行事なのに、2つの呼び方がある。地元の人はこの行事のことを、「タンカミサン(田の神さま)」と言う。かつて、この地の伝統行事を取材に訪れた民俗学者の柳田国男が一部地域で称されていた「あえのこと」を論文などで紹介し、それが1977年に国の重要無形民俗文化財に、そしてユネスコ無形文化遺産の登録名称になった。もともとこの農耕儀礼には正式な名称というものがなかった。
 能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」では毎年公開で儀礼を行っていて、今回40人余りが見学に訪れていた。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、人数に制限を設けたようだ。
能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」では毎年公開で儀礼を行っていて、今回40人余りが見学に訪れていた。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、人数に制限を設けたようだ。
田の神はそれぞれの農家の田んぼに宿る神であり、農家によって田の神さまにまつわる言い伝えが異なる。夫婦二神、あるいは独神の場合もある。共通していることは、目が不自由なこと。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂で目を突いてしまったなど諸説がある。
目が不自由であるがゆえに、農家の人たちはその障がいに配慮して田の神に接する。座敷に案内する際に段差がある場合は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らしながら、独り芝居を演じる。
「能登はやさしや土までも」と江戸時代の文献にも出てくる言葉がある。この農耕儀礼は健常者のちょっとした気遣いと行動で、障害者と共生する場を創ることができることを教えてくれる。「もてなし(ホスピタリティー)」や「分け隔てのない便益(ユニバーサルサービス)」の原点がここにあるのではないかと考える。
(※写真は能登町「合鹿庵」で執り行われた農耕儀礼「あえのこと」行事。田の神にもてなしを演じる中正道さん)
⇒5日(月)夜・金沢の天気 くもり
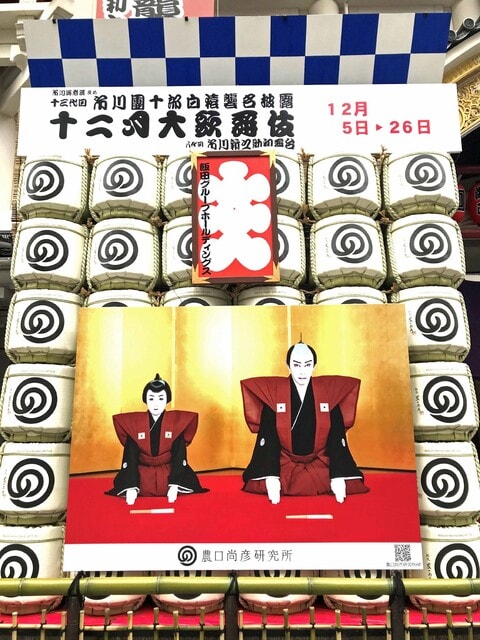 メージを超えた華やかな味わいだ。農口杜氏から「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造った」と説明があった。低温で熟成させるため新鮮な香りがする。500本限定の特別Ver。御年90歳の杜氏のさらなる挑戦でもある。
メージを超えた華やかな味わいだ。農口杜氏から「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造った」と説明があった。低温で熟成させるため新鮮な香りがする。500本限定の特別Ver。御年90歳の杜氏のさらなる挑戦でもある。 きょうは騒がしい朝を迎えた。何しろ、一時バシャバシャとまるで土砂降りのような音がした。あられだった。登校途中の児童たちは傘を差したまま立ち止まっていた。怖かったのだろう。金沢で初あられ。
きょうは騒がしい朝を迎えた。何しろ、一時バシャバシャとまるで土砂降りのような音がした。あられだった。登校途中の児童たちは傘を差したまま立ち止まっていた。怖かったのだろう。金沢で初あられ。 もう一つの騒がしさ。テレビメディアは再び「ドーハの歓喜」だ。サッカーのワールドカップカタール大会。グループEの日本は、第3戦でスペインと対戦し2-1で勝って1次リーグ2勝1敗とし、決勝トーナメントへの進出を決めた。正直な話が、FIFAランキング24位の日本が、7位のスペインに勝てるとは思えなかった。午前4時という試合時間も厳しく、中継番組の視聴はあきらめた。きょう午前7時30分ごろに冒頭の土砂降りのようなあられの降りに目覚めて、寝床でスマホを見て勝利を知った。
もう一つの騒がしさ。テレビメディアは再び「ドーハの歓喜」だ。サッカーのワールドカップカタール大会。グループEの日本は、第3戦でスペインと対戦し2-1で勝って1次リーグ2勝1敗とし、決勝トーナメントへの進出を決めた。正直な話が、FIFAランキング24位の日本が、7位のスペインに勝てるとは思えなかった。午前4時という試合時間も厳しく、中継番組の視聴はあきらめた。きょう午前7時30分ごろに冒頭の土砂降りのようなあられの降りに目覚めて、寝床でスマホを見て勝利を知った。 のうち、審査で1本が認定された。「煌」第1号は重さ15.5㌔で体長94㌢の大物だ。例年、寒ブリは比較的高値がついても15万円から20万円なので、ブランド化によって今回は20倍ほど値が上がったことになる。
のうち、審査で1本が認定された。「煌」第1号は重さ15.5㌔で体長94㌢の大物だ。例年、寒ブリは比較的高値がついても15万円から20万円なので、ブランド化によって今回は20倍ほど値が上がったことになる。 資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。
資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。 ケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になってきた。
ケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になってきた。 テレビ中継を視聴していたが、日本はドイツ戦からスタメンを5人入れ替え、堂安選手や相馬選手らを起用して臨んで、前半は無得点で折り返し。後半36分、日本は先制ゴールを奪われた。以下、サッカーに詳しい知人の分析。
テレビ中継を視聴していたが、日本はドイツ戦からスタメンを5人入れ替え、堂安選手や相馬選手らを起用して臨んで、前半は無得点で折り返し。後半36分、日本は先制ゴールを奪われた。以下、サッカーに詳しい知人の分析。 コスタリカもドイツ戦に勝てば勝ち点6となり、通過の可能性もある。さまさに混戦、サッカーの醍醐味ではある。
コスタリカもドイツ戦に勝てば勝ち点6となり、通過の可能性もある。さまさに混戦、サッカーの醍醐味ではある。 例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。
例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。 CBSは詳細に伝えている。日本人サポーターたちは、開幕戦(現地時間11月20日)のカタール対エクアドル戦が行われた後、自分たちの国が参加する試合でもないにもかかわらず、スタジアムのスタンド席に置き去りにされていたボトルや食べ残しを拾い、ごみ袋に入れる姿が見られた。バーレーンのあるインフルエンサー氏が、サポーターの行いを映像で記録し、自身のインスタグラムで共有した。インフルエンサー氏はこのサポ-ターになぜごみを片付けるのを手伝ったのかと尋ねた。すると、そのサポーターは 「私たちは日本人で、ごみを残さないし、この場所を尊敬している」 と語った、と伝えている。
CBSは詳細に伝えている。日本人サポーターたちは、開幕戦(現地時間11月20日)のカタール対エクアドル戦が行われた後、自分たちの国が参加する試合でもないにもかかわらず、スタジアムのスタンド席に置き去りにされていたボトルや食べ残しを拾い、ごみ袋に入れる姿が見られた。バーレーンのあるインフルエンサー氏が、サポーターの行いを映像で記録し、自身のインスタグラムで共有した。インフルエンサー氏はこのサポ-ターになぜごみを片付けるのを手伝ったのかと尋ねた。すると、そのサポーターは 「私たちは日本人で、ごみを残さないし、この場所を尊敬している」 と語った、と伝えている。 日本サッカー界の育ての親はドイツ人のデットマール・クラマー氏(故人)。同氏は日本サッカー界初の外国人コーチであり、サッカー日本代表の基礎をつくり、日本サッカーリーグの創設にも尽力したことから「日本サッカーの父」と称された人だ(Wikipedia「デットマール・クラマー
日本サッカー界の育ての親はドイツ人のデットマール・クラマー氏(故人)。同氏は日本サッカー界初の外国人コーチであり、サッカー日本代表の基礎をつくり、日本サッカーリーグの創設にも尽力したことから「日本サッカーの父」と称された人だ(Wikipedia「デットマール・クラマー