★能登の里山景観にマッチする「木造長屋」の仮設住宅
能登半島地震の被災地に行くと、プレハブの仮設住宅が目立つようになってきた。石川県では8月までに仮設住宅6400戸余りを整備するとしている。知人から輪島市南志見地区に木造の仮設住宅があると聞いて見に行った(今月3日)。
現地に赴くと、黒瓦で壁面は木板、1棟に4戸の玄関戸がついていた=写真=。外観だけを見ると「長屋」というイメージだ。この木造タイプの仮設住宅は全部で27棟で、1DKや2DKを中心に計100戸になる。知人によると、木造の仮設 住宅はプレハブと比べて長く使用でき、輪島市では原則2年間の入居期間後も市営住宅に転用するなど被災者が長く住み続けることができるようにする計画だという。確かに、プレハブより木造の仮設住宅の方が住み慣れるかもしれない。
住宅はプレハブと比べて長く使用でき、輪島市では原則2年間の入居期間後も市営住宅に転用するなど被災者が長く住み続けることができるようにする計画だという。確かに、プレハブより木造の仮設住宅の方が住み慣れるかもしれない。
仮設住宅の建設が進む一方で、全半壊となった住宅の撤去作業は思うように進んではいない。馳県知事の記者会見(4月25日)によると、所有者に代わって自治体が解体撤去する「公費解体」はこれまでに申請数が8528棟あったものの、着手は244棟にとどまっている。申請の受理から解体着手までには、自治体職員らによる現地調査や住民の立ち会いが必要で、手続きの調整がネックとなっている。
このため、連休明けの今月上旬から、市町が委託する書類審査や費用算定を行う専門のコンサルタント職員を6割増員し、公費解体の手続きを集中的に進めるとしている。さらに、解体事業者らで構成する5人1チームの作業班を新たに500から600班編成し、現地に投入することで作業のペースを加速させる。来年10月の完了を目指す(4月25日・知事記者会見)。大型連休明けから復旧・復興の勢いが加速することを期待したい。
⇒7日(火)夜・金沢の天気 くもり
 同地区は現実問題に直面している。地域メディア各社の報道によると、地区の区長が3月4日に輪島市役所を訪れ、同地区内に仮設住宅を設置するよう申し入れた。金蔵では地震前に53世帯95人が暮らしていたが、現在はそのうちの70人が金沢市などへ避難し、現在は25人に減少している。避難した多くの世帯は地元に仮設住宅ができれば金蔵に戻る意向を示していると区長は説明した。
同地区は現実問題に直面している。地域メディア各社の報道によると、地区の区長が3月4日に輪島市役所を訪れ、同地区内に仮設住宅を設置するよう申し入れた。金蔵では地震前に53世帯95人が暮らしていたが、現在はそのうちの70人が金沢市などへ避難し、現在は25人に減少している。避難した多くの世帯は地元に仮設住宅ができれば金蔵に戻る意向を示していると区長は説明した。 4月28日に投票が行われた衆院3補欠選挙で自民党が不戦敗を含め全敗した。このころから、にわかに衆院解散・総選挙が取り沙汰されるようになった。「6月23日の今国会会期末か」とか、「9月の自民党総裁選の後か」などと。このような新聞・テレビのニュースやコメンテーターの論調を目にするたびに、「能登半島地震のことを忘れるな」と言いたくなる。
4月28日に投票が行われた衆院3補欠選挙で自民党が不戦敗を含め全敗した。このころから、にわかに衆院解散・総選挙が取り沙汰されるようになった。「6月23日の今国会会期末か」とか、「9月の自民党総裁選の後か」などと。このような新聞・テレビのニュースやコメンテーターの論調を目にするたびに、「能登半島地震のことを忘れるな」と言いたくなる。 あす5日は「こどもの日」。今月3日に訪れた輪島の被災地では、焼け跡の近くにこいのぼりが掲げられていた=写真・上=。地域の住民が一日も早い復旧・復興を祈って掲げたのかも知れないと勝手に想像を膨らませた。
あす5日は「こどもの日」。今月3日に訪れた輪島の被災地では、焼け跡の近くにこいのぼりが掲げられていた=写真・上=。地域の住民が一日も早い復旧・復興を祈って掲げたのかも知れないと勝手に想像を膨らませた。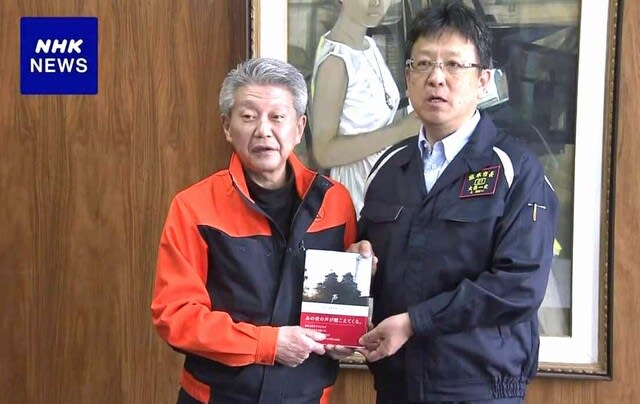 がないと前を向いて歩けない。芸術祭を復興に向けての光にしたい」と答弁した。予定より3週間遅れで開催にこぎつけ、14の国・地域のアーティストたちによる61作品が市内を彩った。このとき、震災にめげずに芸術祭をやり遂げたとの印象が県民にも広く根付いたのではないだろうか。
がないと前を向いて歩けない。芸術祭を復興に向けての光にしたい」と答弁した。予定より3週間遅れで開催にこぎつけ、14の国・地域のアーティストたちによる61作品が市内を彩った。このとき、震災にめげずに芸術祭をやり遂げたとの印象が県民にも広く根付いたのではないだろうか。 わっていないように見えた。続いて千枚田を見に行った。一部田起こしが行われていたが、ほかに地割れが入った田の修復作業も行われていた。
わっていないように見えた。続いて千枚田を見に行った。一部田起こしが行われていたが、ほかに地割れが入った田の修復作業も行われていた。 別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。
別の数字もある。石川県教委の発表(4月27日)によると、今月12日時点で奥能登2市2町の児童・生徒の数は小学生が1266人、中学生が770人だった。 去年5月時点と比べ小学生が453人、中学生が191人、合わせて644人減少していることが分かった。単純に計算すれば、小中合せて児童・生徒数が24%減少したことになる。震災をきっかけに奥能登を離れた家庭が増えたと推測される。