★「歴史的な旅に出る」
「国連生物多様性の10年」のキックオフイベントが17日午後、石川県立音楽堂(金沢市)であり、記念式典と基調講演に出席した。「国連生物多様性の10年」は去年10月の名古屋市で開かれた生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で、NGOの提言をもとに日本政府が国連に提唱し採択されたもの。国連は今年から2020年までの10年間を生態系を守る集中的な行動期間と定めた。COP10では、生態系保全のためにそれぞれの国が2020年までに実行すべき目標を定めた「愛知ターゲット」を採択していて、金沢でのキックオフイベントで目標達成に向けてスタートを切ることになる。
 式典は30ヵ国から政府関係者が集まりにぎやかだった。でも、なぜ金沢で開催するのか、と疑問符がつく。歓迎レセプションで谷本正憲石川県知事と、武内和彦国連大学副学長(東京大学教授)がその理由を明かした。キックオフイベントは環境省と国連大学などが中心となって5月に東京で開催する方向で準備が進んでいた。ところが3月11日に東日本大震災、そして福島の原発事故などがあり、中止となった。「愛知ターゲット」を何とかスタートさせたいと思いを募らせた関係者に浮かんだアイデアが、昨年12月「国際生物多様性年クロージングイベント」を開催した金沢市でキックオフイベントができないか、だった。会場はどこでもよいという訳にはいかない。生物多様性という意味合いが地域で理解され、これに協力的で、国際会議の開催経験があり、しかもそれなりの開催費も負担する自治体となると絞られてくる。知事はどうやら武内氏らに懇願され最終的に引き受けたらしい。
式典は30ヵ国から政府関係者が集まりにぎやかだった。でも、なぜ金沢で開催するのか、と疑問符がつく。歓迎レセプションで谷本正憲石川県知事と、武内和彦国連大学副学長(東京大学教授)がその理由を明かした。キックオフイベントは環境省と国連大学などが中心となって5月に東京で開催する方向で準備が進んでいた。ところが3月11日に東日本大震災、そして福島の原発事故などがあり、中止となった。「愛知ターゲット」を何とかスタートさせたいと思いを募らせた関係者に浮かんだアイデアが、昨年12月「国際生物多様性年クロージングイベント」を開催した金沢市でキックオフイベントができないか、だった。会場はどこでもよいという訳にはいかない。生物多様性という意味合いが地域で理解され、これに協力的で、国際会議の開催経験があり、しかもそれなりの開催費も負担する自治体となると絞られてくる。知事はどうやら武内氏らに懇願され最終的に引き受けたらしい。
記念式典でアフメド・ジョグラフ生物多様性事務局長=写真=は「次世代を担う子どもたちの間でも生物多様性の認知度は低い。分かりやすく説明することから始める必要がある。日本の良寛は最後に残すことは何かと問われ『春の花、丘になく鳥、秋の紅葉』と言った。愛知ターゲットの達成に向けてこれから国際社会は歴史的な旅に出る。選択肢はない」と呼びかけた。また、2012年10月にハイデラバードでCOP11を開催するインドのヘム・パンデ環境森林省担当局長は「インドも生物多様性の恩恵を受けている。COP11のスローガンを『もし私たちが自然を保護すれば、自然は私たちを守ってくれる』としたい」と述べた。
2008年5月にボンで初めてジョグラフ氏を知り、COP9とCOP10でのスピーチを、また金沢大学でもスピーチ(2009年5月)をいただいた。その中でも、今回のジョグラフ氏の「歴史的な旅に出る。選択肢はない」の言葉が一番強く印象を受け、覚悟のようにも聞こえた。
⇒18日(日)朝・金沢の天気 くもり
 ただ、この挨拶も度が過ぎるというのもある。ちょうど6年前の2005年12月17日、いきなり金沢市内で50㌢という積雪に見舞われた。こうなると挨拶どころか、ケンカを売っているようにも思える。「人間ども見ておれ、自然をなめるなよ」といった感じだ。すると、人々は「ちょっと待ってくださいよ。二酸化炭素の排出などで地球は温暖化に向かっているのではないですか。それなのになぜ大雪なのですか」と思ってしまう。すると自然の声もさらに荒々しくなる。「地球温暖化は人間が引き起こしていると思っているようだが、オレに言わせれば、地球の寒冷期がたまたま温暖期に入ったわけで、これはオレが差配している自然のサイクルだ。今後雪を降らせないとか少なくするとかは一体誰が決めたんだ、それは人間の勝手解釈だろう。オレは降らせるときはガツンと降らす。2008年1月にはバクダットにも雪をプレゼントしてやったよ」と。北陸という土地柄では、冬空を見上げながら自然と対話ができる。1936年に世界で初めて人工雪を作ることに成功し、雪の結晶の研究で知られる中谷宇吉郎(1900-62、石川県加賀市出身)は「雪は天から送られた手紙である」という言葉を遺している。
ただ、この挨拶も度が過ぎるというのもある。ちょうど6年前の2005年12月17日、いきなり金沢市内で50㌢という積雪に見舞われた。こうなると挨拶どころか、ケンカを売っているようにも思える。「人間ども見ておれ、自然をなめるなよ」といった感じだ。すると、人々は「ちょっと待ってくださいよ。二酸化炭素の排出などで地球は温暖化に向かっているのではないですか。それなのになぜ大雪なのですか」と思ってしまう。すると自然の声もさらに荒々しくなる。「地球温暖化は人間が引き起こしていると思っているようだが、オレに言わせれば、地球の寒冷期がたまたま温暖期に入ったわけで、これはオレが差配している自然のサイクルだ。今後雪を降らせないとか少なくするとかは一体誰が決めたんだ、それは人間の勝手解釈だろう。オレは降らせるときはガツンと降らす。2008年1月にはバクダットにも雪をプレゼントしてやったよ」と。北陸という土地柄では、冬空を見上げながら自然と対話ができる。1936年に世界で初めて人工雪を作ることに成功し、雪の結晶の研究で知られる中谷宇吉郎(1900-62、石川県加賀市出身)は「雪は天から送られた手紙である」という言葉を遺している。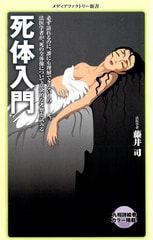 金沢大学の共通教育授業でマスメディア論を教えている。その中で、学生たちに問いかけるテーマの一つが、「マスメディアはなぜ遺体、あるいは死体の写真や映像を掲載・放送しないのか」という論点である。東日本大震災での遺体写真の掲載については、新聞各社は原則、死体の写真を掲載していない。被災地の死者(死体)の尊厳を貶めることにもなりかねないとの各社の判断があり、あえて掲載していない。リアルな現場というのは、遺体(死体)の写真をストレートに見せることはしなくても、なんらかの見せ方によって、犠牲者の多さや無念の死というものを表現することは可能との意見が多い。そのような話を周囲の研究者にすると、「では、これを読んでみてください」と薦められたのがこの本だった。マスメディアで掲載・放送するしないの論議以前の話として、日常生活で遺体(死体)と接することがめったになく、遺体(死体)そのものについて我々は無知である。これでは何も語れない、イメージと感情だけで論じることに等しいと思い、向学のために本を注文した。
金沢大学の共通教育授業でマスメディア論を教えている。その中で、学生たちに問いかけるテーマの一つが、「マスメディアはなぜ遺体、あるいは死体の写真や映像を掲載・放送しないのか」という論点である。東日本大震災での遺体写真の掲載については、新聞各社は原則、死体の写真を掲載していない。被災地の死者(死体)の尊厳を貶めることにもなりかねないとの各社の判断があり、あえて掲載していない。リアルな現場というのは、遺体(死体)の写真をストレートに見せることはしなくても、なんらかの見せ方によって、犠牲者の多さや無念の死というものを表現することは可能との意見が多い。そのような話を周囲の研究者にすると、「では、これを読んでみてください」と薦められたのがこの本だった。マスメディアで掲載・放送するしないの論議以前の話として、日常生活で遺体(死体)と接することがめったになく、遺体(死体)そのものについて我々は無知である。これでは何も語れない、イメージと感情だけで論じることに等しいと思い、向学のために本を注文した。 最初の訪問地は能登ワイン株式会社(石川県穴水町)。2000年からブドウ栽培をはじめ、2006年より醸造を開始している。初出品した国産ワインコンクールで、「能登ロゼ」(品種マスカットベリーA)が銅賞(2007年)、「心の雫」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銅賞(2010年)、そして、ことし2011年で「クオネス」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銀賞を受賞した。年々実力をつけている。
最初の訪問地は能登ワイン株式会社(石川県穴水町)。2000年からブドウ栽培をはじめ、2006年より醸造を開始している。初出品した国産ワインコンクールで、「能登ロゼ」(品種マスカットベリーA)が銅賞(2007年)、「心の雫」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銅賞(2010年)、そして、ことし2011年で「クオネス」(品種ヤマソーヴィニヨン・赤)が銀賞を受賞した。年々実力をつけている。 ていく。もう一つ。能登の土壌で育つブドウはタンニン分が少ない。それをフレンチ・オークやアメリカン・オークの樽で熟成させることでタンニンで補う。するとワインの味わいの一つである渋みが加わる。そのような話を聞くだけでも、「風味」が伝わってくる。
ていく。もう一つ。能登の土壌で育つブドウはタンニン分が少ない。それをフレンチ・オークやアメリカン・オークの樽で熟成させることでタンニンで補う。するとワインの味わいの一つである渋みが加わる。そのような話を聞くだけでも、「風味」が伝わってくる。