★「地デジ」以降‐上‐
サイレント層へのケア
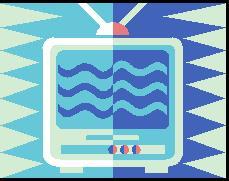 25日付の新聞報道によると、24日未明から同日午後6時までに総務省のコールセンターには9万8千件の電話相談や苦情があった。NHKには午後8時までに3万1千件、民放各社には午後7時までに1万6千件、まとめると14万5千件に上る。
25日付の新聞報道によると、24日未明から同日午後6時までに総務省のコールセンターには9万8千件の電話相談や苦情があった。NHKには午後8時までに3万1千件、民放各社には午後7時までに1万6千件、まとめると14万5千件に上る。
24日午後4時からNHK・民間放送連盟(民放連)による記者会見があった。月刊ニューメディアの吉井勇編集長からのメールレターによると、「12時以降に電話が殺到しましたが、時間を経るに従い、通常の範囲のコールになった」(松本NHK会長)、「心配していた混乱もなく、しっかりとした対応をいただいた」(廣瀬民放連会長)とメディア側は、地デジに向けた最大の転換であるアナログ停波が無事に成し遂げたということに安どの表情を浮かべた。
問題は、電話をかける人ではなく、電話をかけないサイレント層である。目に浮かぶのは、「テレビはついているだけでいい」という独り暮らしのお年寄り世帯だ。たとえば、能登地方の夜道を歩くと、玄関や居間の電気は消され、テレビの画面だけがまるでホタルの光のようにポツンとついている様子が窓越しにうかがえる。80歳以上の独り暮らし世帯が全国150万ともいわれている。文句も言わず、細々と生きている。気がかりなのはこうした層である。民生委員の手でチューナーは届けられているかもしれないが、はたしてうまく設置させているだろうか。特に都市部は「無縁社会」という言葉もあるように、お年寄りの死すら気づかれないほどに人々の関係性が希薄である。
テレビは単に電波政策上ではなく、お年寄りの福祉という観点でとらえる必要がある。このブログで何度か書いたが、昨年7月24日に全国に先駆けてアロナグを停波した能登半島・珠洲地区ではこうしたお年寄りの単身世帯を中心に街の電器屋がローラーをかけてチューナーを取り付け、リモコンの操作説明をした。4回も通ってようやくリモコン操作が可能になったお宅があった、との話も聞いた。このような手厚いケアが全国でなされたのだろうか。
⇒25日(月)夜・金沢の天気 くもり
