☆震災とマスメディア-3-
ユニバーサル・サービスに好感、では7・24はどうなる
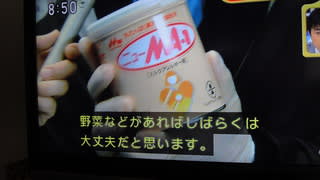 健常者でも障がい者で同じようにマスメディアから情報を得ることをユニバーサル・サービスという。内閣の、たとえば総理や官房長官の会見では、小画面に手話通訳者が出ている。会見場に手話通訳があることで、聴覚障がい者がリアルタイムでテレビから情報を得ることができる。今回の震災は原発事故と連動したため、メディアによるリアルタイムの放送に被災者の耳目が集まる。内閣の伝えようとする意志が見える。災害会見の手話放送はこれ以降、定番化するのではないだろうか。
健常者でも障がい者で同じようにマスメディアから情報を得ることをユニバーサル・サービスという。内閣の、たとえば総理や官房長官の会見では、小画面に手話通訳者が出ている。会見場に手話通訳があることで、聴覚障がい者がリアルタイムでテレビから情報を得ることができる。今回の震災は原発事故と連動したため、メディアによるリアルタイムの放送に被災者の耳目が集まる。内閣の伝えようとする意志が見える。災害会見の手話放送はこれ以降、定番化するのではないだろうか。
好感の持てることばかりではない。震災でCMスポンサーが減っているせいで、CMの空き枠に公共広告機構(AC)のCMがやたらと入っている。しかも、「思いやり」や「生物多様性」など種類が少なく、繰り返しの放送で、このACが画面に流れると、チャンネルサーフィン(切り替え)を始めてしまう。もう条件反射のようになっている。それに、最後の「AC」というサウンドがうるさいと思う。これは視聴者が誰しも感じていることではないだろうか。番組のフォーマットでCM枠がすでに固定化されているので、CMスポンサーが少ないからと言って、CM枠を間引くことはできないのだ。民放の宿命だろう。
被災地の民放には同情する。放送そのものもさることながら、電波を視聴者に届ける前線である中継設備では、ミニサテと呼ぶ小さな局が多数損傷を受けているだろうことは想像に難くない。電気不通によるトラブル、それをカバーする自家発の燃料を届けられないこともあるだろう。テレビ局には、国の放送免許と引き換えに放送電波を人々が「あまねく」受信できるように設備を整えることが使命として課せられている(放送法第2条の6)。震災という困難なときほど使命が問われる。
3月17日、民放連会長による定例会見があった。注目されたのは、ことし7月24日に予定されているアナログ停波(デジタル完全移行)のスケジュールをそのままで進めるのかという点だった。東北地方はデジタル未対応の世帯が少なくない。広瀬道貞会長は「7月24日に(アナログ波を)停波できるような環境作りに対し、歩みを止める必要はない。全国一斉が原則。私自身は(震災でも)引き延ばす理由はないと思っている」、「人とお金をかけ、(地デジへの)切り替えができる環境を作ることが大切」とし、支援策としてデジタル対応テレビを支給するよう政府に求めていきたいと述べた(毎日新聞インターネット版)。難題が次々と。
⇒22日(火)朝・金沢の天気 くもり
