★テレビは進化するのか
先日、TBS系列のテレビ局の知人と会食した。話題になったのが、来年春の番組改編で始まるゴールデンタイムでの大型ニュース番組(平日午後5時50分-7時50分)について。ゴールデンタイムにニュース番組を持ってくる試みは他系列でもプランはあったが実現していない。ある種の賭けだ。が、知人は「いや、時代の流れだ」と改編のポイントを3つ紹介してくれた。一つには、ゴールデンタイムにお笑いタレントを動員して視聴率を稼ごうとするするテレビ局の意図に少なからぬ反発が視聴者にある。二つめのとして、ニュース番組は50代以上の世代に視聴されており、高齢者化社会に対応した番組づくりとなる。三つ目の要素は、番組制作費の上でVTRの使い回しがきくなどニュース番組はバラエティ番組をつくるよりコストダウンになるということだ。経済リセ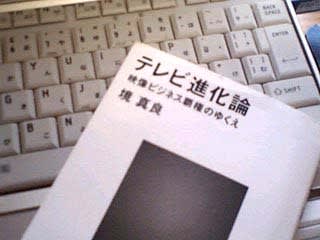 ッションが、「番組の構造改革」ともいえる大胆な編成に背中を押した、ともいえる。
ッションが、「番組の構造改革」ともいえる大胆な編成に背中を押した、ともいえる。
金沢大学でメディア論を講義していて、私自身よく使う言葉は「テレビにあすはあるか」である。国の免許事業で成り立つビジネスモデルは「最後の護送船団」であり、同じメディアでも新聞などと比べると経営の足腰が「ひ弱」に思える。経済不況の荒波を乗り越え、次世代に進む秘策はあるのか。このヒントとなるのが、「テレビ進化論~映像ビジネス覇権のゆくえ~」(境真良著・講談社現代新書・2008)である。著者は経済産業省メディアコンテンツ課などを経て、早稲田大学で教鞭を執る。コンテンツ流通のプロである。
著者は挑発的だ。「メディア・コンテンツ産業の本質は娯楽産業」だと言い切り、しかし、「『娯楽の価値』を認められない官僚の心理傾向が、問題の奥底に潜んでいる」と。単純に読み込めば、護送船団の枠の中でいる限り(監督官庁の顔色を伺っていると)、コンテンツの本流である娯楽に徹した産業にはなり得ない、と。挑発がもう一つ。「コンテンツ産業にとってパソコンと付き合うことは、常にビジネスが海賊版によって壊滅的な打撃を受ける可能性に晒されることと同義なのである」と。マイクロソフトなどはパソコン(PC)を「テレビを呑み込む商品」と見定めて戦略を練り、PC上で動画が自由に動く仕組みを構築してきた。そのおかげで、ユーチューブやGyaoとったサービスが始まった。ところが、テレビはPCとの連携を標榜しながらも、心の奥底に「放送と通信の融合」を避けている。実は前述のようにテレビがPCが呑み込まれることを恐れている。もう一つ、家電メーカーもPCがテレビに置き換わることを恐れている。PCは利益率が低いからだ。それでも著者は「情報と通信の融合」を恐れるな、恐れていては「次のテレビ」はないとぞと、ギョーカイ(テレビ業界)を叱咤しているように感じる。
では、「次のテレビ」とは何か。著者は2004年にネット上で話題になった「グーグルゾン(Googlezon)」をイメージして説明している。要約する。マイクロソフトと戦ってきたグーグルとアマゾンが合併し、その情報サービスの開発競争の中で、ネット上にある新聞ニュースを始めとする様々なデータから新聞記事のような意味ある情報に再編集する技術を開発してしまう。つまり、ネット上で公開された情報がすべてグーグルゾンに利用されてしまうことになった。憤慨したニューヨーク・タイムズ社がグーグルゾンを相手に著作権訴訟を起こすが、敗訴する。ニューヨーク・タイムズ社はネット上から退場し、単なる紙媒体の企業となる。一方のグーグルゾンは世界中のネット上の情報とPC利用者の個人情報を管理する巨大企業へと成長するというストーリーだ。
「次のテレビ」の要は、視聴者が欲しがる番組をネット上で取り出せる仕組みをつくることだ。グーグルゾンは極端な話ではあるが、使ってよい番組コンテンツを限定し、ユーザーが「マイ・チャンネル」をつくれるような巨大なハードディスクレコーダをネット上で構築することである。著者は、「つまり、『次のテレビ』とは、ニューヨーク・タイムズとケンカをしないような、穏健型の映像版『グーグルゾン』なのである」と説明している。
著者が紹介する「次なるテレビ」のくだりから、「10年後、新聞とテレビはこうなる」(藤原治著・朝日新聞社・2007)で紹介されている「eプラットフォーム」を連想した。冒頭に述べたように、いまテレビ業界では編成上での「番組の構造改革」が起きようとしている。おそらく次の改革は経営改革(系列の持ち株会社)、そして2011年の完全デジタル化にともなうメディアとネットの融合・再編へと進むシナリオだろう。そのときに「次のテレビ」あるいは「eプラットフォーム」が熱く論じられることに期待したい。
⇒21日(日)朝・金沢の天気 くもり
