★メディア縦乱‐5
農業と環境の問題にいち早く警鐘を鳴らしたレチェル・カーソンは1960年代に著した「サイレント・スプリング(沈黙の春)」に、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農薬を使った農業で収量は上がったが、生き物は静かになったと警告したのだ。最近、ある現象を肌で感じた。
「そして人は静かになった」
 「パソコンのキーボードはにぎやかだが、人は静かになった」。所用である会社を訪ねると、社員は黙々とパソコンに向かっている。受け付けのカウンターに来訪者が来ても、誰も席を立って応対しようとしない。「あのう」と声をかけて、ようやく振り向く。朝なのに、その職場には「おはよう」とあいさつを交わす言葉も飛び交っていない。沈黙の職場だった。おそらく、隣の席との会話もやり取りはメールで行なっているに違いない。
「パソコンのキーボードはにぎやかだが、人は静かになった」。所用である会社を訪ねると、社員は黙々とパソコンに向かっている。受け付けのカウンターに来訪者が来ても、誰も席を立って応対しようとしない。「あのう」と声をかけて、ようやく振り向く。朝なのに、その職場には「おはよう」とあいさつを交わす言葉も飛び交っていない。沈黙の職場だった。おそらく、隣の席との会話もやり取りはメールで行なっているに違いない。
「固定電話のベルはにぎやかだが、人は受話器を取ろうとしない」。最近よく「自宅にいると固定電話に恐怖に感じる」と耳にする。日中かかる電話はセールスやらアンケートがやたらと多く、応対にうんざりする。しつこく何度でもかかってくる電話もある。受話器を取っても、「はい、○○ですが」とこちらから名乗らないという人が多い。オレオレ詐欺もある。ヘタに電話に出るととんでもことになる、いっそうのこと固定をなくし、携帯電話だけでもよいと考えている人が意外と多い。
「テレビはにぎやかだが、人は見ていない」。テレビはつけておくだけ、という人が増えている。CM総合研究所は、3ヶ月ごとに実施するモニターへのテレビ視聴実態調査で各年齢層のテレビ視聴パターンを「ながら視聴」と「専念視聴」に分けてデータを採集している。それだと、テレビ視聴時間のうち「専念視聴」と「ながら視聴」はそれぞれ5割。つまり、半分の時間はなんとなくテレビをつけているだけ。「テレビは第2の空気」化しているのである。
パソコン、電話、テレビを象徴的に取り上げたが、われわれを取り巻くの通信手段やメディアの有り様が変化しているように思える。そして、人は知らず知らずのうちにコミュニケーション能力を失いつつある。レチェル・カーソンの「サイレント・スプリング」流にいえば、「パソコン、電話、テレビはにぎやかだが、人は静かになった」。これはある意味で次に到来する社会の予兆かもしれない。ちょっと気が重い。
⇒26日(火)夜・金沢の天気 くもり
 【お詫び】2月4日付で「北京オリンピック」を放送するかのような誤った番組広報情報を報道各社にリリースしてしまいました。日本民間放送連盟を除名され、現状では「北京オリンピック」の放送ができないにもかかわらず、このような事態をまねき、視聴者の皆様はじめ、関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、深く陳謝いたします。改めて今回の件を肝に銘じ、原因の究明と再発防止に努め、再生への取り組みに邁進してまいる所存です。
【お詫び】2月4日付で「北京オリンピック」を放送するかのような誤った番組広報情報を報道各社にリリースしてしまいました。日本民間放送連盟を除名され、現状では「北京オリンピック」の放送ができないにもかかわらず、このような事態をまねき、視聴者の皆様はじめ、関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、深く陳謝いたします。改めて今回の件を肝に銘じ、原因の究明と再発防止に努め、再生への取り組みに邁進してまいる所存です。 以下、朝鮮日報の記事を要約して紹介する。海洋汚染を防ぐため、1972年に採択された「ロンドン条約1972」は、海にゴミを投棄することを厳しく規制している。これまでに81カ国がこの条約を批准しており、韓国も93年にようやく批准した。ところが韓国政府は、地上のゴミ埋立地が不足していることや、生ゴミの埋め立てによって悪臭や地下水の汚染といった公害が発生していることを理由に、88年からゴミの海洋投棄を認めてきた。93年にロンドン条約を批准した後もそれは続いてきた。廃棄物の海洋投棄にかかる費用は、種類によっては陸上処分に比べ90%近くも安くつくため、廃棄物処理業者はゴミを海に捨ててきた、という。
以下、朝鮮日報の記事を要約して紹介する。海洋汚染を防ぐため、1972年に採択された「ロンドン条約1972」は、海にゴミを投棄することを厳しく規制している。これまでに81カ国がこの条約を批准しており、韓国も93年にようやく批准した。ところが韓国政府は、地上のゴミ埋立地が不足していることや、生ゴミの埋め立てによって悪臭や地下水の汚染といった公害が発生していることを理由に、88年からゴミの海洋投棄を認めてきた。93年にロンドン条約を批准した後もそれは続いてきた。廃棄物の海洋投棄にかかる費用は、種類によっては陸上処分に比べ90%近くも安くつくため、廃棄物処理業者はゴミを海に捨ててきた、という。 なぜメディアが対応を迫られているかというと、分かりやすく言えば、プロの裁判官と違って、評決に加わる一般市民はテレビや新聞の報道に引きずられる可能性があるとの懸念が司法側にあるからだ。踏み込んで言えば、容疑者や被告を犯人(有罪)と決めつける、いわゆる「犯人視報道」が裁判員に予断を与える恐れがあるというのだ。
なぜメディアが対応を迫られているかというと、分かりやすく言えば、プロの裁判官と違って、評決に加わる一般市民はテレビや新聞の報道に引きずられる可能性があるとの懸念が司法側にあるからだ。踏み込んで言えば、容疑者や被告を犯人(有罪)と決めつける、いわゆる「犯人視報道」が裁判員に予断を与える恐れがあるというのだ。 ディプロマ・ミル問題が明らかになったのは、私が勤める金沢大学。文科省は昨年末に公表した全大学・短大を対象にした調査で、44大学の教員49人の非認定学位が、採用・昇進の際に経歴に記載されていたと公表した。それを詳細に取材フォローした1月26日付の朝日新聞によると、金沢大学医学部保健学科で理学療法を教える男性教授は、2002年にニューポート大学の博士号を取得した。03年にこの学位も記載した書類で選考に臨み、助教授から教授に昇進した。教授選考では、業績、博士の学位、教育の経験など3つの条件が総合的に判断される。選考過程で「ニューポート大とは何だ」と話題になったが、業績が優れているため昇進が認められたという。また、同じく医学部保健学科の女性准教授(看護学)は1997年にこれも同じくニューポート大の修士号を取得して経歴に載せ、99年に講師から昇進した、との記事内容だった。
ディプロマ・ミル問題が明らかになったのは、私が勤める金沢大学。文科省は昨年末に公表した全大学・短大を対象にした調査で、44大学の教員49人の非認定学位が、採用・昇進の際に経歴に記載されていたと公表した。それを詳細に取材フォローした1月26日付の朝日新聞によると、金沢大学医学部保健学科で理学療法を教える男性教授は、2002年にニューポート大学の博士号を取得した。03年にこの学位も記載した書類で選考に臨み、助教授から教授に昇進した。教授選考では、業績、博士の学位、教育の経験など3つの条件が総合的に判断される。選考過程で「ニューポート大とは何だ」と話題になったが、業績が優れているため昇進が認められたという。また、同じく医学部保健学科の女性准教授(看護学)は1997年にこれも同じくニューポート大の修士号を取得して経歴に載せ、99年に講師から昇進した、との記事内容だった。 上記のように書くと、農薬を使った農業者を悪者扱いしてしまうことになるが、私自身は、都市住民のニーズにこたえ、農産物をひたむきに生産してきた農業者を責めるつもりは一切ない。東京で有機農産物の販売を手がける「ポラン・オーガニック・フーズ・デリバリ」社長の神足義博氏も、「これまで都市住民に農産物を供給してきた農業者に『ありがとうございました』とまずお礼を言おう。そして、『これからどうやってなるべく農薬を使わない農産物をつくることができるかいっしょに考えましょう』とお願いをしよう」と提唱している(08年2月1日の講演)。有機農産物を増産するためには、全体的な方向転換しかない。トキやコウノトリが生息できる農村の環境を再生するためには地域の合意形成がどうしても必要なのだ。その合意形成は、過去の批判からは始まらない。
上記のように書くと、農薬を使った農業者を悪者扱いしてしまうことになるが、私自身は、都市住民のニーズにこたえ、農産物をひたむきに生産してきた農業者を責めるつもりは一切ない。東京で有機農産物の販売を手がける「ポラン・オーガニック・フーズ・デリバリ」社長の神足義博氏も、「これまで都市住民に農産物を供給してきた農業者に『ありがとうございました』とまずお礼を言おう。そして、『これからどうやってなるべく農薬を使わない農産物をつくることができるかいっしょに考えましょう』とお願いをしよう」と提唱している(08年2月1日の講演)。有機農産物を増産するためには、全体的な方向転換しかない。トキやコウノトリが生息できる農村の環境を再生するためには地域の合意形成がどうしても必要なのだ。その合意形成は、過去の批判からは始まらない。 本当に害鳥だったのか。機中で読んでいた「コウノトリの贈り物~生物多様性農業と自然共生社会をデザインする」(地人書館・鷲谷いづみ編)によると、兵庫県豊岡市でもコウノトリはかつて「稲を踏み荒らす」とされ、追い払われる対象だった。ところが野生のコウノトリを県と市の職員が観察調査(05年5月)したところ、稲を踏む率は一歩あたり1.7%、60歩歩いて1株踏む確率だった。これを総合的に評価し、「これくらいだと周囲の稲が補うので、減収には結びつかない」としている。それが「害鳥」の烙印をいったん押され、言い伝えられるとイメージが先行してしまう。今回の中国のトキ調査でも同行した新潟大学の本間航介氏は「農村の閉塞状況の中でつくられた犠牲ではないか」(08年1月26日・シンポジウムでの発言)という。つまり、つらい農作業の中で、ストレスのはけ口の対象としてトキやコウノトリが存在したのではないか、との指摘である。
本当に害鳥だったのか。機中で読んでいた「コウノトリの贈り物~生物多様性農業と自然共生社会をデザインする」(地人書館・鷲谷いづみ編)によると、兵庫県豊岡市でもコウノトリはかつて「稲を踏み荒らす」とされ、追い払われる対象だった。ところが野生のコウノトリを県と市の職員が観察調査(05年5月)したところ、稲を踏む率は一歩あたり1.7%、60歩歩いて1株踏む確率だった。これを総合的に評価し、「これくらいだと周囲の稲が補うので、減収には結びつかない」としている。それが「害鳥」の烙印をいったん押され、言い伝えられるとイメージが先行してしまう。今回の中国のトキ調査でも同行した新潟大学の本間航介氏は「農村の閉塞状況の中でつくられた犠牲ではないか」(08年1月26日・シンポジウムでの発言)という。つまり、つらい農作業の中で、ストレスのはけ口の対象としてトキやコウノトリが存在したのではないか、との指摘である。 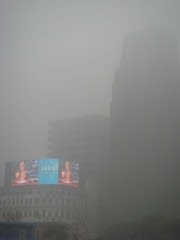 1月11日から4日間、短期間だったが、中国・陝西(せんせい)省を訪れた。冬のトキを観察する狙いがあった。新年度からトキに関する「生態環境整備および地域合意形成に関する学際研究」を始めるに当たって、どうしても一度見ておきたいと思い調査団に加えてもらった。金沢大学の「里山プロジェクト」(研究代表者・中村浩二教授)に関わっていて、トキと共生できるような里山環境を再生しようというのが、研究の狙い。どこからトキを持ってきて放すといった力技の利いた話ではない。
1月11日から4日間、短期間だったが、中国・陝西(せんせい)省を訪れた。冬のトキを観察する狙いがあった。新年度からトキに関する「生態環境整備および地域合意形成に関する学際研究」を始めるに当たって、どうしても一度見ておきたいと思い調査団に加えてもらった。金沢大学の「里山プロジェクト」(研究代表者・中村浩二教授)に関わっていて、トキと共生できるような里山環境を再生しようというのが、研究の狙い。どこからトキを持ってきて放すといった力技の利いた話ではない。