☆メモる2007年-5-
おそらく新聞も書けないし、テレビ局も報じることはことはできない「もう一つの2011年問題」がある。話が余りにもややこしく、業界の話なので理解を超える面がある。しかし、確実に今見ているテレビが視聴できなくなる人たちが続出することになる。ワーキング・プアではない、チャンネル・プアになる話だ。それは今、ケーブルテレビで見ている隣県の民放テレビ局が視聴できなくなるかもしれないという「区域外再送信問題」のことである。
チャンネル・プアになる日
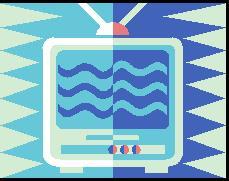 大学の講義でメディア論を担当している。その中で、著作権と放送法の概論は必須なのだが、著作権より放送法の説明が難しく、とくに「県域主義」や「県域免許」などを学生に理解してもらうのにひと苦労する。「県域主義」や「県域免許」とは放送免許は基本的に県単位で与えられており、隣県にはなるべく電波が飛ばないようしてある。しかし、学生はこういうふうに解釈する。「地域のニュースや番組を充実させるためというのは理解できるが、なぜそれが県単位でなければならないのか、電波そのものをブロックできないのに」と。そこでふと考えた。今回の区域外再送信の問題がこじれて、民放局がケーブルテレビ局に「同意せず」を連発すると、テレビ業界の閉鎖性がむしろ世論で問題視され、マイナスイメージが先行するのではないか、と。
大学の講義でメディア論を担当している。その中で、著作権と放送法の概論は必須なのだが、著作権より放送法の説明が難しく、とくに「県域主義」や「県域免許」などを学生に理解してもらうのにひと苦労する。「県域主義」や「県域免許」とは放送免許は基本的に県単位で与えられており、隣県にはなるべく電波が飛ばないようしてある。しかし、学生はこういうふうに解釈する。「地域のニュースや番組を充実させるためというのは理解できるが、なぜそれが県単位でなければならないのか、電波そのものをブロックできないのに」と。そこでふと考えた。今回の区域外再送信の問題がこじれて、民放局がケーブルテレビ局に「同意せず」を連発すると、テレビ業界の閉鎖性がむしろ世論で問題視され、マイナスイメージが先行するのではないか、と。
CATVの区域外再送信にはそれぞれ地域事情や故事来歴があり、デジタル化を機に「同意しない」とすんなり縁切りができるものかどうか、そう簡単ではない。私は1990年代の後半、北陸朝日放送(本社・石川県金沢市)の業務部にいて、隣県(富山、福井)のCATVの区域外再送信を担当した一人だった。北陸3県おける唯一のテレビ朝日系のフルネット局が北陸朝日放送である。チャンネル格差に不満の声を上げたのは東京や大阪から富山、福井にきた転勤族だった。「北陸にきたら『ニュースステーション』を見ることができない。疎外感を感じる」。このような投書が地元新聞社に掲載された。そうした声は両県の県議会でも取り上げられた。この世論がバックにあって、CATV局が地元民放局の確認が得て、石川が発局の区域外再送信がまとまった。
その後、両県で次々とCATV局が立ち上がり、「ニュースステーション」を“売り”に加入契約者を急速に増やした。当時、富山と福井の地元新聞社に北陸朝日放送のテレビ欄をフルサイズで掲載できないか働きかけるのが私の仕事だった。
では、地デジの区域外再送信は可能だろうか。すでに北陸朝日放送の番組がキラーコンテンツとしてCATVに組み込まれ、新聞社のテレビ欄も地元局と同じサイズになっている。富山では実質4局目、そして福井では3局目(あるいは4局目)と地元局では受け止めているだろう。事実、CATVを含む「その他視聴率」が富山ではゴールデンタイムで10%を超える日があるという。これが地元局のGRPの低下をもたらし、セールス枠に支障をきたしているとなれば、地元3局は「(区域外再送信を)確認しない」のは十分理解できる。また、民放連の方針に従えば、北陸朝日放送はCATV側が地元局の確認を取らない限り、発局として同意はできない。
ところが、放送法に基づく県域免許制度で貫かれた民放のスタンスであったとしても、冒頭の学生たち、一般視聴者あるいはCATV契約者たちには「テレビ局の論理で振舞っている」としか映らないかもしれない。これまで北陸における区域外再送信の問題を取り上げたが、これからは一般論として述べる。
事態が行き詰っても、テレビ局側もCATV側もお互い一番選択してほしくない、したくない手段が「大臣裁定」だろう。確実に同じ地域でしこりを残すことになるからだ。そこで両者が話し合うための条件について、いくつか提案したい。それは第一に、CATV側はアナログの区域外再送信を既得権のように主張しないことだ。たとえば、「視聴習慣がついた市民・県民ら視聴者にサービスができなくなる」などという論調だ。ケーブルテレビの加入契約者は、民放局がいう視聴者とは概念が異なる。加入契約者はあくまでも任意のペイヤー(支払い者)であり、民放局が「あまねく」放送するところの地域住民の全体ではない。それをCATV側が「視聴者のために」とひと括りにして表現することに、民放局側は強い違和感を持つことになる。視聴者が何を望んでいて、視聴者の支持を得るためにどのような番組を作ればよいのかと腐心しているからだ。両者のこの行き違いがある限り、論議のスタート台には立てない。
民放側とケーブルテレビ側の個別協議では限界がある。そこで、大臣裁定に極力持ち込まない一つの方策として、地元で第3者による裁定機関をつくってはどうかと考える。県や自治体の行政は入れず、経済界と一般市民で構成された機関である。民放局側とCATV側が経済界に事務局の設立を含めてお任せするのである。民放局側はここで地域のテレビ局の存続が危うくなることを訴え、CATV側はチャンネル格差の解消を地域課題として問えばよい。地元民放局もCATVも潰したくない、そして多くのチャンネルを視聴したいと思う気持ちは皆同じである。経済界にも共通認識を持ってもらえば知恵や提案も出てくる。区域外再送信の問題は政治決着ではなく、地域の課題として解決する「地域力」に期待したい。
⇒20日(木)朝・金沢の天気 くもり
