★メディアのツボ-52-
東京六大学春季リーグ早稲田VS慶応の「早慶戦」(6月2日、3日・神宮球場)が異常な盛り上がりだ。両大学ともすでに2日間の学生チケット1万4千枚が完売したことがニュースとなったほどだ。
早慶戦と日テレ
 盛り上がりの要因は三つある。一つは、昨夏の甲子園で駒大苫小牧を破り優勝投手となった「ハンカチ王子」こと早稲田のルーキー、斎藤佑樹投手(18)の人気だろう。二つ目が、早稲田はルーキー斎藤の活躍もあり現在、8勝0敗の勝ち点4で首位を走っているので、今週末の早慶戦で1勝すれば2季連続の優勝が決まる。三つ目がこれまで東京六大学野球はNHKが中継してきたが、今季から日本テレビが参入し、早稲田戦を中心にBSなどで放送するなどブームを煽っている。
盛り上がりの要因は三つある。一つは、昨夏の甲子園で駒大苫小牧を破り優勝投手となった「ハンカチ王子」こと早稲田のルーキー、斎藤佑樹投手(18)の人気だろう。二つ目が、早稲田はルーキー斎藤の活躍もあり現在、8勝0敗の勝ち点4で首位を走っているので、今週末の早慶戦で1勝すれば2季連続の優勝が決まる。三つ目がこれまで東京六大学野球はNHKが中継してきたが、今季から日本テレビが参入し、早稲田戦を中心にBSなどで放送するなどブームを煽っている。
ちなみに、試合開始時間は2日、3日とも午後1時からで、地上波ではNHKが教育で2日の早慶1回戦を午後1時から、3日の2回戦を午後2時から放送。日本テレビも2回戦を午後2時55分から3時20分までスペシャル番組として生中継する。25分の生中継というのは短い番組枠だが、試合終盤のよいとこ取りを狙っているようだ。斎藤投手の胴上げを期待しているのかもしれない。
ところで、早慶戦と日テレにはちょっとした因果関係がある。もう50年以上も前のことだ。1953年8月、民放テレビの開局の一番乗りを果たした日テレは最初のバラエティ番組「ほろにがショー 何でもやりまショー」を始めた。タイトルの「ほろにがショー」のネーミングは、朝日麦酒(現・アサヒビール)がスポンサーだったため。
番組は視聴者参加型で、ゲームに挑戦し優勝者には賞金が渡された。放送開始2ヶ月で1年先まで出演予約があったほどの人気だったが、「事件」が起きた。56年11月3日放送分の番組で、「今度の早慶戦に、早稲田側の応援席で慶応の大旗を振って応援した人に5000円(当時)を進呈」(要約)というお題を出し、これに乗った視聴者の1人が実際にお題を実行、番組ではこの内容を放送し、授与式を行った。ところが、放送終了後に批判や抗議が相次ぎ、六大学野球連盟は日テレでの中継を拒否した。思わぬ展開に日テレは番組内で謝罪し、六大学野球連盟とは和解した。
しかし、これだけでは済まなかった。辛口のジャーナリストで知られた大宅荘一がこの番組を視聴していて、翌年2月の週刊誌で「テレビに至っては、紙芝居同様、否、紙芝居以下の白痴番組が毎日ずらりと列んでいる。ラジオ、テレビという最も進歩したマスコミ機関によって、『一億総白痴化』運動が展開されていると言って好い」とテレビ批判の大論陣を張るのである。
この一億総白痴化論は、テレビによって受動的に映し出される映像を眺めて、流れて来る音声を聞くだけだと、人間の想像力や思考力が低下し、愚民化するという論理である。その後、作家の松本清張らも主張し、現代でも鋭い文明批評で知られる月尾嘉男氏は「古代ローマ帝国を滅ぼしたのはパンとサーカス、現代日本のテレビはサーカスである」と同論理でテレビ批判を展開している。
テレビ批判を招いた元祖がこの51年前の早慶戦と日テレ番組だったとうわけだ。時代はその後どう変わったか、果たして大宅の主張は正しかったのか、別の機会で検証したい。
⇒31日(木)朝・金沢の天気 あめ
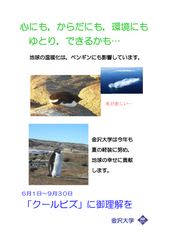
 地元の人たちが「有線」と言っているシステムがある(※4月30日付「メディアのツボ-51-」参照)。同町にケーブルテレビ(CATV)網はなく、同町で有線放送と言えば、スピーカーが内臓された有線放送電話(地域内の固定電話兼放送設備)のこと。この有線放送電話にはおよそ2900世帯、町の8割の世帯が加入する。
地元の人たちが「有線」と言っているシステムがある(※4月30日付「メディアのツボ-51-」参照)。同町にケーブルテレビ(CATV)網はなく、同町で有線放送と言えば、スピーカーが内臓された有線放送電話(地域内の固定電話兼放送設備)のこと。この有線放送電話にはおよそ2900世帯、町の8割の世帯が加入する。 そこで、金沢大学近くにあるPCの修理店に持ち込んだ。店員は、OSを再インストールする必要があるという。そして念のために、ハードディスクがどんな状態かみてもらった。すると、反応がない。コツコツと軽くたたいても反応がない。店員は「やられていますね」と。つまり、壊れている。この一言で頭の中が真っ白になった。ファイルなどのデータは全滅。なかには翌日(21日)と次週28日のメディア論の授業で使うパワーポイントも入っていたのだ。
そこで、金沢大学近くにあるPCの修理店に持ち込んだ。店員は、OSを再インストールする必要があるという。そして念のために、ハードディスクがどんな状態かみてもらった。すると、反応がない。コツコツと軽くたたいても反応がない。店員は「やられていますね」と。つまり、壊れている。この一言で頭の中が真っ白になった。ファイルなどのデータは全滅。なかには翌日(21日)と次週28日のメディア論の授業で使うパワーポイントも入っていたのだ。 S教授はインド哲学が専門で、自ら僧籍にもあった。酒を飲み、タバコも手放さなかった。急逝する前夜も知人と楽しく酒を飲んでいた、という。遺族の話では「人間ドックにひっかかるものは何もなかった」。社会貢献室の室長であり、大学教育開放センター長という学外に開かれたセクションの現場責任者だった。センター長室の机には花が飾られ、「未決」の決済箱には本人が印を押はずだった書類がたまっていた。
S教授はインド哲学が専門で、自ら僧籍にもあった。酒を飲み、タバコも手放さなかった。急逝する前夜も知人と楽しく酒を飲んでいた、という。遺族の話では「人間ドックにひっかかるものは何もなかった」。社会貢献室の室長であり、大学教育開放センター長という学外に開かれたセクションの現場責任者だった。センター長室の机には花が飾られ、「未決」の決済箱には本人が印を押はずだった書類がたまっていた。 能登で生まれ、金沢で高校時代を過ごした。2年生の冬、クラブはESSに所属していて、県英語弁論大会に出場する幸運に恵まれた。高校は同大会で4連勝を果たしていて、5度目の栄誉がかかっていた。このため、前年度優勝者の先輩からイントネーションや発音の厳しいチェックを受けたことを覚えている。また、当時貴重だったテープレコーダーをESSの仲間から借りて、下宿で練習したものだ。
能登で生まれ、金沢で高校時代を過ごした。2年生の冬、クラブはESSに所属していて、県英語弁論大会に出場する幸運に恵まれた。高校は同大会で4連勝を果たしていて、5度目の栄誉がかかっていた。このため、前年度優勝者の先輩からイントネーションや発音の厳しいチェックを受けたことを覚えている。また、当時貴重だったテープレコーダーをESSの仲間から借りて、下宿で練習したものだ。 このゴールデンウイークで行われた石川県七尾市の青柏祭(せいはくさい)を見物してきた(5月4日)。この祭りの山車(だし)の大きさが半端ではない。高さ12㍍だ。ビルにして4階建ての高さになる。車輪の直径が2㍍もある。民家の屋根より高い。通称「でか山」がのっそりと街を練る様はまさに怪獣映画に出てきそうなモンスターではある。
このゴールデンウイークで行われた石川県七尾市の青柏祭(せいはくさい)を見物してきた(5月4日)。この祭りの山車(だし)の大きさが半端ではない。高さ12㍍だ。ビルにして4階建ての高さになる。車輪の直径が2㍍もある。民家の屋根より高い。通称「でか山」がのっそりと街を練る様はまさに怪獣映画に出てきそうなモンスターではある。 とも言われる。先述したように、山車の高さは12㍍、上部の開きは13㍍、車輪の直径2㍍あり、山車としては日本最大級。上段に歌舞伎の名場面をしつらえるのが特徴だ。
とも言われる。先述したように、山車の高さは12㍍、上部の開きは13㍍、車輪の直径2㍍あり、山車としては日本最大級。上段に歌舞伎の名場面をしつらえるのが特徴だ。 4月29日に能登半島地震の被災地、輪島市門前町を訪れた。被災家屋の軒下でツバメが巣づくりをしていた。帰巣本能で飛来したツバメは家屋の様相が一変しているのに戸惑ったに違いない。ツバメは3月25日の能登の震災を知らない。季節は移ろっているのだ。
4月29日に能登半島地震の被災地、輪島市門前町を訪れた。被災家屋の軒下でツバメが巣づくりをしていた。帰巣本能で飛来したツバメは家屋の様相が一変しているのに戸惑ったに違いない。ツバメは3月25日の能登の震災を知らない。季節は移ろっているのだ。
