☆メディアのツボ-24-
電波メディアの老舗と言えばラジオである。あまり知られてはいないが、3月22日の放送記念日は1925年のこの日、東京放送局(現在のNHK東京放送局)が芝浦の仮送信所でラジオ放送を開始した日にちなむ。
政治オンチのラジオ
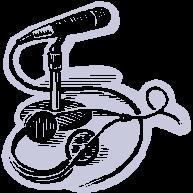 ラジオが誕生した背景には、1923年に起きた関東大震災での情報混乱の経験があったようだ。そして、戦時はラジオの絶頂期と重なる。先の戦争は、「臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス・・・」で始まりを、「堪ヘ難キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ・・・」の玉音放送で終わりをラジオを通じて、国民に知らされた。
ラジオが誕生した背景には、1923年に起きた関東大震災での情報混乱の経験があったようだ。そして、戦時はラジオの絶頂期と重なる。先の戦争は、「臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス・・・」で始まりを、「堪ヘ難キヲ堪ヘ、忍ヒ難キヲ忍ヒ・・・」の玉音放送で終わりをラジオを通じて、国民に知らされた。
だから、お年寄りの中には、ラジオと言うと「何だ大本営か」といまだに揶揄(やゆ)する人もいる。それだけ戦時における情報統制とラジオの使命は重なった印象がある。もちろんかつて深夜族と言われた我々の世代には前述のような印象はない。
ところで、今回のテーマは「政治オンチのラジオ」である。オンチは漢字表記で音痴だが、漢字にするとストレートに意味づけされるので、少しクッションを置いた。というのも、けさのFMラジオでアナウンサーのコメント内容がいかにも稚拙に聴こえ、その理由を考えてみたからである。
その男性アナは今回の北朝鮮の核実験をめぐってコメントしていた。前段で識者のインタビューを受けてのことである。「核実験の狙いは、北朝鮮がアメリカとの2国間での協議を望んでのこととの(識者の)分析があるようです。それだったらアメリカも話し合いに応じてあげればよいと思います。そして、6ヵ国協議での話し合いにも出てもらって、とにかく話し合いを続けることが大切ですね」と言った内容なのだ。
アメリカは前回のクリントン政権での2国間協議は失敗だったとして、6ヵ国協議の枠組みをつくったのである。つまり、男性アナのコメントは入り口と出口が逆なのである。
この男性アナは時折りニュースを読んでいる。上記のアドリブのコメントにはこれまでの時事・外交からの視点があればこのような解にはならない。おそらくニュースは読んでいるものの、政治が絡まった討論番組などに身を置いたことはないのだろう。あるいはまったく外交や政治にこれまで無関心だったのかもしれない。突然、プロデューサーから何かコメントするように突然指示されたのかもしれない。その程度の内容だったのである。しかし、この男性アナがこのようなコメントをするようになったのは果たして彼の責任だろうか。
実は、ラジオは戦争に加担したとの反省から、戦後一転して政治と無関係を装う。情報トーク番組、音楽番組、深夜番組では独自のジャンルを築いた。しかし、報道、とりわけ政治はニュースとして淡々と伝える。速報性という強みがありながらも、政治ネタには頓着しない。そんなメディアになった。
一方、1953年、戦後生まれのテレビはスタートは娯楽だったが、72年の連合赤軍による浅間山荘事件などをきっかけにニュース番組、硬派のドキュメンタリーなど報道へとジャンルを広げた。政治討論なども番組化し、たとえば升添要一氏ら多くの論客を誕生させた。その勢いが強い余り、1993年の細川内閣誕生のころ、「非自民政権が生まれるよう報道せよ、と指示した」とするテレビ朝日の椿貞良報道局長の発言が新聞メディアから叩かれもした。
ラジオが権力者のプロパガンダのツールとして時代を逆戻りすることはもうあるまい。ラジオを「大本営」と称する人も稀有だろう。むしろ、その男性アナを政治の雰囲気に引っぱり張り出してトレーニングさせてやってほしい…。いや、ラジオはもっとリアルの政治を伝えるメディアであるべきだと思ってもいる。
⇒13日(金)午後・金沢の天気 はれ
