★メディアのツボ-02-
地上デジタル放送対応の受信機、つまりテレビはかつて「1インチ1万円」といわれた。ところがいまは37インチのフルハイビジョン液晶テレビが19万円という価格革命が起きている。この激安戦法で薄型テレビ市場に殴りこみをかけているのはベンチャー企業の「バイ・デザイン」(東京)だ。この会社は工場を持たないメーカーで、部品メーカーからパネルなどを買い、主に中国のアモイの工場で組み立てを行う。しかし、この会社がせっせと低価格テレビを製造したとしても、おそらく「2011年7月24日」問題は解決しない。
「2011年7月24日」問題~下~
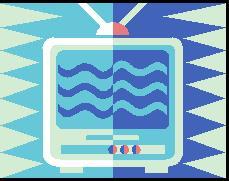 日本の世帯数は4600万以上といわれる。世帯数の4分の3近くを占める「2人以上世帯」のテレビ所有台数は1台と2台がほぼ3割ずつで、3台以上がほぼ4割を占める。以上を計算すると、家庭分だけで少なくとも8000万台から1億台以上のテレビが存在することになる。家庭以外の事業所、公共施設などの分も数えれば1億数千万台になるだろう。前回記したようにことし6月末時点での地デジ対応受信機の普及台数は1190万台だ。あと1億台ぐらいのテレビを5年間で普及させなければならない。経済的に余裕ある家庭は買い替えに積極的かもしれない。
日本の世帯数は4600万以上といわれる。世帯数の4分の3近くを占める「2人以上世帯」のテレビ所有台数は1台と2台がほぼ3割ずつで、3台以上がほぼ4割を占める。以上を計算すると、家庭分だけで少なくとも8000万台から1億台以上のテレビが存在することになる。家庭以外の事業所、公共施設などの分も数えれば1億数千万台になるだろう。前回記したようにことし6月末時点での地デジ対応受信機の普及台数は1190万台だ。あと1億台ぐらいのテレビを5年間で普及させなければならない。経済的に余裕ある家庭は買い替えに積極的かもしれない。
が、独居老人宅などではどうだろう。総務省の「2005年国勢調査抽出速報集計結果の概要」によると、65歳以上の「一人暮らし高齢者」は405万人となっている。この数字は急速に増加していて、2000年の統計と比べると102万人(34%)増となっている。さらに5年後となると500万人を超えても不思議ではない。中には余命いくばくもない独り暮らしのお年寄りの世帯もあるだろう。37インチのフルハイビジョン液晶テレビが19万円という価格革命が起きたとしても、こうした独居老人や生活保護を受けているの傷病や母子世帯に「まもなくアナログが停波するので19万円出してテレビを買い換えてください」と催促できるだろうか。この現状を無視してアナログ波を止めれば、「情報難民」が続出する。あるいは「弱者切り捨て」との批判が渦巻くだろう。これが「2011年7月24日」問題だ。
改正電波法以前は、「地デジ対応受信機の普及率が85%に達し、放送局のエリア内のカバー率が100%に達するまでは、現行のアナログ波を終了しない」となっていた。しかし、国費を使ってアナログ周波数変更対策(アナ・アナ変換=デジタル放送用チャンネル確保のためのアナログチャンネル変更)を実施したことによって、期限を切らざるを得なくなった。それはデジタルとアナログの同時並行放送(サイマル放送)を続けるテレビ局の経営負担を軽くすることにもなる。今回の地上デジタル放送化は行政が主導する「大いなる産業実験」とも言われる。5年後、この「2011年7月24日」問題が間違いなく浮上する。
テレビの買い替えではなく、デジタルのチューナーを取り付けるなどの方策はあり、これはテレビ業界か行政がそれこそ戸別訪問して取り付けなければ解決しない問題かもしれない。
⇒28日(金)夜・金沢の天気 あめ
