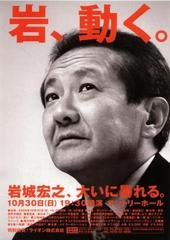☆NHKにCMは流れるか…
一連の不祥事が表面化し受信料の不払いへと連鎖しているNHKを遠巻きに見ながら、民放業界はその周囲の動向をうかがっている。何しろ、受信料未納による減収は年間おそよ500億円にも上る。近い将来NHKが経営危機に直面した場合、国営化なのか民営化なのか、政府はどのように判断するのか、いつ口火を切るのか-。民放が注視しているのはこの点だ。 
NHKにとってショッキングな数字が10日付の日経新聞に掲載された。インターネットによる調査(サンプル1034)で、「NHKがなくなり、テレビ局が民放だけになったら困ると思いますか」の設問に、56.7%が「困らない」と回答した。困らない理由として▽NHKの番組がそれほど優れていない▽ほとんどNHKを見ていない▽受信料を払わなくてよくなる-などといった回答が並んだ。「困る」としたのは23.0%だった。この調査はインターネットによるもので、NHKを比較的よく視聴する高齢層の意見が反映されていないことを加味したとしても、NHKサイドは動揺しただろう。
実はこの日経の調査でもう一つショッキングなデータが載った。「NHK受信料制度を今後どうしていくべきだと思いますか」の設問で、「廃止して民放のようにCM収入で運営」の回答が56.5%と過半数を占めた。「廃止して国の税金で運営」はわずか12.5%、「現状のままでよい」は10.5%である。つまり、NHKを民営化しろ、との意見が圧倒的に多い。確かに、ちまたでも「郵政も民営化するのだから、NHKがそうなって不思議ではない」という声を聞く。でもこの数字で衝撃を受けているのはむしろ民放の方だ。「民業圧迫だ」と。
では、NHK民営化の議論が政府内部であるのだろうか。今年3月15日、衆議院総務委員会でNHKの予算審議が行われた。この中で何人かの委員が広告放送や有料放送化について質問している。その審議のやり取りはインターネットの「衆議院TV」でアーカイブされている。4時間余りの集中審議だ。この中で、麻生太郎総務大臣は「NHKがいまやらなければならないのは信頼回復」「(広告放送などを)検討すべきだと考えているが、今直ちにというつもりはない」との主旨の答弁を繰り返している。麻生大臣でこのレベルの発言ならば当面、 NHKの民営化やCM放送はないと見るべきだろう。
それにしてもである。テレビ受信は全国で4600万件、うち未契約は985万件、1年以上の滞納は135万件、そして支払い拒否が130万件に及んでいる。つまり4件に1件以上が支払っていないのだ。上記のインターネット調査に応じた世代が世帯主になれば、この数字は加速度的に増えるだろう。NHKの経営危機は見えている。
経営危機に見舞われたとしても、「小さな政府」の流れではNHKの国営化は可能性が薄い。とすれば、上記の世論調査のようなCM放送や民営化論が台頭してくるのは時間の問題だろう。では誰がその口火を切るのか。ひょっとして、「番組でもめた」安倍晋三あるいは中川昭一の両氏かもしれないというのはうがった見方か…。
⇒12日(水)朝・金沢の天気 はれ