☆続・マエストロ岩城の視線

2003年9月、石川県立音楽堂で開催されたOEK&仙台フィルのコンサートでのこと。「外山雄三 管弦楽のためのディベルティメント」をテレビ番組用に収録した。その時、ステージ上のイントレ台のカメラマンを、指揮をしていた岩城さんが一瞬にらんだ。タクトを振り上げるようにして顔を上げ、斜め後ろを向きながら0.1秒くらいの早業でにらみつけたのである。ステージの袖にいた私にははっきり見えた。
コンサートが終了し、楽団員の何人かが言葉を交わしていた。「演奏中にノイズがした」と。コンサート終了後に、そのカメラマンが「カメラのネジが一本取れて落ちました」と1㌢ほどの小さなネジを拾ってきた。試しにネジをステージ上で落としてみると確かにボトッという音がする。ノイズはネジが落ちた音だったのである。岩城さんはそのノイズに気がつき、ノイズがした方向を一瞬にらんだ。その目線の先がカメラマンだったというわけである。
翌日、岩城さんに謝りに行った。「今後は気をつけてほしい」と一言だけだった。実はカメラマンも岩城さんの「にらみ」をとっさに感じた。でも、なぜにらまれたのかその時は理解できなかった。「刺すような怖い目で身震いした」とカメラマン。テレビ局の番組スタッフはそれ以降、ノイズに敏感となり、楽譜のコピーも普通紙だとめくる音がするというので、音が少ない和紙を使うようになった。マエストロの「天下一品のにらみ」が、番組制作の改善運動へとつながっていったのである。
⇒12日(日)午前・金沢の天気 曇り



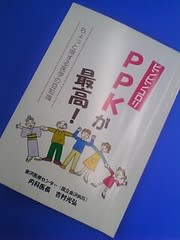
 徳川家の菩提寺・増上寺
徳川家の菩提寺・増上寺 
