アメリカ史上最大の合併といわれ、ウォールストリート最大の失敗に終わったAOLとタイムワーナー社との合併劇の結末を描いたルポルタージュ「虚妄の帝国の終焉」(アレック・クライン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン社刊)を先日読み終えた。その感想を多くの経済誌や専門誌が評論しているが、失敗に終わった合併劇の報告書という観点から冷 静に見つめれば、ワシントン・ポストの「スピード違反をしていたのは誰か、居眠り運転をしていたのは誰か、サイレンの音が近付く中、逃走したのは誰か…アレック・クラインの語り口は鮮やかだ」と交通事故にたとえた書評が一番的確に思える。
静に見つめれば、ワシントン・ポストの「スピード違反をしていたのは誰か、居眠り運転をしていたのは誰か、サイレンの音が近付く中、逃走したのは誰か…アレック・クラインの語り口は鮮やかだ」と交通事故にたとえた書評が一番的確に思える。
ルポルタージュは小説ではない。ノンフィクション、つまり事実の積み上げである。交通事故にもフィクションは一片もない。警察官が両者からその原因を丹念に事情を聴取すれば、その事故は起こるべくして起きた事故なのである。
2000年1月にAOLのスティーブ・ケースとタイムワーナーのジェリー・レビンが合併をぶち上げた。01年1月にようやく政府から合併が承認され、AOLタイムワーナーとなったものの、AOL側で広告収入のうち1億9000万㌦を不適切に処理してしていたことが発覚。この過程でAOL側の最高幹部が次々と辞職を余儀なくされ、そして03年1月にスティーブ・ケースも会長職を辞任する。隆盛を誇ったオランイン事業は1部門に属する1部署に降格され、同年10月には社名から「AOL」の文字が削除される。
この合併劇の失敗は「放送と通信の融合の失敗」とも日本では喧伝されている。が、果たしてそうなのか。私はこの著書を読むに当たって、CNNなどを擁しメディア帝国と呼ばれたタイムワーナーがなぜ企業風土も違う新興のAOLとの合併を決意したのかという点を注視した。つまり、タイムワーナーのジェリー・レビンがなぜ「合併のアクセル」をかけたのか、である。そこを読み解かなければ放送と通信の融合はいつまでたってもこの失敗例が引き合いに出され、話が前に進まないのだ。
このルポを読む限り、実はAOL側のボブ・ピットマンらが放送と通信のシナジー(相乗効果)を盛んに唱え、協調を促したのに対し、タイムワーナー側は「礼儀知らずで利益追求に余念がない」とAOL側を嫌悪した。AOLのEメールプログラムを使うことにすら抵抗したのはタイムワーナー側の社員である。AOL側からすれば、「保守的で意欲がない、お高くとまっている」と見えただろう。では、なぜタイムワーナーのジェリー・レビンが意欲的に合併を打ち出したのか。レビンはこうしたタイムワーナーの企業風土にネット企業のDNAを注入することで現状を打破したいと考えていたからだ。
というのも、タイムワーナー自身に結婚歴があった。映画のワーナー・ブラザーズと、活字文化の雑誌タイムが合併(1989年)したものの、「契約のみで結ばれた中世の封建制度のような結束力のない集合体」だった。収益は上がっていたが、デジタルへの取り組みが遅れ、それを何とも思わない現場にレビンは業を煮やしていたのである。そんなタイミングでAOLの勇ましい連中がやってきて、求愛が始まった。求愛に積極的だったのはタイムワーナーのレビンの方だったのである。
AOLの不適切な経理処理もどちらかというとタイムワーナーとの合併を何とか成功させようとした結果の「ボロ隠し」ともいえる。合併効果で得られるはずのシナジーが十分に得られなかったのは、その言葉にすら嫌悪感を持ったタイムワーナーの現場のせいではなかったか。江戸時代、武家に嫁いだ宮家の姫が「なじまぬ」とダダをこねるさまを想像してしまう。
こうなると放送と通信の問題というより、それぞれの生い立ちによる企業風土の問題ともいえる。失敗するべくして失敗した。ネットバブルの崩壊という時代状況も重なった。どちらが正しく、どちらが悪いとも言えない。それぞれに原因がある。で、冒頭の交通事故のたとえである。ただ、「タイムワーナー」が生き残ったので、「AOL」が悪役を引き受けてしまった。
⇒26日(金)朝・金沢の天気 くもり
 」と
」と 見せてくれたのが昆虫写真。ご覧の通り、クワガタの裏と表がくっきりと写っている。まるで、図鑑のようである。さぞかし特殊なカメラ(スリットカメラなど)でと思ったがそうではない。これがなんと、市販のスキャナで撮った画像なのだ。
見せてくれたのが昆虫写真。ご覧の通り、クワガタの裏と表がくっきりと写っている。まるで、図鑑のようである。さぞかし特殊なカメラ(スリットカメラなど)でと思ったがそうではない。これがなんと、市販のスキャナで撮った画像なのだ。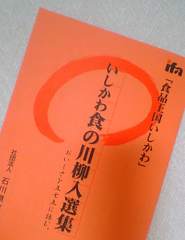 北陸といえば冬の味覚、カニである。冬のシーズン、金沢の近江町市場では観光客がよく手にぶら提げる姿を目にする。「加賀の旅帰りはカニと手をつなぎ」(三重・男性)。太平洋側の人にとっては日本海のカニは珍味でもある。それを持って帰宅するのだが、「手をつなぎ」でニコニコと連れて帰ってきたという雰囲気、そしてどこか誇らしげな雰囲気が伝わる。
北陸といえば冬の味覚、カニである。冬のシーズン、金沢の近江町市場では観光客がよく手にぶら提げる姿を目にする。「加賀の旅帰りはカニと手をつなぎ」(三重・男性)。太平洋側の人にとっては日本海のカニは珍味でもある。それを持って帰宅するのだが、「手をつなぎ」でニコニコと連れて帰ってきたという雰囲気、そしてどこか誇らしげな雰囲気が伝わる。 静に見つめれば、ワシントン・ポストの「スピード違反をしていたのは誰か、居眠り運転をしていたのは誰か、サイレンの音が近付く中、逃走したのは誰か…アレック・クラインの語り口は鮮やかだ」と交通事故にたとえた書評が一番的確に思える。
静に見つめれば、ワシントン・ポストの「スピード違反をしていたのは誰か、居眠り運転をしていたのは誰か、サイレンの音が近付く中、逃走したのは誰か…アレック・クラインの語り口は鮮やかだ」と交通事故にたとえた書評が一番的確に思える。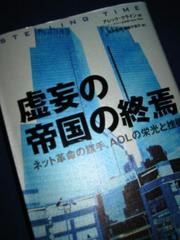 アメリカのネット革命の旗手とまでいわれたAOLがタイムワーナー社との合併に踏み込んだものの、その後に放逐されるまでの栄光と挫折を描いたルポルタージュ、「虚妄の帝国の終焉」(アレック・クライン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン社刊)を読んでいる。実はまだ第3章「世紀の取引」を読んでいる途中で、茂みの中である。それでも、アメリカのメディアとインターネット産業をめぐる大事件として記憶に新しい。370㌻の出だしの3分の1ほどしか読み進んだあたりから、人間の相克と葛藤が次ぎ次ぎと展開されていく。このブログを書いている時点で私も読んでいる途中だが、それでも書評をしたためたくなるほどのボリユーム感がすでにある。
アメリカのネット革命の旗手とまでいわれたAOLがタイムワーナー社との合併に踏み込んだものの、その後に放逐されるまでの栄光と挫折を描いたルポルタージュ、「虚妄の帝国の終焉」(アレック・クライン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン社刊)を読んでいる。実はまだ第3章「世紀の取引」を読んでいる途中で、茂みの中である。それでも、アメリカのメディアとインターネット産業をめぐる大事件として記憶に新しい。370㌻の出だしの3分の1ほどしか読み進んだあたりから、人間の相克と葛藤が次ぎ次ぎと展開されていく。このブログを書いている時点で私も読んでいる途中だが、それでも書評をしたためたくなるほどのボリユーム感がすでにある。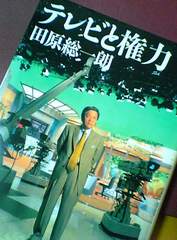 田原氏の近著、「テレビと権力」(講談社)を読んだ。内容は、権力の内幕をさらけ出すというより、田原氏がテレビや活字メディアに出演させた人物列伝とその取材の内幕といった印象だ。岩波映画の時代から始まって、テレビ東京のこと、現在の「サンデープロジェクト」まで、それこそ桃井かおりや小沢一郎、小泉純一郎まで、学生運動家や芸能人、財界人、政治家の名前が次々と出てくる。
田原氏の近著、「テレビと権力」(講談社)を読んだ。内容は、権力の内幕をさらけ出すというより、田原氏がテレビや活字メディアに出演させた人物列伝とその取材の内幕といった印象だ。岩波映画の時代から始まって、テレビ東京のこと、現在の「サンデープロジェクト」まで、それこそ桃井かおりや小沢一郎、小泉純一郎まで、学生運動家や芸能人、財界人、政治家の名前が次々と出てくる。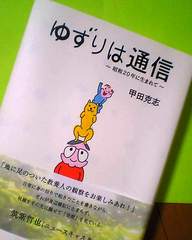 代金を振り込んでそのままにしてあったが、年度末に部屋の整理をしていて、ひょっこり出てきた。その書籍は498㌻もある。タイトルは「ゆずりは通信~昭和20年に生まれて~」。自らの
代金を振り込んでそのままにしてあったが、年度末に部屋の整理をしていて、ひょっこり出てきた。その書籍は498㌻もある。タイトルは「ゆずりは通信~昭和20年に生まれて~」。自らの 河合雅雄氏は京都大学名誉教授で日本の霊長類学の創設に加わった一人。この12月17日に開催する朝日・大学パートナーズシンポジウム「人をつなぐ 未来をひらく 大学の森―里山を『いま』に生かす」で基調講演をしていただくことが決まり、河合氏を知る大学教授から薦められたのうちの一冊が上記の「子どもと自然」だ。
河合雅雄氏は京都大学名誉教授で日本の霊長類学の創設に加わった一人。この12月17日に開催する朝日・大学パートナーズシンポジウム「人をつなぐ 未来をひらく 大学の森―里山を『いま』に生かす」で基調講演をしていただくことが決まり、河合氏を知る大学教授から薦められたのうちの一冊が上記の「子どもと自然」だ。




