☆文明論としての里山17
アメリカの農業というと、大規模経営による「農業の工業化」や、除草剤や病害虫に抵抗性を持つ遺伝子組換え農作物(トウモロコシや大豆など)といったイメージが強い。そのアメリカで地産地消(Buy Local)運動が盛り上がっている。このシリーズ15回目でも述べたCSA(Community Supported Agriculture)と呼ばれる取り組みである。『食料危機とアメリカ農業の選択』(食糧の生産と消費者を結ぶ研究会編・家の光協会・2009)から引用するかたちで紹介する。
今アメリカで起きている地域と農業のうねり
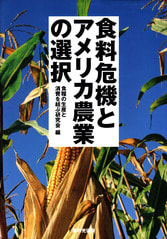 まず、この本を手にした経緯から。今月4日と5日、金沢大学が能登半島で展開して「能登里山マイスター」養成プログラムなどを見学させてほしいと、愛媛大学社会連携推進機構から村田武特命教授ら3人が訪れた。村田氏は欧米の農業政策などが専門で、CSAやスローフードなど生産者と消費者を結ぶ動きにも詳しい。そこで、能登に足を運ばれたついでに、新年度の同プログラムの授業をお願いしたところ、快く引き受けていただいた。講義は「世界の農業と家族農業経営~アメリカの『コミュニティが支える農業』(CSA)運動~」と題して。その講義の参考文献としてリストアップして頂いたのが、村田氏が執筆に加わった上記の本である。ちなみに、講義は4月23日(金)午後6時20分から、能登空港ターミナルビルで。一般公開型の授業なので誰でも自由に聴講できる。
まず、この本を手にした経緯から。今月4日と5日、金沢大学が能登半島で展開して「能登里山マイスター」養成プログラムなどを見学させてほしいと、愛媛大学社会連携推進機構から村田武特命教授ら3人が訪れた。村田氏は欧米の農業政策などが専門で、CSAやスローフードなど生産者と消費者を結ぶ動きにも詳しい。そこで、能登に足を運ばれたついでに、新年度の同プログラムの授業をお願いしたところ、快く引き受けていただいた。講義は「世界の農業と家族農業経営~アメリカの『コミュニティが支える農業』(CSA)運動~」と題して。その講義の参考文献としてリストアップして頂いたのが、村田氏が執筆に加わった上記の本である。ちなみに、講義は4月23日(金)午後6時20分から、能登空港ターミナルビルで。一般公開型の授業なので誰でも自由に聴講できる。
『食料危機とアメリカ農業の選択』の要点を抜き出してみる。金融資本主義など経済のグローバリゼーションの恩恵を受けたアメリカでも、富は一部の産業と階層に集中し、経済格差が拡大して、市民や農業者は「貧困化」しつつある。こうした格差に加え、アメリカの食料をめぐる問題は、貧困層ほど良質な生鮮食料品を入手できず、その食事が、カロリーは高いが栄養的にはバランスの悪い「ジャンクフード」と呼ばれる食品に偏っている。さらに日本でもヨーロッパでも忌避されているのがアメリカの遺伝子組み換え(GM)作物だ。アメリカでは、害虫抵抗性や除草剤耐性などの形質を2つ以上保有する「スタック(Stack)」と呼ばれる新たなGM作物が台頭し、作付面積が拡大している。2008年に農業法が「食料・保全・エネルギー法」と改正され、GMトウモロコシを使ったバイオエタノール増産が加速した。どのような害虫抵抗性がGMトウモロコシにあるのかというと、これまで茎の内部に入り込んでトウモロコシを食べてしまうアワノメイガを駆除するため農薬散布を行ってきた。が、アワノメイガは茎や実の中に入り込んでしまうため外からの殺虫剤散布は効果が少ないとされてきた。そこで、遺伝子組み換えが施されたアワノメイガ耐性のBtコーンでは、Btたんぱく質を食べたコブノメイガ幼虫が消化管にダメージを受けることによって駆除される。このことで、農薬散布の手間が省け、作業労力の軽減、燃料コスト削減などのメリットがあるとして、Btコーンが飛躍的に拡大したのである。
しかし、生産者はそれでよいかもしれない、あるいはエタノールの生産だったらそれでよいかもしれないが、そうしたGM作物が普及すればするほど、違和感を感じる人々が本場アメリカでも増えていて、有機農法で栽培された農作物を求める動きが高まっている。これが、今アメリカで起きているCSA運動のバックグラウンドとしてある。アメリカのCSAは日本語で「地域が支える農業」とも呼ばれ、1970年に公害問題を背景に広がった日本の有機農業運動の「産消提携」と似た仕組みを持っている。有機農家と消費者グループが契約を結び、農家は可能な限りの多種多様な農産物(主に野菜)を生産し、農産物の詰め合わせセットをつくり、毎週消費者グループへ配給する。
アメリカのCSAの特徴は次のようにまとめられる。第1に、農業経験のない新規の就農者によって農場が経営される場合が多い。異業種から若者がCSA農家に弟子入りしてノウハウを学び、独立するケースが多い。第2に、消費者や都市住民からの働きかけでCSA農場を開設するケース。消費者が農場を確保して、そこでSCA向けの野菜をつくってくれる農業体験者を探して来てもらう。第3に、農場の運営組織はNPO法人や協同組合が多く、農作従事者と農場経営者が分離されている。つまり、組織運営や投資は消費者側が行っているいる。第4は、第3とリンクするが、経営継承は親から子へではなく、CSA農場にふさわしいと認められた人である。第5は、農場の所有形態。都市に住む消費者が主導なので、都市近郊の農場のケースが多い。
著書では、ワシントン州シアトルにある「CSAルート・コネクション」という農場の例が挙げられている。経営面積は6.4ヘクタール。栽培のための労働者はフルタイム8人、パートタイム2人、ボランティアが15~20人。ボランティアはすべて女性で、毎日2人がローテーションを組み、1週間に5時間以上働くとレギュラーの詰め合わせセットの野菜がもらえる。農場では豆、ニンジン、トウモロコシ、レタスなど17種を作付けしている。農場を支える会員は560世帯。会費は2009年度で623ドル、前払いである。この前払い制度が生産者の安定した雇用と収入を保証している。会員はシアトル市内など3ヵ所に設けられた「ドロップ・オフ・サイト」と呼ばれる配布所に野菜セットを毎週取りに行く。また、会員が野菜を直接収穫することができる畑「ユーピック」もある。会員に配布した後に余った野菜は福祉団体に寄付される。また、長期間メンバーだった会員で世帯主が死亡した会員には無料で配布するという扶助的な活動も行われる。持続可能な運営を目指し、毎週ニュースレターを出すほか、料理のレシピを配布して料理教室を開催するなど会員拡大の活動も併せて行っている。
このようなCSA農場は2006年に全米で1308ヵ所だったが、2008年には2236ヵ所に急増、さらに増えているという。一つのムーブメントになっているのだ。また、オーガニック農産物を専門に扱うスーパーマーケットも出現しており、「ホールフーズ・マーケット」という店は地域の農産物にこだわって販売し、「ローカルを買う10の理由」というパンフレットを店で配布している。その「理由」とは、1)季節と連結して暮らす、2)農場から食卓までの距離を短くする、3)新鮮な生産物を得ることができる、4)生産物をもっと楽しむ、5)生産者の顔が見える、6)地域の仕事を支援する、7)地域のコミュニケーションを支援する、8)自立した農家を支援する、9)生活できる賃金を農家に払う、10)責任ある土地開発を支持する・・・である。
資本主義の総本山といわれるアメリカで、今起きている地域の新しいうねりを『食料危機とアメリカ農業の選択』を通じて紹介した。
⇒7日(日)朝・金沢の天気 はれ
 この「へんざいもん」という言葉を数年前に知って、中沢新一著『愛と経済のロゴス』(講談社・2003)を想起した。グローバル経済を突き動かしているのは欲望だ。しかし、愛もまた欲望に根ざしている。となれば、愛と経済は深いところでつながっている。そんなところからいまの資本主義の有り様を批判したのが『愛と経済のロゴス』である。以下、著書を自分なり解釈しながら、経済とは何かを考えてみる。
この「へんざいもん」という言葉を数年前に知って、中沢新一著『愛と経済のロゴス』(講談社・2003)を想起した。グローバル経済を突き動かしているのは欲望だ。しかし、愛もまた欲望に根ざしている。となれば、愛と経済は深いところでつながっている。そんなところからいまの資本主義の有り様を批判したのが『愛と経済のロゴス』である。以下、著書を自分なり解釈しながら、経済とは何かを考えてみる。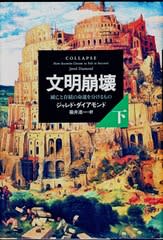 本文を引用しながら、いまから1千年以上前にメキシコ・ユカタン半島とその周辺で崩壊したマヤ文明の謎解きをしてみる。その崩壊のプロセスはこうだ。マヤ民族は少なくとも500万人はいた。「入手可能な資源の量が人口増加の速度に追いつけなくなった」ことで人口と資源の不均衡が始まる。「森林破壊と丘陵地の侵食」が農地の総面積を減らす。減少する食料資源をめぐって、人間が争いあうようになり「戦闘行為が増加」した。小国同士がつばぜり合いを演じた。統一帝国ができなかったのは、マヤにはウマやロバといった運送に利用できる家畜がいなく、陸路の運搬は人の背に載せて行われたからだ。つまり、長距離の戦闘はできなかった。しかも、主食であるトウモロコシを兵士も荷役も食べるので、長期間の戦闘でできなかった。マヤの軍事行動は「期間も距離も大きく制限されていた」のである。そして、マヤを気候変動が襲う。旱魃(かんばつ)だ。
本文を引用しながら、いまから1千年以上前にメキシコ・ユカタン半島とその周辺で崩壊したマヤ文明の謎解きをしてみる。その崩壊のプロセスはこうだ。マヤ民族は少なくとも500万人はいた。「入手可能な資源の量が人口増加の速度に追いつけなくなった」ことで人口と資源の不均衡が始まる。「森林破壊と丘陵地の侵食」が農地の総面積を減らす。減少する食料資源をめぐって、人間が争いあうようになり「戦闘行為が増加」した。小国同士がつばぜり合いを演じた。統一帝国ができなかったのは、マヤにはウマやロバといった運送に利用できる家畜がいなく、陸路の運搬は人の背に載せて行われたからだ。つまり、長距離の戦闘はできなかった。しかも、主食であるトウモロコシを兵士も荷役も食べるので、長期間の戦闘でできなかった。マヤの軍事行動は「期間も距離も大きく制限されていた」のである。そして、マヤを気候変動が襲う。旱魃(かんばつ)だ。 その氾濫する情報の中にあって、逆にマスメディアの果たす役割が重要になっている。というのは、新聞やテレビのニュースや情報はある程度、品質が保証されるからである。情報源からたどり、客観的な判断を加え、あるいは情報の価値を見いだして文字表現や映像表現をする。そのようなプロセスを踏んでいるので信頼性が担保されている。では、マスメディアはどのように品質保証をしているのだろうか。端的に言えば、ニュースや情報の価値を見抜き、文字や映像で伝える専門家(記者、ディレクター)を養成しているからである。記者やディレクターの養成には実に手間隙がかかり、もちろんコストもかかる。逆ピラミッドの記事構成、形容詞を使わない文体、記事を書くスピード、記事用語の習得に時間と労力がかかる。新人記者がこなれた記事を書くまでには4、5年はかかるだろう。
その氾濫する情報の中にあって、逆にマスメディアの果たす役割が重要になっている。というのは、新聞やテレビのニュースや情報はある程度、品質が保証されるからである。情報源からたどり、客観的な判断を加え、あるいは情報の価値を見いだして文字表現や映像表現をする。そのようなプロセスを踏んでいるので信頼性が担保されている。では、マスメディアはどのように品質保証をしているのだろうか。端的に言えば、ニュースや情報の価値を見抜き、文字や映像で伝える専門家(記者、ディレクター)を養成しているからである。記者やディレクターの養成には実に手間隙がかかり、もちろんコストもかかる。逆ピラミッドの記事構成、形容詞を使わない文体、記事を書くスピード、記事用語の習得に時間と労力がかかる。新人記者がこなれた記事を書くまでには4、5年はかかるだろう。 著書では、アメリカの事例が豊富だ。メディアの世界では、アメリカで起きている事象が3年後には日本で起きる傾向がある。その事例のいくつかを。アメリカの新聞社は経営危機にあえいでいる。その主な原因はインターネットで記事を読むようになり、新聞を購読しなくなったからだ。さらに、ネットは新聞から広告収入も奪っている。中でも、クラシファイド広告が顕著だ。日本で言えば、「売ります」「買います」「従業員募集」といった三行広告のこと。アメリカでは300億ドル(およそ3兆円)のマーケットになっていて、その半分以上を新聞が占めていた。この三行広告をインターネットで無料化したのが「クレイグズリスト」。サンフランシスコを本拠地にいまでは全米に広がり、職探し、部屋探し、ルームメイトの募集などさまざま日常で必要な情報を網羅している。月80億ページビューもある。
著書では、アメリカの事例が豊富だ。メディアの世界では、アメリカで起きている事象が3年後には日本で起きる傾向がある。その事例のいくつかを。アメリカの新聞社は経営危機にあえいでいる。その主な原因はインターネットで記事を読むようになり、新聞を購読しなくなったからだ。さらに、ネットは新聞から広告収入も奪っている。中でも、クラシファイド広告が顕著だ。日本で言えば、「売ります」「買います」「従業員募集」といった三行広告のこと。アメリカでは300億ドル(およそ3兆円)のマーケットになっていて、その半分以上を新聞が占めていた。この三行広告をインターネットで無料化したのが「クレイグズリスト」。サンフランシスコを本拠地にいまでは全米に広がり、職探し、部屋探し、ルームメイトの募集などさまざま日常で必要な情報を網羅している。月80億ページビューもある。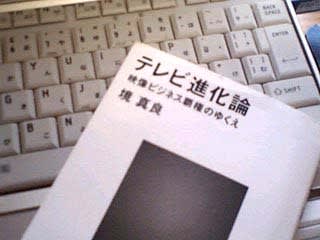 ッションが、「番組の構造改革」ともいえる大胆な編成に背中を押した、ともいえる。
ッションが、「番組の構造改革」ともいえる大胆な編成に背中を押した、ともいえる。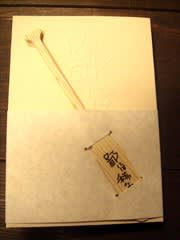 国内外の広告業界の動きや広告活動を紹介する週刊の専門紙「電通報」に平成18年4月から1年間連載された文をまとめたもの。主に月尾氏が全国18ヵ所で主宰する月尾塾での講演旅行などで出会った地域の愉快な人々が稀人(まれびと)として紹介されている。ちなみに、「加賀の稀人」は白波の立つ日本海をクルーザーで出航する豪快な上場企業の会長の話。この会長は創業者だけあって、物怖じしないのだが、暗雲の方向へ向かっていくので、さすがに地元の案内役が止め入った。「途中で日本海で行方不明」となっていたかもしれないと。そんな豪快さの持ち主は今日では稀人なのだろう。
国内外の広告業界の動きや広告活動を紹介する週刊の専門紙「電通報」に平成18年4月から1年間連載された文をまとめたもの。主に月尾氏が全国18ヵ所で主宰する月尾塾での講演旅行などで出会った地域の愉快な人々が稀人(まれびと)として紹介されている。ちなみに、「加賀の稀人」は白波の立つ日本海をクルーザーで出航する豪快な上場企業の会長の話。この会長は創業者だけあって、物怖じしないのだが、暗雲の方向へ向かっていくので、さすがに地元の案内役が止め入った。「途中で日本海で行方不明」となっていたかもしれないと。そんな豪快さの持ち主は今日では稀人なのだろう。
 、最後のロール字幕では「車の燃費を良くすれば、無駄なエネルギー消費を防げます」と呼びかけている。このところトヨタがじりじりとアメリカでの自動車シェアを伸ばしているのも、おそらくこの映画のおかげだ。
、最後のロール字幕では「車の燃費を良くすれば、無駄なエネルギー消費を防げます」と呼びかけている。このところトヨタがじりじりとアメリカでの自動車シェアを伸ばしているのも、おそらくこの映画のおかげだ。 土地取引に関して国会で質問した衆院議員(国民新党)が脅迫された事件にからみ、議員を取材した録音データが漏洩し、インターネット上のブログに掲載された問題で、毎日新聞社は3月12日付でデータを外部に漏らした41歳の記者を諭旨解雇とした。記者が取材した録音データが入ったICレコーダーを議員の了解なしに第三者の取材協力者に渡したのである。その取材協力者とは元暴力団組長だったので背景の根深さと波紋を広げた。
土地取引に関して国会で質問した衆院議員(国民新党)が脅迫された事件にからみ、議員を取材した録音データが漏洩し、インターネット上のブログに掲載された問題で、毎日新聞社は3月12日付でデータを外部に漏らした41歳の記者を諭旨解雇とした。記者が取材した録音データが入ったICレコーダーを議員の了解なしに第三者の取材協力者に渡したのである。その取材協力者とは元暴力団組長だったので背景の根深さと波紋を広げた。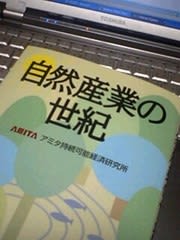 「人類はどこから来て、どこに行くのだろうか」という壮大なテーマを掲げて、持続可能な社会とは何かを徹底して論理的に実践的に追求する、そんなドゥタンクなのだ。設立は2005年7月、京都市上京区室町道にある築150年の京町屋に研究所を構えている。
「人類はどこから来て、どこに行くのだろうか」という壮大なテーマを掲げて、持続可能な社会とは何かを徹底して論理的に実践的に追求する、そんなドゥタンクなのだ。設立は2005年7月、京都市上京区室町道にある築150年の京町屋に研究所を構えている。