★続「災害は進化する」
『日本災害史』(2006、北原糸子編・吉川弘文館)を読んで、ふと思った。なぜ日本人は災害が来ることを忘れるのか。地震情報はこれまで新聞メディアなどに取り上げられ、注意喚起されても、その時代の雰囲気の中でかき消されていつの間にか遠ざかっていく。そして、震災や津波がある日、突然起きて「天災は忘れたころにやってくる」(寺田寅彦の言葉とされる)という状態が繰り返される。
 著書の中で興味深い下りがある。「地震情報が、いわゆる『予言』に近い情報から、純粋科学情報に移行しつつあった時代だったのだが、行政も企業も『予言時代』そのままの対応をしたのであった」「市民は、家具の固定といった、きわめて狭い範囲の防衛策であったとはいえ、生活レベルでの対応を始める兆しがみえるが、行政、企業は、そうした具体的防御策への想像力を全く欠いていた」。これは阪神・大震災(1995年1月17日)が起きる10日前に神戸新聞の一面で報じていた、当時兵庫県猪名川町で続発していた群発地震に触れ「いつM7級の大地震が起きても不思議ではない」との専門家の見方を警告として発していたものだ。しかし、パブル経済の崩壊で行政も企業も内需拡大策、開発に神経を集中していた。むしろ、この記事に反応していたのは市民だったという。
著書の中で興味深い下りがある。「地震情報が、いわゆる『予言』に近い情報から、純粋科学情報に移行しつつあった時代だったのだが、行政も企業も『予言時代』そのままの対応をしたのであった」「市民は、家具の固定といった、きわめて狭い範囲の防衛策であったとはいえ、生活レベルでの対応を始める兆しがみえるが、行政、企業は、そうした具体的防御策への想像力を全く欠いていた」。これは阪神・大震災(1995年1月17日)が起きる10日前に神戸新聞の一面で報じていた、当時兵庫県猪名川町で続発していた群発地震に触れ「いつM7級の大地震が起きても不思議ではない」との専門家の見方を警告として発していたものだ。しかし、パブル経済の崩壊で行政も企業も内需拡大策、開発に神経を集中していた。むしろ、この記事に反応していたのは市民だったという。
それにしても人々は忘れっぽい。災害が起きると世界中の人達が同情し、一時的に自らのこととしてとらえるが、「こうした人道的感情がひとたび麗しくも語られてしまうと、あたかもこんな出来事がぜんぜん突発しなかったかのごとく、以前と同様の気楽さで、人々は自分自身の仕事なり娯楽なりを続け、休息し、気晴らしをやる。彼自身に関して起こる最もささいな災禍のほうがはるかに彼の心を乱すものとなるのである」(経済学者アダム・スミス『道徳感情論』)。この忘れっぽさは、日本人だけではなく、しかもいつの世でも同じなのだ。
では、忘れっぽい我々は次に、ひょっとして明日にもやって来る災害にどのような心構えを持たねばならないのか。それは、著書に述べられているように「減災の思想」だろう。「一人でも多くの命を助け、一戸でも多くの家・建物を守り、一ヵ所でも多くの都市装置の破壊を防ぎ、一円でも多くの経済損失を軽減する」、そのためにどうすればよいのか常日頃、四六時中考えるということだ。このような言葉を述べると、「では昔の非文明社会に戻れということか」との反論もあろう。そうではない、たとえば一極集中型の都市構造を改造する、高速道路を都市のど真ん中に通さないなど、人間生活が機能不全に陥ることを避ける方策を常に考えるということだ。都市を巨大なコンクリート防波堤で囲って、これで津波は大丈夫だ安全という発想ではない。
※写真は、能登半島地震の被災現場(2007年3月25日、輪島市門前町)
⇒25日(土)夜・金沢の天気 くもり
 けさ(17日)は金沢の自宅周辺でも30㌢の積雪となった。2月2日以来、2週間ぶりの銀世界だ。ただ寒気が少々緩く、雪が融け始めている。屋根から雨だれがパラパラと落ちる。早朝から「雪すかし」(除雪のこと)だ。この季節、スコップで道路を除雪すると響く、ザッ、ザッッという音を耳にすると北陸の人は居ても立ってもいられなくなる。「お隣さんが雪すかしを始めた。我が家もしなければ」と、寝ていても目覚めるのだ。そして誰かが始めて30分もすると、近所中で雪すかしをしている光景が見られるようになる。簡単に近所同士で挨拶はするが、皆黙々と除雪を進める。雪すかしには、決まりや町の会則というものがあるわけではない。あたかも、DNAが目覚めるがごとくその行動は始まるのだ。
けさ(17日)は金沢の自宅周辺でも30㌢の積雪となった。2月2日以来、2週間ぶりの銀世界だ。ただ寒気が少々緩く、雪が融け始めている。屋根から雨だれがパラパラと落ちる。早朝から「雪すかし」(除雪のこと)だ。この季節、スコップで道路を除雪すると響く、ザッ、ザッッという音を耳にすると北陸の人は居ても立ってもいられなくなる。「お隣さんが雪すかしを始めた。我が家もしなければ」と、寝ていても目覚めるのだ。そして誰かが始めて30分もすると、近所中で雪すかしをしている光景が見られるようになる。簡単に近所同士で挨拶はするが、皆黙々と除雪を進める。雪すかしには、決まりや町の会則というものがあるわけではない。あたかも、DNAが目覚めるがごとくその行動は始まるのだ。
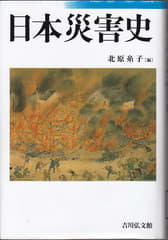 原発だけでなく、高層ビルもまた進化する災害(=文明のパラドックス的逆襲)になりうる。2月13日放送のNHK「クローズアップ現代」でも紹介されたように、東日本大震災では、震源から遠い場所(大阪など)にある高層ビルが大きく揺れたり、同じ敷地にありながら特定の建物だけに被害が出たりするなどの不可解な現象が起きたのだ。原因は、建物と地盤の「固有周期」が一致することで起きた「共振現象」と見られている。事例として紹介されていた、震源から770㌔離れた大阪府の咲州庁舎(地上55階地下3階、高さ256㍍)の揺れ幅は3㍍にも。そのとき大阪府は震度3だった。1995年の阪神淡路大震災では、街中を走る阪神高速道路の高架橋が橋脚ごと横倒しとなった。
原発だけでなく、高層ビルもまた進化する災害(=文明のパラドックス的逆襲)になりうる。2月13日放送のNHK「クローズアップ現代」でも紹介されたように、東日本大震災では、震源から遠い場所(大阪など)にある高層ビルが大きく揺れたり、同じ敷地にありながら特定の建物だけに被害が出たりするなどの不可解な現象が起きたのだ。原因は、建物と地盤の「固有周期」が一致することで起きた「共振現象」と見られている。事例として紹介されていた、震源から770㌔離れた大阪府の咲州庁舎(地上55階地下3階、高さ256㍍)の揺れ幅は3㍍にも。そのとき大阪府は震度3だった。1995年の阪神淡路大震災では、街中を走る阪神高速道路の高架橋が橋脚ごと横倒しとなった。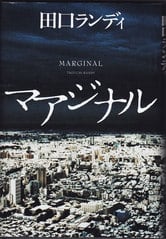 さらに、能登にはUFO伝説がある。羽咋市に伝わる昔話の中にある「そうちぼん伝説」がそれ。そうちぼんとは、仏教で使われる仏具のことで、楽器のシンバルのような形をしている。伝説は、そうちぼんが同市の北部にある眉丈山(びじょうざん)の中腹を夜に怪火を発して飛んでいたというのだ。この眉丈山の辺りには、「ナベが空から降ってきて人をさらう」神隠し伝説も残っているという。同市の正覚院という寺の『気多古縁起』という巻物にも、神力自在に飛ぶ物体が登場する(宇宙科学博物館「コスモアイル羽咋」のホームページより)。
さらに、能登にはUFO伝説がある。羽咋市に伝わる昔話の中にある「そうちぼん伝説」がそれ。そうちぼんとは、仏教で使われる仏具のことで、楽器のシンバルのような形をしている。伝説は、そうちぼんが同市の北部にある眉丈山(びじょうざん)の中腹を夜に怪火を発して飛んでいたというのだ。この眉丈山の辺りには、「ナベが空から降ってきて人をさらう」神隠し伝説も残っているという。同市の正覚院という寺の『気多古縁起』という巻物にも、神力自在に飛ぶ物体が登場する(宇宙科学博物館「コスモアイル羽咋」のホームページより)。 羽柴秀吉の時代の地震が中心に書かれている。秀吉は2度、度胆を抜かれる地震を経験している。1度目は1586年1月18日、中部地方から近畿東部が激しく揺れた天正地震。越中の佐々成政を攻めて、大阪城への帰路、琵琶湖南西岸の坂本城にいた。揺れは4日間も続き、その後、秀吉は馬を乗り継いで大阪に逃げるようにして帰った。この坂本城はもともと明智光秀が築いた城だった。光秀は、本能寺の変を起こし、秀吉に敗れて近江に逃れる途中で殺された(1582年7月)。著者も「明智光秀ゆかりの城にいて、大地の怒りに触れた瞬間、どのような思いが胸をよぎっただろうか」と書いているように、秀吉には因縁めいて居心地が悪くなったに違いない。この地震では、岐阜県白川郷にあったとされる帰雲城(かえりくもじょう)が山崩れで埋まり、城主の内ヶ島氏理ら一族が一瞬にして絶えた。
羽柴秀吉の時代の地震が中心に書かれている。秀吉は2度、度胆を抜かれる地震を経験している。1度目は1586年1月18日、中部地方から近畿東部が激しく揺れた天正地震。越中の佐々成政を攻めて、大阪城への帰路、琵琶湖南西岸の坂本城にいた。揺れは4日間も続き、その後、秀吉は馬を乗り継いで大阪に逃げるようにして帰った。この坂本城はもともと明智光秀が築いた城だった。光秀は、本能寺の変を起こし、秀吉に敗れて近江に逃れる途中で殺された(1582年7月)。著者も「明智光秀ゆかりの城にいて、大地の怒りに触れた瞬間、どのような思いが胸をよぎっただろうか」と書いているように、秀吉には因縁めいて居心地が悪くなったに違いない。この地震では、岐阜県白川郷にあったとされる帰雲城(かえりくもじょう)が山崩れで埋まり、城主の内ヶ島氏理ら一族が一瞬にして絶えた。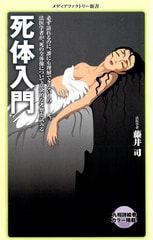 金沢大学の共通教育授業でマスメディア論を教えている。その中で、学生たちに問いかけるテーマの一つが、「マスメディアはなぜ遺体、あるいは死体の写真や映像を掲載・放送しないのか」という論点である。東日本大震災での遺体写真の掲載については、新聞各社は原則、死体の写真を掲載していない。被災地の死者(死体)の尊厳を貶めることにもなりかねないとの各社の判断があり、あえて掲載していない。リアルな現場というのは、遺体(死体)の写真をストレートに見せることはしなくても、なんらかの見せ方によって、犠牲者の多さや無念の死というものを表現することは可能との意見が多い。そのような話を周囲の研究者にすると、「では、これを読んでみてください」と薦められたのがこの本だった。マスメディアで掲載・放送するしないの論議以前の話として、日常生活で遺体(死体)と接することがめったになく、遺体(死体)そのものについて我々は無知である。これでは何も語れない、イメージと感情だけで論じることに等しいと思い、向学のために本を注文した。
金沢大学の共通教育授業でマスメディア論を教えている。その中で、学生たちに問いかけるテーマの一つが、「マスメディアはなぜ遺体、あるいは死体の写真や映像を掲載・放送しないのか」という論点である。東日本大震災での遺体写真の掲載については、新聞各社は原則、死体の写真を掲載していない。被災地の死者(死体)の尊厳を貶めることにもなりかねないとの各社の判断があり、あえて掲載していない。リアルな現場というのは、遺体(死体)の写真をストレートに見せることはしなくても、なんらかの見せ方によって、犠牲者の多さや無念の死というものを表現することは可能との意見が多い。そのような話を周囲の研究者にすると、「では、これを読んでみてください」と薦められたのがこの本だった。マスメディアで掲載・放送するしないの論議以前の話として、日常生活で遺体(死体)と接することがめったになく、遺体(死体)そのものについて我々は無知である。これでは何も語れない、イメージと感情だけで論じることに等しいと思い、向学のために本を注文した。 石巻日日新聞。イシノマキヒビシンブンと読む。ニチニチではない。夕刊紙が専門で、宮城県東部の石巻市や東松島市、女川町などをエリアに震災前は1万4000部を発行していた。従業員は6人の記者を含め28人。典型的な地域紙と言ってよいだろう。この日(3月11日)は夕方から雪の予報が出ていて、夕刊は午後2時半ごろ早めに配達が始まっていた。地震の発生は午後2時46分、その3分後に大津波警報が発令、さらにその50分後の3時40分に石巻市内の同社に津波が到達した。社屋の倒壊を免れたものの、1階にある輪転機の一部が水に浸かり、さらに電気が止まった。来年には創刊100周年を迎える歴史ある新聞を発行できないという危機に陥る。社長の近江弘一は決断する。「今、伝えなければ地域の新聞社なんか存在する意味がない」「紙とペンさえあれば」「休刊はしたくない。手書きでいこうや」と。そして、3月12日付=写真=から6回にわたって壁新聞づくりが始まり、避難所などに貼り出された。
石巻日日新聞。イシノマキヒビシンブンと読む。ニチニチではない。夕刊紙が専門で、宮城県東部の石巻市や東松島市、女川町などをエリアに震災前は1万4000部を発行していた。従業員は6人の記者を含め28人。典型的な地域紙と言ってよいだろう。この日(3月11日)は夕方から雪の予報が出ていて、夕刊は午後2時半ごろ早めに配達が始まっていた。地震の発生は午後2時46分、その3分後に大津波警報が発令、さらにその50分後の3時40分に石巻市内の同社に津波が到達した。社屋の倒壊を免れたものの、1階にある輪転機の一部が水に浸かり、さらに電気が止まった。来年には創刊100周年を迎える歴史ある新聞を発行できないという危機に陥る。社長の近江弘一は決断する。「今、伝えなければ地域の新聞社なんか存在する意味がない」「紙とペンさえあれば」「休刊はしたくない。手書きでいこうや」と。そして、3月12日付=写真=から6回にわたって壁新聞づくりが始まり、避難所などに貼り出された。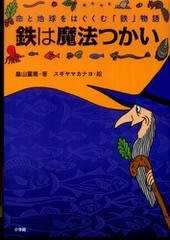 一冊目は畠山重篤氏の『鉄は魔法使い』(小学館)。この本は畠山さんのサイン入りだ。ちょっとした経緯があった。先のコラム(9月3日付)で書いた「地域再生人材大学サミットin能登」(9月1日~3日・輪島市)で畠山さんから依頼を受けた。公開シンポジウム(2日)が始まる30分前の9時半ごろだった。「宇野さん、20冊ほど持ってきたのですが、販売していただけませんか」(畠山)、「急な話でどれだけ売れるか分かりませんが、畠山さんの基調講演が終わった後の昼休みにロビーで販売しましょう。せっかくですからサイン会ということにして、畠山さんもその場に来ていただけませんか」(宇野)、「わかりました。急なお願いですみません」(畠山)。ということで急きょ、畠山氏のサイン会をしつらえた。聴衆はホール満員の入りだったので売り切る自信はあった。私が購入第1号となり、サイン本を掲げ、運営スタッフの女性が「ただいま、畠山さんの本のサイン会を行っています」と呼び込み、畠山氏がサインと握手を。列ができ、7分間で残り19冊は完売となった。「もう本はないのか」と苦情も出た。
一冊目は畠山重篤氏の『鉄は魔法使い』(小学館)。この本は畠山さんのサイン入りだ。ちょっとした経緯があった。先のコラム(9月3日付)で書いた「地域再生人材大学サミットin能登」(9月1日~3日・輪島市)で畠山さんから依頼を受けた。公開シンポジウム(2日)が始まる30分前の9時半ごろだった。「宇野さん、20冊ほど持ってきたのですが、販売していただけませんか」(畠山)、「急な話でどれだけ売れるか分かりませんが、畠山さんの基調講演が終わった後の昼休みにロビーで販売しましょう。せっかくですからサイン会ということにして、畠山さんもその場に来ていただけませんか」(宇野)、「わかりました。急なお願いですみません」(畠山)。ということで急きょ、畠山氏のサイン会をしつらえた。聴衆はホール満員の入りだったので売り切る自信はあった。私が購入第1号となり、サイン本を掲げ、運営スタッフの女性が「ただいま、畠山さんの本のサイン会を行っています」と呼び込み、畠山氏がサインと握手を。列ができ、7分間で残り19冊は完売となった。「もう本はないのか」と苦情も出た。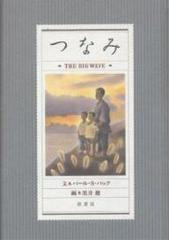 もう一冊の本が、あのノーベル作家のパール・バックの『つなみ ◆THE BIG WAVE◆』(径書房)。日本で滞在した折に取材し、アメリカで1947年に出版された。漁師の息子ジヤと友達の農家の息子キノの2人の少年。ある日突然に村を襲った大津波で、家も家族も失ったジヤをキノの両親が息子同様に育てる。ジアは周囲の愛情に包まれて成長し、やがて生まれ育った漁村に戻り、漁師と生きる決意をする。日本人の自然観や生活観、生死観を巧み取り込み、パール・バックはまるで自らの子のように少年たちを厳しくも優しく眼差しで描く。
もう一冊の本が、あのノーベル作家のパール・バックの『つなみ ◆THE BIG WAVE◆』(径書房)。日本で滞在した折に取材し、アメリカで1947年に出版された。漁師の息子ジヤと友達の農家の息子キノの2人の少年。ある日突然に村を襲った大津波で、家も家族も失ったジヤをキノの両親が息子同様に育てる。ジアは周囲の愛情に包まれて成長し、やがて生まれ育った漁村に戻り、漁師と生きる決意をする。日本人の自然観や生活観、生死観を巧み取り込み、パール・バックはまるで自らの子のように少年たちを厳しくも優しく眼差しで描く。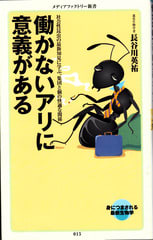 幼いころ読んだイソップ寓話に「アリとキリギリス」がある。夏の間、アリたちは冬の間の食料をためるために働き続け、キリギリスは歌を歌って遊び、働かない。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、アリたちに頼んで、食べ物を分けてもらおうとする。しかし、アリたちは「夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだ」と皮肉を込めて断る下りをいまでも覚えている。ことほどさように、アリは働き者というイメージが世界で共有されている。
幼いころ読んだイソップ寓話に「アリとキリギリス」がある。夏の間、アリたちは冬の間の食料をためるために働き続け、キリギリスは歌を歌って遊び、働かない。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、アリたちに頼んで、食べ物を分けてもらおうとする。しかし、アリたちは「夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだ」と皮肉を込めて断る下りをいまでも覚えている。ことほどさように、アリは働き者というイメージが世界で共有されている。 その熊楠がクジラの塩干しを炭火であぶって、よく酒を飲んだと著書にあり、この塩干しが食べたくなった。和歌山県太地町から「鯨塩干」を取り寄せた。黒くてフワフワ感がある。これをオーブンで5分間焼く=写真=。「これが熊楠の好物だったクジラの塩干しか」とわくわくしながら口にした。どこか覚えのある味だった。スルメイカの一夜干しのあぶったものと歯触りや味がそっくりなのだ。
その熊楠がクジラの塩干しを炭火であぶって、よく酒を飲んだと著書にあり、この塩干しが食べたくなった。和歌山県太地町から「鯨塩干」を取り寄せた。黒くてフワフワ感がある。これをオーブンで5分間焼く=写真=。「これが熊楠の好物だったクジラの塩干しか」とわくわくしながら口にした。どこか覚えのある味だった。スルメイカの一夜干しのあぶったものと歯触りや味がそっくりなのだ。 原作は磯田道史著『武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末維新』(新潮新書)である。2003年に出版された当時読んだ。それこそ今の言葉で表現すれば、政権交代、経済破綻、地価下落、リストラ、教育問題など現代の日本が直面している問題を、140年ほど前に大政奉還後の武士たちや商人が経験していた。江戸時代から明治へと近代日本の姿が一つの家族を通して見えてくる。そんな著書だ。
原作は磯田道史著『武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末維新』(新潮新書)である。2003年に出版された当時読んだ。それこそ今の言葉で表現すれば、政権交代、経済破綻、地価下落、リストラ、教育問題など現代の日本が直面している問題を、140年ほど前に大政奉還後の武士たちや商人が経験していた。江戸時代から明治へと近代日本の姿が一つの家族を通して見えてくる。そんな著書だ。 『なぜ飼い犬に手をかまれるのか』(日高敏隆著、PHPサイエンス・ワールド新書、09年)はタイトル名で注文してしまった。「飼い犬に手をかまれる」という言葉は、部下の反逆を意味する。それに、「なぜ」と付されると、科学の領域のような感じがして手を伸ばしたくなるものだ。動物行動学者の日高氏については、個人的に一度だけ
『なぜ飼い犬に手をかまれるのか』(日高敏隆著、PHPサイエンス・ワールド新書、09年)はタイトル名で注文してしまった。「飼い犬に手をかまれる」という言葉は、部下の反逆を意味する。それに、「なぜ」と付されると、科学の領域のような感じがして手を伸ばしたくなるものだ。動物行動学者の日高氏については、個人的に一度だけ