☆医療と薬を遠ざけて
昨年暮れに中国・雲南省のハニ族の棚田での学術交流に参加した研究者から聞いた話だ。ハニ族の人たちはとても前向きな性格で、「水が飲めたら酒を飲め、声が出たら歌え、歩けたらダンスを踊れ」というそうだ。一言でいうならば、人生を楽しもう、これが長生き健康の秘けつである、と。先祖が創り上げた、壮大な棚田を維持するすためには、勤労意欲、そして健康で長生きでなければならない。そのような前向きな民族性がこの棚田を守る精神的なベースとしてある、というのだ。
もう一つ健康に関する話題を。政府の規制改革会議が、一般用医薬品のインターネット販売に関し、原則として全面自由化を求める方針を固めたとメディア各社が報じている(7日)。あす8日に規制改革会議を開き、厚生労働省に対して薬事法の改正などを求める、という。これまで副作用のリスクが高い第1類など薬のネット販売は省令で禁止されていたが、ネット販売会社が起こした訴訟判決で最高裁はことし1月、省令について「薬事法の委任の範囲を超えて違法」と判断、事実上ネット販売が解禁されている。規制改革会議としては、全面自由化の前提として、販売履歴の管理や販売量の制限といった安全確保策に関して議論する。
 医薬品のネット販売は一見、選挙運動のネット解禁とイメージがだぶり、規制改革のシンボルのように思える。が、個人的な感想で言えば、「これ以上、国民を薬漬けにするな」との思いもわく。高血圧患者4千万人、高コレステロール血症(高脂血症)3千万人、糖尿病は予備軍含めて2300万人・・・と、日本にはすごい数の「病人」がいる(近藤誠著『医者に殺されない47の心得』より引用)。たとえば、高血圧の基準が、最高血圧の基準は160㎜Hgだったものが、2000年に140に、2008年のメタボ検診では130にまで引き下げられた。50歳を過ぎたら「上が130」というのは一般的な数値なので、たいい高血圧患者にされ、降圧剤を飲んで「治療」するハメになる(同)。その結果として、1988年には降圧剤の売上は2000億円だったものが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売上が6倍に伸びた計算だ。
医薬品のネット販売は一見、選挙運動のネット解禁とイメージがだぶり、規制改革のシンボルのように思える。が、個人的な感想で言えば、「これ以上、国民を薬漬けにするな」との思いもわく。高血圧患者4千万人、高コレステロール血症(高脂血症)3千万人、糖尿病は予備軍含めて2300万人・・・と、日本にはすごい数の「病人」がいる(近藤誠著『医者に殺されない47の心得』より引用)。たとえば、高血圧の基準が、最高血圧の基準は160㎜Hgだったものが、2000年に140に、2008年のメタボ検診では130にまで引き下げられた。50歳を過ぎたら「上が130」というのは一般的な数値なので、たいい高血圧患者にされ、降圧剤を飲んで「治療」するハメになる(同)。その結果として、1988年には降圧剤の売上は2000億円だったものが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売上が6倍に伸びた計算だ。
高血圧の原因は、9割以上が不明という。また、日本人の血圧が下げることによって死亡率が下がる、心臓病や脳卒中などが減ると実証されたデータは見当たらない(同)。近藤氏の著書を読んで、話を総合すると、日本人ほど医者と薬を信用する民族はいない。信じ切っている。そして「信じる者は救われる」と思っている。一方で、さして根拠もなく、数値データで「病気」にされ、薬を飲む。
個人的な感想と言ったのも、じつは自分自身も「高血圧症」でもう10年余り前から降圧剤を服用している。首筋あたりが重く感じられ、病院で血圧を測ったところ160だったので、それ以来ずっとである。そのとき医者から「このまま放っておくと血管がボロボロになりますよ」と言われたのが病院通いのスタートだった。毎日4種の降圧剤を飲み続けている。
近藤氏はこう書いている。フィンランドで75歳から85歳までの「降圧剤を飲まない」男女521人の経過の調査で、80歳以上のグループでは、最高血圧が180以上の人たちの生存率が最も高く、140を切った人たちの生存率はガクンと下がる。なのに日本では、最高血圧130で病気にされる、薬で下げさせられている。もし、このようなデータが日本で調査されているのであれば、ぜひ公開していほしいと望む。
本の副題は「医療と薬を遠ざけて、元気に長生きする方法」。なるべくならば薬は飲みたくない、医者にもかかりたくない。持病があったとしても、ハニ族のように「水が飲めたら酒を飲め、声が出たら歌え、歩けたらダンスを踊れ」と前向きに人生をまっとうしたいものだ。
⇒7日(木)夜・金沢の天気 はれ
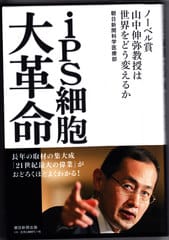 ことし夢と希望と感動を与えてくれた一番の出来事は何かと問われれば、それは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の作製に成功した山中伸弥教授(京都大学)がノーベル医学生理学賞を受賞したこと、と答えたい。先般、朝日新聞科学医療部から本をいただいた。山中教授のiPS細胞開発の経緯や医療応用への課題などをまとめた『iPS細胞大革命 ノーベル賞山中伸弥教授は世界をどう変えるか』(朝日新聞出版)=写真=。その中には、壮大な研究に挑む山中氏の言葉が詰まっている。
ことし夢と希望と感動を与えてくれた一番の出来事は何かと問われれば、それは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の作製に成功した山中伸弥教授(京都大学)がノーベル医学生理学賞を受賞したこと、と答えたい。先般、朝日新聞科学医療部から本をいただいた。山中教授のiPS細胞開発の経緯や医療応用への課題などをまとめた『iPS細胞大革命 ノーベル賞山中伸弥教授は世界をどう変えるか』(朝日新聞出版)=写真=。その中には、壮大な研究に挑む山中氏の言葉が詰まっている。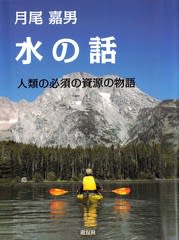 の血液であった水分が現在の河川の水流になったり、昨夜の夕食のスープの材料になっていることも十分にありえます」と筆者、月尾嘉男氏は考えた。おそらく趣味のカヤックをこぎながら海を眺め、そう発想したに違いない。著書『水の話』(遊行社)は水にまつわる時空を超えた壮大な話である。
の血液であった水分が現在の河川の水流になったり、昨夜の夕食のスープの材料になっていることも十分にありえます」と筆者、月尾嘉男氏は考えた。おそらく趣味のカヤックをこぎながら海を眺め、そう発想したに違いない。著書『水の話』(遊行社)は水にまつわる時空を超えた壮大な話である。 冒頭で述べたように、もともと淡水という資源は限られ、人口が増えるにつれ、源流から河口までに複数の国を流れる「国際河川」では紛争が起きやすい。インドシナ半島を流れる大河メコンは、中国南部のチベット高原を源流とし、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムを通過する。中国が最近巨大なダムの建設を開始している、という。中国側は水力発電をするだけで、水はそのまま下流に放水するとから影響はないと言っているが、「下流の国々は疑心暗鬼です」(筆者)と。
冒頭で述べたように、もともと淡水という資源は限られ、人口が増えるにつれ、源流から河口までに複数の国を流れる「国際河川」では紛争が起きやすい。インドシナ半島を流れる大河メコンは、中国南部のチベット高原を源流とし、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムを通過する。中国が最近巨大なダムの建設を開始している、という。中国側は水力発電をするだけで、水はそのまま下流に放水するとから影響はないと言っているが、「下流の国々は疑心暗鬼です」(筆者)と。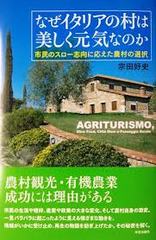 最近読んだ『なぜイタリアの村は美しく元気なのか~市民のスロー志向に応えた農村の選択~』(宗田好史著・学芸出版社)にかかれている状況は、現在の日本のそれと同じだ。イタリアの農業生産はGDPの2.3%、農家は全世帯の3.8%に減った(2009年)。日本は、GDPに占める農業の割合は0.9%だが、農家の全世帯に占める割合は4.5%だ。ただし、農家一戸当たりの耕作面積は日本1.6㌶、イタリア7.9㌶と比較にならないほどイタリアの農家は土地持ちだ。土地面積は少なくとも農業人口の比率はイタリアより多いのでうまく農業経営をやっているとのだと思ってしまうが、日本の場合は農業補助金が現在でも5.5兆円あるので、補助金でなんとか農業人口を支えていると表現した方が良さそうだ。
最近読んだ『なぜイタリアの村は美しく元気なのか~市民のスロー志向に応えた農村の選択~』(宗田好史著・学芸出版社)にかかれている状況は、現在の日本のそれと同じだ。イタリアの農業生産はGDPの2.3%、農家は全世帯の3.8%に減った(2009年)。日本は、GDPに占める農業の割合は0.9%だが、農家の全世帯に占める割合は4.5%だ。ただし、農家一戸当たりの耕作面積は日本1.6㌶、イタリア7.9㌶と比較にならないほどイタリアの農家は土地持ちだ。土地面積は少なくとも農業人口の比率はイタリアより多いのでうまく農業経営をやっているとのだと思ってしまうが、日本の場合は農業補助金が現在でも5.5兆円あるので、補助金でなんとか農業人口を支えていると表現した方が良さそうだ。 元亀2年(1571)、織田信長は比叡山延暦寺を焼き討ちし、僧侶などを皆殺しにしたといわれている。後世の人々は、丸腰の坊さんや罪のなき人たちを皆殺しにしたことから織田信長は残酷残忍で、宗教弾圧を行った人と脳裏に焼き付けている。では、当時、坊さんたちは丸腰だったのか。比叡山延暦寺は「天文法華の乱」という、京都の法華寺院を焼き討ちし大量虐殺を行っている。広辞苑ではこう記されている。「天文五年(1536)、比叡山延暦寺の僧徒ら18万人が京都の法華宗徒を襲撃した事件。日蓮宗21寺が焼き払われ、洛中ほとんど焦土と化した。天文法難。」と。平安時代中ごろから「強訴(ごうそ)」と呼ばれた威圧的なデモンストレーション(僧兵が神輿を担いで都に押し掛ける)を通じて朝廷に圧力をあけるいったこともやっていた。その延長線上に天文法華の乱がある。
元亀2年(1571)、織田信長は比叡山延暦寺を焼き討ちし、僧侶などを皆殺しにしたといわれている。後世の人々は、丸腰の坊さんや罪のなき人たちを皆殺しにしたことから織田信長は残酷残忍で、宗教弾圧を行った人と脳裏に焼き付けている。では、当時、坊さんたちは丸腰だったのか。比叡山延暦寺は「天文法華の乱」という、京都の法華寺院を焼き討ちし大量虐殺を行っている。広辞苑ではこう記されている。「天文五年(1536)、比叡山延暦寺の僧徒ら18万人が京都の法華宗徒を襲撃した事件。日蓮宗21寺が焼き払われ、洛中ほとんど焦土と化した。天文法難。」と。平安時代中ごろから「強訴(ごうそ)」と呼ばれた威圧的なデモンストレーション(僧兵が神輿を担いで都に押し掛ける)を通じて朝廷に圧力をあけるいったこともやっていた。その延長線上に天文法華の乱がある。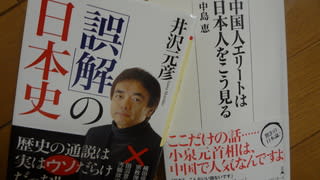 『中国人エリートは日本人をこう見る』で紹介されている中国人エリートは中国共産党や政府の将来を嘱望された若手といった現役ではなく、日本の大学で学ぶ留学生や日本の企業で職を得て働く若者ら、いわば「未来のエリート」たちである。筆者は、彼らに粘り強くインタビューして、日本に対する本音を引き出している。
『中国人エリートは日本人をこう見る』で紹介されている中国人エリートは中国共産党や政府の将来を嘱望された若手といった現役ではなく、日本の大学で学ぶ留学生や日本の企業で職を得て働く若者ら、いわば「未来のエリート」たちである。筆者は、彼らに粘り強くインタビューして、日本に対する本音を引き出している。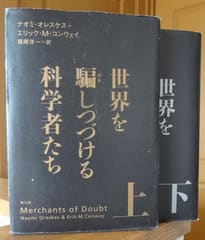 原題(『Merchants of Doubt』)の直訳は「疑念の商人たち」。信頼に値する全米科学アカデミー総裁を務めた人やアメリカ合衆国政府の科学顧問らの実名を挙げて、環境保護に関する研究をことごとく批判してきた経緯を列挙している。それらの肩書を持つ科学者の語りや論評、書評、著作だったら、取材するジャーナリスト、あるいは彼らが書く『ウオールストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』での掲載記事は読者は信頼するだろう。ところが、肩書きを持った科学者たちの論は一見して健全な科学批判に見えるが、タバコ産業などの企業と組んで環境保護に関する研究に疑念を売り込み、政府の対応を遅らせてきた。だから「疑念の商人たち」なのである。
原題(『Merchants of Doubt』)の直訳は「疑念の商人たち」。信頼に値する全米科学アカデミー総裁を務めた人やアメリカ合衆国政府の科学顧問らの実名を挙げて、環境保護に関する研究をことごとく批判してきた経緯を列挙している。それらの肩書を持つ科学者の語りや論評、書評、著作だったら、取材するジャーナリスト、あるいは彼らが書く『ウオールストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』での掲載記事は読者は信頼するだろう。ところが、肩書きを持った科学者たちの論は一見して健全な科学批判に見えるが、タバコ産業などの企業と組んで環境保護に関する研究に疑念を売り込み、政府の対応を遅らせてきた。だから「疑念の商人たち」なのである。 先日、能登空港の観光ガイドコーナーで『Fのさかな‐22号』という無料の冊子を手にした。特集が鯔(ぼら)だった。この冊子の名前が面白い。「F」はフィッシュ(魚)やフード(食)、フレンド(友)の意味合いや、能登半島の地形も「F」に似ているので、さまざまな意味をかけているらしい。要するに「能登半島の魚」という意味だ。石川県漁業協同組合などがスポンサーになっている。ボラの特集記事は読み応えがある。いくつか抜粋しながら、寿司屋での談義として再構成してみた。
先日、能登空港の観光ガイドコーナーで『Fのさかな‐22号』という無料の冊子を手にした。特集が鯔(ぼら)だった。この冊子の名前が面白い。「F」はフィッシュ(魚)やフード(食)、フレンド(友)の意味合いや、能登半島の地形も「F」に似ているので、さまざまな意味をかけているらしい。要するに「能登半島の魚」という意味だ。石川県漁業協同組合などがスポンサーになっている。ボラの特集記事は読み応えがある。いくつか抜粋しながら、寿司屋での談義として再構成してみた。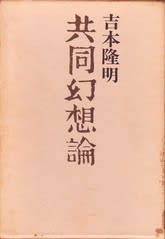 本棚の『共同幻想論』=写真・表紙=を再び手に取ってページをめくってみると、ラインを入れたり、書き込みもあって当時はそれなりに読み込んだ形跡がある。思い出しながら、共同幻想を一言で表現すれば、社会は言葉で創った幻想の世界を共同で信じ、それを実体のものと思い込んで暮らしている、ということか。言葉で編み込まれた世界を「現実そのもの」といったん勘違いすると、そこから抜け出すのは困難だ。相対化、客観化が難しいのである。今の言葉でたとえれば、マインドコントロールの状態か。遠野物語や古事記の2つの文献の分析を通して、共同幻想、対幻想、自己幻想という3つの幻想領域を想定し、吉本隆明の考える幻想領域の意味を次第に明確化し、古代国家成立の考察に至る過程は当時新鮮だった。
本棚の『共同幻想論』=写真・表紙=を再び手に取ってページをめくってみると、ラインを入れたり、書き込みもあって当時はそれなりに読み込んだ形跡がある。思い出しながら、共同幻想を一言で表現すれば、社会は言葉で創った幻想の世界を共同で信じ、それを実体のものと思い込んで暮らしている、ということか。言葉で編み込まれた世界を「現実そのもの」といったん勘違いすると、そこから抜け出すのは困難だ。相対化、客観化が難しいのである。今の言葉でたとえれば、マインドコントロールの状態か。遠野物語や古事記の2つの文献の分析を通して、共同幻想、対幻想、自己幻想という3つの幻想領域を想定し、吉本隆明の考える幻想領域の意味を次第に明確化し、古代国家成立の考察に至る過程は当時新鮮だった。 もう一つ。ことし金沢の自宅周辺は雪が多かった。スコップでの除雪は、2月前半は来る日も来る日もだった。そのうち、右肩が上がらなくなってきた。軽い腱鞘炎だと自己判断している。カバンがいつもより重い。テーブルに座って、ワインのボトルを持って、グラスに注ぐのでさえ痛みがある。57歳の身にとって、数日安静にして、休養すればよいのに、不徳のいたすところで、毎日酒は欠かさず、夜中に起きてはPCに向かってもいる。
もう一つ。ことし金沢の自宅周辺は雪が多かった。スコップでの除雪は、2月前半は来る日も来る日もだった。そのうち、右肩が上がらなくなってきた。軽い腱鞘炎だと自己判断している。カバンがいつもより重い。テーブルに座って、ワインのボトルを持って、グラスに注ぐのでさえ痛みがある。57歳の身にとって、数日安静にして、休養すればよいのに、不徳のいたすところで、毎日酒は欠かさず、夜中に起きてはPCに向かってもいる。