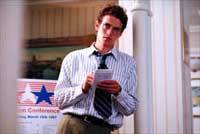★デジタル・ブラックホール

5月31日付の朝日新聞経済面では、関西の主な民放テレビ5社の3月期決算が紹介されていた。おおむね好決算の内容の記事の末尾は「だが、地上デジタル放送に対応した放送機材の高度化費用が負担となっており、06年3月期はほぼ全社で経常減益を見込む」と締めくくられていた。簡単に言えば、今年度はデジタル放送関連の設備投資が膨らみ、経常利益は減るというのだ。この記事の意味するところは何か。
東京、大阪、名古屋のいわゆる東名阪地区はローカル局より早く地上波のデジタル化を終えている(2003年12月)。記事にある「放送機材の高度化費用」とは、データ放送の充実や、携帯向けの「1セグ放送」などの次なるデジタル化への設備投資なのだ。放送機材はそれぞれの局に応じたオーダーメイドで生産されるため高コストが常だ。問題は、データ放送や1セグ放送の設備投資をしたからと言って、十分なペイがあるかという一点に尽きるが、これはない。企業の広告宣伝費がデータ放送、つまりテキストコンテンツにまで回るだろうか。さらに、地上放送とは別の番組を流すことになっている1セグ放送も余程魅力あるコンテンツでないと課金などのビジネスモデルの構築は難しいだろう。
民放は利益率が高い。国はそこをよく見ていて、地上波のデジタル化によるさまざまな可能性を試すことによって、家電の売れ行きなど経済への波及効果を期待している。これは、とりもなおさず「大いなる産業実験」なのだ。いくら利益を出しても、国の産業実験に次から次へと付き合わされ利益を吐き出していく。際限なきデジタル化投資、まるで、ブラックホールかアリ地獄に落ちた徒労感を感じている経営者も少なくないはずだ。民放が国のライセンス事業である限りつきまとわれる。
そうこうしているうちにインターネットの広告市場がテレビCM市場を追い上げてくる。ブロードバンド放送(ビデオ・オン・デマンド)が爆発的に普及し始めるのも時間の問題だ。そうなればテレビメディアのそのものの存在感が薄れ、広告シェアが落ちる。テレビ業界は今後どう新たなビジネスモデルを開発していくのか。
→1日(水)午前・金沢の天気 晴れ