☆JanJanからの手紙
きょう8日、出張から帰宅すると、「日本インターネット新聞社」から封書が届いていた。「何だろうインターネット新聞社って。まさか架空請求書じゃないだろうな」と少々疑念を持ちながら封を切った。すると「編集委員選賞」の受賞のお知らせと図書カード(1000円分)=写真=が同 封されていた。これで日本インターネット新聞社はインターネット新聞サイト「JanJan」を運営する会社だったことに気づいた。
封されていた。これで日本インターネット新聞社はインターネット新聞サイト「JanJan」を運営する会社だったことに気づいた。
JanJanにはたまに投稿している。私が勤める金沢大学のイベントや、地域の話題など。今回、編集委員選賞に選ばれたのは6月14日に投稿した「マエストロ岩城の死を悼む」である。選ばれた理由は、記事の内容より、むしろタイムリーに投稿したためではなかったかと考えている。指揮者・岩城宏之さんの死去は13日、投稿は翌日だった。
ところで、インターネット新聞といえば、日本ではJanJanが独走している。ここにきて強力なライバルが出現した。韓国で大きな影響力を持つインターネット新聞「オーマイニュース」の日本版が8月下旬にも立ち上がる。5月の記者発表で、編集長には元毎日新聞記者でジャーナリストの鳥越俊太郎氏が就任することが明らかに。さらに、日本語版を発行する現地法人のオーマイニュース・インターナショナル(東京)は、70%を韓国のオーマイニュース、30%をソフトバンクが出資している。ソフトバンクという強力なバックが存在するのだ。
そのライバル出現をかなり意識してか、今回届いた封書には、「ぜひご参加ください」と呼びかけるパンフレットも同封されていた。同社の会社概要によれば、代表取締役は竹内謙氏(前鎌倉市長、元朝日新聞編集員)。ソフト開発大手の「富士ソフト」会長で創業者の野沢宏氏が取締役に、同じく取締役に岩見隆夫氏(毎日新聞社特別顧問)らが名を連ねる。
競争はよい意味でお互いのレベルを高める。図書カードをもらったからではないが、エールを送りたい。
⇒8日(土)夜・金沢の天気 あめ
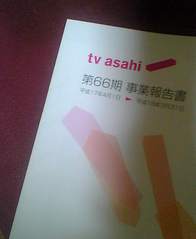 。この数字で見る限り、すでに株式公開(2000年10月)で得た手元資金でデジタル化を乗り切り、経済循環の好転を受けて巡航速度で母船(キー局)は走り出している、との印象だ。
。この数字で見る限り、すでに株式公開(2000年10月)で得た手元資金でデジタル化を乗り切り、経済循環の好転を受けて巡航速度で母船(キー局)は走り出している、との印象だ。
 手はそこまで意識して書いているのか、と逆に推測したりする。
手はそこまで意識して書いているのか、と逆に推測したりする。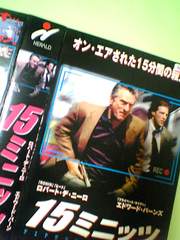 故や人種暴動、ピストル事件、凶悪殺人犯ら徒(あだ)花も数多く描かれた。そして、ウォーホルはこんな言葉を残した。「人は誰でも、その生涯の中で15分間は有名になれる時代がくる」
故や人種暴動、ピストル事件、凶悪殺人犯ら徒(あだ)花も数多く描かれた。そして、ウォーホルはこんな言葉を残した。「人は誰でも、その生涯の中で15分間は有名になれる時代がくる」  ると伝えている。
ると伝えている。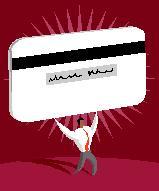 17日付の記事。見出しは「アジア太平洋地域諸国のうち、ゴールドカードを最もたくさん使っているのは韓国人」。ビザカード・コリアによると、今年3月現在、韓国人が保有しているビザ・ゴールドカードは1400万枚で、アジア太平洋地域全体のビザ・ゴールドカードの34%を占め、日本(480万枚)より3倍も多い。ゴールドカードよりワンランク上のプラチナカードの場合、韓国は260万枚(日本5万枚)になる。この数字を見る限り、4600万人の国民の3人に1人がゴールドカードを持つ、アジアでもっとも裕福でエクセレンな国が韓国となる。
17日付の記事。見出しは「アジア太平洋地域諸国のうち、ゴールドカードを最もたくさん使っているのは韓国人」。ビザカード・コリアによると、今年3月現在、韓国人が保有しているビザ・ゴールドカードは1400万枚で、アジア太平洋地域全体のビザ・ゴールドカードの34%を占め、日本(480万枚)より3倍も多い。ゴールドカードよりワンランク上のプラチナカードの場合、韓国は260万枚(日本5万枚)になる。この数字を見る限り、4600万人の国民の3人に1人がゴールドカードを持つ、アジアでもっとも裕福でエクセレンな国が韓国となる。 に突風が吹き、テントの中にあった棚の上の陶器が飛ばされたという。
に突風が吹き、テントの中にあった棚の上の陶器が飛ばされたという。 94日間で読んだ本は200冊に上ったという。百科事典のほか、中国の歴史書である「史記」や「白い巨塔」(山崎豊子著)、それに韓国語の勉強もしていたらしい。体重は8㌔減量。ダイエットした人なら想像はつくかもしれないが、3ヵ月で8㌔は無理のない数字である。適度な運動をし、間食せず、就寝前3時間は物を口にしなければ無理しなくともこのくらいの減量は可能だろう。
94日間で読んだ本は200冊に上ったという。百科事典のほか、中国の歴史書である「史記」や「白い巨塔」(山崎豊子著)、それに韓国語の勉強もしていたらしい。体重は8㌔減量。ダイエットした人なら想像はつくかもしれないが、3ヵ月で8㌔は無理のない数字である。適度な運動をし、間食せず、就寝前3時間は物を口にしなければ無理しなくともこのくらいの減量は可能だろう。 サンデープロジェクト」にも見入った。
サンデープロジェクト」にも見入った。