☆メディアのツボ-38-
宮崎県の官製談合事件での前知事の辞職に伴う出直し知事選がきのう21日行われ、新人の元タレント・そのまんま東氏(49)=無所属=が初当選を果たした。知名度を生かし、草の根選挙を展開。入札制度改革や農産物を「そのまんまブランド」として売り出すことなどを訴え、激戦を制した。
「そのまんま東」トップにせず
 当初、「泡沫候補」とも言われていた元タレント候補が激戦を制したとあって、各新聞やテレビはトップニュースの扱いで報じた。ところが、このニュースを朝日新聞大阪本社はトップ扱いにしなかった。同じ朝日新聞でも、東京本社はトップだったのにである。大阪本社の一面トップは生活福祉資金の貸付金の272億円が未回収であることを報じたものだ。ホットなニュースである「そのまんま東氏当選」は準トップだった。なぜか、である。
当初、「泡沫候補」とも言われていた元タレント候補が激戦を制したとあって、各新聞やテレビはトップニュースの扱いで報じた。ところが、このニュースを朝日新聞大阪本社はトップ扱いにしなかった。同じ朝日新聞でも、東京本社はトップだったのにである。大阪本社の一面トップは生活福祉資金の貸付金の272億円が未回収であることを報じたものだ。ホットなニュースである「そのまんま東氏当選」は準トップだった。なぜか、である。
きょう、私が担当する「プロと語る実践的マスメディア論」の授業の中で、その答えを直接聞くことができた。授業で講義をお願いした朝日新聞大阪本社の嶋田数之編集局長補佐が授業の中でこう説明した。「確かに、(そのまんま東氏の)当選はニュースだ。しかし、未知数のものをトップで扱って、最初から持ち上げることはできない」と編集判断で抑制を効かせたことを語った。
その背景の一つは、「横山ノックの記憶」がまだ新しいからだろう。大阪府知事だった横山ノック氏は1999年、APECの成功など実績も評価されて2期目の選挙で235万票という大阪新記録の得票によって再選された。しかしその選挙活動の際に自陣営の運動員をしていた女子大生にセクハラをしていたことが選挙終了後に発覚し、当初は否定して2期目に就任したものの、同年12月に強制わいせつ罪で在宅起訴され、2000年1月に辞職に追い込まれた。
嶋田氏が「未知数」というのも、今回の選挙は官製談合事件が背景にあり、田中康夫氏(前長野県知事)の「脱ダム宣言」のように新しい政治の風をつくったというわけではない。さらに、1998年に当時16歳の少女からいかがわしいサービスを受けて、児童福祉法違反で事情聴取を受けるなど、「横山ノックの記憶」と微妙にダブってくる。トップ扱いにするには、確かに「未知数」な部分が多い。
当選後の会見で、そのまんま東氏は本名の東国原英夫(ひがしこくばる・ひでお)で今後、政治活動をしていくと言う。確かに、選挙中もかつての同僚のタレントの応援を断って草の根運動を「マラソン」で展開した。それだったら、「脱タレント宣言」をして、立候補の段階から本名を名乗るべきだったろう。
当選のニュースを聞いて、何人かと話題にした。すると、「宮崎県政はさらに混乱するのではないか」との話になり、巷間では決して好意的には受け止められていない。当選は驚きであったが、期待感がついてこない。この意味でも、ニュース価値としてトップにしなかった朝日新聞大阪本社の扱いはプロの冷静な判断であったと言える。
⇒22日(月)夜・金沢の天気 くもり
 「単なる物販サイトではない。地域おこしの心意気でやっている」。北陸朝日放送(HAB)業務部、能田剛志部長は力を込めた。講演タイトルは「ECサイト『金沢屋』の6年で得たローカル独自のコマース展開とは」。放送エリアである石川県の地場産品にこだわり、この6年で生産者とともに100余りの商品を開発した。商品の採用が決まると、プロの写真家とライターが現地に入り、取材する。生産者の人となりや商品ができるまでの物語がテキストベースで紹介される。単に商品の画像を並べただけのショッピングモールとは異なり、手間ひま(コスト)をかけている。そのせいもあり、売上は緩やかな右肩上がりであるものの、単年度の黒字決算には至っていない。「(単年度黒字は)08年を目標にしている」と。今年5月、姉妹サイトとして「山形屋」(山形テレビ)が誕生した。システムと運営ノウハウを系列局にのれん分けするほどになったのである。
「単なる物販サイトではない。地域おこしの心意気でやっている」。北陸朝日放送(HAB)業務部、能田剛志部長は力を込めた。講演タイトルは「ECサイト『金沢屋』の6年で得たローカル独自のコマース展開とは」。放送エリアである石川県の地場産品にこだわり、この6年で生産者とともに100余りの商品を開発した。商品の採用が決まると、プロの写真家とライターが現地に入り、取材する。生産者の人となりや商品ができるまでの物語がテキストベースで紹介される。単に商品の画像を並べただけのショッピングモールとは異なり、手間ひま(コスト)をかけている。そのせいもあり、売上は緩やかな右肩上がりであるものの、単年度の黒字決算には至っていない。「(単年度黒字は)08年を目標にしている」と。今年5月、姉妹サイトとして「山形屋」(山形テレビ)が誕生した。システムと運営ノウハウを系列局にのれん分けするほどになったのである。 表格の番組がテレビ朝日系・火曜日夜9時の「ロンドンハーツ」かもしれない。何しろ、系列内部では「平均14%を超える高い視聴率をマークした」と評判がすこぶるいい。中でも05年10月に放送された「青木さやかパリコレへ!」は19.2%を獲得して、裏番組のガリバー「踊る!さんま御殿!!」を9.8%と1ケタに落とすというテレ朝にとっては「快挙」も成し遂げた。
表格の番組がテレビ朝日系・火曜日夜9時の「ロンドンハーツ」かもしれない。何しろ、系列内部では「平均14%を超える高い視聴率をマークした」と評判がすこぶるいい。中でも05年10月に放送された「青木さやかパリコレへ!」は19.2%を獲得して、裏番組のガリバー「踊る!さんま御殿!!」を9.8%と1ケタに落とすというテレ朝にとっては「快挙」も成し遂げた。 法案を出す出さないは内閣が今夏の参院選挙をにらんだり、各種の経済指標と照らし合わせてを決定することで論評する気はない。ただ、私自身、この残業問題というのは、この言葉を聞いただけでも正直うんざりするくらい憂鬱な気分になる。この問題で2年間苦しんだことがある。
法案を出す出さないは内閣が今夏の参院選挙をにらんだり、各種の経済指標と照らし合わせてを決定することで論評する気はない。ただ、私自身、この残業問題というのは、この言葉を聞いただけでも正直うんざりするくらい憂鬱な気分になる。この問題で2年間苦しんだことがある。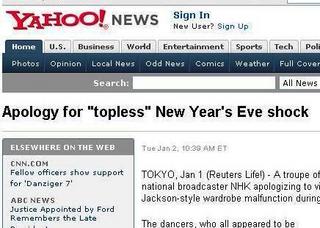 NHKホームページの紅白歌合戦のページでお詫びが出た。3日午後11時ごろにチェックした。文面は以下だった。「DJ OZMAのバックダンサーが裸と見間違いかねないボディスーツを着用して出演した件について、NHKではこのような姿になるということは放送まで知りませんでした。衣装の最終チェックであるリハーサルでは放送のような衣装ではありませんでした。今回の紅白のテーマにふさわしくないパフォーマンスだったと考えます。視聴者の皆様に深いな思いをおかけして誠に申し訳なく考えております」
NHKホームページの紅白歌合戦のページでお詫びが出た。3日午後11時ごろにチェックした。文面は以下だった。「DJ OZMAのバックダンサーが裸と見間違いかねないボディスーツを着用して出演した件について、NHKではこのような姿になるということは放送まで知りませんでした。衣装の最終チェックであるリハーサルでは放送のような衣装ではありませんでした。今回の紅白のテーマにふさわしくないパフォーマンスだったと考えます。視聴者の皆様に深いな思いをおかけして誠に申し訳なく考えております」 そのおさらい。政府のタウンミーティング調査委員会の最終報告書(12月13日)を読んでいくと、15回の「やらせ」のうち6回が法務省がらみ。04年12月18日(東京)、05年1月15日(香川)、05年4月17日(宇都宮)、05年6月25日(金沢)、05年10月23日(那覇)、06年3月25日(宮崎)の6回のうち、宮崎を除く5回で一致点があった。そのすべてに当時の法務大臣、南野(のおの)知恵子氏(参議員)が出席していた。南野氏と言えば、04年8月の第2次小泉改造内閣で法務大臣に就任して以来、「なにぶん専門家ではないもので」と述べて失言が取りざたされていた。もともと看護婦さんだったので、支援団体は日本看護協会。法務とは畑違いなので、前述のような発言になったのだろう。
そのおさらい。政府のタウンミーティング調査委員会の最終報告書(12月13日)を読んでいくと、15回の「やらせ」のうち6回が法務省がらみ。04年12月18日(東京)、05年1月15日(香川)、05年4月17日(宇都宮)、05年6月25日(金沢)、05年10月23日(那覇)、06年3月25日(宮崎)の6回のうち、宮崎を除く5回で一致点があった。そのすべてに当時の法務大臣、南野(のおの)知恵子氏(参議員)が出席していた。南野氏と言えば、04年8月の第2次小泉改造内閣で法務大臣に就任して以来、「なにぶん専門家ではないもので」と述べて失言が取りざたされていた。もともと看護婦さんだったので、支援団体は日本看護協会。法務とは畑違いなので、前述のような発言になったのだろう。 政府が発表した「タウンミーティング調査委員会最終報告」(今月13日)をもとに金沢でのタウンミーティングの「やらせ」を検証すると、法務省から金沢地検と金沢地方法務局に質問者探しの指示があった。実際、去年6月25日のタウンミーティングでは地検や法務局の職員の友人・親戚3人が発言した。
政府が発表した「タウンミーティング調査委員会最終報告」(今月13日)をもとに金沢でのタウンミーティングの「やらせ」を検証すると、法務省から金沢地検と金沢地方法務局に質問者探しの指示があった。実際、去年6月25日のタウンミーティングでは地検や法務局の職員の友人・親戚3人が発言した。 大手紙の全国調査は選挙人名簿から3000人を地域的や性別・年代などの偏りがないように無作為で選び、「有権者全体の縮図」をつくる。全国の有権者は1億330万人(05年)なので、1人がおよそ3万人余りの代表となるわけだ。ちなみに私が住む石川県の場合だと28人が調査対象数だ。
大手紙の全国調査は選挙人名簿から3000人を地域的や性別・年代などの偏りがないように無作為で選び、「有権者全体の縮図」をつくる。全国の有権者は1億330万人(05年)なので、1人がおよそ3万人余りの代表となるわけだ。ちなみに私が住む石川県の場合だと28人が調査対象数だ。 記事によると、記者はゴルフ場に生息してたオオタカの取材をきっかけにゴルフ経営者と知り合った。そして、02年8月に記者が異動する際、餞別として封筒を受け取り、04年9月に大阪本社に戻った時にも、出産祝いとして封筒を渡された。記者は「いつか返そう」と思い、封筒の封を切らずにカンバに入れていた。ところが、今月15日に一部の情報誌が「ゴルフ場経営者が大手紙記者に現金百万円」とする記事を掲載したことから、記者が上司に報告した。そして、未開封だった封筒を弁護士立ち合いで開けて、異動祝いが10万円、出産祝いが5万円だったことが分かったという。
記事によると、記者はゴルフ場に生息してたオオタカの取材をきっかけにゴルフ経営者と知り合った。そして、02年8月に記者が異動する際、餞別として封筒を受け取り、04年9月に大阪本社に戻った時にも、出産祝いとして封筒を渡された。記者は「いつか返そう」と思い、封筒の封を切らずにカンバに入れていた。ところが、今月15日に一部の情報誌が「ゴルフ場経営者が大手紙記者に現金百万円」とする記事を掲載したことから、記者が上司に報告した。そして、未開封だった封筒を弁護士立ち合いで開けて、異動祝いが10万円、出産祝いが5万円だったことが分かったという。 月尾氏は文明批評家でもある。金沢での講演では、経済優先主義で没落したカルタゴ、造船の技術革新に出遅れたベネチアなどの事例を挙げ、「現代の日本は歴史に学ぶべき」と。
月尾氏は文明批評家でもある。金沢での講演では、経済優先主義で没落したカルタゴ、造船の技術革新に出遅れたベネチアなどの事例を挙げ、「現代の日本は歴史に学ぶべき」と。