☆避難住民を難民と見る視線
新潟県中越沖地震の被災地、柏崎市で奇妙な「事件」が起きた。産経新聞のインターネット版などによると、同市側は日本テレビ系列の中京テレビ(名古屋市)のスタッフが避難所のテントに「隠しマイクを仕掛けた」と公表した。中京テレビ側は市に「中継で背景の音を拾うためのワイヤレスの集音マイクで、隠す意図はなかった」と説明したという。
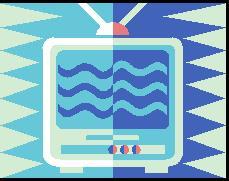 事実関係を記事で拾うと、マイクが設置されていたのは学校の屋外に張られた炊き出し用のテントで、21日午後4時ごろ、スタッフが支柱にマイクを張り付けているのを職員が見つけて注意した。スタッフはすぐに取り外した。住民からの要望で、市側が一時的に報道各社に避難所(学校)での取材の自粛を要請。中京テレビは市に同日午後6時からのニュースで中継するつもりだったと説明したが、設置は各社が屋内での取材を自粛していた最中だった。中京テレビの現地担当デスクは、「隠しマイクという発表があったようだが、誤解だったということを理解していただいた。現場の説明不足で誤解を受けたことは遺憾だ。反省している」と話しているという。
事実関係を記事で拾うと、マイクが設置されていたのは学校の屋外に張られた炊き出し用のテントで、21日午後4時ごろ、スタッフが支柱にマイクを張り付けているのを職員が見つけて注意した。スタッフはすぐに取り外した。住民からの要望で、市側が一時的に報道各社に避難所(学校)での取材の自粛を要請。中京テレビは市に同日午後6時からのニュースで中継するつもりだったと説明したが、設置は各社が屋内での取材を自粛していた最中だった。中京テレビの現地担当デスクは、「隠しマイクという発表があったようだが、誤解だったということを理解していただいた。現場の説明不足で誤解を受けたことは遺憾だ。反省している」と話しているという。
どんな説明があったとして、無断で仕掛けたのであれ、「隠しマイク」ではないか。要は、取材の自粛要請があったので、中京テレビ側はテント周辺での中継は無理と判断し、その代わり、離れた位置から望遠のカメラで現場を撮影し、中継することにした。しかし、遠く離れると現場音が取れないので、マイクを現場のテントの柱に仕掛けた、ということなのだろう。
被災者からの要望での取材の自粛要請はある意味で当然のことなのである。16日の震災発生から5日たって、避難住民にとっては避難所はすでに「生活の場」となっていて、いわば、お互いが顔見知り同士の共同生活の場なのである。見知らぬ顔は、メディアの記者たちなのである。その記者たちが避難所に入ってきて、炊き出しの中身まで取材していく。これは避難住民にとって、とても違和感があるに違いない。事実、私が「震災とメディア」というテーマで調査した能登半島地震(ことし3月25日)でも、同様に避難住民からの苦情で取材自粛の要望があった。
避難所を運営しているのは地区の自治体であり、炊き出しを行っているのはボランティアではなくその地区の住民のはずである。炊き出しの野外テントは共同の炊事場、つまり生活の場である。そこにマイクを仕掛ける(設置する)というのはどんな感覚だろうか。あたかも、被災地から逃れてきた不特定多数の難民がボランティアに支えられ、食事をするというイメージを描いての取材だとすれば、それは勘違いの視線ではないのだろうか。
取材の自粛を要請する住民の気持ちを理解せず、しかも、「生活の場」である避難所のテントにマイクを断りなく仕掛ければ、これはどう見ても「隠しマイク」ではないのか。少なくても避難住民はそう理解するだろう。雑踏の集音マイクとはわけが違う。22日午前8時現在、中京テレビのホームページを閲覧しても、この一件についての説明がないのでテレビ局側のスタンスがよく理解できない。
⇒22日(日)午前・金沢の天気 くもり
 元NHK記者は大津市などで2005年4月から6月にかけて、JR大津駅付近の住宅を全焼させるなど大津市や大阪府岸和田市で8件の放火や放火未遂を繰り返した(1審判決)。大津地裁で懲役7年の実刑判決を受け、9日に控訴審の初公判。上記の無罪を主張し、この日、結審した。判決は9月と4日に言い渡されるという。
元NHK記者は大津市などで2005年4月から6月にかけて、JR大津駅付近の住宅を全焼させるなど大津市や大阪府岸和田市で8件の放火や放火未遂を繰り返した(1審判決)。大津地裁で懲役7年の実刑判決を受け、9日に控訴審の初公判。上記の無罪を主張し、この日、結審した。判決は9月と4日に言い渡されるという。 震災の翌日(26日)に輪島市門前町の被災地に入った。能登有料道路は一部を除いて通行止めとなった。「下路(したみち)」と呼ぶ県道や市道など車で走って3時間50分かかった。金沢大学から目的地は本来1時間50分ほどの距離だ。被災地をひと回りして、夕方になり、コンビニの看板が見えたので夕食を買いに入った。ところが、弁当の棚、惣菜の棚は売り切れ。ポテトチップスなどスナック類の菓子もない。店員に聞いた。「おそらくテレビ局の方だと思うのですが、まとめて買っていかれましてね」との返事だった。
震災の翌日(26日)に輪島市門前町の被災地に入った。能登有料道路は一部を除いて通行止めとなった。「下路(したみち)」と呼ぶ県道や市道など車で走って3時間50分かかった。金沢大学から目的地は本来1時間50分ほどの距離だ。被災地をひと回りして、夕方になり、コンビニの看板が見えたので夕食を買いに入った。ところが、弁当の棚、惣菜の棚は売り切れ。ポテトチップスなどスナック類の菓子もない。店員に聞いた。「おそらくテレビ局の方だと思うのですが、まとめて買っていかれましてね」との返事だった。 聞き取り調査の中で、輪島市門前町在住の災害ボランティアコーディネーター、岡本紀雄さん(52)の提案は具体的だった。「新聞社は協力して避難住民向けのタブロイド判をつくったらどうだろう。決して広くない避難所でタブロイド判は理にかなっている」と。岡本さんは、新潟県中越地震でのボランティア経験が買われ、今回の震災では避難所の「広報担当」としてメディアとかかわってきた一人である。メディア同士はよきライバルであるべきだと思うが、被災地ではよき協力者として共同作業があってもよいと思うが、どうだろう。
聞き取り調査の中で、輪島市門前町在住の災害ボランティアコーディネーター、岡本紀雄さん(52)の提案は具体的だった。「新聞社は協力して避難住民向けのタブロイド判をつくったらどうだろう。決して広くない避難所でタブロイド判は理にかなっている」と。岡本さんは、新潟県中越地震でのボランティア経験が買われ、今回の震災では避難所の「広報担当」としてメディアとかかわってきた一人である。メディア同士はよきライバルであるべきだと思うが、被災地ではよき協力者として共同作業があってもよいと思うが、どうだろう。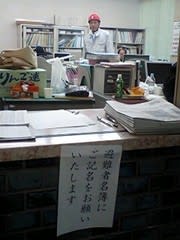 タブロイド判の裏表1枚紙で、文字が大きく行間がゆったりしている。住民が「役に立った」というのは、災害が最も大きかった被災地・輪島のライフライン情報に特化した「ミニコミ紙」だったからだ。
タブロイド判の裏表1枚紙で、文字が大きく行間がゆったりしている。住民が「役に立った」というのは、災害が最も大きかった被災地・輪島のライフライン情報に特化した「ミニコミ紙」だったからだ。 に及んだ。多くの住民は避難所でテレビやラジオのメディアと接触することになる。ここで、注目すべきことは、門前町を含める45ヵ所のすべての避難所にテレビが完備されていたことだ。地震で屋根のテレビアンテナは傾き、壊れたテレビもあったはず。一体誰が。
に及んだ。多くの住民は避難所でテレビやラジオのメディアと接触することになる。ここで、注目すべきことは、門前町を含める45ヵ所のすべての避難所にテレビが完備されていたことだ。地震で屋根のテレビアンテナは傾き、壊れたテレビもあったはず。一体誰が。 盛り上がりの要因は三つある。一つは、昨夏の甲子園で駒大苫小牧を破り優勝投手となった「ハンカチ王子」こと早稲田のルーキー、斎藤佑樹投手(18)の人気だろう。二つ目が、早稲田はルーキー斎藤の活躍もあり現在、8勝0敗の勝ち点4で首位を走っているので、今週末の早慶戦で1勝すれば2季連続の優勝が決まる。三つ目がこれまで東京六大学野球はNHKが中継してきたが、今季から日本テレビが参入し、早稲田戦を中心にBSなどで放送するなどブームを煽っている。
盛り上がりの要因は三つある。一つは、昨夏の甲子園で駒大苫小牧を破り優勝投手となった「ハンカチ王子」こと早稲田のルーキー、斎藤佑樹投手(18)の人気だろう。二つ目が、早稲田はルーキー斎藤の活躍もあり現在、8勝0敗の勝ち点4で首位を走っているので、今週末の早慶戦で1勝すれば2季連続の優勝が決まる。三つ目がこれまで東京六大学野球はNHKが中継してきたが、今季から日本テレビが参入し、早稲田戦を中心にBSなどで放送するなどブームを煽っている。
 現在、集計中なので気がついた点だけを述べる。実は「最初に使ったメディア」はテレビでもラジオでもなく、「ユウセン」なのだ。カラオケなどの音楽配信サービスのユウセンではない。門前町地区の人たちがユウセンと呼ぶのは防災無線と連動した有線放送のこと。街頭のスピーカーと、家庭で特別に敷設したスピーカー内臓の有線放送電話が同時に音声を発する。門前町地区オリジナルの防災情報システムだ。
現在、集計中なので気がついた点だけを述べる。実は「最初に使ったメディア」はテレビでもラジオでもなく、「ユウセン」なのだ。カラオケなどの音楽配信サービスのユウセンではない。門前町地区の人たちがユウセンと呼ぶのは防災無線と連動した有線放送のこと。街頭のスピーカーと、家庭で特別に敷設したスピーカー内臓の有線放送電話が同時に音声を発する。門前町地区オリジナルの防災情報システムだ。 現在は無職の32歳の男性の話だ。震災では自宅が全壊した。9時41分、母親はたまたま愛犬をシャンプーするため、風呂場に入っていて被災した。家は全壊したものの、ユニットバスというある意味で「シェルター」に守られ、九死に一生を得た。男性は、全壊した自宅や地域の惨状をなんとかしてほしいと思い、取材に来た新聞記者に惨状を訴えるつもりで上記の話をした。
現在は無職の32歳の男性の話だ。震災では自宅が全壊した。9時41分、母親はたまたま愛犬をシャンプーするため、風呂場に入っていて被災した。家は全壊したものの、ユニットバスというある意味で「シェルター」に守られ、九死に一生を得た。男性は、全壊した自宅や地域の惨状をなんとかしてほしいと思い、取材に来た新聞記者に惨状を訴えるつもりで上記の話をした。 被災者へのアンケート調査や、マスメディアへのヒアリングなどを重ね、全体像を浮かび上がればと考えている。しかし、足元がおぼつかない。アンケート調査では、学生の協力を得ようと先日、講義室で100人ほどの学生に「被災者の生の声を聞いてみよう」と呼びかけたが、反応はいまひとつ。19日と20日に開くアンケートの事前説明会では学生が集まるだろうかと不安もよぎる。何しろ新学期で、学生は何かと忙しそうだ。
被災者へのアンケート調査や、マスメディアへのヒアリングなどを重ね、全体像を浮かび上がればと考えている。しかし、足元がおぼつかない。アンケート調査では、学生の協力を得ようと先日、講義室で100人ほどの学生に「被災者の生の声を聞いてみよう」と呼びかけたが、反応はいまひとつ。19日と20日に開くアンケートの事前説明会では学生が集まるだろうかと不安もよぎる。何しろ新学期で、学生は何かと忙しそうだ。