☆メディアのこと‐下‐
そのアナログ中継局群は丘陵地に広がる葉タバコ畑の中に忽然と現れた=写真=。中にはUFOを感じさせる丸型の中継局もあり、壮観だ。石川県能登町明野(あけの)。珠洲市街に向けて建てられた大型の中継局で、能登半島の情報インフラを支えている。ここを訪れたのは、2011年7月24日のアナログ停波のちょうど2年前に当たる7月24日のこと。
能登半島の先端で「アナログ停波」リハーサル
 この日、珠洲(すず)市では全国に先駆けてアナログ停波のリハーサルが行われた。同市は能登半島の先端にある人口1万7000人の過疎化が進む地域である。戦後間もなく4万もいた人口が高度成長期を境に人口流出が起きた。揚げ浜塩田や珠洲焼、能登杜氏が有名であるほか、農業や漁業、そして街を取り巻く山々には30基の風力発電が建設され、新しいエネルギー発電に取り組んでいる。市内の電力需要を賄うには10基で足り、あと20基分は電力会社に売っている。三方を海に囲まれ、アナログ放送の停波リハーサルが行うのに、他の自治体に迷惑かからないというのが地デジ移行の国のモデル実験地に選ばれた理由だ。
この日、珠洲(すず)市では全国に先駆けてアナログ停波のリハーサルが行われた。同市は能登半島の先端にある人口1万7000人の過疎化が進む地域である。戦後間もなく4万もいた人口が高度成長期を境に人口流出が起きた。揚げ浜塩田や珠洲焼、能登杜氏が有名であるほか、農業や漁業、そして街を取り巻く山々には30基の風力発電が建設され、新しいエネルギー発電に取り組んでいる。市内の電力需要を賄うには10基で足り、あと20基分は電力会社に売っている。三方を海に囲まれ、アナログ放送の停波リハーサルが行うのに、他の自治体に迷惑かからないというのが地デジ移行の国のモデル実験地に選ばれた理由だ。
同日は10時から11時の1時間、くだんの葉タバコ畑に林立する珠洲中継局のアナログ放送電波が停止された。実際にアナログ停波の対象になったのは7500世帯だ。うちデジタル未対応は1300世帯。デジサポ珠洲では5回線10の電話を用意して、問い合わせに対応したが、この間に寄せられた電話は全部で12件だった。「リハーサルの停波は本当に1時間で終わるのか」「どうすれば地デジが見られるのか」など。そのうち1件はなんと沖縄の宮古島からの問い合わせだった。当日、NHKが特別番組を編成し、その画面にデジサポ珠洲の電話番号が大写しなった。その電話の内容は、「テレビをデジタル対応に買い替えたのに、アナログの表示が出るのなぜか」との問い合わせだった。また、「高校野球石川大会の生番組が見られないのは困る、孫が出る試合を見ることができない」と、地域ならではの苦情電話もあった。
問い合わせ件数12では、アナログ停波と地デジ対応の課題を浮き彫りにする点で、十分に検証できたとは言えないのではなかったか。市民の戸惑いがどこにあり、もっと長い時間の停波リハーサルが必要となる。これは来年1月に数日の長さでアナログ停波が行われる。 ところで、日本より一足お先にことし6月に完全デジタル化に移行したアメリカでは、今なお150万世帯がデジタル未対応という。アメリカの調査会社ニールセンによると、デジタル未対応世帯のうち、60%以上はカナダ、あるいはメキシコからのアナログ放送を視聴していて、テレビがまったく見られないわけではない。アメリカとカナダ、アメリカとメキシコの国境沿いはお互いの放送が見える。メキシコとの国境近くのヒスパニック系移民の場合は、もともと英語放送は見ていなかったのである。
四方海に囲まれた日本の場合、そのような「クッション」はない。今回の珠洲中継局のアナログ停止1時間で12件の電話をベースに、全国一斉(5000万世帯)として計算すると少なくとも8万件の電話が予想される。現時点で、沖縄、岩手、長崎、秋田、青森の5県はデジタル受信機の世帯普及率が50%に届いていない。2011年7月24日正午にアナログ波は停止し、地デジへ完全移行する。が、このときどれだけの「テレビ難民」が発生するのか、想像はつかない。
⇒12日(水)夜・金沢の天気 くもり
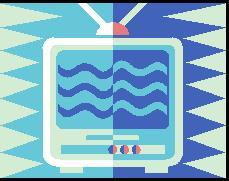 組織には何がしかの光と影がある。テレビ局の場合、どれだけ視聴率を取って、スポットライトを浴びた番組であっても、影の部分を残したまま増幅させてしまうと、その矛盾がいつかは番組に曝露してしまうものだ。520回余り続き、平均視聴率15%も取った「発掘!あるある大辞典」が問題発覚からわずか6日で番組打ち切りが宣言された。その影とは下請け問題だった。調査報告書によると、関西テレビから元請け会社(テレワーク)に渡った制作費は1本当たり3162万円だったが、孫請け会社(アジトなど9社)へは887万円だった。テレワークの粗利益率は18.6%あったという。しかし、孫請け会社は過酷な条件下に置かれた。
組織には何がしかの光と影がある。テレビ局の場合、どれだけ視聴率を取って、スポットライトを浴びた番組であっても、影の部分を残したまま増幅させてしまうと、その矛盾がいつかは番組に曝露してしまうものだ。520回余り続き、平均視聴率15%も取った「発掘!あるある大辞典」が問題発覚からわずか6日で番組打ち切りが宣言された。その影とは下請け問題だった。調査報告書によると、関西テレビから元請け会社(テレワーク)に渡った制作費は1本当たり3162万円だったが、孫請け会社(アジトなど9社)へは887万円だった。テレワークの粗利益率は18.6%あったという。しかし、孫請け会社は過酷な条件下に置かれた。 その日の日経新聞の別刷り面では、「夏休みに行きたい農園レストラン」のランキングが掲載されていた。1位の山形県鶴岡市の農家レストランは「農村の隠れ家」と紹介され、農業のサービス産業化を強調するような内容だった。農業参入にしても、農家レストランにしても何も珍しいことではないが、日経がこのように農業関連の記事を正面から取り上げること自体に何か新鮮さを感じる。
その日の日経新聞の別刷り面では、「夏休みに行きたい農園レストラン」のランキングが掲載されていた。1位の山形県鶴岡市の農家レストランは「農村の隠れ家」と紹介され、農業のサービス産業化を強調するような内容だった。農業参入にしても、農家レストランにしても何も珍しいことではないが、日経がこのように農業関連の記事を正面から取り上げること自体に何か新鮮さを感じる。 ワンセグの受信契約についてNHKのホームページで確認すると、「ワンセグ受信機も受信契約の対象です。ただし、ご家庭ですでに受信契約をいただいている場合には、新たにワンセグの受信機を購入されたとしても、改めて受信契約をしていただく必要はありません」と記載されている。問題は、一人暮らしの学生の場合である。そこで、視聴者コールセンターに電話(5月11日)をして、①学生は勉強をするために大学にきているので、受信料契約は親元がしていれば、親と同一生計である学生は契約する必要がないのではないか②携帯電話(ワンセグ付き)の購入の際、受信契約の説明が何もないのもおかしい、携帯所持後に受信契約を云々するのでは誰も納得しないーとの2点を、学生たちの声を代弁するつもりで問うてみた。すると、電話口の男性氏は「ワンセグの受信契約の対象になります。いろいろご事情はあるかと思いますが、別居の学生さんの場合は家族割引(2ヵ月で1345円)がありますのでご利用ください」と、要約すればこのような言葉を繰り返した。
ワンセグの受信契約についてNHKのホームページで確認すると、「ワンセグ受信機も受信契約の対象です。ただし、ご家庭ですでに受信契約をいただいている場合には、新たにワンセグの受信機を購入されたとしても、改めて受信契約をしていただく必要はありません」と記載されている。問題は、一人暮らしの学生の場合である。そこで、視聴者コールセンターに電話(5月11日)をして、①学生は勉強をするために大学にきているので、受信料契約は親元がしていれば、親と同一生計である学生は契約する必要がないのではないか②携帯電話(ワンセグ付き)の購入の際、受信契約の説明が何もないのもおかしい、携帯所持後に受信契約を云々するのでは誰も納得しないーとの2点を、学生たちの声を代弁するつもりで問うてみた。すると、電話口の男性氏は「ワンセグの受信契約の対象になります。いろいろご事情はあるかと思いますが、別居の学生さんの場合は家族割引(2ヵ月で1345円)がありますのでご利用ください」と、要約すればこのような言葉を繰り返した。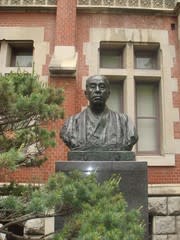 福沢は新聞事業と出版事業を巧みにメディアミックスしている。時事新報の社説で自らの論説を一つのテーマで連続的に掲載していく。そのテーマの中から読者から手応えがあったものを、今度は出版するという手法だ。「時事大勢論」「帝室論」などのヒット作品が次々生まれた。いまの手法で言えば、コンテンツの二次利用。テレビの連続ドラマの中で視聴率が高かったものを映画化して劇場公開、その後にDVD化、BC放送やCS放送で放送し、最後に「地上波初放送」とPRして自社の映画番組で放送する。一粒で二度も三度もおいしい(利益が出る)コンテンツビジネスの先駆けである。
福沢は新聞事業と出版事業を巧みにメディアミックスしている。時事新報の社説で自らの論説を一つのテーマで連続的に掲載していく。そのテーマの中から読者から手応えがあったものを、今度は出版するという手法だ。「時事大勢論」「帝室論」などのヒット作品が次々生まれた。いまの手法で言えば、コンテンツの二次利用。テレビの連続ドラマの中で視聴率が高かったものを映画化して劇場公開、その後にDVD化、BC放送やCS放送で放送し、最後に「地上波初放送」とPRして自社の映画番組で放送する。一粒で二度も三度もおいしい(利益が出る)コンテンツビジネスの先駆けである。 「政府の提灯は持たぬが、国家の提灯は持つ」。そう言い切って、福沢は明治15年(1882)3月1日に
「政府の提灯は持たぬが、国家の提灯は持つ」。そう言い切って、福沢は明治15年(1882)3月1日に 福沢諭吉展のテーマは「異端と先導~文明の進歩は異端から生まれる」。1万円札に描かれている人のどこが異端なのかというと、明治維新後、蘭学を修めたような知識人たちはこぞって官職を求めたが、福沢は生涯を無位無官、一人の民間人で通した。「独立自尊」を身上とし、政党に属さず、民間人の立場から演説をし、言論というものを追求していった。請われても、権力に属さなかった。幕府を打倒し新たな権力構造をつくり上げていった薩摩や長州の「藩閥の群像」とは明らかに異なる。「際立つ個」、明治という時代にあってこれは異端だった。
福沢諭吉展のテーマは「異端と先導~文明の進歩は異端から生まれる」。1万円札に描かれている人のどこが異端なのかというと、明治維新後、蘭学を修めたような知識人たちはこぞって官職を求めたが、福沢は生涯を無位無官、一人の民間人で通した。「独立自尊」を身上とし、政党に属さず、民間人の立場から演説をし、言論というものを追求していった。請われても、権力に属さなかった。幕府を打倒し新たな権力構造をつくり上げていった薩摩や長州の「藩閥の群像」とは明らかに異なる。「際立つ個」、明治という時代にあってこれは異端だった。 た。それぞれが体を張って現場に、あるいは最先端に立っているのだ。
た。それぞれが体を張って現場に、あるいは最先端に立っているのだ。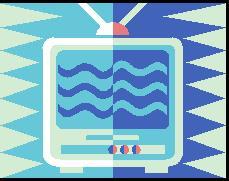 「恐慌」の文字を使わないようにしている。が、数字は強烈に物語っているではないか。
「恐慌」の文字を使わないようにしている。が、数字は強烈に物語っているではないか。 教育界では子供たちの理科離れが進んでいるとよくいわれるが、メディアの世界では科学記事の割合が広がり、たとえば朝日新聞社では30年前に20人ほどだった科学担当記者は現在では50人ほどに増えている。戦後は60年安保、70年安保と大学キャンパスでも政治闘争の嵐が吹き荒れた。が、高度成長に伴ってハイテク、ロボット、宇宙、IT、新型感染症、医療・生命倫理、食の安全と危機管理、そして環境へと、メディアの記事テーマは政治・社会から科学への「理系シフト」が起きている。それが極まったのが、ことし8月の洞爺湖サミットだ。地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構であるIPCCの科学者たちが動いて、地球環境問題をサミットの主議題に押し上げたといわれる。少なくとも、政治家が地球環境問題を無視できないような状態になった。科学者のメッセージで世界が動く時代に入ったともいえる。
教育界では子供たちの理科離れが進んでいるとよくいわれるが、メディアの世界では科学記事の割合が広がり、たとえば朝日新聞社では30年前に20人ほどだった科学担当記者は現在では50人ほどに増えている。戦後は60年安保、70年安保と大学キャンパスでも政治闘争の嵐が吹き荒れた。が、高度成長に伴ってハイテク、ロボット、宇宙、IT、新型感染症、医療・生命倫理、食の安全と危機管理、そして環境へと、メディアの記事テーマは政治・社会から科学への「理系シフト」が起きている。それが極まったのが、ことし8月の洞爺湖サミットだ。地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構であるIPCCの科学者たちが動いて、地球環境問題をサミットの主議題に押し上げたといわれる。少なくとも、政治家が地球環境問題を無視できないような状態になった。科学者のメッセージで世界が動く時代に入ったともいえる。