☆地デジ化の扉・中
珠洲市が総務省が募集した地デジへのリハーサル候補地に手を挙げ、先行モデル地区に採択された理由に一つに能登半島の地形をうまくアピールしたという点がある。それは、三方を海に囲まれ、実験的にアナログを停波しても近隣の市町には影響がほどんどないということ。もう一つはエリアが8800世帯(珠洲市6600世帯と能登町の一部2200世帯)という、実験としては適切な規模であり、また、少子高齢化の過疎地として全国の「地デジ化モデル」となりうることだった。もちろん、切実感を持って取り組んだ首長の意欲もあり、総務省とすると実験地としては最適だったに違いない。もう一つ上げるなら、国の事業として、能登空港があることで、東京からのアクセスが良かったということだろう。
「珠洲モデル」といわれた町の電器店の働き
 地デジ化ほぼ100%にこぎつけたもっとも大きな理由は2つある。一つは、ケーブルテレビ加入率が高いこと。珠洲市の場合は65%、能登町は94%に達している。珠洲市のケーブルテレビは「デジアナ変換」をで、加入世帯は現行のままの状態で視聴できる。そのコストは工事費3万9900円、年間の利用料1万2100円が少なくともかかる。二つの理由は、チューナーの無料貸与があげられる。これは、デジタル波を直接受信する世帯(約3000世帯)を対象に無料で貸与されるもので、1世帯当たり4台を限度に貸し出される。チューナーはデジタル波をアナログ変換するので、従来のアナログテレビで取り付けて視聴する。3000世帯の中にはデジタル専用テレビに買い換えた世帯もあるが、家庭内の2台目や3台目にまで手が届かない場合はチューナーでとなる。希望があったホテルや事業所、民宿などにも対応した。その総計が4200台にも及んだ。
地デジ化ほぼ100%にこぎつけたもっとも大きな理由は2つある。一つは、ケーブルテレビ加入率が高いこと。珠洲市の場合は65%、能登町は94%に達している。珠洲市のケーブルテレビは「デジアナ変換」をで、加入世帯は現行のままの状態で視聴できる。そのコストは工事費3万9900円、年間の利用料1万2100円が少なくともかかる。二つの理由は、チューナーの無料貸与があげられる。これは、デジタル波を直接受信する世帯(約3000世帯)を対象に無料で貸与されるもので、1世帯当たり4台を限度に貸し出される。チューナーはデジタル波をアナログ変換するので、従来のアナログテレビで取り付けて視聴する。3000世帯の中にはデジタル専用テレビに買い換えた世帯もあるが、家庭内の2台目や3台目にまで手が届かない場合はチューナーでとなる。希望があったホテルや事業所、民宿などにも対応した。その総計が4200台にも及んだ。
では、テレビ電波の直接受信世帯にチューナーを貸与さえすれば、人々は上手に取り付けて、それでOKなのだろうか。能登は少子高齢化のモデルのような地域なのだ。珠洲同市では6600世帯のうち40%が高齢者のみの世帯で、さらにその半分に当たる1000世帯余りが独居である。問題はここから始まる。高齢者世帯を町の電器屋が一軒一軒訪問し、チューナーの取り付けからリモコンの操作を丁寧に教える。このリモコンにはチューナーとテレビの2つの電源がある。一つだけ押して、お年寄りからは「テレビが映らないと」とSOSの電話が入る。このような調子で、「4回訪ねたお宅もある」(電器店経営・沢谷信一氏)という。おそらくこれからもフォローが続くだろう。
24日の記念セレモニーの中で、泉谷満寿裕市長は「高齢者世帯を一軒一軒回っていただき、電器店のみなさんには本当に感謝したい」とあいさつの中で2度も述べた。今回地デジに対応に一肌脱いだ町の電器屋は珠洲が11軒、能登町が4件の15軒。もちろんボランティアではない。ただ、ボランティア以上に「お年寄りのお宅は何度も何度も、丁寧に丁寧に」対応した。
地元をよく知る電器店だから動くことができたといえる。この働きは予期せぬ効果を上げたことから、「珠洲モデル」と評価されている。記念セレモニーのステージで、デジタル放送推進協議会の木村政孝理事が一人ひとり電器店の店主の名前を読み上げ感謝状を贈った=写真=。泉谷市長が2度も「感謝したい」と述べた理由がここにある。
地デジ受信機の世帯普及率は83%(ことし3月、総務省調べ)であり、地デジに対応していない世帯数は1000万近く残っている。全国的には、大型家電店の進出で町の電器屋は減っているという。「珠洲モデル」が果たして、全国のお手本となるのか、どうか。
⇒25日(日)夜・金沢の天気 はれ
 停波に向けたカウントダウンの声が上がったのは、正午より30秒ほど前だ。地元の民放テレビ局の社長らが「スイッチオンセレモニー」に立ち会い、定刻にステージ上に並べた民放とNHKのアナログ放送のモニター放送が一斉に砂の嵐状態になった。すかさず、北陸総合通信局長の吉武洋一郎氏による「珠洲地区デジタル化完了宣言」があった。つまり、ここにアジアでの地デジの第一歩を記したと宣言したのだ。
停波に向けたカウントダウンの声が上がったのは、正午より30秒ほど前だ。地元の民放テレビ局の社長らが「スイッチオンセレモニー」に立ち会い、定刻にステージ上に並べた民放とNHKのアナログ放送のモニター放送が一斉に砂の嵐状態になった。すかさず、北陸総合通信局長の吉武洋一郎氏による「珠洲地区デジタル化完了宣言」があった。つまり、ここにアジアでの地デジの第一歩を記したと宣言したのだ。 民主党は、知名度が抜群なテレビ局関係者をイメージ戦略として利用したのだろう。国政選挙にあるいは、政界に打って出たいというテレビ関係者はいくらでもいる。ちょっとした人脈を得て、候補者として起用されたであろうことは想像に難くない。また、こう述べると、「テレビ局関係者はタレントとは違うので、軽々に選挙に出るべきはない」と言っているのではない。自らのポリシーを持って、国政に出ればよい。
民主党は、知名度が抜群なテレビ局関係者をイメージ戦略として利用したのだろう。国政選挙にあるいは、政界に打って出たいというテレビ関係者はいくらでもいる。ちょっとした人脈を得て、候補者として起用されたであろうことは想像に難くない。また、こう述べると、「テレビ局関係者はタレントとは違うので、軽々に選挙に出るべきはない」と言っているのではない。自らのポリシーを持って、国政に出ればよい。 昨日は家族といっしょに投票場に出かけた。ここ数年、市議選から国政選挙まで欠かしたことがない。政権交代など流動化している政治が面白いし、当落予想は楽しみだ。その実感をつかむには投票行動を起こすことが何よりと考えているからだ。投票場の出入り口には、NHKと地元新聞社の調査員が待機していた。出口調査のためだ。新聞社の調査員が寄ってきて、「ご協力をお願いします」と依頼され応じた。今回の選挙区では誰に、比例ではどの政党にのほかに結構細かな質問がある。「石川県知事を評価するか」などといった、今回の参院選に直接関連しない項目もある。地元新聞社なので、県内の動向をつかんでおきたいのだろうと、むしろその姿勢に好感が持てた。この出口調査の結果は新聞社系列のローカルテレビ局にもデータが共有され、当確打ちの判断材料となっているはずだ。
昨日は家族といっしょに投票場に出かけた。ここ数年、市議選から国政選挙まで欠かしたことがない。政権交代など流動化している政治が面白いし、当落予想は楽しみだ。その実感をつかむには投票行動を起こすことが何よりと考えているからだ。投票場の出入り口には、NHKと地元新聞社の調査員が待機していた。出口調査のためだ。新聞社の調査員が寄ってきて、「ご協力をお願いします」と依頼され応じた。今回の選挙区では誰に、比例ではどの政党にのほかに結構細かな質問がある。「石川県知事を評価するか」などといった、今回の参院選に直接関連しない項目もある。地元新聞社なので、県内の動向をつかんでおきたいのだろうと、むしろその姿勢に好感が持てた。この出口調査の結果は新聞社系列のローカルテレビ局にもデータが共有され、当確打ちの判断材料となっているはずだ。 この1ヵ月余りの間、鳩山氏は5月4日と23日2度沖縄を訪れ、仲井真弘多知事らに対し、アメリカ軍普天間基地飛行場を、キャンプ・シュワブ沿岸部のある辺野古崎に移設する方針を表明した。「県外移設」を明言していた鳩山氏が、自ら「公約違反」のデモンストレーションを行ったわけで、訪問先の沖縄県庁や名護市の万国津梁館では、「怒」と書いた紙を持った県民が集まり「裏切りだ」と声を上げる様子がテレビで繰り返し伝えられた。「友愛」を口にする鳩山氏ならば、ここで車を降りて、もみくちゃにされるのを覚悟で県民に直接詫びるべきではなかったか。ところが、鳩山氏が乗った車の列は、その声を無視するように猛スピードで通過したのだった。友愛を行動で示す度胸がなかったのだろう。
この1ヵ月余りの間、鳩山氏は5月4日と23日2度沖縄を訪れ、仲井真弘多知事らに対し、アメリカ軍普天間基地飛行場を、キャンプ・シュワブ沿岸部のある辺野古崎に移設する方針を表明した。「県外移設」を明言していた鳩山氏が、自ら「公約違反」のデモンストレーションを行ったわけで、訪問先の沖縄県庁や名護市の万国津梁館では、「怒」と書いた紙を持った県民が集まり「裏切りだ」と声を上げる様子がテレビで繰り返し伝えられた。「友愛」を口にする鳩山氏ならば、ここで車を降りて、もみくちゃにされるのを覚悟で県民に直接詫びるべきではなかったか。ところが、鳩山氏が乗った車の列は、その声を無視するように猛スピードで通過したのだった。友愛を行動で示す度胸がなかったのだろう。 スカイツリーが建設される意味合いは、関東エリアの地上デジタル放送と密接に関係している。東京タワー(正式名称「日本電波塔」、高さ333㍍)から新タワーに移行すると、地上デジタル放送の送信高は現在の約2倍となる。関東の地デジは2003年12月から放送が開始されたが、都心部に林立する200㍍級の高層ビル群から抜ける600㍍級の新タワーからの送信が始まれば、電波障害なども低減し、放送エリアも拡大するという技術的な面での有利さが強調されている。しかし、ハードルの高い問題がいくつかある。
スカイツリーが建設される意味合いは、関東エリアの地上デジタル放送と密接に関係している。東京タワー(正式名称「日本電波塔」、高さ333㍍)から新タワーに移行すると、地上デジタル放送の送信高は現在の約2倍となる。関東の地デジは2003年12月から放送が開始されたが、都心部に林立する200㍍級の高層ビル群から抜ける600㍍級の新タワーからの送信が始まれば、電波障害なども低減し、放送エリアも拡大するという技術的な面での有利さが強調されている。しかし、ハードルの高い問題がいくつかある。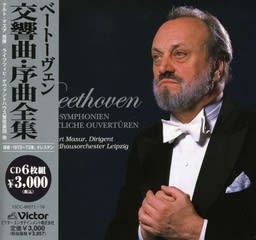 NHK教育で、N響による第九の演奏が放送された。指揮者はクルト・マズアだ。82歳・マズアといえば、「あれから20年」である。ベルリンの壁崩壊につながったとされる1989年10月9日、旧東ドイツのライプチヒで「月曜デモ」が起きた。民主化を要求するデモ参加者に、秘密警察と軍隊が銃口を向け、にらみ合いとなった。このとき、マズアは東ドイツ当局と市民に「私たちに必要なのは自由な対話だ」と平和的解決を要望するメッセージを発表した。この流血なき非暴力の反政府デモが広がり、「月曜デモ」の9日後にホーネッカー議長が退任し、11月9日のベルリンの壁崩、東西ドイツは統一へと向かう。そして、ベートーベンの第九は東西ドイツ統一の賛歌になった。そんなマズアの歴史的な功績に思いを重ね合わせながら、NHK教育の第九に耳を澄ませていた。
NHK教育で、N響による第九の演奏が放送された。指揮者はクルト・マズアだ。82歳・マズアといえば、「あれから20年」である。ベルリンの壁崩壊につながったとされる1989年10月9日、旧東ドイツのライプチヒで「月曜デモ」が起きた。民主化を要求するデモ参加者に、秘密警察と軍隊が銃口を向け、にらみ合いとなった。このとき、マズアは東ドイツ当局と市民に「私たちに必要なのは自由な対話だ」と平和的解決を要望するメッセージを発表した。この流血なき非暴力の反政府デモが広がり、「月曜デモ」の9日後にホーネッカー議長が退任し、11月9日のベルリンの壁崩、東西ドイツは統一へと向かう。そして、ベートーベンの第九は東西ドイツ統一の賛歌になった。そんなマズアの歴史的な功績に思いを重ね合わせながら、NHK教育の第九に耳を澄ませていた。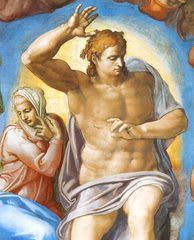 アメリカで一番有名な社説というのがある。取り上げるタイミングとしては少々遅きに失したが、「サンタはいるの」という8歳の女の子の質問に答えた社説だ。1897年9月、アメリカの新聞ニューヨーク・サンに掲載され、その後、目に見えないけれども心に確かに存在し、それを信じる心を持つことの尊さを説いた社説と評価され、掲載されてから110年余り経った今でも、クリスマスの時期になると世界中で語り継がれている。その社説を掲載する。
アメリカで一番有名な社説というのがある。取り上げるタイミングとしては少々遅きに失したが、「サンタはいるの」という8歳の女の子の質問に答えた社説だ。1897年9月、アメリカの新聞ニューヨーク・サンに掲載され、その後、目に見えないけれども心に確かに存在し、それを信じる心を持つことの尊さを説いた社説と評価され、掲載されてから110年余り経った今でも、クリスマスの時期になると世界中で語り継がれている。その社説を掲載する。 新聞各紙やテレビのニュースをまとめる。11月27日、フロリダ・オーランドの自宅前でウッズが乗用車で自損事故を起こし重傷との一報を、地元テレビ局が報じた(11月27日)。スーパースターのけが。マイケル・ジャクソンの急逝も記憶に新しいアメリカでは、国民の関心が一気にウッズに集中したのも無理はない。ウッズは顔面に軽い傷を負った程度で、病院で手当して帰宅したが、ウッズの退院後の姿を取材しようと、「ゲートコミュニティ」と呼ばれる塀で囲まれた高級住宅街のメインゲートにはテレビ中継用のSNG(Satellite News Gathering)車がずらりと並んた。このSNG車はカメラで撮影した素材(映像と音声)を電波として通信衛星を経由させ、本局に伝送する装置を搭載していて、パラボラアンテナが付いている。つまり、「おわん」の付いた車が横一列に並ぶ、日本のニュース現場ではおなじみの光景がオーランドでも再現されたのである。
新聞各紙やテレビのニュースをまとめる。11月27日、フロリダ・オーランドの自宅前でウッズが乗用車で自損事故を起こし重傷との一報を、地元テレビ局が報じた(11月27日)。スーパースターのけが。マイケル・ジャクソンの急逝も記憶に新しいアメリカでは、国民の関心が一気にウッズに集中したのも無理はない。ウッズは顔面に軽い傷を負った程度で、病院で手当して帰宅したが、ウッズの退院後の姿を取材しようと、「ゲートコミュニティ」と呼ばれる塀で囲まれた高級住宅街のメインゲートにはテレビ中継用のSNG(Satellite News Gathering)車がずらりと並んた。このSNG車はカメラで撮影した素材(映像と音声)を電波として通信衛星を経由させ、本局に伝送する装置を搭載していて、パラボラアンテナが付いている。つまり、「おわん」の付いた車が横一列に並ぶ、日本のニュース現場ではおなじみの光景がオーランドでも再現されたのである。 出版の世界では、「生きる権利をめぐる半世紀の闘争の裁判記録」となる。ところが、今回の映像では印象として「たくましき山の民の物語」である。映像では、法廷への出入りのシーンがあるだけで、ムシロ旗を掲げての抗議行動などのシーンというものが出てこない。村の生活やお祭りを交えながら淡々と映像は流れて行く。120分。 会場で配布された「あらすじ」からこのドキュメンタリーの流れを引用する。岩手県盛岡市の北、50㌔の山里。二戸郡一戸町小繋。ここへ今から50年前、映像カメラマンの菊池周、写真家の川島浩、ドキュメンタリー作家の篠崎五六の3人が通い、小繋の人々の暮らしの記録を取るようになった。小繋は戸数50戸に満たない山間の農村。村を取り巻く小繋山から燃料の薪や肥料にする草・柴を刈り取って暮らしている。山は暮らしに欠くことのできない入会地だ。入会地とは、一定地域の住民が慣習的な権利によって特定の山林・原野・漁場の薪材・緑肥・魚貝などを採取することを目的に共同で使用することを指す。
出版の世界では、「生きる権利をめぐる半世紀の闘争の裁判記録」となる。ところが、今回の映像では印象として「たくましき山の民の物語」である。映像では、法廷への出入りのシーンがあるだけで、ムシロ旗を掲げての抗議行動などのシーンというものが出てこない。村の生活やお祭りを交えながら淡々と映像は流れて行く。120分。 会場で配布された「あらすじ」からこのドキュメンタリーの流れを引用する。岩手県盛岡市の北、50㌔の山里。二戸郡一戸町小繋。ここへ今から50年前、映像カメラマンの菊池周、写真家の川島浩、ドキュメンタリー作家の篠崎五六の3人が通い、小繋の人々の暮らしの記録を取るようになった。小繋は戸数50戸に満たない山間の農村。村を取り巻く小繋山から燃料の薪や肥料にする草・柴を刈り取って暮らしている。山は暮らしに欠くことのできない入会地だ。入会地とは、一定地域の住民が慣習的な権利によって特定の山林・原野・漁場の薪材・緑肥・魚貝などを採取することを目的に共同で使用することを指す。