★震災とマスメディア-6-
「メディアにできること」の可能性を追求したFMピッカラ
 震災から3ヵ月後、被災地を取材に訪れた。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった。復旧半ばという印象だった。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった。祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。
震災から3ヵ月後、被災地を取材に訪れた。住宅街には倒壊したままの家屋が散見され、柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくかった。復旧半ばという印象だった。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった。祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。
通常のピッカラの生放送は平日およそ9時間だが、災害時の緊急編成は24時間の生放送。柏崎市では75ヵ所、およそ6000人が避難所生活を余儀なくされた。このため、市の災害対策本部にスタッフを常駐させ、被災者が当面最も必要とする避難所や炊き出し、仮設の風呂の場所などライフライン情報を中心に4人のパーソナリティーが交代で流し続けた。
コミュニティー放送局であるがゆえに「被災者のための情報」に徹することができたといえるかもしれない。インタビューに応じてくれた、パーソナリティーで放送部長の船崎幸子さんは「放送は双方向でより深まった」と振り返った。ピッカラは一方的に行政からの情報を流すのではなく、市民からの声を吸い上げることでより被災者にとって価値のある情報として伝えた。たとえば、水道やガスの復旧が遅れ、夏場だけに洗髪に不自由さを感じた人も多かった。「水を使わないシャンプーはどこに行けばありますか」という被災者からの質問を放送で紹介。すると、リスナーから「○○のお店に行けばあります」などの情報が寄せられた。行政から得られない細やかな情報である。
また、知人の消息を知りたいと「尋ね人」の電話やメールも寄せられた。放送を通して安否情報や生活情報をリスナー同士がキャッチボールした。市民からの問い合わせや情報はNHKや民放では内容の信憑性などの点から扱いにくいものだ。しかし、船崎さんは「地震発生直後の電話やメールに関しては情報を探す人の切実な気持ちが伝わってきた。それを切り捨てるわけにはいかなかった」と話した。
7月24日にはカバーエリアを広げるために臨時災害放送局を申請したため、24時間放送の緊急編成をさらに1ヵ月間延長し8月25日午後6時までとした。応援スタッフのオファーも他のFM局からあったが、4人のパーソナリティーは交代しなかった。「聞き慣れた声が被災者に安心感を与える」(船崎さん)という理由だった。このため、リスナーから「疲れはないの、大丈夫ですか」とスタッフを気遣うメールが届いたほどだった。
ピッカラの放送は情報を送るだけに止まらなかった。夜になると、「元気が出る曲」をテーマにリクエストを募集した。その中でリクエストが多かったのが、女性シンガー・ソングライターのKOKIAの「私にできること」=写真=だった。実は、東京在住のKOKIAが柏崎在住の女性ファンから届いたメールに応え、震災を乗り越えてほしいとのメッセージを込めて作った曲だった。KOKIAからのメールで音声ファイルを受け取った女性はそれをFMピッカラに持ち込んだ。「つらい時こそ誰かと支えあって…」とやさしく励ますKOKIAの歌は、不安で眠れぬ夜を過ごす多くの被災者を和ませた。そして、ピッカラが放送を通じて呼びかけた、KOKIAによる復興記念コンサート(8月6日)には3千人もの市民が集まった。人々の連携が放送局を介して被災地を勇気づけたのだった。
ピッカラの災害放送対応を他のコミュニティー放送が真似ようとしても、おそらく難しいだろう。コミュニティー放送局そのものが被災した場合、放送したくても放送施設が十分確保されないケースもある。そして、災害の発生時、その場所、その状況によって放送する人員が確保されない場合もあり、すべてのコミュニティー放送局が災害放送に対応できるとは限らない。その意味で、発生から1分45秒後に放送ができた「FMピッカラ」は幸運だったともいえる。そして、「情報こそライフライン」に徹して、コミュニティー放送の役割を見事に果たした事例としてピッカラは評価される。
⇒30日(水)朝・金沢の天気 はれ
 被災地に放送が果たす役割は大きいが、なんといってもインフラの整備だ。テレビを視聴できるようにすることだ。2007年3月25日、震度6強の能登半島地震では全体で避難住民は2100人余りに及んだ。多くの住民は避難所でテレビやラジオのメディアと接触することになった。注目すべきことがった、被害が大きかった輪島市門前町を含め45ヵ所の避難所すべてにテレビが完備されていたことだ=写真=。地震で屋根のテレビアンテナは傾き、壊れたテレビもあったはず。一体誰が。
被災地に放送が果たす役割は大きいが、なんといってもインフラの整備だ。テレビを視聴できるようにすることだ。2007年3月25日、震度6強の能登半島地震では全体で避難住民は2100人余りに及んだ。多くの住民は避難所でテレビやラジオのメディアと接触することになった。注目すべきことがった、被害が大きかった輪島市門前町を含め45ヵ所の避難所すべてにテレビが完備されていたことだ=写真=。地震で屋根のテレビアンテナは傾き、壊れたテレビもあったはず。一体誰が。 2007年3月25日の能登半島地震から4年になる。現地でのボンラティア活動でも上記と同じ思いをした。各地からさまざま善意が届けられる。しかし、それを受ける現地の状況が理解されていないために、返って混乱を招いている。私が目撃した一つの例を述べる。被災者の避難所には毎日、新聞各紙がどっさりと届けられる。ところが、避難所となっている地区の集会場は体育館のように大きくはない。被災者は肩を寄せ合っている状態だ。そこに新聞が山積みされても、まず新聞を広げて読むスペースが十分にない。しかも、新聞を広げても被災者が欲しい情報、たとえば回診や被災相談などの細かな情報は掲載されていない。読まれない新聞が日々どっさりとたまる。それを廃棄場所に持って行き始末するのはボランティアの役目だった。
2007年3月25日の能登半島地震から4年になる。現地でのボンラティア活動でも上記と同じ思いをした。各地からさまざま善意が届けられる。しかし、それを受ける現地の状況が理解されていないために、返って混乱を招いている。私が目撃した一つの例を述べる。被災者の避難所には毎日、新聞各紙がどっさりと届けられる。ところが、避難所となっている地区の集会場は体育館のように大きくはない。被災者は肩を寄せ合っている状態だ。そこに新聞が山積みされても、まず新聞を広げて読むスペースが十分にない。しかも、新聞を広げても被災者が欲しい情報、たとえば回診や被災相談などの細かな情報は掲載されていない。読まれない新聞が日々どっさりとたまる。それを廃棄場所に持って行き始末するのはボランティアの役目だった。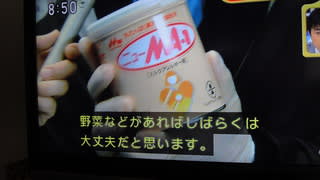 健常者でも障がい者で同じようにマスメディアから情報を得ることをユニバーサル・サービスという。内閣の、たとえば総理や官房長官の会見では、小画面に手話通訳者が出ている。会見場に手話通訳があることで、聴覚障がい者がリアルタイムでテレビから情報を得ることができる。今回の震災は原発事故と連動したため、メディアによるリアルタイムの放送に被災者の耳目が集まる。内閣の伝えようとする意志が見える。災害会見の手話放送はこれ以降、定番化するのではないだろうか。
健常者でも障がい者で同じようにマスメディアから情報を得ることをユニバーサル・サービスという。内閣の、たとえば総理や官房長官の会見では、小画面に手話通訳者が出ている。会見場に手話通訳があることで、聴覚障がい者がリアルタイムでテレビから情報を得ることができる。今回の震災は原発事故と連動したため、メディアによるリアルタイムの放送に被災者の耳目が集まる。内閣の伝えようとする意志が見える。災害会見の手話放送はこれ以降、定番化するのではないだろうか。 そのころ、能登半島の輪島市で記者活動をしていた。デスクから電話があり、輪島漁港に行ってみると、足元まで波が来て、危うく逃げ遅れるところだった。1枚だけ撮った、渦に飲み込まれる寸前の漁船の写真は翌日の一面を飾った。2004年にテレビ局を退職し、大学の地域連携コーディネーターという仕事をしている。2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)、翌日26日に被害がもっとも大きかった輪島市門前町に現地入りした。そこで見たある光景がきっかけで、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。
そのころ、能登半島の輪島市で記者活動をしていた。デスクから電話があり、輪島漁港に行ってみると、足元まで波が来て、危うく逃げ遅れるところだった。1枚だけ撮った、渦に飲み込まれる寸前の漁船の写真は翌日の一面を飾った。2004年にテレビ局を退職し、大学の地域連携コーディネーターという仕事をしている。2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)、翌日26日に被害がもっとも大きかった輪島市門前町に現地入りした。そこで見たある光景がきっかけで、「震災とメディア」をテーマに調査研究を実施することになる。 一方、今朝のニュースは、ニューヨーク外国為替市場で、円相場が一時1ドル=76円台に急騰し、1995年4月19日につけた1ドル=79円を超えて史上最高値となった。3月末の決算期を控えた日本企業の円需要が増しているのと、保険金の支払いに備え、保険会社が外貨資産を売るといった思惑、さらに日本政府が外貨準備として保有するアメリカ国債を売るのではないかとの観測まで広がっている。日本政府が国債増発ではなく、外貨準備に手をつけ、米国債を売却するのではないか、という憶測だ。アメリカとの外交問題が絡む。注視したい。
一方、今朝のニュースは、ニューヨーク外国為替市場で、円相場が一時1ドル=76円台に急騰し、1995年4月19日につけた1ドル=79円を超えて史上最高値となった。3月末の決算期を控えた日本企業の円需要が増しているのと、保険金の支払いに備え、保険会社が外貨資産を売るといった思惑、さらに日本政府が外貨準備として保有するアメリカ国債を売るのではないかとの観測まで広がっている。日本政府が国債増発ではなく、外貨準備に手をつけ、米国債を売却するのではないか、という憶測だ。アメリカとの外交問題が絡む。注視したい。 すでに観光名所になっているスカイツリー本来の役割はテレビ塔としての機能である。問題は、「本家テレビ塔」の東京タワーとの電波の切り替えだ。ことし2011年7月24日正午にアナログが停波された後は、東京タワーから地デジの電波が発射されるが、来年2012年春にスカイツリーがオ-プンすれば、試験放送期間を経て、地デジの電波は東京タワーからスカイツリーにスイッチされる。つまり、武蔵の国では地デジは2度切り替わる。
すでに観光名所になっているスカイツリー本来の役割はテレビ塔としての機能である。問題は、「本家テレビ塔」の東京タワーとの電波の切り替えだ。ことし2011年7月24日正午にアナログが停波された後は、東京タワーから地デジの電波が発射されるが、来年2012年春にスカイツリーがオ-プンすれば、試験放送期間を経て、地デジの電波は東京タワーからスカイツリーにスイッチされる。つまり、武蔵の国では地デジは2度切り替わる。 1月17日は東京へ日帰り出張だった。先日から大雪となり、風も風も強かったので、早朝JR金沢駅から「はくたか1号」に乗った。乗り換え駅の越後湯沢付近は1㍍を超える積雪で、屋根雪を下ろす人々の姿が車窓から見えた。上越新幹線で長野を過ぎると、とたんに顔空になった。目的地の市ヶ谷では駅のプラットホームから釣り堀が見え、のんびりと釣り糸を垂れる人々の姿があった。越後湯沢で見た屋根雪下ろしの光景と余りにも対照的だった。人は生まれた環境に育まれる。粘り強く、持続性がある北陸の人の行動パターンは案外、雪が育んでいるのかもしれない。
1月17日は東京へ日帰り出張だった。先日から大雪となり、風も風も強かったので、早朝JR金沢駅から「はくたか1号」に乗った。乗り換え駅の越後湯沢付近は1㍍を超える積雪で、屋根雪を下ろす人々の姿が車窓から見えた。上越新幹線で長野を過ぎると、とたんに顔空になった。目的地の市ヶ谷では駅のプラットホームから釣り堀が見え、のんびりと釣り糸を垂れる人々の姿があった。越後湯沢で見た屋根雪下ろしの光景と余りにも対照的だった。人は生まれた環境に育まれる。粘り強く、持続性がある北陸の人の行動パターンは案外、雪が育んでいるのかもしれない。 東京の空をにぎわせているスカイツリー。正式には「東京スカイツリー」。高さ634㍍の世界一の電波塔を目指している。ことし12月に完成、来年春に開業を予定している。NHKと在京民放5局が利用する。総事業費は650億円。このツリーを下から眺めると、いろいろなことを思う。その一つが、「電波は空から降ってくる」という発想は、東京のものだ、と。東京タワー(333㍍)しかり、東京にいるとシャワーを浴びるように、電波が空から降ってくる。もちろん一部にビル陰による電波障害があり、そのビル陰の障害を極力減らすために600㍍級のタワーが構想された。まるで「恐竜進化論」だ。電波塔(東京タワー)が立つ。周囲に200㍍を超える超高層ビルが林立するようになる。すると今度は、さらに高い電波塔(スカイツリー)を立てなければならないと、どんどんと図体が大きくなってきた。「電波を空から降らせる」ために、限りなく巨大化し続けているのだ。
東京の空をにぎわせているスカイツリー。正式には「東京スカイツリー」。高さ634㍍の世界一の電波塔を目指している。ことし12月に完成、来年春に開業を予定している。NHKと在京民放5局が利用する。総事業費は650億円。このツリーを下から眺めると、いろいろなことを思う。その一つが、「電波は空から降ってくる」という発想は、東京のものだ、と。東京タワー(333㍍)しかり、東京にいるとシャワーを浴びるように、電波が空から降ってくる。もちろん一部にビル陰による電波障害があり、そのビル陰の障害を極力減らすために600㍍級のタワーが構想された。まるで「恐竜進化論」だ。電波塔(東京タワー)が立つ。周囲に200㍍を超える超高層ビルが林立するようになる。すると今度は、さらに高い電波塔(スカイツリー)を立てなければならないと、どんどんと図体が大きくなってきた。「電波を空から降らせる」ために、限りなく巨大化し続けているのだ。 珠洲モデルというのは、地域の電器店15軒が手分けして、高齢者世帯などを一軒一軒回り、アナログ受信機(テレビ)にチューナーの取り付けをした。ボランティアではない。ただ、お年寄り宅を何度も訪ね、丁寧に対応し、見事に地デジ化のウイークポイントといわれた高齢者世帯の普及に成し遂げたと評価された。記念セレモニーでは、デジタル放送推進協議会の木村政孝理事が一人ひとり電器店の店主の名前を読み上げ感謝状を贈ったほどだ=写真=。
珠洲モデルというのは、地域の電器店15軒が手分けして、高齢者世帯などを一軒一軒回り、アナログ受信機(テレビ)にチューナーの取り付けをした。ボランティアではない。ただ、お年寄り宅を何度も訪ね、丁寧に対応し、見事に地デジ化のウイークポイントといわれた高齢者世帯の普及に成し遂げたと評価された。記念セレモニーでは、デジタル放送推進協議会の木村政孝理事が一人ひとり電器店の店主の名前を読み上げ感謝状を贈ったほどだ=写真=。 では、能登半島が先行モデル地区として役割は果たせたのだろうかと振り返ってみる。丘の上から珠洲市内を眺めると、受信障害となるような高いビルはないし、当地の民放4局のうち3局がいわゆる「Uチャン」なのでアンテナ交換の必要もない。都市型の地デジ問題とは一見かけ離れているようにも思えるが、山陰や北風・塩害問題による共聴施設が市内で36ヵ所あり、市の世帯の40%をカバーしていた。しかも、珠洲市の場合、65歳以上の最高齢者率は40%を超え、高齢者のみの世帯率は36%、さらに高齢者世帯の半分1000世帯余りが独居のまさに過疎・高齢化の地域だ。電波障害による共聴と高齢者宅の対策は地デジの2大問題で、それを乗り切った能登の先行実施は「モデル」といえるだろう。
では、能登半島が先行モデル地区として役割は果たせたのだろうかと振り返ってみる。丘の上から珠洲市内を眺めると、受信障害となるような高いビルはないし、当地の民放4局のうち3局がいわゆる「Uチャン」なのでアンテナ交換の必要もない。都市型の地デジ問題とは一見かけ離れているようにも思えるが、山陰や北風・塩害問題による共聴施設が市内で36ヵ所あり、市の世帯の40%をカバーしていた。しかも、珠洲市の場合、65歳以上の最高齢者率は40%を超え、高齢者のみの世帯率は36%、さらに高齢者世帯の半分1000世帯余りが独居のまさに過疎・高齢化の地域だ。電波障害による共聴と高齢者宅の対策は地デジの2大問題で、それを乗り切った能登の先行実施は「モデル」といえるだろう。