★メディアの選挙モード
 では、なぜそうしなけらばならないのか。これは法律で決められている。「新聞紙(これに類する通信類を含む)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載する自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」(公選法第148条)
では、なぜそうしなけらばならないのか。これは法律で決められている。「新聞紙(これに類する通信類を含む)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載する自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」(公選法第148条)
「放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。1.公安及び善良な風俗を害しないこと。2.政治的に公平であること。3.報道は事実をまげないですること。4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法第4条)
私がテレビ局に在籍していたころの経験だ。「神の国」発言で森喜朗内閣が解散して行われた第42回総選挙(2000年6月25日)のときだったと記憶している。公示の日、候補者の第一声で12秒ほどの取り切りを使った。ところが、ある党の選挙事務所から「おたくのテレビは扱いが平等ではない」とクレームがついた。調べてみると、その党の候補者は10秒だった。昼のニュースだったので、時間がなかったのと、ちょうど10秒で切れがよかったのでそのまま放送したのだった。意図的ではなかった。選挙事務所では録画してチェックしていたのである。率直に詫びて、夕方のニュースでは12秒にした。話の内容ではなく、公平な扱いにこだわるというのが選挙期間のシビアのところではある。
とくに今回の選挙は多党乱立。困っているのはテレビ局だ。比例代表には12党が届け出ている。2日に放送されたNHK「日曜討論」は壮観だった。この日は11党の幹部が勢ぞろいしていた。司会者が「1回の発言は1分以内」と念押ししていた。全員が発言を終えたときには、放送開始から20分経過していた。番組として争点や論点を戦わせるというより、「なるべく公平に話してもらう」という司会者の気遣いが目立った。こうなると番組の体をなさないため、とくに民放テレビ局は選挙期間中はニュース番組でも選挙ネタをなるべく避け、経済や環境といったテーマにシフトさせる。
「テレビ選挙」といわれるアメリカでもかつて、フェアネスドクトリン(Fairness Doctrine)があり、番組の内容を政治的公平にしなければならないとされていた。ところが、ケーブルテレビなどマルチメディアの発達で言論の多様性こそ確保されなければならないとの流れになる。1987年にこのフェアネスドクトリンは撤廃された。つまり、フェアネスドクトリンは、チャンネル数が少なかった時代のもので、多チャンネル時代にはそぐわないという考えだった。
日本の場合、全国紙の系列であるテレビキー局が固定され、一長一短はあるが多チャンネル化とはいまだにほど遠い。
⇒4日(火)夜・金沢の天気 くもり
 これより2月余り前の9月21日、アメリカのワシントン・ポストは、尖閣諸島をめぐる中国との対立などを背景に、日本が「緩やかだが、かなりの右傾化」を始めていると指摘、周辺地域での行動は「第2次大戦後、最も対決的」になっていると1面で伝えた。日本のメディアが報じたこのニュースの内容を読むと、同紙は、日本の政治家が与野党問わず集団的自衛権の行使容認を主張するようになり、憲法改正論が高まっていると分析し、与那国島への陸上自衛隊配備計画などを挙げ、自衛隊にも「より強力な役割」が与えられつつあるとの見方を示したという。
これより2月余り前の9月21日、アメリカのワシントン・ポストは、尖閣諸島をめぐる中国との対立などを背景に、日本が「緩やかだが、かなりの右傾化」を始めていると指摘、周辺地域での行動は「第2次大戦後、最も対決的」になっていると1面で伝えた。日本のメディアが報じたこのニュースの内容を読むと、同紙は、日本の政治家が与野党問わず集団的自衛権の行使容認を主張するようになり、憲法改正論が高まっていると分析し、与那国島への陸上自衛隊配備計画などを挙げ、自衛隊にも「より強力な役割」が与えられつつあるとの見方を示したという。 犯人による派手な振る舞いは「劇場型犯罪」とも言われる。ポップアーチストのアンディ・ウォーホル(1928-1987)の名言「誰でも15分間は有名人でいられる時代が来る」は、劇場型犯罪の時代を予見した言葉でもある。犯行を予告、事件を派手に起こし、捜査が入る、テレビの中継が入る。テレビメディアにとっては、「血が流れればトップニュース」である。テレビメディアはショッキングな映像を求め続ける。事実、金嬉老事件では、テレビ局のスタッフが「ライフルを空に向けて撃ってくれませんか」と依頼し、犯人が実際に空に向かって数発撃っている映像を流したのだった。
犯人による派手な振る舞いは「劇場型犯罪」とも言われる。ポップアーチストのアンディ・ウォーホル(1928-1987)の名言「誰でも15分間は有名人でいられる時代が来る」は、劇場型犯罪の時代を予見した言葉でもある。犯行を予告、事件を派手に起こし、捜査が入る、テレビの中継が入る。テレビメディアにとっては、「血が流れればトップニュース」である。テレビメディアはショッキングな映像を求め続ける。事実、金嬉老事件では、テレビ局のスタッフが「ライフルを空に向けて撃ってくれませんか」と依頼し、犯人が実際に空に向かって数発撃っている映像を流したのだった。 3社とも自民が民主を上回る傾向は同じものの、維新の会が1ケタの朝日と共同、2ケタの毎日とでは数字の印象がまったく異なる。たとえば、総選挙でキーワードとなりそうな「第3極」について、朝日と共同では維新と太陽はこれからとのイメージだが、毎日だと維新と太陽は「第3極」として、すでに民主を凌いで自民と肩を並べているとの読み方になる。17日は、「太陽の党」が解党して「日本維新の会」に合流した日なので、調査する側にも多少の混乱はあったかもしれないと察するが、それにしてもこの数値の違いはどこからくるのか。
3社とも自民が民主を上回る傾向は同じものの、維新の会が1ケタの朝日と共同、2ケタの毎日とでは数字の印象がまったく異なる。たとえば、総選挙でキーワードとなりそうな「第3極」について、朝日と共同では維新と太陽はこれからとのイメージだが、毎日だと維新と太陽は「第3極」として、すでに民主を凌いで自民と肩を並べているとの読み方になる。17日は、「太陽の党」が解党して「日本維新の会」に合流した日なので、調査する側にも多少の混乱はあったかもしれないと察するが、それにしてもこの数値の違いはどこからくるのか。 前回のブログで述べたように、知り合いの新聞記者からメールがあった。「選挙の投開票の日に開披台調査を実施するので学生たちの協力を得たい」との相談だった。「開披台(かいひだい)調査」をもう一度簡単に説明すると、投票日の午後8時に投票は締め切られ、各投票場の票が開票場に集められる。全部集まったところで、自治体の職員が一斉に開票、集計の作業を行う。この開票作業の様子を双眼鏡でウオッチし、刻一刻と積み上がる票数を開票者の手元で数え、マスメディアの選挙報道センターに伝えるのが開披台調査だ。新聞社と連携したテレビの選挙特番では、こうした開披台調査や、投票所の出口で有権者にどの候補に投票したのか記入してもらう出口調査のデータなどを突き合わせ、リアルタイムに当選確実の速報を打っていく。記者の相談は、「この開披台調査、学生の参加が多ければ多いほどいい」という。
前回のブログで述べたように、知り合いの新聞記者からメールがあった。「選挙の投開票の日に開披台調査を実施するので学生たちの協力を得たい」との相談だった。「開披台(かいひだい)調査」をもう一度簡単に説明すると、投票日の午後8時に投票は締め切られ、各投票場の票が開票場に集められる。全部集まったところで、自治体の職員が一斉に開票、集計の作業を行う。この開票作業の様子を双眼鏡でウオッチし、刻一刻と積み上がる票数を開票者の手元で数え、マスメディアの選挙報道センターに伝えるのが開披台調査だ。新聞社と連携したテレビの選挙特番では、こうした開披台調査や、投票所の出口で有権者にどの候補に投票したのか記入してもらう出口調査のデータなどを突き合わせ、リアルタイムに当選確実の速報を打っていく。記者の相談は、「この開披台調査、学生の参加が多ければ多いほどいい」という。 首位は、オークリッジ国立研究所(アメリカ)の「タイタン」。1秒間に1京(京は1兆の1万倍)7590兆回の計算速度を記録したという。3位の「京」は1京510兆回。速さだけを競うのであれば「3位」だが、実用的という意味では「京」は優れている。計算科学研究機構(AICS)のホームページで掲載されている立花隆氏(ジャーナリスト)の文が分かりやすいので、以下部分引用させていただく。
首位は、オークリッジ国立研究所(アメリカ)の「タイタン」。1秒間に1京(京は1兆の1万倍)7590兆回の計算速度を記録したという。3位の「京」は1京510兆回。速さだけを競うのであれば「3位」だが、実用的という意味では「京」は優れている。計算科学研究機構(AICS)のホームページで掲載されている立花隆氏(ジャーナリスト)の文が分かりやすいので、以下部分引用させていただく。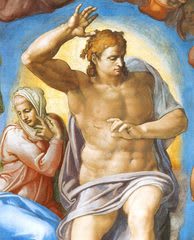 新聞社のウエッブニュースを検索すると、盛んに取り上げられている。被告は、イタリアを代表する国立地球物理学火山学研究所の所長(当時)や、記者会見で事実上の「安全宣言」をした政府防災局の副長官(同)で、マグニチュード6.3の地震が発生する直前の「高リスク検討会」に出席した7人。求刑の禁錮4年を上回る重い判決で、執行猶予はついていない。被告側は控訴するという。
新聞社のウエッブニュースを検索すると、盛んに取り上げられている。被告は、イタリアを代表する国立地球物理学火山学研究所の所長(当時)や、記者会見で事実上の「安全宣言」をした政府防災局の副長官(同)で、マグニチュード6.3の地震が発生する直前の「高リスク検討会」に出席した7人。求刑の禁錮4年を上回る重い判決で、執行猶予はついていない。被告側は控訴するという。 日本と中国は明治以降、日清戦争、日中戦争と戦火を交えた。戦後、中国共産党が政権を奪取して、毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言した。しかし、日本はアメリカとともに、共産党との内戦で台湾に渡った中華民国の蒋介石政権を中国の代表とした。当時の国際情勢は、アメリカなど欧米や日本などの資本主義陣営と、ソ連や東欧、中国などの共産主義陣営に分かれて対立していた。しかし1960年代に入ると、同じ共産主義陣営のソ連と中国の対立が鮮明になり、中国の方がソ連に対抗するために、アメリカや日本との関係改善を望んでいた。米ソ対立を有利に進めたいアメリカは1971年7月、ニクソン大統領が中国訪問を「電撃発表」し、翌1972年2月にニクソン大統領の訪中が実現した。この間、71年10月に中華人民共和国が国際連合に加盟し、台湾から代表権が移った。
日本と中国は明治以降、日清戦争、日中戦争と戦火を交えた。戦後、中国共産党が政権を奪取して、毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言した。しかし、日本はアメリカとともに、共産党との内戦で台湾に渡った中華民国の蒋介石政権を中国の代表とした。当時の国際情勢は、アメリカなど欧米や日本などの資本主義陣営と、ソ連や東欧、中国などの共産主義陣営に分かれて対立していた。しかし1960年代に入ると、同じ共産主義陣営のソ連と中国の対立が鮮明になり、中国の方がソ連に対抗するために、アメリカや日本との関係改善を望んでいた。米ソ対立を有利に進めたいアメリカは1971年7月、ニクソン大統領が中国訪問を「電撃発表」し、翌1972年2月にニクソン大統領の訪中が実現した。この間、71年10月に中華人民共和国が国際連合に加盟し、台湾から代表権が移った。 「日本製品ボイコット」を叫びながら日系スーパーをことごとく襲い商品を略奪する。「反日無罪」を叫びながら日本の自動車メーカーの車を焼き、日系ディーラーの建物を破壊する。日本料理店を襲う。テレビで見る中国の反日デモは単なる暴徒にしか見えない。おそらく常識ある中国の人々は恥じているに違いない。
「日本製品ボイコット」を叫びながら日系スーパーをことごとく襲い商品を略奪する。「反日無罪」を叫びながら日本の自動車メーカーの車を焼き、日系ディーラーの建物を破壊する。日本料理店を襲う。テレビで見る中国の反日デモは単なる暴徒にしか見えない。おそらく常識ある中国の人々は恥じているに違いない。 ロンドンでのオリンピックは1908年、48年に続き同一都市で3度目だった。東京も2度目の2020年大会誘致向けて余念がないが、ハプニングも。IOC国際オリンピック委員会は、IOCの選手委員に立候補していた陸上男子ハンマー投げの室伏広治が、選挙活動規定に違反したとして、候補者から取り消したと発表した(11日)。室伏は立候補した21人中、選手間による投票数は1位、つまりほぼ当確だった。その違反とは、選手村のダイニングホールで選挙活動をしたとのこと。当選すれば、IOC委員もかねるため、東京五輪招致に向けての活動が期待されていただけに、JOC日本オリンピック委員会の落胆ぶりが目に浮かぶ。うがった見方をすれば、ダイニングホールでの名刺交換を「選挙活動だ」とIOCに指したライバルがいるということだ。後味が悪い。
ロンドンでのオリンピックは1908年、48年に続き同一都市で3度目だった。東京も2度目の2020年大会誘致向けて余念がないが、ハプニングも。IOC国際オリンピック委員会は、IOCの選手委員に立候補していた陸上男子ハンマー投げの室伏広治が、選挙活動規定に違反したとして、候補者から取り消したと発表した(11日)。室伏は立候補した21人中、選手間による投票数は1位、つまりほぼ当確だった。その違反とは、選手村のダイニングホールで選挙活動をしたとのこと。当選すれば、IOC委員もかねるため、東京五輪招致に向けての活動が期待されていただけに、JOC日本オリンピック委員会の落胆ぶりが目に浮かぶ。うがった見方をすれば、ダイニングホールでの名刺交換を「選挙活動だ」とIOCに指したライバルがいるということだ。後味が悪い。