★シェアの呪縛
「呪縛」とは、まじないをかけて動けなくすること。あるいは、心理的な強制によって、人の自由を束縛することの意味である。日本人ほど、シェア(市場占有率)にこだわり、自ら呪縛されている国民はないのではないかと最近考えている。
 シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。
シェアにこだわること、それは、そこそこ品質がよいものを低価格で売り、市場の占有率を高めることだ。シェア1番でなければ存在意味がないと、ライバルが現れると価格競争でしのぎを削り、競り勝つ、それが勝利の方程式だった。ところが、2007年に起きたサブプライム問題に端を発したリーマンショック以降、世界的な金融不安が市場を覆い、リスク回避の流れからヨーロッパやアメリカのヘッジファンドなどが円買いに走った。円高にぶれてきて、日本の家電製品も自動車も価格競争という手を打てなくなった。もともと商品はそこそこの品質だったので、韓国や台湾、中国といったメーカーの追い上げを食らうようになる。日本のメーカーは、円高で価格競争ができない分、多機能化することで魅力をアップしようとした。ただ、多機能化の行き過ぎが製品の魅力を低下させることもある。
むしろ、多機能より単純で使いやすい方がその機能のチカラというものを発揮させるものだ。海外が住む友人から、「日本製はやたらと多機能で値段が高い。韓国のサムスンなどは求められている、あるいは必要な機能に絞って販売している。結果、使いやすい」と聞いたことがある。世界の人々は日本人ほど器用でない。その日本人でさえ、地上デジタルテレビのリモコンに今でも辟易している。デジタルカメラもボタンが多く、静止画を撮ろうしして、動画撮影になったりすることがままある。日本企業にめぼしい技術革新もなかった。リーマンショックから5、6年が過ぎて、日本製品は海外で随分とシェアを落とした。
ここで最近、よく話題になるのが、日本製品とドイツ製品はどこで違いが出てきたのか、ということである。『日経ビジネス』(2013年2月25日)の記事が興味深かった。ドイツ人実業家ハーマン・サイモン氏の言葉を引用して、「日本企業はブランドや高級感の創出力に欠け、技術的な強みを活用しきれていない」と。つまり、「ソニーやパナソニックがなぜ10~20%上乗せの価格で売り、消費者を引きつけることができないのか」「市場シェアを追求する追及する限り、値下げによる価格競争に巻き込まれざるを得ない」と。シュアを落としてでもブランドイメージを創造すべきだというのだ。知名度の高さとブランドイメージを混同してはならない。ドイツの中小企業は高価格で売ることに努力を惜しまなかった。シェアより、利益にこだわったからだ。
シェアにこだわるのは何も工業製品だけと限らない。これは直観だが、国内ではマスメディアがこのシェアの罠に落ちている。部数というシェア争いを新聞社は演じている。かつて広告費はテレビに食われ、いまはインターネット広告に浸食されている。それでも、何とか各社が新聞を発行し続けることができているのは宅配制度という強固な販売システムに支えられているからだろう。では、紙面の中身はどうか。1面から社会面まで各紙ほとんど同じなのである。我先にセンセーショナリズムに走っている。しかも、うがった見方をすれば、発表を先取りすることを「スクープ」と称している。ここのところ、昨今の新しい日銀総裁の人事案件などはその典型だろう。数日経れば発表される記事を、各社血まなこになって先を争い追いかけた。
日経新聞はもともと別だが、全国紙のうちの1紙ぐらいは「クオリティペーパーを目指す」と宣言して、発表の先取り型から独自の調査報道に重心を置く新聞社が現れないものだろうか。ただ、報道現場は賛成しても、販売や広告の現場が反対するかもしれない。「シェアを落とす」と。「読者はテレビやネットに出たニュースを最終的に新聞で確認したいと思っている。新聞はニュースのアンカーだ」として、独自の調査報道路線には承服しないだろう。
シェア(視聴率)を取れる番組とは何かを追求しているテレビ局も同じだ。大衆迎合だと視聴者から言われても、子どもに見せたくない番組だと言われても、ゴールデン番組はお笑いタレントが占める。番組タイトルは違うが、どこもコンセプトはどこかよく似ている。短いキャッチフレーズでお笑いを取り、視聴者も満足している。そして、いま、日本国中がB級グルメ選手権ばやりだ。A級グルメを目指さない風潮になった。A級では人が集まらないからだ。
シェアには、市場に対する影響力や発言力の拡大や、顧客の囲い込みといったメリットがあるものの、世界的な競争の中でシェアは崩されやすく、消耗度が高い。ドイツ企業はシェアより利益をどう高めるかを模索した。
⇒2日(土)朝・金沢の天気 くもり
 「5大シャトー」は、1855年のパリ万国博覧会で、皇帝ナポレオン3世は世界中から集まる訪問客に向けて、フランスのボルドーワイン(赤)の展示に格付けが必要だと考えた。 そこで、ボルドー・メドック地区で、ワイン仲買人が評判や市場価格に従って、ワインをランク付けした。その格付けで4つのシャトーに「第一級」の称号を与えられた。それ以来、ボルドーワインの公式格付けとなった。その4つとは「Ch.Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」、「Ch.Margaux(シャトー・マルゴー)」、「Ch.Latour(シャトー・ラトゥール)」、「Ch.Haut Brion(シャトー・オー・ブリオン)」のこと。これに、1973年の格付けで昇格した、「Ch.Mouton Rothschild(シャトー・ムートン・ロスシルド)」を加え、これら5つが世界トップクラス・シャトーといわれるようになった。インターネットで調べてみても、それぞれ1本5万円は下らない。ちなみの、今回の講座の会費は2万3千円。グラスに1杯ずつ5大シャトーが飲めるのだから。一生に一度のチャンスと思えば、案外お得かも知れない。
「5大シャトー」は、1855年のパリ万国博覧会で、皇帝ナポレオン3世は世界中から集まる訪問客に向けて、フランスのボルドーワイン(赤)の展示に格付けが必要だと考えた。 そこで、ボルドー・メドック地区で、ワイン仲買人が評判や市場価格に従って、ワインをランク付けした。その格付けで4つのシャトーに「第一級」の称号を与えられた。それ以来、ボルドーワインの公式格付けとなった。その4つとは「Ch.Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」、「Ch.Margaux(シャトー・マルゴー)」、「Ch.Latour(シャトー・ラトゥール)」、「Ch.Haut Brion(シャトー・オー・ブリオン)」のこと。これに、1973年の格付けで昇格した、「Ch.Mouton Rothschild(シャトー・ムートン・ロスシルド)」を加え、これら5つが世界トップクラス・シャトーといわれるようになった。インターネットで調べてみても、それぞれ1本5万円は下らない。ちなみの、今回の講座の会費は2万3千円。グラスに1杯ずつ5大シャトーが飲めるのだから。一生に一度のチャンスと思えば、案外お得かも知れない。 前々回に紹介した金沢の料亭「大友楼」でいただいた「鯛の唐蒸し(たいのからむし)」=写真=が誤解の一つだった。二匹の鯛の腹に卯の花(おから)を詰めて大皿に並べたもの。婚礼に際して供される料理。、「にらみ鯛」や「鶴亀鯛」と呼ばれることもある。嫁入り道具とともに花嫁が持参する鯛を、婿側が調理して招待客にふるまうのがならわしである。子宝に恵まれるように、銀杏・百合根・麻の実・きくらげ・人参・蓮根などを入れた卯の花を鯛の腹一杯に詰め、雌雄二匹の鯛を腹合せにして並べる。これまで、知人や同僚の婚礼の披露宴に出席して、何度か口にした。が、正直見栄えだけ豪華でおいしくない料理との印象が残っていた。それが誤解だった。
前々回に紹介した金沢の料亭「大友楼」でいただいた「鯛の唐蒸し(たいのからむし)」=写真=が誤解の一つだった。二匹の鯛の腹に卯の花(おから)を詰めて大皿に並べたもの。婚礼に際して供される料理。、「にらみ鯛」や「鶴亀鯛」と呼ばれることもある。嫁入り道具とともに花嫁が持参する鯛を、婿側が調理して招待客にふるまうのがならわしである。子宝に恵まれるように、銀杏・百合根・麻の実・きくらげ・人参・蓮根などを入れた卯の花を鯛の腹一杯に詰め、雌雄二匹の鯛を腹合せにして並べる。これまで、知人や同僚の婚礼の披露宴に出席して、何度か口にした。が、正直見栄えだけ豪華でおいしくない料理との印象が残っていた。それが誤解だった。 これはニュースにおけるスクープやスピードだけのことなのだろうか。先日、現役の新聞記者と話す機会があり、話題になった。記者によると、「夜討ち・朝駆けという取材手法があるのは世界で日本と韓国だけらしい」と。続けて、「複数の記者たちを前に事件が経緯や概要を発表するのはある意味で建て前だ。ただ、捜査の経緯の中で隠されたことや、謎の部分で公表したくてもできない場合がある、つまりその本音を聞きたい」と。面白いのはそれが日本と韓国だけらしい、という点だ。確かに、両国とも本音と建て前の精神性がある。かしこまっての公の場ではなかなか本音が出ない。ならば、裏の非公式な場でその本音の話を聞こうとなる。ただ、本音の話を聞き出せても、実名はなかなか書けない。そこで、「警察幹部によると」などの書き出しで始まることになる。匿名である。
これはニュースにおけるスクープやスピードだけのことなのだろうか。先日、現役の新聞記者と話す機会があり、話題になった。記者によると、「夜討ち・朝駆けという取材手法があるのは世界で日本と韓国だけらしい」と。続けて、「複数の記者たちを前に事件が経緯や概要を発表するのはある意味で建て前だ。ただ、捜査の経緯の中で隠されたことや、謎の部分で公表したくてもできない場合がある、つまりその本音を聞きたい」と。面白いのはそれが日本と韓国だけらしい、という点だ。確かに、両国とも本音と建て前の精神性がある。かしこまっての公の場ではなかなか本音が出ない。ならば、裏の非公式な場でその本音の話を聞こうとなる。ただ、本音の話を聞き出せても、実名はなかなか書けない。そこで、「警察幹部によると」などの書き出しで始まることになる。匿名である。
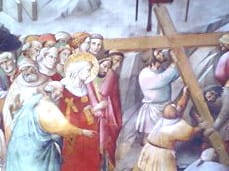 石川県は高齢者が子供と暮らす割合が高い方だ。厚生労働省の平成24年版「国民生活基礎調査(平成22年)」によると、「65歳以上の者の子との同居率」は全国平均42.3%に対し、県別では石川51.9%、もっとも高い山形は65.1%となる。にもかかわらず増えている、と。新聞記事を続けよう。石川県には65歳以上の高齢者が27万5千人(2011年10月現在)、うち一人暮らしは3万6千人(2010年10月現在)、高齢者夫婦のみの世帯は4万4千世帯(同)である。そうした中で、高齢者の孤独死が年々増えている。石川県警では、一人暮らしの高齢者の変死事案は2003年には126人、2010年に203人、2012年では11月末現在で223人となった。
石川県は高齢者が子供と暮らす割合が高い方だ。厚生労働省の平成24年版「国民生活基礎調査(平成22年)」によると、「65歳以上の者の子との同居率」は全国平均42.3%に対し、県別では石川51.9%、もっとも高い山形は65.1%となる。にもかかわらず増えている、と。新聞記事を続けよう。石川県には65歳以上の高齢者が27万5千人(2011年10月現在)、うち一人暮らしは3万6千人(2010年10月現在)、高齢者夫婦のみの世帯は4万4千世帯(同)である。そうした中で、高齢者の孤独死が年々増えている。石川県警では、一人暮らしの高齢者の変死事案は2003年には126人、2010年に203人、2012年では11月末現在で223人となった。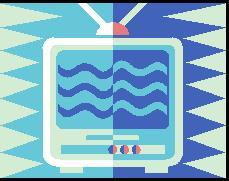 読売新聞は検証記事(10月26日付)で、「当時の取材は、実験記録や年齢、肩書など確認が不十分だった」など取材の不備を認めた。共同通信も「速報を重視するあまり、専門知識が必要とされる科学分野での確認がしっかりできないまま報じてしまった」という。しかし、これは言い訳にすぎない。報道に「伝えない」という選択肢はなく、伝える以上は裏付けに手を尽くすのが報道機関の使命である。当然、その結果責任はつきまとう。
読売新聞は検証記事(10月26日付)で、「当時の取材は、実験記録や年齢、肩書など確認が不十分だった」など取材の不備を認めた。共同通信も「速報を重視するあまり、専門知識が必要とされる科学分野での確認がしっかりできないまま報じてしまった」という。しかし、これは言い訳にすぎない。報道に「伝えない」という選択肢はなく、伝える以上は裏付けに手を尽くすのが報道機関の使命である。当然、その結果責任はつきまとう。 現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じている。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていない。これまで、ネット選挙解禁についての論議は何度もありながらも、政治の混乱の中で法案は提出されてこなかった。たとえば、2010年の参院選挙の前に、民主、自民、公明の与野党は候補者・政党が選挙期間中にホームページやブログを更新できるとする公選法改正に合意していたのに、である。
現行の公職選挙法は、公示・告示後の選挙期間中は、法律で定められたビラやはがきなどを除き、「文書図画(とが)」を不特定多数に配布することを禁じている。候補者のホームページやツイッターなどソーシャルメディアの発信は、こうした文書図画に相当し、現行では認められていない。これまで、ネット選挙解禁についての論議は何度もありながらも、政治の混乱の中で法案は提出されてこなかった。たとえば、2010年の参院選挙の前に、民主、自民、公明の与野党は候補者・政党が選挙期間中にホームページやブログを更新できるとする公選法改正に合意していたのに、である。 テレビ朝日『選挙ステーション』では、20時34分に石川一区(金沢市)の出口調査の得票数をパーセントで発表していた。そのポイント。馳浩(自民)47.6%、奥田建(民主)23.4%、小間井俊輔(維新)19.3%、熊野盛夫(未来)5.5%と続いた。では、実際の得票率はどうだったのか。翌日の北陸中日新聞で掲載された確定票をもとにした獲得率は、馳浩47.87%、奥田建22.88%、小間井俊輔19.82%、熊野盛夫5.11%だった。馳の誤差はマイナス0.2、奥田プラス0.6、小間井マイナス0.5、熊野プラス0.4なのである。つまり、どの候補者も出口調査と確定票の得票率の誤差は1.0ポイント以下だったことになる。
テレビ朝日『選挙ステーション』では、20時34分に石川一区(金沢市)の出口調査の得票数をパーセントで発表していた。そのポイント。馳浩(自民)47.6%、奥田建(民主)23.4%、小間井俊輔(維新)19.3%、熊野盛夫(未来)5.5%と続いた。では、実際の得票率はどうだったのか。翌日の北陸中日新聞で掲載された確定票をもとにした獲得率は、馳浩47.87%、奥田建22.88%、小間井俊輔19.82%、熊野盛夫5.11%だった。馳の誤差はマイナス0.2、奥田プラス0.6、小間井マイナス0.5、熊野プラス0.4なのである。つまり、どの候補者も出口調査と確定票の得票率の誤差は1.0ポイント以下だったことになる。 一方、先日、金沢の知人から「あなたの英知に判断ゆだねる」とある候補者の推薦の葉書が届いた。能弁な友人なのだから自分の思いを葉書ではなく、電話なり、直接の会話で表現すればよいだろうと思う。日本全体がこの時期、人に向かって「私は○○候補に一票を投じたい。それの理由はこうだ」と話すことを控え、まるで自粛しているようだ。そのくせ、新聞やテレビの世論調査に目を凝らし、耳を傾けている。そして、最近声がかすれた候補者の乗った選挙カーが市内を走り回っている。この風景は何十年も変わらない。盛り上がらない、まさに、選挙停滞の風景なのだ。
一方、先日、金沢の知人から「あなたの英知に判断ゆだねる」とある候補者の推薦の葉書が届いた。能弁な友人なのだから自分の思いを葉書ではなく、電話なり、直接の会話で表現すればよいだろうと思う。日本全体がこの時期、人に向かって「私は○○候補に一票を投じたい。それの理由はこうだ」と話すことを控え、まるで自粛しているようだ。そのくせ、新聞やテレビの世論調査に目を凝らし、耳を傾けている。そして、最近声がかすれた候補者の乗った選挙カーが市内を走り回っている。この風景は何十年も変わらない。盛り上がらない、まさに、選挙停滞の風景なのだ。 この過剰適合の悲劇は実際に日本の社会のあちこちで起きている。人種も言語も多様ではない、この国の社会は画一性を生み、工業化社会では断トツのチカラを発揮した。しかし、多様性が発揮される情報化社会では出遅れてしまった。その代表例が「民主主義と選挙」の関係ではないかと考える。
この過剰適合の悲劇は実際に日本の社会のあちこちで起きている。人種も言語も多様ではない、この国の社会は画一性を生み、工業化社会では断トツのチカラを発揮した。しかし、多様性が発揮される情報化社会では出遅れてしまった。その代表例が「民主主義と選挙」の関係ではないかと考える。