★報道被害
 リポートを提出した200人の学生がインタビューしたい相手として選ばれたトップは小保方晴子さん(「STAP細胞」研究者)。24人の学生が選んだ。主な質問は「STAP細胞の再検証実験により、STAP細胞の存在を証明する自信はありますか」というものだった。2番目に多かったのが、安倍晋三・総理大臣の23人。主な質問は「集団的自衛権の行使を憲法改正ではなく憲法解釈により容認した理由は」。3番目がサッカー選手の本田圭祐氏。主な質問は「優勝を目標に掲げて挑んだ今回のW杯の結果についての感想は」というものだった。学生のインタビューの相手は時代の世相を反映している。ちなみに、あの泣きの野々村竜太郎・元兵庫県議には8人の学生がインタビューを望んだ。
リポートを提出した200人の学生がインタビューしたい相手として選ばれたトップは小保方晴子さん(「STAP細胞」研究者)。24人の学生が選んだ。主な質問は「STAP細胞の再検証実験により、STAP細胞の存在を証明する自信はありますか」というものだった。2番目に多かったのが、安倍晋三・総理大臣の23人。主な質問は「集団的自衛権の行使を憲法改正ではなく憲法解釈により容認した理由は」。3番目がサッカー選手の本田圭祐氏。主な質問は「優勝を目標に掲げて挑んだ今回のW杯の結果についての感想は」というものだった。学生のインタビューの相手は時代の世相を反映している。ちなみに、あの泣きの野々村竜太郎・元兵庫県議には8人の学生がインタビューを望んだ。
2010年12月の課題リポートでも同じように、インタビューしたい相手を書いてもらった。4年前である。この時は188人の学生から回答を得た。1位が野球選手のイチローだった。主な質問は「どうしたらプレッシャーに打ち勝つことができますか」「セコイという質問にどう答えますか」だった。このセコイというのは外国人の眼で、内野安打を確実に稼いでいくイチローの野球に対して、ホームランの一発を期待する海外のファンの見立てをそのまま質問にしたのだろう。冒頭の課題リポートは7月下旬に提出してもらった。その後、予期せぬことが起きた。
NHKスペシャル「STAP細胞不正の深層」(7月27日放送)の事前取材(同月23日)で、小保方氏を追いかけ、全治2週間のケガを負わせたと報道された。さらに、放送の9日後の8月5日朝、小保方氏の研究指導の中心メンバーだった理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長、笹井芳樹氏(52)が自殺した。NHK番組は、笹井氏が小保方氏の実験の不備を把握していたのに、それを怠ったのではないかとする内容の、責任追及もしていた。また、笹井氏と小保方氏の2人が交わしたメールの文章を読む声がなんともに2人の「特別な関係」の雰囲気を与える印象だった。
NHKスペシャルの取材班としては、どうしても小保方氏のインタビュー(肉声)を撮りたかったのだろう。そして、ホテルに駆け込んだ小保方氏を逃がすまいと記者・カメラマンを含め4、5人で囲んだのだろうことは想像に難くない。事件を報道した新聞・テレビのニュースを読み比べると、「そこまで追い詰める必要はあったのか」との論調が多い。小保方氏にとっては、ケガをしたのだから「報道被害」ではある。今、学生たちに同じインタビューをしたい相手は誰かと尋ねれば、おそらく「NHKスペシャルのプロデューサー」だろう。その質問の趣旨は「そこまで小保方さんを追い詰め、どんなインタビューの返事を期待したのか」ではないだろうか。
⇒6日(水)夜・金沢の天気 くもり
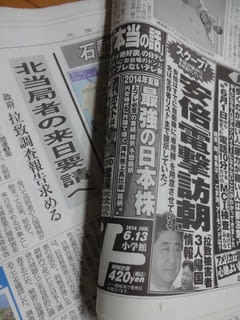 今回の拉致をめぐる日朝交渉でいろいろとイメージが膨らむ。「安倍総理の電撃的な訪朝はあるのか」。つい先日も、マスメディアの友人たちと雑談を交わした。「ある」「ない」と意見は二手に分かれる。「ある」とする方は、安倍総理の外交の柱の一つであり、ある意味で悲願でもあるので、「訪朝するくらいの覚悟はできているだろう」と。今月8日で放送されたNHK「日曜討論」で、自民党の高村副総裁は「(安倍総理が訪朝する可能性は)ゼロでない」と語っていた。おそらく総理訪朝のメリット、デメリットなど当然検討されているのだろう。
今回の拉致をめぐる日朝交渉でいろいろとイメージが膨らむ。「安倍総理の電撃的な訪朝はあるのか」。つい先日も、マスメディアの友人たちと雑談を交わした。「ある」「ない」と意見は二手に分かれる。「ある」とする方は、安倍総理の外交の柱の一つであり、ある意味で悲願でもあるので、「訪朝するくらいの覚悟はできているだろう」と。今月8日で放送されたNHK「日曜討論」で、自民党の高村副総裁は「(安倍総理が訪朝する可能性は)ゼロでない」と語っていた。おそらく総理訪朝のメリット、デメリットなど当然検討されているのだろう。 話は変わる。能登半島には一連の拉致被害の第1号の現場がある。最近何度か訪れた。警察関係者の間では、「宇出津(うしつ)事件」と称される。1977年9月19日、東京都三鷹市役所の警備員だった久米裕さん(当時52歳)が石川県能登町宇出津の海岸で失踪した。当時事件を取材した元新聞記者から話を聞いた。
話は変わる。能登半島には一連の拉致被害の第1号の現場がある。最近何度か訪れた。警察関係者の間では、「宇出津(うしつ)事件」と称される。1977年9月19日、東京都三鷹市役所の警備員だった久米裕さん(当時52歳)が石川県能登町宇出津の海岸で失踪した。当時事件を取材した元新聞記者から話を聞いた。 安倍総理にとって拉致問題の解決は政治家としての「ライフワーク」とも言える。これまでの記憶をたどる。安倍氏は小泉内閣時に官房副長官と官房長官を務めた。2002年3月に官房副長官に就任し「拉致疑惑に関するPT(プロジェクトチーム)」を発足させ、さらにその年の4月には衆参院で「拉致疑惑の早期解決を求める決議」が採択された。その年の9月にあの電撃的な小泉訪朝が実現する。当時の金正日総書記と会談し、拉致を認めさせた。翌10月には蓮池薫さんら拉致被害者5人が帰国した。さらに2004年5月、小泉総理が再訪朝し、拉致被害者の子5人が帰国した。小泉氏が総理として爆発的な人気を得たのは、郵政民営化だけでなく、何と言ってもこの拉致被害者の帰国があったというのも大きい。当時、小泉訪朝を支えた安倍氏は一貫して「日本人拉致疑惑をうやむやにして、国交正常化などすべきではない」が持論だった。影の立役者だった。
安倍総理にとって拉致問題の解決は政治家としての「ライフワーク」とも言える。これまでの記憶をたどる。安倍氏は小泉内閣時に官房副長官と官房長官を務めた。2002年3月に官房副長官に就任し「拉致疑惑に関するPT(プロジェクトチーム)」を発足させ、さらにその年の4月には衆参院で「拉致疑惑の早期解決を求める決議」が採択された。その年の9月にあの電撃的な小泉訪朝が実現する。当時の金正日総書記と会談し、拉致を認めさせた。翌10月には蓮池薫さんら拉致被害者5人が帰国した。さらに2004年5月、小泉総理が再訪朝し、拉致被害者の子5人が帰国した。小泉氏が総理として爆発的な人気を得たのは、郵政民営化だけでなく、何と言ってもこの拉致被害者の帰国があったというのも大きい。当時、小泉訪朝を支えた安倍氏は一貫して「日本人拉致疑惑をうやむやにして、国交正常化などすべきではない」が持論だった。影の立役者だった。 北ベトナムとアメリカによる、いわゆるベトナム戦争の真っただ中の1974年、当時の南ベトナムが支配していた西沙諸島を中国人民軍が武力で確保し、「領土」とした。ベトナム戦争が終結した1988年には、さらに南沙諸島にも中国が進出し、統一ベトナムとの間で軍事衝突が起きた。中国は南シナ海のほぼ全域を覆うように「九段線」と呼ぶマーキングエリアを設定し、中国の主権と権益が及ぶと公言している。
北ベトナムとアメリカによる、いわゆるベトナム戦争の真っただ中の1974年、当時の南ベトナムが支配していた西沙諸島を中国人民軍が武力で確保し、「領土」とした。ベトナム戦争が終結した1988年には、さらに南沙諸島にも中国が進出し、統一ベトナムとの間で軍事衝突が起きた。中国は南シナ海のほぼ全域を覆うように「九段線」と呼ぶマーキングエリアを設定し、中国の主権と権益が及ぶと公言している。 この件の事情を韓国メディアの掲載記事で検索すると、2013年9月23日付の中央日報WEB版(日本語)は嘆いている。経済協力開発機構(OECD)加盟国で交通事故死亡率1位(2010年基準)、人口100万人当たり死亡者は114人。「交通事故死亡者5392人のうち57.4%に当たる3093人が歩道と車道が区分されていない幅9㍍未満の生活道路で犠牲になった。高速道路や広い道路よりも住宅地周辺の狭い道がさらに危険なのが韓国の現実だ」と。ちなみに、同じ統計で日本では100万人当たり死亡者45人なので、韓国の死亡事故は日本の2倍以上となる。ただ、交通死亡事故の定義は日本は24時間以内で死亡した統計であり、各国との比較は微妙だが、それにしても韓国の死亡事故は多い。
この件の事情を韓国メディアの掲載記事で検索すると、2013年9月23日付の中央日報WEB版(日本語)は嘆いている。経済協力開発機構(OECD)加盟国で交通事故死亡率1位(2010年基準)、人口100万人当たり死亡者は114人。「交通事故死亡者5392人のうち57.4%に当たる3093人が歩道と車道が区分されていない幅9㍍未満の生活道路で犠牲になった。高速道路や広い道路よりも住宅地周辺の狭い道がさらに危険なのが韓国の現実だ」と。ちなみに、同じ統計で日本では100万人当たり死亡者45人なので、韓国の死亡事故は日本の2倍以上となる。ただ、交通死亡事故の定義は日本は24時間以内で死亡した統計であり、各国との比較は微妙だが、それにしても韓国の死亡事故は多い。 もちろん、4人の教師は無断欠席したわけではなく、校長に事前に届けていたので、「倫理」を問うというのはおおげさかもしれない。ただ、新入生の担任が入学式の当日にいないとなると、どうなっているのかと不審に思う保護者(父母など)もいるだろ。一方で、擁護する人は、教師は聖職者ではあるが、人の親でもあり、職業より私生活を優先させるケースがあったとしてもそう目くじらを立てることもない。それは、校長との話し合いでの上の判断なのだから、相当な理由があったはず、と。
もちろん、4人の教師は無断欠席したわけではなく、校長に事前に届けていたので、「倫理」を問うというのはおおげさかもしれない。ただ、新入生の担任が入学式の当日にいないとなると、どうなっているのかと不審に思う保護者(父母など)もいるだろ。一方で、擁護する人は、教師は聖職者ではあるが、人の親でもあり、職業より私生活を優先させるケースがあったとしてもそう目くじらを立てることもない。それは、校長との話し合いでの上の判断なのだから、相当な理由があったはず、と。 今月上旬、埼玉県の県立高校で、それぞれ勤務校は別々だが、新入生の担任の教師4人が入学式を欠席した。その理由は、いずれも自分の子供の入学式に出席するため。式はいずれも8日にあり、4人はそれぞれ子供の小学校や中学校、高校の入学式に出た。4人のうち3人は女性教師だった。1人の男性教師は2人の子供の入学式が重なり、妻と手分けして出席したのだという。4人とも事前に校長に相談していて、有給休暇を取った。
今月上旬、埼玉県の県立高校で、それぞれ勤務校は別々だが、新入生の担任の教師4人が入学式を欠席した。その理由は、いずれも自分の子供の入学式に出席するため。式はいずれも8日にあり、4人はそれぞれ子供の小学校や中学校、高校の入学式に出た。4人のうち3人は女性教師だった。1人の男性教師は2人の子供の入学式が重なり、妻と手分けして出席したのだという。4人とも事前に校長に相談していて、有給休暇を取った。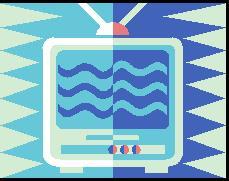 韓国のテレビ局の無神経なインタビューも話題になった。テレビ局の記者が事故現場付近での取材で、助かった女子生徒に対し、「友達死んだの、知ってるか」と質問し、その生徒は「知らない。聞いていない」と大声で泣きだした。このシーンが放送され、視聴者の批判が殺到したのはいうまでもない。現場では緊張感がみなぎっているので違和感なく記者がインタビューしたつもりでも、視聴する側の茶の間感覚では悲しみにくれる生徒にさらに追い打ちをかけるような行為に見えるものだ。気になったのは、このシーンは生中継で送られた映像なのかどうかということだ。普段このような映像が現地から送られてきた場合、本社での編集段階で問題となって、映像を使うのを取りやめるケースが多々ある。しかし、生中継の場合はダイレクトに各家庭に映像が飛び込んでくるので、こうした問題の画像は防ぎようがない。今回はどのケースだったのだろうか。
韓国のテレビ局の無神経なインタビューも話題になった。テレビ局の記者が事故現場付近での取材で、助かった女子生徒に対し、「友達死んだの、知ってるか」と質問し、その生徒は「知らない。聞いていない」と大声で泣きだした。このシーンが放送され、視聴者の批判が殺到したのはいうまでもない。現場では緊張感がみなぎっているので違和感なく記者がインタビューしたつもりでも、視聴する側の茶の間感覚では悲しみにくれる生徒にさらに追い打ちをかけるような行為に見えるものだ。気になったのは、このシーンは生中継で送られた映像なのかどうかということだ。普段このような映像が現地から送られてきた場合、本社での編集段階で問題となって、映像を使うのを取りやめるケースが多々ある。しかし、生中継の場合はダイレクトに各家庭に映像が飛び込んでくるので、こうした問題の画像は防ぎようがない。今回はどのケースだったのだろうか。