☆土下座の記者会見
とても違和感を感じた謝罪会見だった。長野県軽井沢町で15日に起きたスキーバス転落事故(乗客の学生、運転手ら14人が死亡)で、バスを運行していた「イーエスピー」(東京都羽村市)の社長や営業部 長ら3人が16日に本社で記者会見した様子が新聞やテレビで報じられた。
長ら3人が16日に本社で記者会見した様子が新聞やテレビで報じられた。
この記者会見で、出発前の健康チェックやアルコール検査は法律で義務づけられているにもかかわらず、事故を起こしたバスの運転手に対する健康チェックを出発前にしていなかったことを明らかにした。しかも、そのチェックを社長自らが確認する予定だったが、「時間を勘違いして遅刻し、運転手が先に行った」と釈明していた。
その記者会見の最後、午後4時40分いきなり社長ら3人が土下座を始めたのである。テレビの画面で見る限りで、顔を真っ赤にした社長は涙を流しながら床に額をつけ、「心よりお詫びを申し上げます」と。60秒余りの土下座だったろうか、その後も動かず、社員に引き離されるカタチで退出した。
14人もの命が失われた大事故であり、土下座の謝罪は無理もないだろう。違和感を感じたのは、その土下座を会見で使った机の後ろ側で行ったことである。本来ならば、机の前に出てきて、カメラに向かっての土下座ポーズが本来の姿だろう。社長は土下座をしたものの、誰に向かっての謝罪かおそらく混乱して頭が回らなかったのではないかと想像した。
この土下座で動揺したのは報道各社のカメラマンたちだった。社長らの土下座のポーズが机の下に隠れてしまい、慌ててカメラマンたちが前に出てきて、あるいは机の下から撮影するというハプニングだった。
この事故報道でもう一つ、犠牲者の顔写真の入手にいかにフェイスブックやツイッタ-が役立ったかということが実感できた。中日新聞の例だと、死亡した12人の学生たちの全員の顔写真を掲載しているが、そのうち、8人の顔写真がインターネットからの引用である。フェイスブックが6人、ツイッターが1人、ホームページが1人の内訳だ。同紙は「※写真はフェイスブックから」などと引用元を明記している。
一般的に考えれば、いくら引用元を明記しているとは言え、勝手に新聞社やテレビ局が掲載してよいのか、と思って不思議ではない。メディア側とすれば、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載されている画像や画像の利用は、報道利用であれば、投稿者の許諾が得られない場合でも利用が可能との判断をしている。肖像権より報道利用は優先されるのである。投稿者本人が利用を拒否した場合でも、事件・事故に絡む報道利用であるならば、法律上での問題はない。メディアによっては引用元すら明記しないところもある。 ただ、読者や視聴者は顔写真を見たいか、見たくないかは別判断だ。
⇒17日(日)夜・金沢の天気 くもり
 者が多いだろうと想像していたのだが、当日の顔ぶれをみると、北海道の札幌テレビ放送、南は琉球朝日放送からの参加があり、4Kの番組制作についての関心の高さがうかがえた。
者が多いだろうと想像していたのだが、当日の顔ぶれをみると、北海道の札幌テレビ放送、南は琉球朝日放送からの参加があり、4Kの番組制作についての関心の高さがうかがえた。
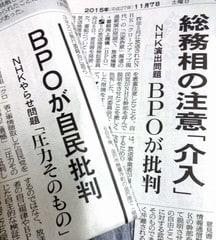 ことを悪用して別人を装い、金融機関から融資をだまし取るケースが広がっていると紹介した。ところが、番組内で多重債務者に出家を指南するブローカーとされた男性が今年3月18日付の週刊文春に「NHKのやらせ」と告発した。
ことを悪用して別人を装い、金融機関から融資をだまし取るケースが広がっていると紹介した。ところが、番組内で多重債務者に出家を指南するブローカーとされた男性が今年3月18日付の週刊文春に「NHKのやらせ」と告発した。 り続けているテント村を訪ねた。「座り込み4175日」とある。東京から来たという女子学生3人がテント村の人たちと話し込んでいた。「私たちはこのきれいな海を戦場にしたくない。新基地がどれだけ県民の心の負担になるか察してほしい」とテント村のスタッフが訴えていた。
り続けているテント村を訪ねた。「座り込み4175日」とある。東京から来たという女子学生3人がテント村の人たちと話し込んでいた。「私たちはこのきれいな海を戦場にしたくない。新基地がどれだけ県民の心の負担になるか察してほしい」とテント村のスタッフが訴えていた。 踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪防止条約)では、日本政府とこれまで、日本人拉致問題を念頭に「国境を越えた拉致」を条約案に盛り込むよう働きかけて、採択されている。こうした条約の中に、知事が訴える「基地は人権問題」という概念を落とし込む条約は見当たらないのではないか。見当たらないとしても、沖縄タイムスが記事にしているように、人権理事会の円形会議場には「同じように助けを求めに来ている人がたくさんいた」ということだ。
踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪防止条約)では、日本政府とこれまで、日本人拉致問題を念頭に「国境を越えた拉致」を条約案に盛り込むよう働きかけて、採択されている。こうした条約の中に、知事が訴える「基地は人権問題」という概念を落とし込む条約は見当たらないのではないか。見当たらないとしても、沖縄タイムスが記事にしているように、人権理事会の円形会議場には「同じように助けを求めに来ている人がたくさんいた」ということだ。 午前2時すぎに記名投票が始まった。壇上の野党議員は「戦争法案反対」などと叫びながら、法案反対の青票を掲げていた。与党議員は賛成の白票を積み上げていた。午前2時18分。野党議員が「憲法違反」と叫ぶ中、賛成多数で同法は可決した。中谷防衛大臣が議長と議場に向かって頭を3回下げた。賛成148票、反対90票だった。
午前2時すぎに記名投票が始まった。壇上の野党議員は「戦争法案反対」などと叫びながら、法案反対の青票を掲げていた。与党議員は賛成の白票を積み上げていた。午前2時18分。野党議員が「憲法違反」と叫ぶ中、賛成多数で同法は可決した。中谷防衛大臣が議長と議場に向かって頭を3回下げた。賛成148票、反対90票だった。 立 平和主義転換、米支援拡大」、地元紙の北國新聞は「安保法が成立 集団的自衛権可能に 戦後政策の大転換」だった。北陸に輪転工場がない朝日新聞、毎日新聞の各紙はコンビニでは売っていない。
立 平和主義転換、米支援拡大」、地元紙の北國新聞は「安保法が成立 集団的自衛権可能に 戦後政策の大転換」だった。北陸に輪転工場がない朝日新聞、毎日新聞の各紙はコンビニでは売っていない。 本会議の採決を退席した民主の議員は「これほど国会の中の光景と、国会の外の国民の声がかけ離れて聞こえた経験はない」と語った。議員は審議を振り返り、「総理は何をしてもいいとお考えなら、勘違いされているのでは」(7月17日付・朝日新聞)
本会議の採決を退席した民主の議員は「これほど国会の中の光景と、国会の外の国民の声がかけ離れて聞こえた経験はない」と語った。議員は審議を振り返り、「総理は何をしてもいいとお考えなら、勘違いされているのでは」(7月17日付・朝日新聞) 金沢でテレビを視聴ていると、最近、安保法制に関して「国会周辺では…」とのフレーズをやたらと耳にする。国会内での政治的な動きより、むしろ外の動きをメディアは気しているのではいかと思うほど、アナウンサーやキャスターが「国会周辺では…」と繰り返している。そこで、国会周辺は一体どうなっているのか、どのような人たちが行動を起こしているのか、気になったので、ちょっと現場を覗いてみたということだ。滞在時間はわずか15分ほどだった。
金沢でテレビを視聴ていると、最近、安保法制に関して「国会周辺では…」とのフレーズをやたらと耳にする。国会内での政治的な動きより、むしろ外の動きをメディアは気しているのではいかと思うほど、アナウンサーやキャスターが「国会周辺では…」と繰り返している。そこで、国会周辺は一体どうなっているのか、どのような人たちが行動を起こしているのか、気になったので、ちょっと現場を覗いてみたということだ。滞在時間はわずか15分ほどだった。 こうした事故の様子、たとえば死者や負傷者の数は日本の場合、消防当局がその都度記者会見して発表する。中国でもこの天津の爆発に関して13日午後に会見した、と日本のテレビが伝えている。それによると、これまでに44人が死亡し、けが人は521人にのぼっているとの発表だった。爆風で広範囲のマンションなどに被害が出ていて、住民3500人ほどが避難しているという。
こうした事故の様子、たとえば死者や負傷者の数は日本の場合、消防当局がその都度記者会見して発表する。中国でもこの天津の爆発に関して13日午後に会見した、と日本のテレビが伝えている。それによると、これまでに44人が死亡し、けが人は521人にのぼっているとの発表だった。爆風で広範囲のマンションなどに被害が出ていて、住民3500人ほどが避難しているという。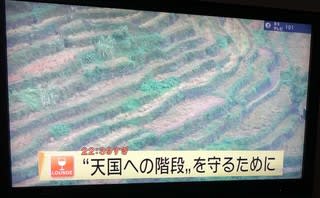 「おはよう日本」でも紹介されていて、知人からは「テレビ見たよ」とメールをいただいた。
「おはよう日本」でも紹介されていて、知人からは「テレビ見たよ」とメールをいただいた。 温泉にかつてあった「白雲楼ホテル」は戦後、GHQ(連合軍総司令部)のリゾートホテルとして接収され、マッカーサー元帥らアメリカ軍将兵が訪れていた、と。
温泉にかつてあった「白雲楼ホテル」は戦後、GHQ(連合軍総司令部)のリゾートホテルとして接収され、マッカーサー元帥らアメリカ軍将兵が訪れていた、と。