講義科目「マスメディアと現代を読み解く」(全8回、1単位)では「震災とマスメディア」をテーマに2回(6月26日、7月3日)にわたって講義した。その中で記者時代の体験談も語った。津波を体験している。1983年5月26日正午ごろ、秋田沖が震源の日本海中部沖地震が起きた。輪島では震度そのもは3だったが、猛烈な津波がその後に押し寄せた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように向かってくる。当時、新聞記者で輪島支局員だった。輪島港が湾内に大きな渦が出来て、漁船同士が衝突し沈没しかかっている船から乗組員を助け上げているを見て、現場へ走り、1回シャッターを切ってすぐ逃げた。大波が間近に見えていたからである。「あの時、取材で欲を出して数回シャッターを切っていたら、おそらくこの講義はなかったろう」と話すと、学生たちは複雑な顔で聴いていた。
~震災被災地でシャッターチャンスを狙う取材者と被災者目線の違和感~
 2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)では翌日現場に駆け付けた。学生たちを復旧ボランティアに参加させる計画を立てるためだった。このとき、地震対策本部からは「余震が続いているのでボランティアは見合わせてほしい」と告げられた。全半壊の街を歩くと、半壊となっていた家屋が余震で壊れるシーンを撮影しようと身構えるカメラマンたちがいた=写真・上=。とても違和感を感じた。しかし、自身が現役の報道デスクだったら、「チャンスを逃すな」と激励していたに違いない。被災地の感覚と、取材者側の感覚の違いが自身の中で浮かんだ。
2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)では翌日現場に駆け付けた。学生たちを復旧ボランティアに参加させる計画を立てるためだった。このとき、地震対策本部からは「余震が続いているのでボランティアは見合わせてほしい」と告げられた。全半壊の街を歩くと、半壊となっていた家屋が余震で壊れるシーンを撮影しようと身構えるカメラマンたちがいた=写真・上=。とても違和感を感じた。しかし、自身が現役の報道デスクだったら、「チャンスを逃すな」と激励していたに違いない。被災地の感覚と、取材者側の感覚の違いが自身の中で浮かんだ。
同じ年の7月16日、同じ日本海側で新潟県中越沖地震(震度6強)が発生した。被災地を取材に訪れたのは震災から3ヵ月後だった。柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくく、復旧半ばという印象だった=写真・下=。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった。 祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。
祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。
通常のピッカラの生放送は平日およそ9時間だが、災害時の緊急編成は24時間の生放送。柏崎市では75ヵ所、およそ6000人が避難所生活を余儀なくされた。このため、市の災害対策本部にスタッフを常駐させ、被災者が当面最も必要とする避難所や炊き出し時刻、物資の支給先、仮設の風呂の場所、開店店舗の情報などライフライン情報を中心に4人のパーソナリティーが交代で流し続けた。
コミュニティー放送局であるがゆえに「被災者のための情報」に徹することができたといえるかもしれない。インタビューに応じてくれた、パーソナリティーで放送部長の船崎幸子さんは「放送は双方向でより深まった」と当時を振り返った。ピッカラは一方的に行政からの情報を流すのではなく、市民からの声を吸い上げることでより被災者にとって価値のある情報として伝えた。たとえば、水道やガスの復旧が遅れ、夏場だけに洗髪に不自由さを感じた人も多かった。「水を使わないシャンプーはどこに行けばありますか」という被災者からの質問を放送で紹介。すると、リスナーから「どこそこのお店に行けばあります」などの情報が寄せられた。行政から得られない細やかな情報である。
24時間の生放送を41日間。この間、応援スタッフのオファーも他のFM局からあったが、4人のパーソナリティーは交代しなかった。「聞き慣れた声が被災者に安心感を与える」(船崎さん)という理由だった。このため、リスナーから「疲れはないの、大丈夫ですか」とスタッフを気遣うメールが届いたほどだった。
ピッカラの災害放送対応を他のコミュニティー放送が真似ようとしても、おそらく難しいだろう。コミュニティー放送局そのものが被災した場合、放送したくても放送施設が十分確保されないケースもある。そして、災害の発生時、その場所、その状況によって放送する人員が確保されない場合もある。その意味で、発生から1分45秒後に放送ができた「FMピッカラ」は幸運だったともいえる。そして、「情報こそライフライン」に徹して、コミュニティー放送の役割を見事に果たした事例としてピッカラは評価される。
取材の後、柏崎の街を歩きながらなぜ震災の復旧が進まないのかと改めて考えた。中越沖地震の場合、マスメディアを通した耳目が柏崎刈羽原発に集中してしまい、街の復旧や復興の様子が視聴者には見えにくくなっていたのではないだろうか。もちろん行政は全力投球していただろう。しかし、マスメディアの取材の優先度が原発が先になると、行政もそれに引きずられる。原発というシリアスな問題では、街の復興・復旧は盲点となりかねない。柏崎の街を歩きながら考えたことも学生たちに話した。
⇒16日(火)朝・金沢の天気 あめ
 会見で記者が海外で「スマイルシンデレラ」というニックネームで親しまれていていることについて質問すると、渋野選手は「そうやって名付けてもらえるのはうれしかったが、シンデレラは良く言いすぎ」「ゴルフは自分が楽しんでやらないとみんな楽しくないのでそこは心がけている」「世界でも笑顔は共通だと思った」と話していた。ギャラリーとのハイタッチが負担にならないかという質問に対しては、「無視されるより、注目されるほうがずっといい。大会中は、どんどんタッチをしてくれる人が増えていってすごくうれしかった」と笑顔で話していたのが印象的だった。
会見で記者が海外で「スマイルシンデレラ」というニックネームで親しまれていていることについて質問すると、渋野選手は「そうやって名付けてもらえるのはうれしかったが、シンデレラは良く言いすぎ」「ゴルフは自分が楽しんでやらないとみんな楽しくないのでそこは心がけている」「世界でも笑顔は共通だと思った」と話していた。ギャラリーとのハイタッチが負担にならないかという質問に対しては、「無視されるより、注目されるほうがずっといい。大会中は、どんどんタッチをしてくれる人が増えていってすごくうれしかった」と笑顔で話していたのが印象的だった。

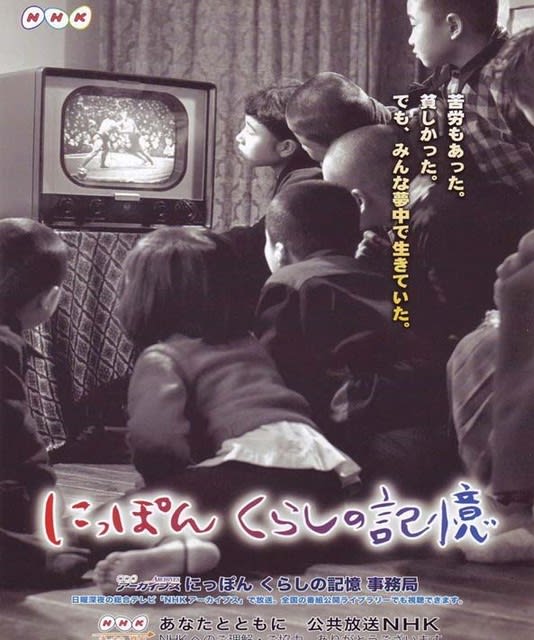
 2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)では翌日現場に駆け付けた。学生たちを復旧ボランティアに参加させる計画を立てるためだった。このとき、地震対策本部からは「余震が続いているのでボランティアは見合わせてほしい」と告げられた。全半壊の街を歩くと、半壊となっていた家屋が余震で壊れるシーンを撮影しようと身構えるカメラマンたちがいた=写真・上=。とても違和感を感じた。しかし、自身が現役の報道デスクだったら、「チャンスを逃すな」と激励していたに違いない。被災地の感覚と、取材者側の感覚の違いが自身の中で浮かんだ。
2007年3月25日の能登半島地震(震度6強)では翌日現場に駆け付けた。学生たちを復旧ボランティアに参加させる計画を立てるためだった。このとき、地震対策本部からは「余震が続いているのでボランティアは見合わせてほしい」と告げられた。全半壊の街を歩くと、半壊となっていた家屋が余震で壊れるシーンを撮影しようと身構えるカメラマンたちがいた=写真・上=。とても違和感を感じた。しかし、自身が現役の報道デスクだったら、「チャンスを逃すな」と激励していたに違いない。被災地の感覚と、取材者側の感覚の違いが自身の中で浮かんだ。
 東日本大震災では報道する側も被災者となり、連絡不能のなかで、スタッフは独自判断で行動することが求められた。仙台空港に駐機していたヘリは津波で機体が損壊して空撮ができず、災害の全体像を把握できなかった。それでもテレビ各社は3日間にわたって緊急特番を報じた。停電や輪転工場の損壊で一時印刷できなくなった石巻日日新聞は6日間にわたって「壁新聞」を発行し続けた。アメリカのニュース博物館「NEWSEUM」はこの壁新聞を展示し、「この新聞は人間の知ることへのニーズとそれに応えるジャーナリストの責務の力強い証しである」と評価している。震災時におけるメディアの宿命を端的に表現した事例だった。
東日本大震災では報道する側も被災者となり、連絡不能のなかで、スタッフは独自判断で行動することが求められた。仙台空港に駐機していたヘリは津波で機体が損壊して空撮ができず、災害の全体像を把握できなかった。それでもテレビ各社は3日間にわたって緊急特番を報じた。停電や輪転工場の損壊で一時印刷できなくなった石巻日日新聞は6日間にわたって「壁新聞」を発行し続けた。アメリカのニュース博物館「NEWSEUM」はこの壁新聞を展示し、「この新聞は人間の知ることへのニーズとそれに応えるジャーナリストの責務の力強い証しである」と評価している。震災時におけるメディアの宿命を端的に表現した事例だった。




