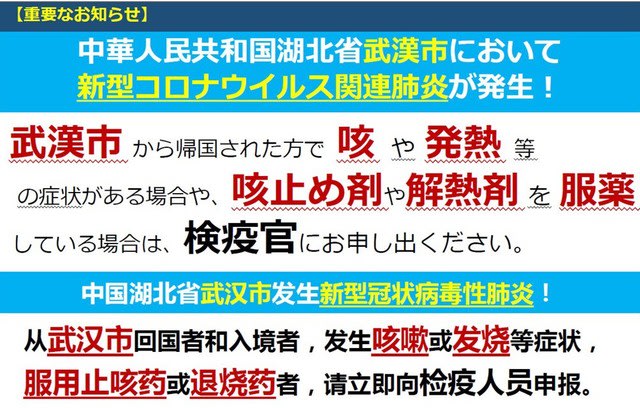☆「Say it?」のトランプ会見から読めること
健康不安説が浮上している北朝鮮の金正恩党委員長の状態について、アメリカのトランプ大統領が記者会見(27日)で「大体分かっている」と述べたと報じられた(28日付・共同通信Web 版)。記者会見の中身を詳しく知りたいと思い、ホワイトハウスの公式ホームページを検索し、27日の会見の内容を読んでみる。(※写真はホワイトハウスのツイッターから)
版)。記者会見の中身を詳しく知りたいと思い、ホワイトハウスの公式ホームページを検索し、27日の会見の内容を読んでみる。(※写真はホワイトハウスのツイッターから)
会見は55分間。前半は新型コロナウイルスに関する経済対策などのブリーフィング、後半は記者からの質問で、金正恩氏の健康状態に関しては最後の方に出てくる。以下、気になった箇所をピックアップする。
Q Do you have any update on Kim Jong Un’s health?
THE PRESIDENT: Say it?
I — I hope he’s fine. I do know how he’s doing, relatively speaking. We will see. You’ll probably be hearing in the not-too-distant future.
All right. One or two more. Go ahead, please.
Q Is he alive? Are — are you confirming he’s alive?
記者からの質問にトランプ氏が発した言葉は「 Say it?」だった。「それを言うか」と。つまり、「この件は質問してほしくなかった」との意味だろう。意味深なのは次の言葉だ。「彼が元気であることを願っている。私は彼の状態をおおむね分かっている。様子を見ましょう。遠くない将来にあなたたちも知ることになるでしょう」と。その後、トランプ氏は「さあ(質問を)さらに一つ二つ続けて」と言うと、記者が「正恩氏は生きているのでしょうか、大統領は彼が生きていることを確認していますか」と食い下がったが、トランプ氏はその質問には一切答えず、次の大統領選についての質問に答えていた。
今月21日付でCNNは金正恩氏が手術を受けて重篤な状態にあるという情報があると伝えた。病名などは特定していない。この報道を受けて、トランプ氏は記者団から尋ねられ、「私に言えるのはこれだけだ。彼の健康を願う」と述べるにとどめていた(22日付・CNNニュースWeb版)。その後も、中国が金氏の容体について助言を行うための医療専門家チームを北朝鮮に派遣したと報じられた(25日付・ロイター通信Web版)。
「Say it?」の記者会見の文脈やニュースの流れを読めば、「次なるニュース」は想像に難くない。
⇒28日(火)朝・金沢の天気 くもり



 で27日以降の予約受付を停止する。大型連休に営業すると、客が来るので人の流れをつくってしまう。これは人の流れを最小化する政府方針に逆行することにもなり、感染防止に協力するかたちで予約をストップする。加賀屋は「もてなし」の質の高さに定評があり、「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(主催・旅行新聞新社)で36年連続総合1位に輝いている。
で27日以降の予約受付を停止する。大型連休に営業すると、客が来るので人の流れをつくってしまう。これは人の流れを最小化する政府方針に逆行することにもなり、感染防止に協力するかたちで予約をストップする。加賀屋は「もてなし」の質の高さに定評があり、「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」(主催・旅行新聞新社)で36年連続総合1位に輝いている。 イギリスのBBCニュースW
イギリスのBBCニュースW