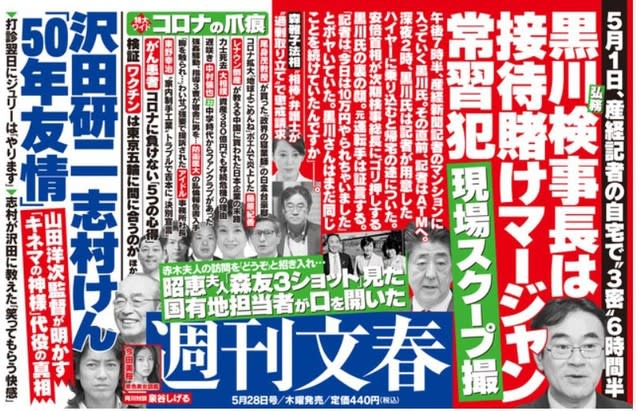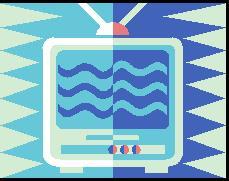★先鋭化する米中「ハイテク」戦
ウィズコロナの時代とともに世界は不穏な曲がり角に転換したのではないだろうか。それ象徴するのがアメリカと中国の対立の先鋭化だ。すでにニュースが飛び交っている。
アメリカ政府はアリババやバイドゥなど中国企業をアメリカ株式市場から締め出す可能性のある法案を検討している。法案は企業の監査をアメリカの公開会社会計監督委員会(PCAOB)が検証することを求めている。法案の意図は、中国企業にアメリカの会計規則を順守させることだが、中国側はこれを一貫して拒否していて、中国企業の上場廃止につながる可能性がある。法案は5月に上院を全会一致で通過し、今は下院が審議している。中国企業の排除にはナスダックなどは反対している(7月10日付・Bloomberg日本語Web版からの引用)。
 アメリカで上場する中国企業は250社と多い。アメリカは中国企業の監査に携わる中国本土の監査法人への立ち入り調査などを要求し続けてきたが、中国は立入調査は中国当局の監督下で行うとの立場を貫いている。が、ナスダック上場のラッキン・コーヒーの不正会計がことし4月に明らかとなったこともあり、アメリカ側は中国企業の経営に懸念を募らせている。これは憶測だが、中国企業がアメリカ市場に上場することで、中国のドル調達のプールになっているのではないか。だから、中国政府はPCAOBに立入検査をさせないのではないかと見るのが自然だ。
アメリカで上場する中国企業は250社と多い。アメリカは中国企業の監査に携わる中国本土の監査法人への立ち入り調査などを要求し続けてきたが、中国は立入調査は中国当局の監督下で行うとの立場を貫いている。が、ナスダック上場のラッキン・コーヒーの不正会計がことし4月に明らかとなったこともあり、アメリカ側は中国企業の経営に懸念を募らせている。これは憶測だが、中国企業がアメリカ市場に上場することで、中国のドル調達のプールになっているのではないか。だから、中国政府はPCAOBに立入検査をさせないのではないかと見るのが自然だ。
アメリカ政府はファーウェイなど中国のハイテク企業5社の製品を使用する企業との取り引きを禁じる法律をことし8月施行する(7月17日付・NHKニュースWeb版)。中国製品の締め出しを世界各国に広げるアメリカ側の意図を受け、イギリスも5G移動通信システムからファーウェイ製品を排除する方針を明らかにしている。
ファーウェイは5Gの技術やコスト競争では代表的な企業の一つ。特許の出願件数も多く、国連の専門機関、WIPO(世界知的所有権機関)を通じた国際特許を出願した件数でも、企業別でファーウェイが世界1位となっている(2017年の国際特許登録の出願数、WIPOプレスリリース)。2018年12月にカナダのバンクーバー国際空港で、ファーウェイCEOの娘の副会長が、アメリカの要請でカナダ捜査当局に逮捕された。この事件で、アメリカがファーウェイの5Gに安全保障の上で懸念があり、締め出しに動いていることが世界に拡散した。
先鋭化する一方の米中対立には背景がある。2017年6月に施行された中国の「国家情報法」だ。法律では、11項目にわたる安全(政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核)を守るために、「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があればファーウェイCEOはハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。
中国の「国家情報法」に遅れて、アメリカは2018年8月に「国防権限法」を発効させた。上記で述べた、中国5社から政府機関が製品を調達するのを2019年8月から禁止、ことし8月から5社の製品を使う各国企業との取引も打ち切るなど徹底する。この動きがさらに先鋭化するとこの先どうなるのか。ここまで来ると、トランプ流のディール(取引)は通用しないだろう。勝つか負けるかの「ハイテク」戦ではないか。
⇒22日(水)朝・金沢の天気 くもり