★グランド・カバーの攻防 相手の巧みな戦術
それにしてもこの雑草は恐ろしいほどに手ごわい。向き合って戦いを挑んでも、必ず復活してくる。しかも、復活するとさらに茎を張りめぐらし、勢力を拡大しているのだ。これまでグランド・カバーの戦い(庭の雑草取り)で、いくつかの雑草と勝 負してきたが、レベルが格段に高い相手だ。その雑草の名はチドメグサ。漢字では「血止め草」と書き、学名は「Hydrocotyle sibthorpioides」。
負してきたが、レベルが格段に高い相手だ。その雑草の名はチドメグサ。漢字では「血止め草」と書き、学名は「Hydrocotyle sibthorpioides」。
チドメグサは実に巧妙に戦いを仕掛けてくる。その特徴は「隠れ蓑」戦術だろう。細い茎はよく枝分かれし、節から根を出して地面をはうのだが、芝生の生息地に入り込み、目立たないように勢力を拡大している。先日、「堂々と勝負しろ」と戦いを挑んだ。まず芝刈り機で芝生を刈り込み、隠れていた相手をリングに引きずり出した。
ところが、葉や茎は取れたが、芝生の根にチドメグサの根が絡まって離れようとしない。一本一本外すとなると膨大な労力と時間がかかる。「オレに勝ちたいのならば、芝生の根を絶やしてみろ」と不敵な笑みを浮かべているのだ。この日の戦いは午後7時を回り、時間切れでドローとなった。悔し涙がポロリと落ちた。
チドメグサとの戦いの第二幕は、スギゴケの庭での勝負となった。芝生ゾーンとは違って、スギゴケを刈り込むわけにはいかない。それだけに、相手の姿が見えにくい。葉と茎を1本取ったかと思ったら、隠れるように別の葉と茎がある。まるで分身があちこちにあり、根っ子がある本体が見つからない。これは忍法「空蝉(うつせみ)の術」だ。自分の分身を周囲につくり、敵の注意を分身に向けているのだ。根っ子がある本体はどこか。スギゴケをかき分けかき分け、チドメグサの根を探し出し、手繰り寄せるようにして抜く。こちらも誤って、大切にしているスギゴケを抜くこともある。
実に根気のいる勝負になると予測し、日曜日の午後に試合に挑んだ。ただ、気温がぐんぐんと上がり、水分補給も限界、熱中症が心配になり途中で退場した。すると、相手のせせら笑いが背後から聞こえた。「しょせん人間は弱い、オレたちに勝てるはずがない」と。闘争心がめらめらと燃えてきた。
⇒16日(月・海の日)夜・金沢の天気 はれ
 らも心がすっきりとするのだ。
らも心がすっきりとするのだ。
 6月13日、金沢市に本社がある、地元民放テレビ局のMRO北陸放送の取材を受けた。テーマはズバリ、ブログだ。ブログを作成するノウハウや楽しみ方、注意点などについてインタビューがあった。なぜ私にというと、実は私のかつての同業のM氏は現在MROの報道制作担当の現場のトップ。取材の数日前、彼から「宇野さんのブログ(「自在コラム」)をたまに読ませてもらっている。ぜひインタビューさせて」と電話で取材の依頼があった。インタビューというからにはインタビューに耐えるだけのレベルのブロガーであると評価してくれた証左でもあると勝手に解釈し、「OKですよ」とその場で返事をした。
6月13日、金沢市に本社がある、地元民放テレビ局のMRO北陸放送の取材を受けた。テーマはズバリ、ブログだ。ブログを作成するノウハウや楽しみ方、注意点などについてインタビューがあった。なぜ私にというと、実は私のかつての同業のM氏は現在MROの報道制作担当の現場のトップ。取材の数日前、彼から「宇野さんのブログ(「自在コラム」)をたまに読ませてもらっている。ぜひインタビューさせて」と電話で取材の依頼があった。インタビューというからにはインタビューに耐えるだけのレベルのブロガーであると評価してくれた証左でもあると勝手に解釈し、「OKですよ」とその場で返事をした。 テーマ「自ら検証し、実感する」
テーマ「自ら検証し、実感する」  た光ネットワークインフラ、そして携帯電話事業、これらをひとまとめにして定額でいくら、といったビジネス展開だ。
た光ネットワークインフラ、そして携帯電話事業、これらをひとまとめにして定額でいくら、といったビジネス展開だ。 マ「季節の変わり目を撮る」
マ「季節の変わり目を撮る」 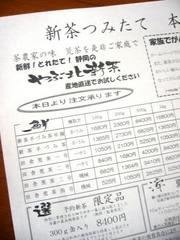
 視界」
視界」 マ「定点撮影のすすめ」
マ「定点撮影のすすめ」  あるいは別の見方で、軒下に迫る雪の量を見て、年間降水量のことを連想するかもしれない。北陸は年間降水量が2000㍉を超えていつも全国上位だ。こうした説明にもこの写真は説得力を持つ。
あるいは別の見方で、軒下に迫る雪の量を見て、年間降水量のことを連想するかもしれない。北陸は年間降水量が2000㍉を超えていつも全国上位だ。こうした説明にもこの写真は説得力を持つ。 
 実際に写真グラフを作ってみる。タイトルは<街角ショット3題>としよう。まずはことしのエトにちなんで。一番上の写真は、04年夏に神戸市内のオモチャ店で撮影したもの。イヌのオモチャが入った箱に「飼主募集中、エサは単3電池2本です」のキャッチコピーが面白い。気の利いたキャッチコピーが付いているとそれ自体が完結して、写真そのものが一枚の広告ポスターのようだ。
実際に写真グラフを作ってみる。タイトルは<街角ショット3題>としよう。まずはことしのエトにちなんで。一番上の写真は、04年夏に神戸市内のオモチャ店で撮影したもの。イヌのオモチャが入った箱に「飼主募集中、エサは単3電池2本です」のキャッチコピーが面白い。気の利いたキャッチコピーが付いているとそれ自体が完結して、写真そのものが一枚の広告ポスターのようだ。 真ん中は、先日12月31日に東京のJR浜松町駅で撮った企業広告のスナップ写真。ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手とニックネームでもあるゴジラと並べてデザインされた東芝のデジタル対応テレビのPRポスターだ。このポスターはどこにでもあるわけではない。JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。
真ん中は、先日12月31日に東京のJR浜松町駅で撮った企業広告のスナップ写真。ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手とニックネームでもあるゴジラと並べてデザインされた東芝のデジタル対応テレビのPRポスターだ。このポスターはどこにでもあるわけではない。JR浜松町駅近くに東芝の本社があり、ここでしか見れない、いわば「ご当地ポスター」のようなもの。

