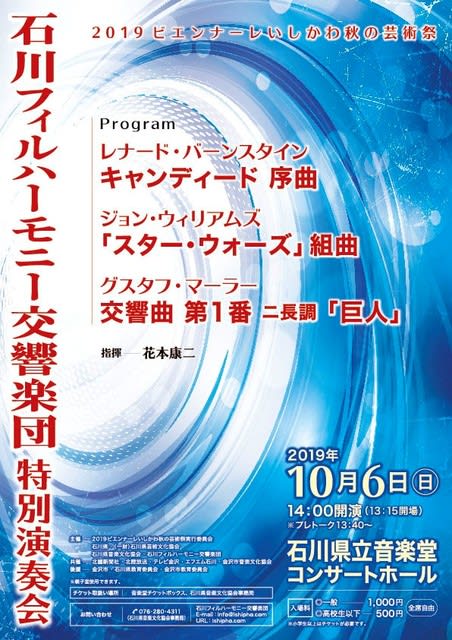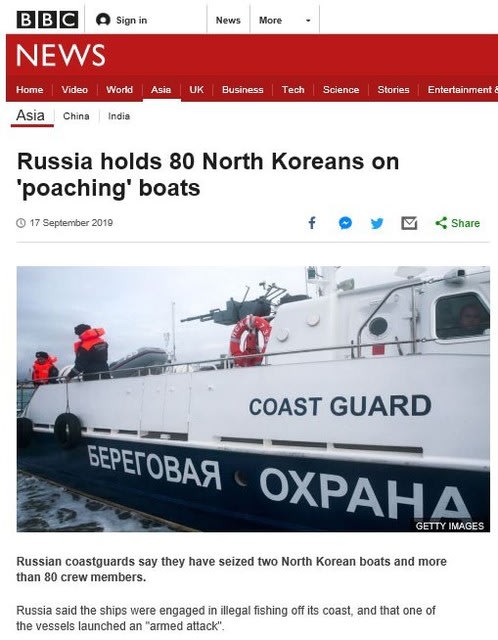★祝意と違和感と
191の国と国際機関から代表が参列し、天皇陛下の中心的な儀式である「即位礼正殿の儀」が滞りなく執り行われた。国民を代表して安倍総理が「寿詞(よごと)」という祝辞を読み上げた。テレビで即位礼正殿の儀を視聴したのは人生で二度目だ。今回も古式にのっとり行われ、タイムスリップした感覚で見ていた。
 正直、違和感があったのは安倍総理の「天皇陛下万歳」の三唱だった。ほかに言い方はなかったのだろうかと思った。というのも、私は小さいころ亡き父から聞いていた話は、戦時中、仏領インドシナ(ベトナム)の戦線でフランス軍と戦うとき、兵士たちは「天皇陛下万歳」と叫びながら突進していった、と。父はそれを否定的に言っていたのではなく、今思い起こせば、戦友たちは勇敢に戦ったと表現するために「天皇陛下万歳」という言葉を持ち出して話を聞かせてくれたのだと思う。
正直、違和感があったのは安倍総理の「天皇陛下万歳」の三唱だった。ほかに言い方はなかったのだろうかと思った。というのも、私は小さいころ亡き父から聞いていた話は、戦時中、仏領インドシナ(ベトナム)の戦線でフランス軍と戦うとき、兵士たちは「天皇陛下万歳」と叫びながら突進していった、と。父はそれを否定的に言っていたのではなく、今思い起こせば、戦友たちは勇敢に戦ったと表現するために「天皇陛下万歳」という言葉を持ち出して話を聞かせてくれたのだと思う。
もう少し詳細に父が話してくれたことを述べる。父が所属したのは歩兵第八十三連隊第六中隊。フランス軍との戦闘で、カンボジアとの国境の町、ロクニンに転戦。昭和20年8月15日、敗戦の報をこの地で聞くことになる。終戦処理の占領軍はイギリスが任に当たり、父の部隊はサイゴンで捕虜となる。このころから部隊を逃亡する兵士が続出。その数は600人とも言われている。多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する元日本兵たちもいた。父はゲリラ組織には加わらなかったが、ベトナム解放戦線に加わりその後再び捕虜となった元同僚の兵士から聞いた話として、はやりフランス軍に突進するときには「天皇陛下万歳」と声を上げていた、と。
当時日本軍兵士は死を覚悟で敵に対峙するときに、このフレーズを使ったのだろう。戦場の叫びだ。安倍総理はこうした事実を理解しているのだろうか。私は戦争体験者である父から聴いて知っていたので違和感が残った。ご存命の元兵士の方々は今回の万歳三唱を視聴してどのような思いだっただろうか。
⇒23日(水)夜・金沢の天気 くもり



 中止となり、試合はドロー(引き分け)扱いとなると報じられている。確かにこの2会場は19号の直撃コースだ。
中止となり、試合はドロー(引き分け)扱いとなると報じられている。確かにこの2会場は19号の直撃コースだ。