★キャンデーの警告
4月2日午後、能登半島に出張した。市役所など5ヵ所を車で回り、昼食は14時を回っていた。この日の16時30分から金沢で打ち合わせがあるので、ファミリーレストランに駆け込んで、「海鮮スープスパゲティ」を注文した。「大盛りはできますか」と店員に尋ねると、「スパゲティはできません」と言う。きょうのテーマの伏線はおそらくここから始まる。
 海鮮スープスパゲティは具沢山でそれはそれで満足感はあった。が、早食いのせいで、「ひもじさ」が少々残った。レジで代金を払い、ふとレジの周りを見ると「特濃黒ごまミルク」という文字が目に飛び込んできた。「これください」と言ってしまった。黒ゴマは好きな食材で、「黒ゴマ入りのミルクキャラメル」と勝手に解釈して手にとってしまった。126円だった。1粒が17kcal、黒ゴマが入るとカロリーは高いと思いながら口に入れ、再び車に乗リ込んだ。軟らかなキャラメルを期待したのだが、キャンデーだった。口に含んだらゆっくりとは出来ない性分で、すぐ噛んでしまう。ガリガリと。農厚な味だが甘くはない。さらに2粒目を口に入れ、ガリガリと。事件はここで起きた。
海鮮スープスパゲティは具沢山でそれはそれで満足感はあった。が、早食いのせいで、「ひもじさ」が少々残った。レジで代金を払い、ふとレジの周りを見ると「特濃黒ごまミルク」という文字が目に飛び込んできた。「これください」と言ってしまった。黒ゴマは好きな食材で、「黒ゴマ入りのミルクキャラメル」と勝手に解釈して手にとってしまった。126円だった。1粒が17kcal、黒ゴマが入るとカロリーは高いと思いながら口に入れ、再び車に乗リ込んだ。軟らかなキャラメルを期待したのだが、キャンデーだった。口に含んだらゆっくりとは出来ない性分で、すぐ噛んでしまう。ガリガリと。農厚な味だが甘くはない。さらに2粒目を口に入れ、ガリガリと。事件はここで起きた。
嫌な予感と同時に口の中に違和感が走った。舌に「重い」ものが転がってきたのである。瞬間、「またやってしまった」と後悔の念がこみ上げ、思わず特濃黒ごまミルクのパッケージを左手で握りしめた。右下あごの奥歯に被せてあった金属がポロリと取れたのだ。ガリガリと噛むと、歯に大きなバイアスがかかり、とくに硬いキャンデーの場合は一点にその力が集中するので、角度が悪いと歯が欠けたり、被せた金属が取れると歯医者から言い聞かされていた。実は10年ほど前にも同じ経験をしていたのだ。後悔は、2度同じ過ちを繰り返した不注意さと、ひもじさに勝てない理性に対してである。と同時に、歯科治療の現場で起きるであろう苦痛のドラマを想像すると身の毛がよだった。
翌日3日、職場の近くの歯科医に予約を入れた。夕方、出かけた。歯のレントゲン撮影から始まった。モニター画面に映し出されたX線写真を指し示しながら、歯科医は「金属を支えていた心棒が途中で折れていますね。これを抜き取るのは少々面倒かもしれませんが…」と続けて、「それにしても歯周病が随分と進んでいますよ。このまま放っておいたら、あと2年ぐらいで歯がガタガタになるかもしれませんね」「まず、歯石を徹底的に取り除きましょう」と。これは心外な言葉だった。
6年ほど前から歯周病には気を使っていて、朝晩の歯磨き。それに歯間ブラシも欠かさなかった。そして仕上げは洗口液「リステリン」だ。磨き残しの歯垢に細菌がいても、リステリンの殺菌効果で除去できる。それ以来、朝起きたときの口内の粘りもなく、歯周病対策は完璧だと確信していた。だから、「歯周病が進んでいる」という医者の言葉は意外だったのだ。しかし、現実に写真で説明を受けると、歯石が付着し、歯肉で見えない歯の部分は確かに以前よりやせ細っていいる。歯だと思っていたのは歯石だった。歯周病が進行中と分かり愕然とした。よく考えれば、歯磨きは手抜きだったかもしれない。リステリンで殺菌していると思っていたが、口でゆすぐのはせいぜいが10秒程度でその効果は薄かったのかもしれない。つまり、その効果を過信していただけだったのだ。
目隠しをされ、下あごの歯石の除去作業が始まった。「痛みを感じたら左手を挙げて」と歯科衛生士の女性が丁寧に言ってくれたが、正直痛く、涙がにじんだ。目隠しはその涙を隠すのにちょうどよいと思った。それにしてもキューンという機械音は神経的な苦痛を倍加させる。除去が始まる前、歯科衛生士に「手掘りにしていただけませんか」と申し出たのだが、「それだと歯に負荷がかかるので、超音波の方がよいと思いますよ」と説得された。
レントゲン撮影と歯石除去、抜けた歯の部分の「型どり」までざっと90分。悔恨と苦痛、そして再生への希望とストーリーはめまぐるしく展開した。治療イスで時折、口をゆすぎながら思った。ひょっとして、あの時、特濃黒ごまミルクのキャンデーを食べなかったら、歯科クリニックには来なかった。クリニックに来なければ、歯周病が密かに進行していることに気づくこともなかった。気づかなければ、2年後には入れ歯をする運命になるかもしれない。そうか、これは「キャンデーの警告」だったのだ。
ちなみに、通院を始めた歯科医院は「オードリー歯科(Audrey Dental Office)」。通勤バスの通り道にあり、その医院名が以前から気になっていた。最後にその日の治療費を払って、思い切って受付の女性に尋ねてみた。「オードリーという名は、院長先生がオードリー・ヘップバーンのファンなのですか」と。すると女性は「その質問はたまにあるのですが、大通りに面しているのでオードリーと名付けたようですよ。お大事に」と手短に。歯科医院を出ると、辺りはすでに暗く、18時47分だった。
⇒4日(金)朝・金沢の天気 くもり

 ろう。その玉虫厨子を現代に蘇らせるプロジェクトが完成し、その制作過程を追ったドキュメンタリー映画が輪島市と金沢市で上映されることになった(3月16日付・北陸中日新聞)。
ろう。その玉虫厨子を現代に蘇らせるプロジェクトが完成し、その制作過程を追ったドキュメンタリー映画が輪島市と金沢市で上映されることになった(3月16日付・北陸中日新聞)。  昔からカニを食べると寡黙になる、というのが常識だが、この日は様子が違った。同席したのは宮崎、福岡、大阪、奈良、東京、仙台と出身はバラバラ。すると、食べ方が慣れないせいか、「カニは好きだが食べにくい」「身をほじり出すのがチマチマしている」などという話になる。出されたカニには包丁が入っていて、すでに食べやすくしてある。これを「食べにくい」といってはバチが当たるというものだ。つまり、カニの初心者なのだ。
昔からカニを食べると寡黙になる、というのが常識だが、この日は様子が違った。同席したのは宮崎、福岡、大阪、奈良、東京、仙台と出身はバラバラ。すると、食べ方が慣れないせいか、「カニは好きだが食べにくい」「身をほじり出すのがチマチマしている」などという話になる。出されたカニには包丁が入っていて、すでに食べやすくしてある。これを「食べにくい」といってはバチが当たるというものだ。つまり、カニの初心者なのだ。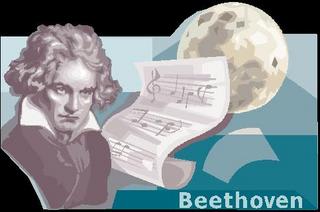 最近、岩城さんが指揮したベートーベンの交響曲3番「エロイカ(英雄)」を聴いている。2005年12月31日にベートーベンの1番から9番までを演奏したチクルス(連続演奏)をCS放送「スカイ・A」が生放送したものを私的録音で時折、視聴している。番組の合間に岩城さんが曲を解説するコーナーがある。「ベートーベンはナポレオンの革命的行為を礼賛して、この曲をつくった。しかし、ナポレオンが皇帝になって、いやけがさして曲名を差し替えた」のがエロイカだと。当初の曲名は「ボナバルト」だったといわれる。
最近、岩城さんが指揮したベートーベンの交響曲3番「エロイカ(英雄)」を聴いている。2005年12月31日にベートーベンの1番から9番までを演奏したチクルス(連続演奏)をCS放送「スカイ・A」が生放送したものを私的録音で時折、視聴している。番組の合間に岩城さんが曲を解説するコーナーがある。「ベートーベンはナポレオンの革命的行為を礼賛して、この曲をつくった。しかし、ナポレオンが皇帝になって、いやけがさして曲名を差し替えた」のがエロイカだと。当初の曲名は「ボナバルト」だったといわれる。 S教授はインド哲学が専門で、自ら僧籍にもあった。酒を飲み、タバコも手放さなかった。急逝する前夜も知人と楽しく酒を飲んでいた、という。遺族の話では「人間ドックにひっかかるものは何もなかった」。社会貢献室の室長であり、大学教育開放センター長という学外に開かれたセクションの現場責任者だった。センター長室の机には花が飾られ、「未決」の決済箱には本人が印を押はずだった書類がたまっていた。
S教授はインド哲学が専門で、自ら僧籍にもあった。酒を飲み、タバコも手放さなかった。急逝する前夜も知人と楽しく酒を飲んでいた、という。遺族の話では「人間ドックにひっかかるものは何もなかった」。社会貢献室の室長であり、大学教育開放センター長という学外に開かれたセクションの現場責任者だった。センター長室の机には花が飾られ、「未決」の決済箱には本人が印を押はずだった書類がたまっていた。 能登で生まれ、金沢で高校時代を過ごした。2年生の冬、クラブはESSに所属していて、県英語弁論大会に出場する幸運に恵まれた。高校は同大会で4連勝を果たしていて、5度目の栄誉がかかっていた。このため、前年度優勝者の先輩からイントネーションや発音の厳しいチェックを受けたことを覚えている。また、当時貴重だったテープレコーダーをESSの仲間から借りて、下宿で練習したものだ。
能登で生まれ、金沢で高校時代を過ごした。2年生の冬、クラブはESSに所属していて、県英語弁論大会に出場する幸運に恵まれた。高校は同大会で4連勝を果たしていて、5度目の栄誉がかかっていた。このため、前年度優勝者の先輩からイントネーションや発音の厳しいチェックを受けたことを覚えている。また、当時貴重だったテープレコーダーをESSの仲間から借りて、下宿で練習したものだ。 被災者だから、本当に何が必要なのかよく理解できる。その経験を生かし、新潟県中越地震(2004年10月)では被災地で支援活動をした経験を持つ。2週間余り、炊き出しやがれきの後片付けをした。前回のブログ(4月10日付)で紹介した「猿回し慰問ボランティア計画」は、避難所生活のお年寄りはストレスや疲労がたまりやすく、エコノミークラス症候群などにかかりやすいので、「何とか、外に出て歩いてもらうきっかけを」とアイデアを出し合ってひらめいたのが猿回し公演だ。細やかなことにまで気が回るのも、被災地で支援活動をした経験を持つからこそだ。
被災者だから、本当に何が必要なのかよく理解できる。その経験を生かし、新潟県中越地震(2004年10月)では被災地で支援活動をした経験を持つ。2週間余り、炊き出しやがれきの後片付けをした。前回のブログ(4月10日付)で紹介した「猿回し慰問ボランティア計画」は、避難所生活のお年寄りはストレスや疲労がたまりやすく、エコノミークラス症候群などにかかりやすいので、「何とか、外に出て歩いてもらうきっかけを」とアイデアを出し合ってひらめいたのが猿回し公演だ。細やかなことにまで気が回るのも、被災地で支援活動をした経験を持つからこそだ。 ーブルのひ孫だ。が、この作品を実際に見た人はブログの写真と実物はちょっと違うと言うだろう。そう、男が胴から腰にかけて白い布をまとっている。この写真を撮影した2004年9月、台風16号と18号が立て続けにやってきた。何しろ屋上に設置されているので台風で倒れるかもしれないと、まず布を胴体に巻いて、その上にワイヤーを巻いて左右で固定したものだ。
ーブルのひ孫だ。が、この作品を実際に見た人はブログの写真と実物はちょっと違うと言うだろう。そう、男が胴から腰にかけて白い布をまとっている。この写真を撮影した2004年9月、台風16号と18号が立て続けにやってきた。何しろ屋上に設置されているので台風で倒れるかもしれないと、まず布を胴体に巻いて、その上にワイヤーを巻いて左右で固定したものだ。 ことしの総合トップは52.7%で「サッカー・2006FIFAワールドカップ 日本VSクロアチア」(6月18日・テレビ朝日)だった。試合はドローだったが、175分の緊張感はこのゼロの試合展開で保たれ、高視聴率に結びついた。以下8位まで「ワールド・ベースボール・クラシック」「ボクシング・亀田兄弟ダブルメイン」「トリノオリンピック」と続く。9位にようやくドラマ「HERO」31.8%(7月3日・フジテレビ)がランキングされてくる。そして、10位で「ボクシング・世界ライトフライ級 亀田興毅VSファン・ランダエタ」となる。つまり、年間の高視聴率10番組のうち、9つもスポーツものがランキングされた。
ことしの総合トップは52.7%で「サッカー・2006FIFAワールドカップ 日本VSクロアチア」(6月18日・テレビ朝日)だった。試合はドローだったが、175分の緊張感はこのゼロの試合展開で保たれ、高視聴率に結びついた。以下8位まで「ワールド・ベースボール・クラシック」「ボクシング・亀田兄弟ダブルメイン」「トリノオリンピック」と続く。9位にようやくドラマ「HERO」31.8%(7月3日・フジテレビ)がランキングされてくる。そして、10位で「ボクシング・世界ライトフライ級 亀田興毅VSファン・ランダエタ」となる。つまり、年間の高視聴率10番組のうち、9つもスポーツものがランキングされた。