☆加賀の酔い-下
「酒蔵の科学者」農口杜氏が小松の里山で現場復帰「世界に通用する酒を」
 酒蔵と別棟の杜氏と蔵人(くらんど)の詰め所に案内された。朝の作業が終わり休憩中だった。「よう来てくださった」。張りのある声だった。昭和7年(1932)12月生まれ、85歳だ。杜氏室に案内され、開口一番に「世界に通じる酒を造りたいと、この歳になって頑張っておるんです」と。いきなりカウンターパンチを食らった気がした。グローバルに通じる日本酒をつくる、と。そこで「世界に通じる日本酒とはどんな酒ですか」と突っ込んだ。「のど越し。のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。整然とした言葉運びに圧倒された。
酒蔵と別棟の杜氏と蔵人(くらんど)の詰め所に案内された。朝の作業が終わり休憩中だった。「よう来てくださった」。張りのある声だった。昭和7年(1932)12月生まれ、85歳だ。杜氏室に案内され、開口一番に「世界に通じる酒を造りたいと、この歳になって頑張っておるんです」と。いきなりカウンターパンチを食らった気がした。グローバルに通じる日本酒をつくる、と。そこで「世界に通じる日本酒とはどんな酒ですか」と突っ込んだ。「のど越し。のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」。整然とした言葉運びに圧倒された。
農口氏と最後に会ったのは2015年7月。地元紙で能登杜氏の「四天王」が引退すると大きく扱われていて、能登町のご自宅にお邪魔した。当時82歳で「そろそろ潮時」と普通の高齢者の落ち着いた話しぶりだった。その当時に比べ、きょうは身のこなしの軽やかさ、声のテンションも高い。そこで「なぜ現役復帰の決意を」と尋ねた。「家にいても頭にぽっかりと穴が開いたような状態だった。 この歳になると片足を棺桶に突っ込んでいるようなものだから、どうせなら酒蔵に戻ろうと。弥助寿司の森田さんも、陶芸の吉田さん(美統、人間国宝)も同じ歳、皆現役で頑張っておられるからね」。酒造り2季のブランクを経て、建物の設計などにかかわり、満を持して昨年暮れに酒造りの現場に復帰した。
この歳になると片足を棺桶に突っ込んでいるようなものだから、どうせなら酒蔵に戻ろうと。弥助寿司の森田さんも、陶芸の吉田さん(美統、人間国宝)も同じ歳、皆現役で頑張っておられるからね」。酒造り2季のブランクを経て、建物の設計などにかかわり、満を持して昨年暮れに酒造りの現場に復帰した。
農口氏と初めて会ったのは2009年。金沢大学の共通教育科目「いしかわ新情報書府学」という地域学の講義の非常勤講師として、ひとコマ(90分)能登杜氏の酒造りをテーマに、3年連続で講義をいただいた。必ず自身の日本酒を持参され、講義の終わりには学生にテイスティングしてもらって、学生たちの感想に耳を傾けていた。農口氏自身はまったくの下戸(げこ)で飲めない。その分、飲む人の話をよく聴く。日本酒通だけでなく、女性や学生からの客観的な評価にも率直に耳を傾けるプロとの印象を持っている。
もう一つ、農口氏の酒造りの特徴、それは客観的なデータづくりだ。1970年代中ごろからいい酒をコンスタントにつくるには数字になるものはすべて記録しなければならないと考え、酒米の種類、精米歩合、麹の品温、酒米を浸水させた時間、水温などのデータを毎日、几帳面にノートに記している。実験と検証を繰り返す「酒蔵の科学者」の雰囲気がある。「農口尚彦研究所」という会社名もそこが由来だ。分析室に酵母の培養装置があり、麹は色別センターで温度管理しているというから本格的な研究所だ。
もちろん独りで立ち上げたのではなく、小松の財界人や行政が手厚く支援し、ディレクターとして陶芸家の大樋長左衛門氏らが関わり、知恵とチカラが結集されている。また、地域の人たちの理解を得るため、地元の農家の人たちに酒米「五百万石」を栽培してもらい昨秋は300俵購入した。若手を育てるため全国から蔵人を公募すると20人が応募、8人を採用した。営業基盤を固めてグローバル展開するため、大手酒造メーカーのOBを役員に迎えた。
初年度は1升瓶(1.8㍑)で8万本の出荷を予定し、昨年12月26日に本醸造無濾過生原酒を初めて発売した。アルコール度数19度。帰りがけに、生原酒を手渡された。「(生原酒は)生きていますから、瓶を振らんとおいてください。なるべく寒いところに置いてくださいよ」と。農口氏の人生の決意の1本、ありがたくいただいた。その後、今夜の宿泊先の片山津温泉に車を走らせた。暖房を切って、瓶を揺らさないようにゆっくり運転で。(写真・上は酒蔵のイメージを脱した農口尚彦研究所の外観=小松市観音下町、写真・下は酵母の培養を確かめる農口杜氏)
⇒6日(土)夜・加賀市の天気 くもり
 旅館の従業員に法師(ほうし)という名前の由来を尋ねると、「それはですね」とちょっと身を乗り出すようにして説明してくれた。加賀地方で霊峰と呼ばれる白山(はくさん)は泰澄大師が荒行を積んだことでも知られる。その泰澄にインスピレーションが働いて粟津の地で村人といっしょに温泉を掘り当てた。そこで、弟子の一人の雅亮法師(がりょうほうし)に命じて湯守りをさせた。それが旅館の始まり、とか。一時期、もっとも古い温泉旅館としてギネスブックにも登録されたこともあるそうだ。
旅館の従業員に法師(ほうし)という名前の由来を尋ねると、「それはですね」とちょっと身を乗り出すようにして説明してくれた。加賀地方で霊峰と呼ばれる白山(はくさん)は泰澄大師が荒行を積んだことでも知られる。その泰澄にインスピレーションが働いて粟津の地で村人といっしょに温泉を掘り当てた。そこで、弟子の一人の雅亮法師(がりょうほうし)に命じて湯守りをさせた。それが旅館の始まり、とか。一時期、もっとも古い温泉旅館としてギネスブックにも登録されたこともあるそうだ。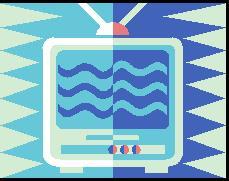 判決の内容をよく読むと、NHKが契約を求める裁判を起こし、勝訴すれば、契約が成立し、テレビを設置した時点からの受信料を支払わなければならない。つまり、最高裁が出した答えは「義務」と同じだ。納得いかないのは、その義務を親から仕送りをもらって学んでいる学生たちにも課しているという点なのだ。
判決の内容をよく読むと、NHKが契約を求める裁判を起こし、勝訴すれば、契約が成立し、テレビを設置した時点からの受信料を支払わなければならない。つまり、最高裁が出した答えは「義務」と同じだ。納得いかないのは、その義務を親から仕送りをもらって学んでいる学生たちにも課しているという点なのだ。 今月12月に新書『実装的ブログ論―日常的価値観を言語化する』(幻冬舎ルネッサンス新書)を出版した。実は、この本を出版した動機の一つとして、若者たちにブログを書いてほしいという思いがあったからだ。
今月12月に新書『実装的ブログ論―日常的価値観を言語化する』(幻冬舎ルネッサンス新書)を出版した。実は、この本を出版した動機の一つとして、若者たちにブログを書いてほしいという思いがあったからだ。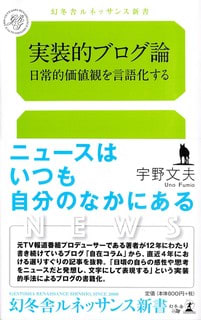 ブログを書く作業は、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのSNSと違って実に孤独だ。ただ、誰にも気兼ねせず、邪魔されずに自分の価値観を言語として実装するには最高の場でもあると実感している。では、ブログ自体の価値はどこにあるのだろうか。ブログ、つまりウェブログ(ウェブ上の記録)は書き溜めである。日々使うことができるブログに一体何を書き溜めるのか。
ブログを書く作業は、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのSNSと違って実に孤独だ。ただ、誰にも気兼ねせず、邪魔されずに自分の価値観を言語として実装するには最高の場でもあると実感している。では、ブログ自体の価値はどこにあるのだろうか。ブログ、つまりウェブログ(ウェブ上の記録)は書き溜めである。日々使うことができるブログに一体何を書き溜めるのか。 23日夜、ハノイに到着。24日にハノイから100㌔ほど離れたハナム省モックバック村に向かった。ここに「革命烈士の墓」がある。ベトナムは1954年のディエンビエンフーの戦いでフランスを破り、その後、ベトナム戦争でアメリカを相手に壮絶な戦いを繰り広げた。革命烈士の墓は普段は入口の門の鍵がかかる、まさに聖地なのだ。日本名は分からないが、ベトナム独立のために命を捧げた日本人の墓地があると管理人の女性が案内してくれた。
23日夜、ハノイに到着。24日にハノイから100㌔ほど離れたハナム省モックバック村に向かった。ここに「革命烈士の墓」がある。ベトナムは1954年のディエンビエンフーの戦いでフランスを破り、その後、ベトナム戦争でアメリカを相手に壮絶な戦いを繰り広げた。革命烈士の墓は普段は入口の門の鍵がかかる、まさに聖地なのだ。日本名は分からないが、ベトナム独立のために命を捧げた日本人の墓地があると管理人の女性が案内してくれた。 質問が集中したのは海上保安庁に対してだった。海上保安庁も巡視船で退去警告や放水で違法操業に対応していたのが、イタチごっこの状態だった。漁業関係者からは「退去警告や放水では逆に相手からなめられる(疎んじられる)」と声が上がった。違法操業の漁船に対して、漁船の立ち入り調査をする臨検、あるいは船長ら乗組員の拿捕といった強い排除行動を実施しないと取り締まりの効果が上がらない、と関係者は苛立ちを募らせ、石川県漁協の組合長が強い排除行動を求める要望書を手渡したのだった。
質問が集中したのは海上保安庁に対してだった。海上保安庁も巡視船で退去警告や放水で違法操業に対応していたのが、イタチごっこの状態だった。漁業関係者からは「退去警告や放水では逆に相手からなめられる(疎んじられる)」と声が上がった。違法操業の漁船に対して、漁船の立ち入り調査をする臨検、あるいは船長ら乗組員の拿捕といった強い排除行動を実施しないと取り締まりの効果が上がらない、と関係者は苛立ちを募らせ、石川県漁協の組合長が強い排除行動を求める要望書を手渡したのだった。 ことし3月、元Googleアメリカ本社副社長兼日本法人代表取締役の村上憲郎氏の講演を聴く機会に恵まれた。話の中でショックだったのは、人がこなしてきた仕事が近い将来、AIに取って代わられるかもしれないということだった。そのポイントが言語処理。「推論機構」という、複雑な前提条件からIf、Then、など言葉のルールを駆使して結論を推論するハードウエアの開発だ。村上氏が述べたAIに取って代わられるかもしれない仕事がたとえば、簿記の仕訳や弁護士の業務を補助するパラリーガルだという。
ことし3月、元Googleアメリカ本社副社長兼日本法人代表取締役の村上憲郎氏の講演を聴く機会に恵まれた。話の中でショックだったのは、人がこなしてきた仕事が近い将来、AIに取って代わられるかもしれないということだった。そのポイントが言語処理。「推論機構」という、複雑な前提条件からIf、Then、など言葉のルールを駆使して結論を推論するハードウエアの開発だ。村上氏が述べたAIに取って代わられるかもしれない仕事がたとえば、簿記の仕訳や弁護士の業務を補助するパラリーガルだという。 つい、いっしょに歌いたくなるようなインスピレーションが働く。古代、バビロニア王ナブッコがユダヤの国に攻め込み、捕らえられ、強制労働を強いられるユダヤ人たちが故郷を想って歌う合唱曲なのだ。力強く、したたかに、希望を持って、そしてゆっくりと。
つい、いっしょに歌いたくなるようなインスピレーションが働く。古代、バビロニア王ナブッコがユダヤの国に攻め込み、捕らえられ、強制労働を強いられるユダヤ人たちが故郷を想って歌う合唱曲なのだ。力強く、したたかに、希望を持って、そしてゆっくりと。 朝鮮の木造漁船はさらに転覆軒数が増えるのではないかと不安がよぎる。それはまさに自分の中にあるニュースだ。
朝鮮の木造漁船はさらに転覆軒数が増えるのではないかと不安がよぎる。それはまさに自分の中にあるニュースだ。