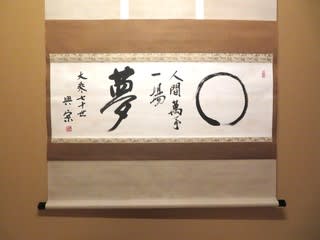☆ドキュメント「平成と私」~下~
新紙幣を2024年度に発行すると過日(9日)の記者会見で麻生財務大臣が発表した。新元号の次は新紙幣だ。1万円、5千円、千円の紙幣(日本銀行券)の全面的な刷新だ。このニュースでは、45兆円もあるとされるタンス預金を吐き出させることにあるのではないかと論評するコメンテーターの言葉が妙に説得力があった。
1万円札の福沢諭吉は交代も、未来も変わらぬ「独立自尊」の品位
 1万円札の人物変更は聖徳太子から福沢諭吉に代わった昭和59年(1984)以来、40年ぶりというから確かにそろそろ交代の時期なのかもしれない。その福沢が19歳まで過ごした大分県中津市の旧居と記念館を訪れたことがある。平成24年(2012)10月のことだ。豪邸ではなく、簡素な平屋建ての家屋だった。天保5年(1835)に大阪・堂島の中津藩倉屋敷で生まれた。父の百助は堂島の商人を相手に勘定方の仕事をしていた。翌天保6年、父の死去にともない中津に帰藩することになる。
1万円札の人物変更は聖徳太子から福沢諭吉に代わった昭和59年(1984)以来、40年ぶりというから確かにそろそろ交代の時期なのかもしれない。その福沢が19歳まで過ごした大分県中津市の旧居と記念館を訪れたことがある。平成24年(2012)10月のことだ。豪邸ではなく、簡素な平屋建ての家屋だった。天保5年(1835)に大阪・堂島の中津藩倉屋敷で生まれた。父の百助は堂島の商人を相手に勘定方の仕事をしていた。翌天保6年、父の死去にともない中津に帰藩することになる。
中津の旧居近くに看板があった。これに福沢の文が引用されていた。「今より活眼を開て先ず洋学に従事し 自から労して自から食い 人の自由を妨げずして我自由を達し、・・・人誰か故郷を思わざらん 誰か旧人の幸福を祈ざる者あらん」(明治三年十一月二十七 旧宅敗窓の下に記 「中津留別之書」)。明治3年(1870)、中津に残した母を東京に迎えるため一時帰郷した福沢が旧居を出る際に郷里の人々に残したメッセージだ。「中津留別之書」は『学問のすゝめ』の思想のベースとも言われる。そのメッセージで心が揺さぶられるのは、「自から労して自から食い 人の自由を妨げずして我自由を達し」の箇所だ。その後の福沢を人生を突き動かす「独立自尊」の強烈なメッセージが読み取れる。
ここで考えたのは、これは誰に発したメッセージなのだろうか、ということだ。翌明治4年に福沢は、新政府に仕えるようにとの命令を辞退し、東京・三田に慶応義塾を移して、経済学を主に塾生の教育に励む。その年、廃藩置県で大勢の武士たちが職を失い、落ちぶれていった。武士が自活できるように、新たな時代の教育を受ける学校が必要なことを福沢は痛感していたに違いない。「中津留別之書」はその強い筆力とメッセージ性から、武士たちに新たな世を生き抜けと発した檄文ではなかったのだろうか、と。では、なぜそのようなメッセージを武士に発したのか。武士たちが怨念を募らせて刀や鉄砲を手にすることで再び混乱の世に戻り、「自由が妨げられる」と危惧したのではないか。
「中津留別之書」から30年後、福沢は慶応義塾の道徳綱領を明治33年(1900)に創り、その中で「心身の独立を全うし自から其身を尊重して人たるの品位を辱めざるもの、之を独立自尊の人と云う」(第2条)と盛り込み、「独立自尊」を建学の基本に据えた(「慶応義塾」ホームページより)。翌明治34年(1901)2月、福沢は66歳で逝去する。武士が新たな世を生き抜く「人生モデル」を自ら示したのだった。法名は「大観院独立自尊居士」。
平成の1万円札の主役を担った福沢から、令和は渋沢栄一に代わる。しかし、「独立自尊」の精神は未来も変わることのない人の品位である。
⇒11日(木)夜・金沢の天気 はれ
 このとき自身は金沢大学の地域連携推進センターでコーディネーターの職に就いていた。2年前の平成17年(2005)1月に北陸朝日放送報道制作局長の職を辞していた。50歳になり「人生ひと区切り」と。すると、かつての取材先でもあった金沢大学の理事・副学長から誘われた。平成19年に学校教育法が改正され、大学のミッション(教育・研究)に新たに社会貢献が加わることになるとの話だった。「地域にどのような課題があって、そのキーマンは誰か、宇野さんはよく知っているはずだ。新聞・テレビでの知見を大学で活かしてみないか」と。テレビ局を辞した年の4月に大学の地域連携コーディネーターに採用となった。
このとき自身は金沢大学の地域連携推進センターでコーディネーターの職に就いていた。2年前の平成17年(2005)1月に北陸朝日放送報道制作局長の職を辞していた。50歳になり「人生ひと区切り」と。すると、かつての取材先でもあった金沢大学の理事・副学長から誘われた。平成19年に学校教育法が改正され、大学のミッション(教育・研究)に新たに社会貢献が加わることになるとの話だった。「地域にどのような課題があって、そのキーマンは誰か、宇野さんはよく知っているはずだ。新聞・テレビでの知見を大学で活かしてみないか」と。テレビ局を辞した年の4月に大学の地域連携コーディネーターに採用となった。