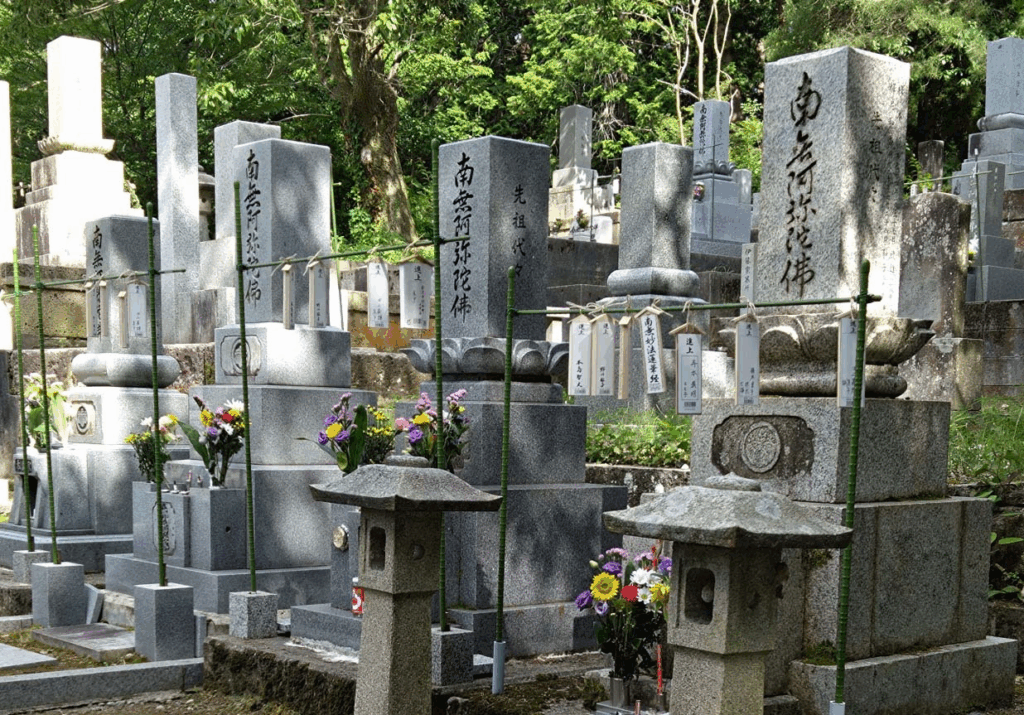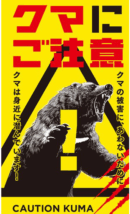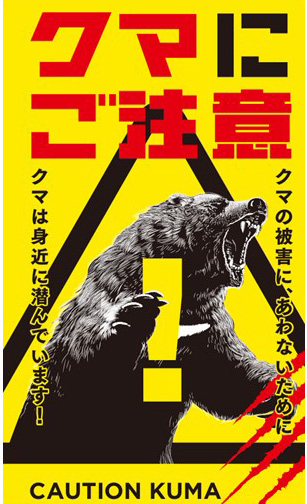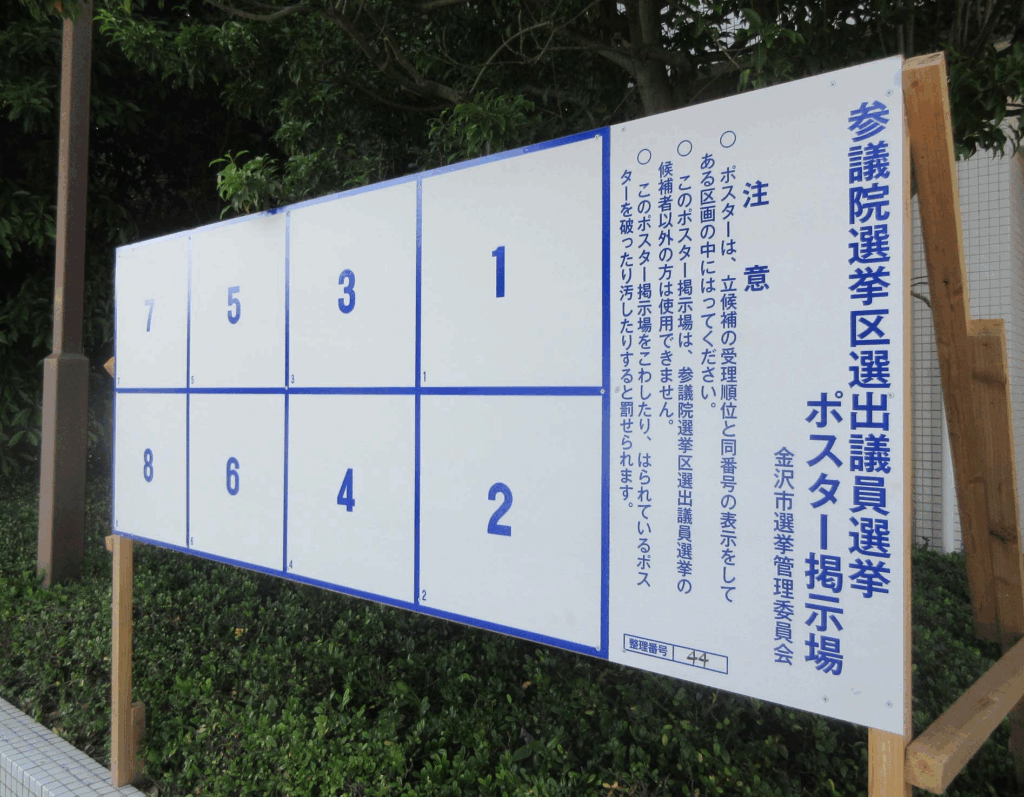☆AⅠが能登の現場に 交通誘導を仕切る、「言葉の壁」を超える

去年元日に能登半島地震があり、それを機に金沢から能登を頻繁に往復している。被災地がどうなっているのか、その後どうなったのか気になるからだ。そのときに利用するのが自動車専用道路「のと里山海道」。先日、その道路を走行すると横田IC付近で看板が出ていた。「この先 AⅠ誘導中」と書いてある=写真・上=。さらに、看板の上の方をよく見ると、「AⅠ交通システム」とある。ここはこれまで警備員のおじさんたちが数人で仕切っていた。それがいつの間にか、AⅠが仕切っていた。
看板の先は片側交互通行の道路になっていて、設置されたディスプレイの画面が「STOP」と「GO」のサインを出している=写真・下=。カメラで画像解析を行い、車の通過状況をAⅠが解析しているのだろう。車は表示された指示に従い、スムーズに流れていた。

能登では、AⅠをインバウンド観光で駆使している事例もある。半島北部の能登町にある民宿が並ぶ「春蘭の里」。インバウンド観光のツアーや体験型の旅行の受け入れを積極的に行っている。47軒の民宿経営の人たちが自動通訳機「ポケトーク」を使いこなして対応している。
春蘭の里の代表から聞いた話だ。「ポケトークだと会話の8割が理解できる。すごいツールだよ」と。ポケトークは74の言語に対応していて、春蘭の里は通訳機を使うようになって年間20ヵ国・2000人余りを受け入れるようになった。70歳や80歳のシニアの民宿経営者たちがポケトークを使いながらインバウンド観光の人たちと笑顔でコミュニケーションを取っている姿はAⅠの進化、まさに「文明の利器」を感じさせる。そして、困難と言われ続けていた「言葉の壁」をしなやかに乗り越えた事例だ。
さらに多様な役目をこなすAⅠが現れるだろう。たとえば、会議を仕切るAⅠだ。会議で出た話を分析してまとめを行い、次の議事進行へと淡々と進める。そんな時代が間もなくやって来るのかもしれない。
⇒23日(水)夜・金沢の天気 はれ