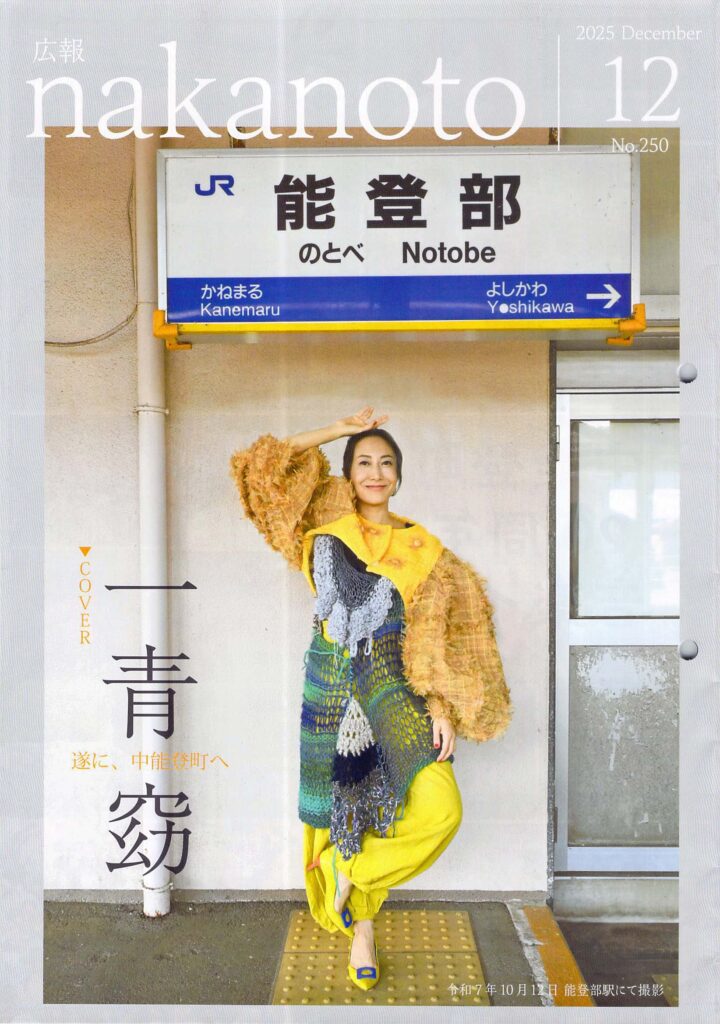★雪をすかすとスコップの先から海の環境問題が見えてくる
けさ午前5時過ぎに能登半島の尖端、珠洲市で震度4の地震があった。震源をチェックすると、2024年元日の震度7、マグニチュード7.6の能登半島地震の震源と近い。まだ、能登地震は収まっていないのか。そしてけさから強風が吹いている。気象庁では、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、北陸地方に落雷や突風、高波が発生する恐れががり、注意を呼びかけている。大雪の心配はないようだ。

このところ毎日のように「雪すかし」をしてきたが、やはり気にかかるのはマイクロプラスチックのことだ。かつて、スコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化。さらに、最近はプラスチックなど樹脂製が主流だ。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・上=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。
粉々に砕けたプラスチックは海を漂い、海中の有害物質を濃縮させる。とくに、油に溶けやすいPCB(ポリ塩化ビフェニール)などの有害物質を表面に吸着させる働きを持っているとされる。そのマイクロプラスチックを小魚が体内に取り込み、さらに小魚を食べる魚に有害物質が蓄積される。食物連鎖で最後に人が魚を獲って食べる。この不都合な真実の解決方法はただ一つ。一部には製品化されたものもあるが、スコップのさじ部分の尖端を金属にすることだろう。これを法令で措置すべきではないだろうか。使い捨てプラスチック製品を規制す法律はあるものの、スコップ先まで規制する細やかな規制はまだない。

海の環境問題をテーマにした作品を思い出す。2021年に能登半島先端の珠洲市で開催された「奥能登国際芸術祭2020+」で、インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」。大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった=写真・下=。プラスチック製浮子(うき)や魚網などの漁具のほか、ポリタンク、プラスチック製容器など生活用品、自然災害で出たと思われる木材などさまざまな海洋ゴミだ。実際にグプタ氏が能登の海岸を歩き、この作品づくりを発想した。作品の漂着ごみのほとんどが実際にこの地域に流れ着いていたものを拾い集めた、とあった(ガイドブック)。
日本海の漂着ごみは大陸の沿岸からも流れてくる。ポリタンクのほか、医療系廃棄物の不法な海洋投棄もあり、まさに国際問題だ。「地中海の汚染防止条約」とも呼ばれるバルセロナ条約(1978年)があるように、日本海にも汚染防止条約が必要だ、とグプタ氏の作品を見て考えるようになった。「Think about me」と訴えかけてくる。
⇒13日(火)午前・金沢の天気 くもり時々あめ