☆続々・ニュージーランド記
ニュージーランドの南島の牧場では羊が飼われ、北島では牛が草を食む、それこそ牧歌的な光景をよく目にした。農業国といわれる理由なのだが、豚の放牧は1度しか見なかった。寝るための小屋が必要で設備投資に金がかかる、というわけだ。牛や羊とは違って病気にかかりにくく栄養価でも優れている家畜なのだが、酪農大国ニュージーランドは豚の輸入国に甘んじている。
羊の毛刈り職人の深き悩み
クイーンズタウンの空港からクライストチャーチ空港へ、さらに、飛行機を乗り継いで北島のロトル アに着いた(8月18日)。ロトルアには、温泉が数十㍍も吹き上げる有名な間欠泉がある。日本の別府市と姉妹都市だそうだ。
アに着いた(8月18日)。ロトルアには、温泉が数十㍍も吹き上げる有名な間欠泉がある。日本の別府市と姉妹都市だそうだ。
ロトルアではもう一つ有名な毛刈りショーを堪能した。羊はおとなしい動物なのだが、中には暴れるのもいる。特にシェリオットという種は気性が荒いので毛刈り職人にとっては厄介者だったが、いまは品種改良されて随分とおとなしくなった、などと司会者が軽妙な語りでショーを進めていく。これを日本人スタッフが通訳しながら実況中継する。それをヘッドホンで聞く。台湾、韓国からの見学者もいるので、それぞれの言語のスタッフが中継する。ショーを終えた後で国際会議もできそうだ。
ところで、ウール王国のニュージーランドで羊の毛刈り職人はさぞかし優遇されているのだろうと観光ガイド氏に訪ねた。すると「かつてはそうだったのですが…」と前置きし、内実を話してくれた。毛刈り職人の労賃は1匹につき1㌦40㌣(ニュージーランドの1㌦=76円換算で106円)である。電動バリカンだと一人前の職人は平均して37秒に1匹をさばく。1日に300匹ほどの毛を刈ることになる。つまり労賃は420㌦、3万2千円ほどだ。
「でも、数年前までは2㌦から2㌦50㌣だったのです」とガイド氏。羊毛の重要が落ちているのだ。その証拠に、かつて数億匹といわれたニュージーランドの羊は今は4000万匹だ。
その羊の毛刈り職人を窮地に立たせているのがポリエステルの繊維素材、フリースの登場だといわれる。フリースは高級ウールを目指してつくられた。保温性が高く、軽量、簡単に洗濯できるので、登山家らアウトドアの人たちの必需品だった。それが、アメリカのクリントン元大統領のヒラリー夫人も愛用しているなどと評判になり、一躍、タウン着として世界中から注目されるようになった。ペットボトルを再生して製造される道筋がついているので原材料には事欠かない。天然素材が化学素材に圧迫されている。羊の毛刈り職人の悩みは深いのである。
ちなみに「羊の毛を刈る」という英語表現は「shear a sheep」あるいは「fleece a sheep」と書く。fleeceは名詞で「羊の毛」のことである。
⇒24日(木)夜・金沢の天気 はれ
 クライストチャーチを後にして8月16日はクイーンズタウンを訪れた。湖畔沿いに街がつくられ、雪のサザン・アルプスが背景に連なる。雑誌などでよく見る北欧かスイスの街のようなイメージだ。南緯45度、地球儀をひっくり返してみれば、北緯45度は日本の北海道・稚内、何となく北国であることが想像できる。が、ヨーロッパと比較するとイタリアのミラノやフランスのルグノーブルに相当し、北欧とは遠い。
クライストチャーチを後にして8月16日はクイーンズタウンを訪れた。湖畔沿いに街がつくられ、雪のサザン・アルプスが背景に連なる。雑誌などでよく見る北欧かスイスの街のようなイメージだ。南緯45度、地球儀をひっくり返してみれば、北緯45度は日本の北海道・稚内、何となく北国であることが想像できる。が、ヨーロッパと比較するとイタリアのミラノやフランスのルグノーブルに相当し、北欧とは遠い。 関空からのフライト。セーターや厚手のズボンやコート、靴を持参したので大きいほうのトランクは34㌔にもなった。10時間半でニュージーランド南島のクライストチャーチ国際空港に着いた。現地の時間は午後0時30分、到着を告げるアナウンスでは日中気温は7度。金沢だと2月下旬ぐらいの気温だ。機内でさっそく上着を羽織った。
関空からのフライト。セーターや厚手のズボンやコート、靴を持参したので大きいほうのトランクは34㌔にもなった。10時間半でニュージーランド南島のクライストチャーチ国際空港に着いた。現地の時間は午後0時30分、到着を告げるアナウンスでは日中気温は7度。金沢だと2月下旬ぐらいの気温だ。機内でさっそく上着を羽織った。 後4時から本番とあって、リハーサルにもかかわらず、上条恒彦のボリューム感のある声が園内に響き渡っていた。人のにぎわいと音で騒然としていた、と表現した方が分かりやすいかもしれない。
後4時から本番とあって、リハーサルにもかかわらず、上条恒彦のボリューム感のある声が園内に響き渡っていた。人のにぎわいと音で騒然としていた、と表現した方が分かりやすいかもしれない。 (おもむき)があった。
(おもむき)があった。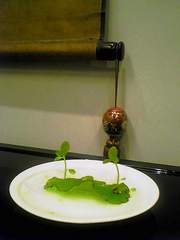
 通りには花見のぼんぼりが取り付けられ、春のムードを醸し出している。その広坂通りを歩いていると、旧・県庁の正面にある2本の巨樹の目立つ。
通りには花見のぼんぼりが取り付けられ、春のムードを醸し出している。その広坂通りを歩いていると、旧・県庁の正面にある2本の巨樹の目立つ。 なんとも威風堂々とした感じだ。
なんとも威風堂々とした感じだ。
 で自分をカラオケモードに切り替える。1969年のデビュー曲だから、私もかれこれ30年余り歌い込んできたことになる。
で自分をカラオケモードに切り替える。1969年のデビュー曲だから、私もかれこれ30年余り歌い込んできたことになる。 ている地区もあるのだとか。坂の街の福祉ではある。
ている地区もあるのだとか。坂の街の福祉ではある。 

 料理のパエリアなどは賞賛に値すると思う。
料理のパエリアなどは賞賛に値すると思う。 吟醸といった高級化路線でブームをつくった日本酒の業界だが、最近はワインや焼酎に押されてかつての勢いはないと思っていた。ところが、妙なところからブームが起きているのである。カップ酒だ。そういえば、コンビニでも棚に占めるカップ酒の面積や種類が増えている。
吟醸といった高級化路線でブームをつくった日本酒の業界だが、最近はワインや焼酎に押されてかつての勢いはないと思っていた。ところが、妙なところからブームが起きているのである。カップ酒だ。そういえば、コンビニでも棚に占めるカップ酒の面積や種類が増えている。 してこまめに顔を出している。
してこまめに顔を出している。
