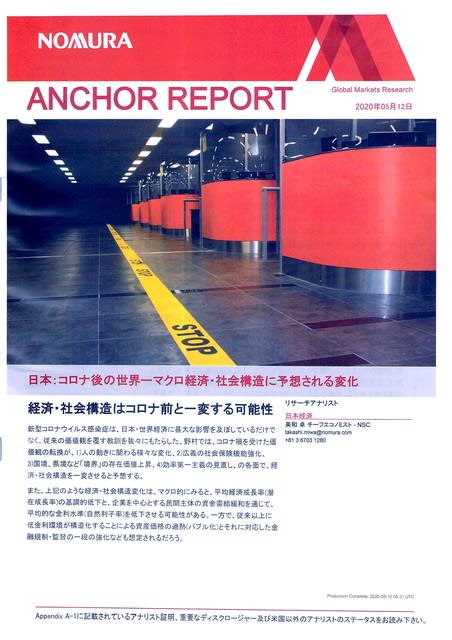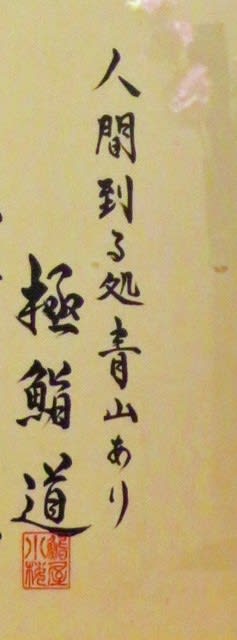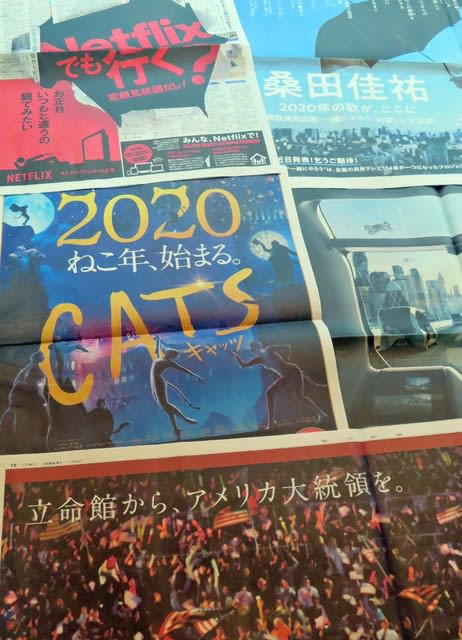☆昔「百姓の持ちたる国」、今「住みよき加賀」
面白いデータをネットで見つけた。「東洋経済ONLINE」に、「住みよさランキング2020」の全国総合トップ50が掲載されている。1位が石川県の野々市市で、以下、文京区(東京)、武蔵野市(同)、白山市(石川)、福井市(福井)、吉倉市(鳥取)、金沢市(石川)、小松市(同)、長久手市(愛知)、能美市(石川)と続く。トップ10を石川県の自治体が半数 を占めている。実際にこの地に住んでいる者としては名誉なことなのだが、それほど「住みよさ」を意識したことはなかったので、「なぜ」とも思う。
を占めている。実際にこの地に住んでいる者としては名誉なことなのだが、それほど「住みよさ」を意識したことはなかったので、「なぜ」とも思う。
気になって、前回「2019」のデータを検索してみる。すると、1位に白山市、3位に野々市市、8位に能美市がランキングされていてトップ10に3つが入っている。石川県のほか、4位に福井市、7位に黒部市(富山)、9位に魚津市(同)が入っていて、北陸3県で実に6つを占めていた。冒頭で述べたように、「住みよさ」をそれほど意識したことはなかった。というのも、北陸は冬になれば雪が降り、自宅ガレージ前の道路を除雪するのが日課となる。凍結した路面ではのろのろ運転だ。日照時間も少なく、日中でも薄暗い日々が続き、冬のストレスがたまる。それが「住みやすいのか」と。
そこで、このランキングの評価基準が気になった。ホームページに記されていた。その指標はA「安心度」(人口当たりの病院・病床数、介護老人定員数、0~4歳児数、刑法犯認知数、交通事故件数)、B「利便度」(人口当たり小売り販売数、店舗面積、飲食店小売事業所数、飲食店数)、C「快適度」(転出入人口比率、水道料金、汚水処理人口普及率、公園面積、最低最高気温・日照時間・最深積雪)、D「富裕度」(財政力指数、法人市民税、所得、床面積、地価)。20のデータをもとに算出し、AからDの視点でそれぞれ全国812の市と区をランキングしている。積雪や日照時間も入れての総合評価だった。
 では今回、トップ10のうち5つを占めた石川県の自治体の何が特徴なのか。野々市市は利便性が10位と際立っているが、ほかは安心度134位、快適度170位、裕福度171位とそれほど高くはない。金沢の郊外という立地でスーパーマーケットが多数あり、大学もあるので周囲には飲食店も目立つ。人口5万人余りのコンパクトな自治体なのだ。白山市は快適度6位。その名前の通り、霊峰白山のふもとにあり、豊かな水資源に恵まれ、企業立地も数多く、海浜公園など自然環境にも恵まれている。
では今回、トップ10のうち5つを占めた石川県の自治体の何が特徴なのか。野々市市は利便性が10位と際立っているが、ほかは安心度134位、快適度170位、裕福度171位とそれほど高くはない。金沢の郊外という立地でスーパーマーケットが多数あり、大学もあるので周囲には飲食店も目立つ。人口5万人余りのコンパクトな自治体なのだ。白山市は快適度6位。その名前の通り、霊峰白山のふもとにあり、豊かな水資源に恵まれ、企業立地も数多く、海浜公園など自然環境にも恵まれている。
今回トップ10に入った野々市、白山、金沢、小松、能美はそれぞれに立地条件や地域資源など特徴があり、それを最大限に活かす努力をしている点が評価されたといえる。この地に住む者としてふと思うのは、この5つの自治体は加賀とよばれる地域だ。戦国時代は「百姓の持ちたる国」として中央政権と距離を置き、独自に栄えた地でもある。今は「住みよき加賀」として輝きを放っている。
(※写真は、「住みよさランキング2020」で全国総合トップとなった石川県野々市市の市役所)
⇒18日(木)朝・金沢の天気 くもり